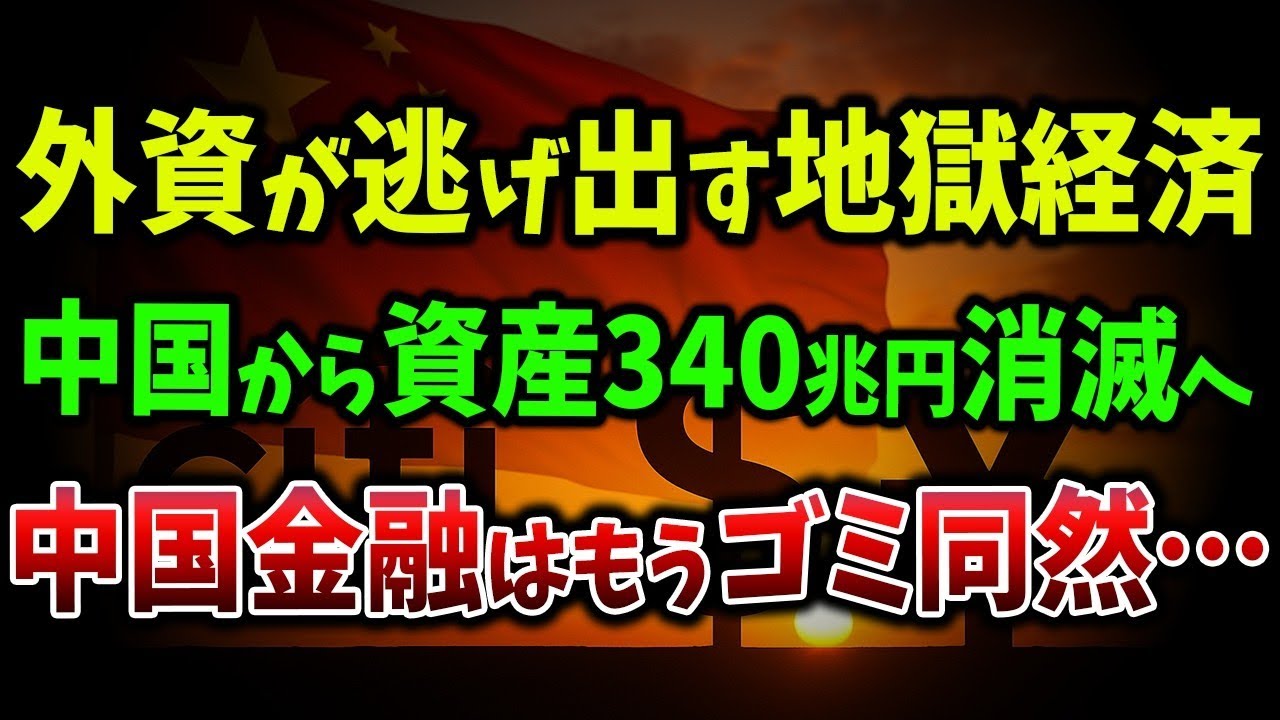【海外の反応】58兆円市場が消え外資系銀行が中国から手を引く決定的理由!ドル体制に激震走り人民元はもう終わりだ【ゆっくり解説】
グループが中国から撤退したってニュース見た?ついにアメリカの大手銀行まで逃げ出すとかもう中国終わってない。ゆっくり霊夢ちゃんと [音楽] 解説役のゆっくり魔理沙だ。そうだな。今回はユニオンペイコール銀からも完全に手を引いたって発表だった。これ単なる業務整理じゃなくて戦略的撤退だ。 ユニオンペイって中国の決済ネットワークでしょ。あそこから外されるってもう中国内で銀行業務まともにできないってことじゃん。 実際そう、外し系のカードやは中国でどんどん使いづらくなってる。しかも規制もガチガチ。アリペやに完全に市場を奪われた。 中国側が外を排除してるようにしか見えないんだけど、このままだと全部の外銀行が消えるんじゃ。 すでにその流れに入ってる指だけじゃなく、他の外系も氷部門は撤退方向。法人向けのサービスに絞って生き残りを測ってるんだ。 [音楽] でもさ、法人向けってそんなに儲かるの?個人の講座とかカードの方が利益率構想じゃない? [音楽] 中国ではもう個人向けの収益が落ち込んでる上に情報管理や規制が厳しすぎてリスクだらけだから法人向けに資源集中するしかない。 なるほど。つまり逃げられるうちに逃げるってことか。まるでカジから脱出してる感じだよね。 それだけじゃない。 中国経済全体も鈍化してるし、人民の信用もガ落ち、外しからすれば残る理由がもうないんだよ。 てなわけで今回は 58 兆円市場が消え返し系銀行が中国から手を引く決定的理由。ドル体制に激進人民人民人間はもう終わりだ。ゆっくり解説を紹介するぜ。 [音楽] それじゃあ早速ゆっくりしていってね。 今回の発端はシティグループが中国の銀つまりユニオンペとの関係を正式に切ったっていう発表だった。日付は 9月5 日プレスリースで名言された内容だ。 ユニオンペイって中国で 1 番メジャーな決済ネットワークよね。つまりビザとかマスターカードの中国版みたいなものでしょ。 その認識であってるユニオンペは 2002 年に設立されてから中国本土のあらゆる銀行カードに組み込まれてきた。 海外でも183 カ国で使えるようになっていて、加盟している金融期間は 2600社を超える。 え、それってすごくない?それだけ広がってるネットワークからアメリカの大手銀行が抜けるってかなりの衝撃じゃない? [音楽] 衝撃というよりもある種の潮目の変化だな。シティグループは中国市場から個人銀行量を完全に撤退させた後、今度はその余波としてユニオンペとの定携も終了させたわけだ。 ってことはこれ単なるビジネス判断ってよりもっと寝深い理由がありそうだよね。最近の米中関係とかリスクとか。 まさにそこだ。指の撤退は単に儲からないからやめたってだけの話じゃない。実際 2010 年代までは外使系銀行も中国の個人金融市場での拡大を狙って積極的に投資してた。 でもその後中国政府の規制強化と不透明な金融制度、さらに外科の有出制限なんかが重なって運営リスクが爆増したんだ。 うわ、まるではなみたいな市場だね。最初は自由層に見せておいて途中で手のひ返して締め上げる。どっかで見た展開。 実際それにはまった会社は少なくない。特に中国における情報の対象。 つまり外だけが情報を握れず現地だけが有利に立てるような状況が頻繁に発生してる。これは金融に限らず製造量や [音楽] ITでも同じ。 それってただの不公平じゃなくてもう外国企業に対する罠みたいなもんじゃん。しかもそれを制度としてやってるってのが怖い。 ちなみにシティグループは 2021 年時点ですに個人向け銀行務は最散が取れないと判断して中国だけじゃなく韓国、インドネシア、などの新国市場からも撤退を進めてたんだ。 あれ中国だけじゃないんだ。他のアジア諸国でもってことはそれだけ外にとって進国市場ってもう旨味がなくなったってこと? いや、旨味がなくなったというより旨味よりリスクが上回るようになったって言った方が正しい。 特に中国の場合は国営企業量との癒着、共産党との距離感、法律の的運用、これら全部が金融を押し上げるファクターになってる。 それってつまりつ講座が凍結されても文句言えないって状況じゃん。もはや放置国家とは呼べない気がするけど。 [音楽] さらに今回の動きで注目すべきなのは企業期間向けのサービスだけは残すって名言したこと。 つまりは中国の個人とは付き合わないけど国家や大企業とは取引するってスタンスを取った。な んだろうその選別の仕方。結局リスクを最小限に抑えつ残った理権は取りに行くって感じ。あざいけど現実的すぎて逆に関心しちゃうわ。 でもそれがグローバル資本主義の生存ってやつだ。無理に全方位と付き合うのではなく信用できる相手とだけ取引する。 その結果ユニオンペイとの縁を切ったのも自然な流れだったんだろうな。 でもさ、ユニオンペイって中国内では使えないと生活すらできないレベルのインフラじゃない?そんなところから撤退するってよったんだろうな。 実際のところ死が失うものも小さくはない。ただそれ以上に今後失う可能性のあるリスクが大きすぎた。それが中国市場の本質ってわけ。 [音楽] うん。 でもこれって他の欧米系銀行にも波及するんじゃない?だって 1 社だけが特別に危ないってわけじゃないよね。 その通り。すでにイギリスの HSBC なんかも中国本土と距離を取る動きは加速させてる。スイスの UBS も人民立て資産の比率を下げてるし、アメリカの JPモルガンも中国向け投資を縮小中だ。 それってもう外しの中国撤退ラッシュって言っても言いすぎじゃないよね。 よくもまあこんな環境でビジネス続けてたなって逆に関心するレベル。 この撤退劇にはもう1 つ重要な流れがある。それが 2023 年にしてグループが中国で保有していた氷ある層事業を売却した件だ。単なる店舗閉鎖ではなく事業そのものの移転だった。 富裕総向けってことはいわゆるハイエンドな顧客の資産管理や金融コンサルみたいな部門よね。それを丸ごと他者に引き渡したの? そう、その通り。 その時買収を受けたのがイギリス系の大手銀行 HSBCつまり香港海銀行だ。しかも HSBC はフォリオの買収によって中国本土の不裕層マーケットで一気にシェアを広げた形になる。 あれHSBC って確かに中国での展開も強めてた。 印象って逆に返しが引いていってるんじゃなかった?なんか矛盾してない? それが面白いところで HSBC は一時的にポジションを取りに行ったんだけど 2024 年以降は一転して中国リスクに直面し始める。例えば中国内の人権被圧力や当局の監視強化、それに情報の遮断男性といった問題が次々に浮上してきた。 ああ、それってつまり最初は儲かると思って突っ込んだけど蓋を開けてみたら地雷ゲだったってパターン。 まさにそれ。 しかもこの売却に合わせてクレジットカード部門も別の企業不凡という中堅金融期間に譲渡されることが決まっていた。この取引は 2024 年中に完了する予定だったが正確な進捗は明かされていない。 不凡いバンクって台湾系の銀行よね。 それが中国内の事業を引き継ぐってなんか知性学的に微妙じゃない?つ摩擦の日種になるか分からない気がする。そういったリスクもあるがそれ以上に外から現地資本へ引き継がせると当局の意図が透けて見える構造だった。指が抜けたら中国企業か。少なくとも中国当局に近い企業が後を継ぐ。それが脱害師の規定路線とも言える。 あんたそれ非肉混じりで言ってるよね。 でも正直資本の中立性とか全然守られてない感じするわ。 さらに注目すべきは 2023年8 月に発生した企業登記情報の変更だ。シティグループ中国法人の会長だった理名が辞任し、新たに警報連が公認についた。この人事は表面上は交代に過ぎないが実際には内部構造の大幅な見直しを意味していた。 人事道ってそんなに深刻なの?ただの引退や年じゃなくて戦略転換の一環ってこと? その通り。このレベルの交代劇は単なる人事じゃなくて資本と経営の主導権が完全に変わるサインだ。しかもこのタイミングで交代っていうのが絶妙でまさにクレジットカードやローン事業の遺憾と足並が揃っていた。 それ計画的っていうか外師がコントロールしてたものを猫そぎ切り離すプロセスの一部に見えてくるよね。 もはや外排除のテンプレみたい。 そしてこれは孤立した事例ではなかった。他の欧米銀行も同じように中国市場から静かに身を引き始めていた。例えば 2025年2 月ボール街全体で中国向けの投資学が前年同期費で約 28%減少したという報道もある。 28% って金融界でそれだけ引いたってよっぽどやばい空気が漂ってる証拠じゃない。 しかもそれが教界全体って 実際にJP モルガン、チェイスやモルガン、スタンレイといった巨大プレイヤーでさえも人員削減や中国市場での採用凍結を実施している。すでに成長戦略そのものを全面的に見直している状況だ。 じゃあもう成長市場としての中国っていう幻想は完全に崩れ去ったってことね。あのバブルの頃の中国寝室ラッシュは何だったんだってレベル。 ちなみにスタンダードチャータード銀行も 2024 年に中国の交理量を縮小し、法人取引に特化した形での事業再編を断行している。 HSBC も同時期にウェルスマネジメント部門の再編を開始した。 まさに連鎖反応って感じだね。 1 社がやると他もつ随。しかも競合でさえも似た判断を下すってどれだけリスクが露定してるのか想像もつかないわ。 さらに注目すべきが 2025年7 月に発生したウェルズファーゴの中国全住要員への都行禁止命令。なんと業務出張すら全面的に禁止されていた。 [音楽] うわ、出張禁止ってそれもう事実上の撤退宣言じゃない?行けないんじゃ仕事にならないでしょ。 [音楽] 背景には外国企業への調査を理由とした当局の外国人高速リスクがあったとある幹部の証言によると中国での調査に巻き込まれた外国籍の役員が空港で突然足止めを食らい数日関連絡が取れなくなった。 うわ、それってほとんど人質じゃん。どこの独裁国家だよって話よ。 こういったケースが増えば増えるほど外景企業は投資判断を慎重にせざるを得ない。つまり中国に金は入れない。 社員も送らないっていう空気が金融会全体で満し始めている。 でもその流れって今に始まった話じゃないよね。中国のシティグループだってそもそも 1902 年に上海視点を開いたって言うからもう 1世紀以上も前から続いてたんでしょ。 そう。それだけの歴史を持ってた企業がわざわざ全部を手放してまで撤退を選ぶっていうのは本当に異常な事態なんだ。 100年の歴史に幕を引いたってわけさ。 それってもう単なる経済的な判断とかじゃなくて文明や価値観の衝突レベルだよね。お金じゃ決できない根本的な信頼の崩壊というか。 実はシティグループって中国に進出した最初期のアメリカ系銀行の 1 つなんだ。しかもその歴史は驚くほど古くてなんと 1902年に上海に視点を解説している。 192 年ってもう120 年以上前じゃん。それ日進戦争のちょっと後ぐらいよね。 そんな頃から中国にアメリカの銀行がなんてびっくり。 そう、その当時は欧米列教が中国で繁殖民地的な検疫を広げていた時代。特に上海は外国訴会の中心地で貿易や金融のハブになっていた。外国銀行の役割は主に国際貿易の資金決済や者との取引に特化していた。 なるほどね。当時は中国人向けじゃなくて外国企業向けの銀行ってたち位置だったんだ。でもその後 1度撤退してるんだよね。 その通り共産家や戦争の混乱で一旦撤退したが 1983 年になってシティグループは中国市場への最入を果たす改革解放政策が始まったことで外の受け入れが段階的に解禁されたからだ。 それってつまり当翔平の南巡和の後くらいのタイミング中国が市上経済っぽい顔をし始めた時期よね。 まさにその空気感だな。 シティはその流れに乗って 1998 年にはアメリカ系銀行として初めて人民原立て業務の営業許可許可を受けた。これが当時としてはかなりの解だった。 人民間でビジネスできるって当時はすごい特権だったはず。しかも他の外系はまだ様子見してたんでしょ。 その後2007 年にはシティグループチャイナリミテッドっていう現地法人が正式に設立される。これは中国当局に認可された最初期の外系銀行法人の 1つだった。 つまり本格的に中国の氷銀行量へ参入したってことだ。 うわ、それってガチの本気じゃん。当時は外しはこれから中国の内樹を取るって期待されてた頃だったよね。 [音楽] 実際にシティは北京、上海公衆州新といった大都市に次々と拠点を設けて個人向けクレジットカードやプライベートバンキング富裕層向けの資産運用までフルラインナップを展開してた。 ああ、その頃ってちょうど中国が不動産バブルで浮かれてた時期と重なるよね。中層の資産が増してたから金融商品を売るには格好のタイミングだったのかも。 その通り当時の雰囲気は中国は成長市場儲かることしかないって幻想に包まれてた。特に海外の経済士や投資家の間ではこそが外系銀行で中国市場を制する最有力候補とまで言われてた。 それが今や全撤退でしょ。ま、逆の展開になってるじゃん。 どれだけ現実が甘くなかったかがよくわかる。 実際今回のユニオンペーリ脱もその延長戦上で見ないと本質が見えてこない。経済アナリストたちの意見を見ても単なる事業整理ではなく多重構造のリスク回避と指摘されている。 [音楽] うわ、それってなんか含みある言い方。具体的にどういうリスクが絡んでるの? まず第1 にユニオンペイの個人向けビジネス自体が縮小傾向にある。 これは単純な消費名じゃなくて中国全体の経済成長がど化してる影響が大きい。例えば 2024年度の中国GDP 成長率は政府目標の5.0%を下回って 4.5%程度にとまった。 へえ。表向きは回復基調とか言ってたけど数字で見るとかなり鈍いのね。しかも地方債務とか若者の出要率もえぐいでしょ。 そう。それが第2 の要因。消費者信用市場が崩れてきてる。 都市部の弱年喪失用率は 1時20% 以上に達したと報道されてるし、クレジットカードの支払い遅延率も上昇中。ああ、つまりカード作っても払えない人が増えてるってことね。金融期間としては貸倒れリスクが高くなるから事業を絞るしかないと。 さらに第3 の要因として中国政府によるフィンテック企業や外系銀行への締め付け強化がある。 例えば2023 年にはある欧州銀行が中国内で突然の税務調査を受け栄養停止に追い込まれた例もあった。 え、それって完全に嫌がらせじゃん。外が信用できないっていうより中国政府が信用ならない感じ。 最後に地性学的な緊張も無視できない。米中関係の悪化、台湾情勢の緊張してウクライナ戦争の影響で西側資本の中国会費が本格化してる。 金融界だけじゃなく製造量や IT でもサプライチェーンの見直しが進んでる。 つまりもう中国にはかけないって有空気があちこちに広がってるってことね。幻想が終わった瞬間って感じ。 さて、直近の中国経済の実情だけど 2024年から2025 年にかけての全体的なケーキの空気はあえて言えば見た目は持ち直してるけど中身はボロボロって感じなんだ。 うわ、それってもう針みたいなもんじゃん。 外から見たら派手だけど、触った瞬間に崩れるみたいな。 実際政府が掲げてる GDPの成長目標は例通り約 5% なんだけど、これがもはや形式的な数字になってる。 2024年の実績は4.5% 前後にとまったとされ、 2025年も達成困難と見られている。 あれ、それって結構きつくない? 5% 成長ってかつての中国なら余裕で超えてた数字じゃなかった? そう。それこそ2000年代や2010 年前半なら7から9% 成長が当たり前だった。今の 5% ですら低成長と見なされてる状況なのにそれさえも届かないとなると実態はかなり深刻だ。 しかもあの国って都合の悪い数字はなかったことにする体質だから表に出てる数値も相当マイルドに加工されてる可能性あるよね。 そこが1 番の問題で数字が信用できない国であることが投資家にとっての最大のリスク要因になっている。そして今中国経済の足を引っ張ってる最大の要素が不動産セクターの崩壊だ。 不動産ってずっと中国経済を支えてきた中核じゃなかった。バブルがどれだけ膨らんでも見て見ぬふりされてた印象だけど。 その通り。実際中国のGDP のうち不動産関連が占める割合は 20から30% とも言われていた。土地の売買、住宅建設、家具販売、家電、リフォーム全部が連動してたんだ。 つまり家が売れないとそこにつる業種まで一緒に友倒れするってことか。ドミノタみたいな連鎖。 実際2024年時点で中古宅の価格は 2級都市で前年非中から15%の下落。 新築の在庫も積み上がっていて、地方ではゴーストマンションが再び問題視されている。 [音楽] ああ、そういえば一時期誰も住んでない新築高層マンション軍が話題になってたよね。あれって結局国ぐるみの投資詐欺みたいなもんじゃん。 加えて地方政府の財政界を迎えてる。土地を売って資金を得るモデルが崩壊し負債比率は表に出ている数字以上に膨れ上がってる。 影の債務と呼ばれる地方有融資プラットフォームの累計負債はすでに船長円規模に達したと見られている。 え、それって国家予算の倍よ。そんな中で会社が安心して投資できるわけないじゃん。 そうなんだ。実際に 2025 年前半中国の務省が発表したデータによると外国からの実際の資本留入学は約 3580億元。日本円にして7 兆円程度にとまり、前年度同期費で 13%の大幅減少。 それって減ってるってレベルじゃなくて逃げ出してるって言った方が正しい数字じゃない?危機感が数字に現れてるっていうか。 一方で新しく登録された外景企業量の数は増えてると政府は強調しているが、これも実態とは駆け離れてる。多くはペーパーカンパニーに近い状態で実際に工場を立てたり社員を雇ったりしている企業は少ない。 つまり数だけ増やして中身は空っぽってわけか。数字だけでメンツを保とうとする中国らしいやり方だね。 特に影響が大きいのが氷や不動産製造量といった従来型産業への害の関心の喪失。逆に今でも資本が流しているのはハイテや [音楽] IT あるいは医療関連といった戦略セクターに偏ってる。 あれってさ、結局中国政府に睨まれてもいい覚悟がある企業しか残ってないってことよね。 逆に言えばちょっとでも不利になったら即撤退するようなギリギリのつ渡り。 さらに金融会の中でも特に氷銀行量が最も打を受けている。理由は明確でクレジットカード、分割払い音ン、資産運用商品。これら全部が消費者の信用と勾配欲に直結してるからだ。 要するにお金を借りても返せない。そもそも欲しいものがない。将来が不安だから節約って見えくってことか。 なんその地獄モード。 実際2025 年上半期には個人向けロの新規発行額が前年同期費で 18% 減少。消費者信用スコアの平均も全国的に低下しており、金融期間のリスクは極端に慎重になっている。 それってもう消費の市ってやつじゃん。クレジットカードが回らない社会なんて都市経済としては完全に終わってる。 さっきまで話してた経済の失速息と消費の冷え込み。 その影響がもろに出てるのが氷バンキングつまり一般個人向けの金融なんだよな。特にローンとかクレジットカード、あと資産運用商品の分野で ああ、つまりお金借りる人もいないし投資する余裕もないってことか。そりゃ銀行の儲けなんて出ないに決まってるよね。 実際中国内の銀行利用者の多くが今や増やすより守るを優先しててちょっとでもリスクがある商品は経されてる。 クレジットカードも使い控えが広がってて、分割払いとかリボ払いの需要もガがクっと落ちた。 それってあれでしょ?ケーキ悪い時は貯金しかたんって空気になるやつ。何年か前の日本でも同じことあったよね。 [音楽] まさにそれ。そしてその守りに入った消費者が選ぶのがリターンは低くても安定した預金や元本保障の金融商品。リスク資産は経引され、資産運用部門の売上も大幅に減少している。 そうなると銀行側も新しい商品なんて作る気なくなるよね。どうせ売れないんだから悪循環ってやつ。 しかもシグループにとってはさらに不利な状況が重なっていた。中国市場では地元の大手国有銀行、例えば中国交渉銀行や中国建設銀行みたいな巨人たちが全国規模の視点と政府の後ろ立てを持ってて外系は完全に脇役だった。 なるほど。最初から不利な土俵で戦ってたってわけね。 外師にとっては勝負する前から積んでたって感じかも。 その通り。市場視野も圧倒的に小さくてそもそもブランド認知も弱い。さらに顧客の信頼感も低いから外国の銀行にお金預けるのはちょっと怖いって心理が根強く残ってる。 [音楽] ああ、それって多分中国政府が外しは信用するなって裏で空気作ってるよね。そういう誘導はあの国のお家ゲーだし。 その結果シティグループみたいな外国銀行はクレジットカードやローンなどの定番商品でさえも拡大できなかった。規模が小さいから広告にかける予算も限られてさらに集客コストが高くつく。 それに加えて害はコンプライアンス。つまり法令種の面でも中国特有の厳格な審査や報告義務があるでしょ。それで時間と金ばっかり食われるってやつ。 そう。それがまた地元銀行とは不公平な部分でもある。 中国政府は国内企業には甘く外には厳しく接することで自国優先のルールを徹底している第 3者の証言でも 外系銀行で働いていたが監査や報告の手続きだけで毎週 20 時間以上取られていた。地元の銀行ではそんな規制はなかった。 それ力の無駄すぎるでしょ。しかもその間に地元銀行は栄養に走れてシェア奪っていくんだからそりゃ勝てるわけないよ。 [音楽] さらに言えばこういった構造的な不利が積み重なってシティグループがこれ以上この市場に金かけても回収できないと判断するのも当然の流れだった。リターンが見込めないなら撤退は最前種。 無理して続けて存するくらいなら早く切った方がマしってわけね。ビジネスとしては正しいけど長年の歴史がある分ちょっと切ない感じもあるな。 でもこれは中国経済全体を見渡せば銀行だけの話じゃない。 2025年時点で中国はすでに 2024 年の下傾向を引き継いでいて、成長率は公式には 4.5% 程度と予測されているが民間分析ではもっと低いと見る向きもある。 それってもう成長国と呼べる水準じゃないよね。むしろ日本型の停滞モードに片足突っ込んでる気がする。 特に影響が出ているのが製造や自動車両界。 かつて我が師がこぞって進出していた分野だけど、今は生産拠点を東南アジアやインドに移す企業が続出している。これが外国直接投資 FDIの休にもつがってる。 つまりもはや中国で作るメリットがなくなったってことか。人権費も上がってるし政治リスクも高いし誰が好き好んで残るのって話だよね。 自動車産業で言えば 2025 年上未半期の外系メーカーの新規投資額は前年と比べて 35%減少。 ドイツやアメリカの大手も設備投資を凍結するか縮小を明言してる。 それだけ逃げられてるのに外国企業がどんどん中国に来てます。ってプロパガンダだけは 1 人歩きしてるよね。もはや見苦しいレベル。 加えて外撤退の背景には中国社会の構造的な問題も絡んでる。高すぎる貯蓄率過剰な設備投資累積された債務どれを取っても健全な経済とは言えない。 [音楽] 結局1 人っこ作のけとか見せかけの成長をやりすぎた結果ってことよね。ごまかしきれなくなった瞬間全部崩れてくるのが早すぎた。 [音楽] 今回のシティグループの氷部門問題客つまり HSBC への管理業務の遺憾。これは単なる 1 企業の撤退劇じゃない。むしろ外全体が中国市場から静かにしかし確実に引き上げを始めている流れの祝図なんだよ。 なるほど。 死がやったことってただの撤退じゃなくて山の一角ってことね。他の企業も同じルートを辿どってるとしたら結構ゾっとする。 その通り。そして実は HSBC ですらその撤退の引き継ぎ役になった後で結局似たような不強に直面してる。つまりから事業を引き取ったはいいけど儲かるどころか重になってる可能性が高い。 ああ、それって倒産寸前の店を買い取って立て直そうとしたら自分まで友倒れってやつ。 典型的な負の連鎖じゃん。 ここでポイントなのはこれが単なる経済的な意思決定ではなく知学的な背景を含んだ判断であるってこと。指の撤退は米中金融のデカップリングつまり切り離手とも受け取れる。 [音楽] ってことはアメリカが本気でもう中国とは金融的につがらないって路線を強化してる証拠ってこと?まるで経済戦争じゃん。 実際2025年に入ってからアメリカは 中国に対して段階的に関税を強化している 。特に狙い打ちされてるのが反動体AI 関連そして太陽光発電パネルの上流工程。 この辺りは軍事用の可能性があるとして 輸出だけでなく投資も規制対象に含まれ てるってことは資本が入るも技術が出て いくルートも同時に締め上げてるってわけ 。もうほとんどホイ毛じゃん。 加えてアメリカではCFIUS 外国投資委員会という期間が中国とのあらゆる投資買収案件を事前審査するようになっていて、 2025 年からはそれが高級措置として制度化された。 え、それってつまり中国企業がアメリカでなんか買おうとしてもほぼ全部ブロックされるってこと?まさに鉄壁すぎる。 しかもこれは米中だけの話じゃない。カナダは 2024年の時点で中国 EVに対して100% の関税を貸すと発表済み。 しかもアルミア鉄鉱といった機関素材にまで制裁が拡大してる。 もう完全に中国は排除しますっていう空気が西側全体で固まってきてるわけね。環境同向こ言ってたのどこの国よ。 ヨーロッパも動いてる。EUは2025 年に入り、中国電気自動車に対して最終的な反補助金完税を貸すと発表した。これは中国政府から過剰に補助金を受けて不当な競争をしていると判断された結果だ。 それ皮肉だよね。 事象脱機種だったはずの EV がまさか貿易戦争のヒ種になるとはやっぱ環境ビジネスって建前が多いわ。 こういった関税や規制の連発で中国に拠点を置いていた他国籍企業の生産モデルそのものが破綻しかけてる。以前は中国で作って欧米で売るが鉄板だったが今やそれが完全に通用しなくなってる。 ああ、それって輸出存モデルの周演ってやつ。どれだけ効率が良くても売れなきゃ意味ないもんね。 しかも地元中国政府も完全に知り滅烈な対応をしてる。一方で外国資本を呼び戻したいと言って税優遇や規制緩和を打ち出してるんだけど、もう片方では治安維持名目での企業監視を強化している。 いや、それって投資家からしたら入ってこい。でも自由はないぞって言われてるようなもんじゃん。誰がそんなとこ行くのよ。 実際に内部文書では公案当局が外国企業の社員の行動をモニタリングしていることが明らかになっていて、特に幹部クラスには GPS 付きの専用形態端末を強制させる事例も報告されている。 もうそれってビジネスの世界じゃなくてスパイ映画の領域じゃん。自由経済の川をかぶった監視国家って本当にシャれにならない。 だからこういう多想的なリスクが重なって今や中国でのビジネスは利益を取るか安全を取るかの 2 択にまでなってる。もう昔の成長率が高いから進出しようって時代じゃない。 結局リターンが見合わなければ投資は止まるし用が崩れれば資本も逃げ出す。それが今まさに起きてるってことだよね。 さてここからさらに重要な視点を掘り下げていくよ。今回のシティグループの撤退って単なるビジネス判断じゃないんだ。 背後には知性学的な動き、つまり政治的な駆け引きが色濃く影響してる。 え、それってつまりさ、銀行が経済の問題だけじゃなくて国家同士の争いに巻き込まれてるってこと?それ企業にとっても普通に地獄じゃない? まさにその通り。例えばアメリカでは 2025 年以降中国からの特定分野への輸入に対して完税を段階的に引き上げてる反道体や太陽光パネルの原材料なんかが代表例で完税率は一部で最大 [音楽] 100%長に跳ね上がってる。 はいはいま太陽光をパネルか。中国っていつも補助金ジャブジャブで環境ビジネスごっこしてるけど結果として世界中の産業つしにかかってるよね。もうそれ緑の侵略じゃない。 [音楽] その感覚正しいかも。 で、当然だけどアメリカも黙ってない。 2025 年からは外国投資審査メカニズムが高級化されて、中国企業による米企業の買収や死には事前承認が必須になった。 それまるっきりブロックじゃん。もう実質的に中国排除モード全開って感じね。じゃあ中国から見たらどうなってるの? ここがまた複雑なんだ。表向きは外関係と言ってるけど裏では厳しい規制をどんどん増やしてる。 2023 年にはハンスパイ法が改正されて、国家安全保障の範囲が無限に拡大された わ。国家安全保障って何でもありなの?例えば外国人がビジネス調査してもスパイ扱いってこと?なんかもうファンタジー国家だね。 実際にそうなってる。 2023 年にはアメリカ系の調査会社民ツグループの北京オフィスが襲撃されて地元スタッフが拘速された。 他にもベインカンパニーやキャップビジョンなんかも統計調査や情報収集で当局のターゲットになってる。 企業が調査しただけで警察に連行。それも経済活動をしてはいけませんって言ってるようなもんでしょ。怖すぎ。 その結果として今中国で活動してる外景企業は情報収集すらできなくなってる。市場調査もダめ。銃リジェンスも罰金対象。これじゃ経営判断なんて下せるわけがない。 [音楽] まさに見えない手錠ってやつだね。で、そのくせ外しに投資して欲しいとか都合良すぎて笑える。いや、笑えないけど。 [音楽] さらに悪いのはデータセキュリティ法と個人情報保護法のコンボ。これがまた地雷で海外にデータを送るには複雑な証人手続きが必要。しかも審査はいつ終わるかわからない。 え、例えば社員の給与売上情報をアメリカ本社に送るだけでも審査対象、もはや分断の時代って感じだわ。 [音楽] 実際それが原因でグローバルに展開してた企業の多くが中国での業務を完結させろという圧力を受けてる。しかもそれは暗黙の了解じゃなくて事実上の命令なんだ。 外式量ってもう完全に壁の中に閉じ込められてるね。それってまるで経済的な看韓国って感じ だからシティグループのユニオンペ体って単なる銀行の判断では片付けられないんだ。 中国の金融セクターが国際的な信頼を失いかけてる象徴的な事件なんだよ。 しかもユニオンペって海外の ATM とかでも普通に見かける巨大ブランドだよね。そこからアメリカ資本が消えるってやっぱり異常事態だよ。 ユニオンペイは中国産銀行をはめとする国有銀行の連合隊で世界 183 カ国以上で使える決済ネットワークだけどその中でアメリカのメガバンクが消えたってことはいわば西川資本の脱出なんだ。 [音楽] それってさ、もはや撤退じゃなくて退避でしょ?中国市場が戦場みたいな危険地帯って証拠だよね。もう誰も残りたくないんじゃない? [音楽] よし、さっきの流れを踏まえてさらに踏み込んだ話をするよ。 ユニオンペイの本質ってのは単なる決済ネットワークじゃなくて中国が国際金融の主導権を握ろうとする国家戦略の象徴だったんだ。 え、ちょっと待って。つまりあれって銀カードって名前だけど裏では中国の国際的野望の最前線ってこと?なんかただの ATMカードじゃなかったのね。 そうなんだ。2000 年代初島に始まったユニオンペイの構想は最初は中国内の銀行カードネットワークを統合するっていうインフラ整備が目的だった。でもそれだけじゃ終わらなかった。 ふん。国内向けだったはずの仕組みがつの間にか海外展開の野望に変わってたってわけね。なんかありがちなパターンかも。 その通り。ユニオンペはその後急速にグローバルネットワーク化に火事を切って目標は明確に中国版のビザマスターカードを作ることだったんだ。 その結果2024年時点で180 以上の国と地域で利用可能にまで成長してる。 180 カ国って数字だけ見たら確かにすごいけどそれって使える場所が多いってだけで信用されてるとは限らないよね。しかも誰が信頼してるかって超重要じゃない。 そこがポイント。国際市場での信頼性を高めるには単に加盟点を増やすだけじゃ足りない。 だからこそ中国政府はユニオンペに外国銀行を参加させて国際イを演出したんだ。 え、それって外国のメガバンクを信用の人形みたいに使ってたってこと?表向きはグローバル企業連合みたいな顔してさ。 言い方はきついけどほぼ合ってる。例えばアメリカのシティグループ、イギリスの HSBC ドイツ銀行なんかは単なる金融参加者というより信頼の保証人という意味合いも大きかった。 でもそのうちの一者死が撤退したって話よね。それ見た目以上にでかい損失なんじゃない? [音楽] うん。かなり深刻というのもこれは単に 1 つの銀行が抜けたって話じゃなくユニオンペイの国際的信頼の柱が 1 本崩れたってことだから。しかもそれは自然な市場競争の結果じゃない。 つまり政治的リスクが原因ってわけね。自由な撤退じゃなく逃げざるを得なかったって話に聞こえるよ。 実際第3 者の金融アナリストもこう指摘してるよ。 外し系金融期間は透明性、貸性、余可能性のある環境を必要とします。中国の規制環境はそのまま逆です。 なんかもうここにいてはいけませんって言われてるようなもんじゃん。 しかもその後に残るのが中国遊銀行だけっていうのがまた非肉。 実際現在のユニオンペの構成を見てもメンバーはほぼ全員が中国の国有銀行かそれに近い企業隊ばかりになってる。 しかもそのグループ内の相互監視やも年々強まってる。 それって昔のソ連の国営器用グループと何が違うの?なんか多様性ゼって感じしかしない。 [音楽] さらに問題なのはこういう閉鎖的な構造ではグローバル品質外示できないってことなんだ。例えば海外でクレームが発生しても現地の対応ができず信用がじわじわ削られる。 確かにトラブル時にローカル対応できない決済会社なんて普通の人から見たら使えないで終わりだよね。 カードは便利さと信用が命なのに。 それに加えて規制の面でも矛盾がある。中国政府和表では経済の解放性を拡大するって言ってるけど実際には外国企業への圧力や制限が年々厳しくなってる。 え、それって解放しますと言いながら裏ではでもお前らは黙って従えって言ってるようなもんじゃん。完全に 2枚自じゃない。 まさにそう。2023 年以降北京や海の金融権では外国銀行の新規センス得が事実上停止されてる。そればかりか既の業務にも見えない圧力が強まってる。 でもニュースでは外流地に力を入れるって報道されてたよ。なんで実態は逆なんだろう。 [音楽] 実際地方政府の発表と中央政府の方針が理してる場合もあるし、統一的な政策が存在しないのも問題。 結果的に現場ではリスク回避のための自鉄撤退が進んでる。 それじゃあユニオンペの海外進出なんて夢のままた夢だよね。だって土台がどんどん崩れていってるわけでしょ。 その通り。そしてこれは単なるカードネットワークの話にとまらず中国への外国直接投資 FDI全体に冷や水を浴びせてる。 2024年には前年費でFDIが約15% も減少してるんだ。15% もそれって相当やばいよ。 つまりみんなもう中国にはかけられないって思ってる証拠じゃん。 さっきの話を踏まえると中国経済って一見回復策を打ってるように見えて実は逆の動きも同時に進んでるのが怖いところなんだ。例えば株式市場を盛り上げようとしてる一方で外国資本は着々と撤退してるんだよな。 [音楽] え、それってアクセル踏みながらサイドブレーキ引いてるみたいなもんじゃない?制作が矛盾してたらそり返しも不安になるでしょ。 まさにそれ。 しかもその矛盾の象徴みたいなのがシティグループの撤退なんだよ。実は 2021年に指ティはすでに世界の14 市場から消費者向け業務を撤退するって発表してて、中国もその対象の 1つだったんだ。 ってことは中国だけの問題じゃなくて川にも選んでる意図があったってことか。でもなんで中国は切られたの? それにはいくつか要因があるけどまず国有銀行の存在がでかい。 ICBCとかCCB みたいな巨大氷銀行が幅を効かせてるから外にとっては市場産入のハードルが異様に高いんだよ。確かに国ぐるみで地元引きされたら外は勝ちめないよね。しかもただでさえ規制も多そうだし。 その通り規制面では特にデータローカライゼーションが重たくの仕掛かってる。つまり外国企業でも中国人顧客のデータは中国内で保管しろってやつ。これがインフラコストを大きく跳ね上げてる。 [音楽] ああ、それって情報統制の一環でもあるでしょ。もう時絡めじゃん。 さらに厄介なのがマネーロンダリング規制とか消費者保護制度。もちろん名目上は安全のためなんだけど、実際我会社にとって足かせにしかなってない。運用コストが念々膨れ上がってる。 え、それって普通に考えたら追い出したいってサインじゃない?こんなに障害物だらけならよっぽどのことがないと残らないよ。 そう。 それに加えて中国の消費者がクレジットカードよりもモバイル決済ばっかり使ってるのも大きなポイント。 WチャットPayとかIPAY が圧倒的でカード会社の主力商品が通用しない市場なんだ。 なるほど。てことは分割払いとかリボ払いとかそういうアメリカ式のサービスが刺さらないってことか。文化も違うしモデル自体が噛み合ってないのね。 それだけじゃなくて物理的な視点毛の拡大も難しい。 中国って土時代や人権費が上がってて、しかも出点には政府の許可や監視がついて回る。全体的に投資回収までが長期化する。 長期投資って安定しててこの話でしょ。規制がコロコロ変わる国でそれはリスキーすぎるよ。しかも利益率も低いとなればうん。撤の判断も納得かも。 その点はシンガポールやロンドン、香港、 UAE といった他の都市ではプレゼンスを維持してる。 どこも共通してるのがオフショ足本プールが豊富で税が有利ってこと。 うわ、それ逆じゃん。つまり金持ちが集まりやすくて国が邪魔してこない場所ってことでしょ。そりゃ中国なんて選ばないわけだ。 そして忘れちゃいけないのがこうした動きが外国直接通しわゆる FDI の輸入に冷やみ水を浴びせてるってこと。ユニオンペイからの撤退金融量の縮小全部が外しの投避シグナルになってる。 FDI が減るってことは結局は技術も雇用もノハウも入ってこなくなるってことでしょ。見かけの経済成長だけ追いかけて土台がボロボロじゃ本末点灯すぎる。 しかも世界銀行は中国の成長率が 2026年には4% まで落ちるって予測してる。実はこの数字 1990 年代のバブル崩壊後の日本とかなり似てるんだ。 うわ、日本の失われた 30 年みたいな未来が中国にも来るってこと?それさすがにやばすぎじゃない?日本よりも人工いのに。 人工現象と少子高齢化。そして不動産バブルの崩壊まで重なってるからね。これは単なる成長のど化じゃなくて構造的な転換機に入ったって見た方がいい。 経済の構造が変わるって一気にドミノ倒しになるよね。 器用が撤退からの雇用が減るからの消費が冷えるからのケーキ交代みたいな流れで その連鎖を止めるに我がしの呼び戻しが不可欠なんだけどその鍵を握るシティア JP モルガンバークレーズといった大手はすでに中国離れを加速させてる。ユニオンペー撤退はその象徴の 1つなんだ。 皮肉な話だよね。 国際ブランドを作ろうとして始めたユニオンペイが今じゃ国際じゃなくて国内向け専用期間になりつつあるなんて膨らませた風船が絞でくみたい。 今回の重要な転換点はシティグループが中国の個人向けサービスを切り捨てたことで完全に期間投資か企業向けに軸足を移したことなんだ。それもただの企業相手の営業じゃなくて高度な金融に特化してる。 ふん。 つまりお金持ち専用ってこと?個人相手はもう用済みだから国際的な大企業だけを相手にしていくって感じなのね。なんか冷たい気もするけどビジネスとしては合理的か? その通り。実際シティは今グローバルに展開するプライベートバンキングモデルの中核をシンガポールやアラブ市長国連邦ロンドンといった金融ハブに置いてる。これらの都市は規制も透明で税優遇もあるから資金が集まりやすい。 なるほど。 それって日本で言うなら昔のバブル機の東京みたいな感じかな。金が金を呼ぶ環境ってやっぱり大企業には魅力的だもんね。 まさにそれ。例えば外国かわせの取引やキャッシュマネジメント、いわゆる資金の最適化サービスってやつ。企業は売上や支出を世界中に分散してるからそれを効率よく回すための金融技術が求められるんだ。 あ、それって輸出入やってる企業が通貨の変動で損しないように調整するやつ。 日本の照者とかも使ってそう。 そうそう。あと貿易金融ってのもある。これは商品を輸出入する企業に対して信用を使って資金繰りを支援するサービス。銀行が間に入ることでリスクを減らして取引を成立させるんだ。 兵から個人が口座解説して預金してっていう世界とは全然違うね。銀行って本気出すと企業の生命みたいなことまでやってんだ。 [音楽] さらにしてはグローバルカストディっていう資産管理サービスも強化してる。 これは機関投資家が保有する株式や債権などの金融資産を安全に保管し、利息や配当の受け取りまで代行する仕組み。 なんか金持ちがもっと金持ちになる仕組みが全部揃ってるって感じね。しかもそれをやるのに中国は向いてないって判断されたってことでしょ。 そこが1 番重要なポイントなんだ。中国の効理市場って規模はでかいけど効率が悪い。 銀行にしてみれば膨大な視点や人員を維持しなきゃならないし、しかも収益性が低い。 つまり数はいるけど儲からない客ってことか。なんかそれって地方のコンビニみたいな話ね。人件費だけかかって売上が追いつかないパターン。 その上ユニオンPayやwチャット Pay、アリペayのような国内税がすでに市場を抑えて害が入る余地が少ないんだ。国有銀行も国家からの支援を受けて今庫に支配してる。 でもそれって逆に言えば市場経済じゃなくて統制経済に近いってことじゃない。外国企業がまともに勝負できる土標じゃないよね。 そう。経済自由度が低いとどんなに市場規模があっても投資対象としての魅力は落ちる。それに国有銀行の巨大家はむしろ収益悪化を招いているというデータも出てる。 え、でかくなったら普通儲けも増えるんじゃないの?なんで逆に悪化するの? それは効率性の問題。 巨大化しすぎると意思決定が遅くなったり貸し倒れリスクが増えたりする。実際第 3 者中国の国有銀行は政策的な勇資が多く経済合理性よりも国策が優先される傾向があると継承を鳴らしている。 うわ、それって利益よりも政府の顔色重視ってこと?そり返しにしてみればやってられないわね。 [音楽] 一方でユニオンペイは国際展開をまだ諦めてないみたいだけど現実は厳しい。 アメリカ、欧州、日本などではすでにビザやマスターカードが圧倒的で新規入の壁が高すぎる。 そういえば銀カードって日本でも一部の店しか使えないよね。なんか存在感が薄いなとは思ってたけどやっぱ世界的には苦戦してるのか。 加えて米中体率の影響も大きい。デジタル決済や金融インフラって今や国家安全保障の一部と見なされていて政治的な圧力がかかりやすい。 結果的にユニオンペイが海外で制限される事例も増えてる。 経済だけじゃなくて政治も絡むとなるともう戦場だね。銀行の話してたはずなのにまるで外交戦争みたい。 その通り。だからこそシティグループは戦場ではなく中立地帯で稼げる市場に集中してる。これは単なるじゃなくてリスクを最小化して収益性を最大化する戦略的再配置なんだよ。 なるほど。 ただの逃げじゃなくて戦わずして勝つってやつか。やっぱ死に偽の師は生き残り方をよく知ってるんだね。 今回の話の肝はここからだよ。グループが氷務を畳んだ背景には人民の国際家が進んでいないという根本的な問題が横たわってるんだ。 [音楽] ああ、人民ってよく将来はどにって変わるかもって言われてたけど結局それってただの夢物語だったってこと? 現時点ではまさにその通り人民を国際通貨にするには外国人投資家が積極的に人民立て資産を保有したくなる環境が必要なんだけどそれが全く整ってない。中国経済の原則に加えて資本規制も依然として厳しい。 つまり持ってても使いづらいし金もしにくいし買える商品も限られてるってことか。そりゃドルやユロの方がよっぽど安心だよね。 それだけじゃなくせの透明性が一しくかけてる。人民の例とは市場原理で決まるというより中国人民銀行が毎日発表する基準地に依存してる。 これって実質的にコントロールされてるってこと? え、じゃあ好きなタイミングで好きなレートに動かせるってこと?それってもう通過操作じゃないの? その疑いは常にある。実際米国は何度も中国を買わせ捜査国としてなししてきたし、人民を通過バスケットに入れた。国際通貨基金 IMF でさえ実に基づいた透明な市場形成が課題と認めてるんだ。 なんか表向きだけ綺麗に見せようとしてるけど実際には中身スカスカな感じだね。にも中国らしい巨制って感じ。 それに加えて外が中国市場から撤退するもう 1 つの理由が規制の強化なんだ。例えばデータ管理法や国家安全法のように曖昧な基準で外国企業にプレッシャーをかける制度が増してる。 確かにちょっとでも情報漏洩が疑われたら栄養停止とか罰金とかどこまでが違法でどこまでが合法かわかんないって話はよく聞くよね。まるで地雷源現の上でビジネスしてるようなもん。 [音楽] そうなんだ。結果外国企業はホームコンプライアンスのコストが爆発的に上がる。それで見返りとなる利益が小さいならそ撤退する方が合理的ってことになる。 まさに割に合わないってやつだ。 しかもそういう撤退が一社だけなら、まだしも今後連鎖的に続くって予想されてるんでしょ。 その通り。実際に第 3 者これからは外資銀行にとって氷部門はリスク資産と見なされるようになるだろうと予測してる金融アナリストもいる。これってもう市場そのものの信用が落ち始めてる証拠だよ。 [音楽] え、それって中国離れが金融の分野にまで広がるってことじゃん。 これまで製造用量やIT 企業の話だと思ってたけど銀行もか。 そしてもう1 つ重要なのがクロスボーダー決済。つまり国境を超えた資金決済の安定性。これが今中国では致名的に弱い。結局人民は使える範囲が限られてるしかせリスクが高すぎるから。 じゃあシティが中国市場を捨ててシンガポール宿に集中したのって安定した通過県に軸足を置きたかったからってこと? [音楽] まさにそう。しかもそれらの地域は AB米法ベースにしていて金融規制も透明。さらに外に対してもオープンだから企業側としては予測可能性が高いんだよ。 [音楽] それってまるで勝ち組と負け組の通過戦争みたいな構図になってきてない?人民は集回遅れでどんどん孤立してるように見える。 それも否定できない。加えて中国が構築してる CPS っていう人民現の国際送金システムもまだまだ利用率は低い。 スイフトの代替を狙ってるけど圧倒的なシェアさは埋まってない。 え、CPS ってなんか聞いたことあるけど世界中で使えるの?っていうか使ってる国って実際どれくらいあるの? 登録銀行は世界で100 両以上あるけど実際に日常的な取引に使ってる国は限られてる。大半が中国と関係の深い国だけ。アメリカや日本欧州主要国ではほぼ無視されてる。 結局 いくら地前のインフラを作っても他国に信用されなきゃ意味がないってことね。それってもう完全に袋工事じゃん。 だからこそ指だけじゃなくて他の他国籍金融も今後同じ決断を迫られる可能性が高い。今後の商点は残るか撤退するかじゃなくて逃げ切るかに移ってきてる。 うわ、その言い方ちょっと怖いけど納得しちゃったわ。 中国史場ってもはや成長じゃなくて脱出ゲームの舞台になってるんじゃない? ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。 [音楽] う 。
「ニュースはゆっくりと更新されます」へようこそ!当チャンネルは、特に中国の経済、社会、そして「報道されない」または隠された問題に関する出来事やニュースを分析し、報道することに特化しています。分かりやすい「ゆっくり解説」スタイルで、見過ごされがちな物語を深く掘り下げ、多角的な視点を提供し、国際社会からの反応をまとめています。私たちと一緒に、見出しの裏にある真実を探求し、世界をより深く理解しましょう!
#ゆっくり未報道JAPAN, #未報道JAPAN, #ゆっくり解説, #海外の反応, #中国経済, #中国崩壊, #中国問題, #時事問題, #国際情勢, #社会問題, #未公開情報, #ニュース解説