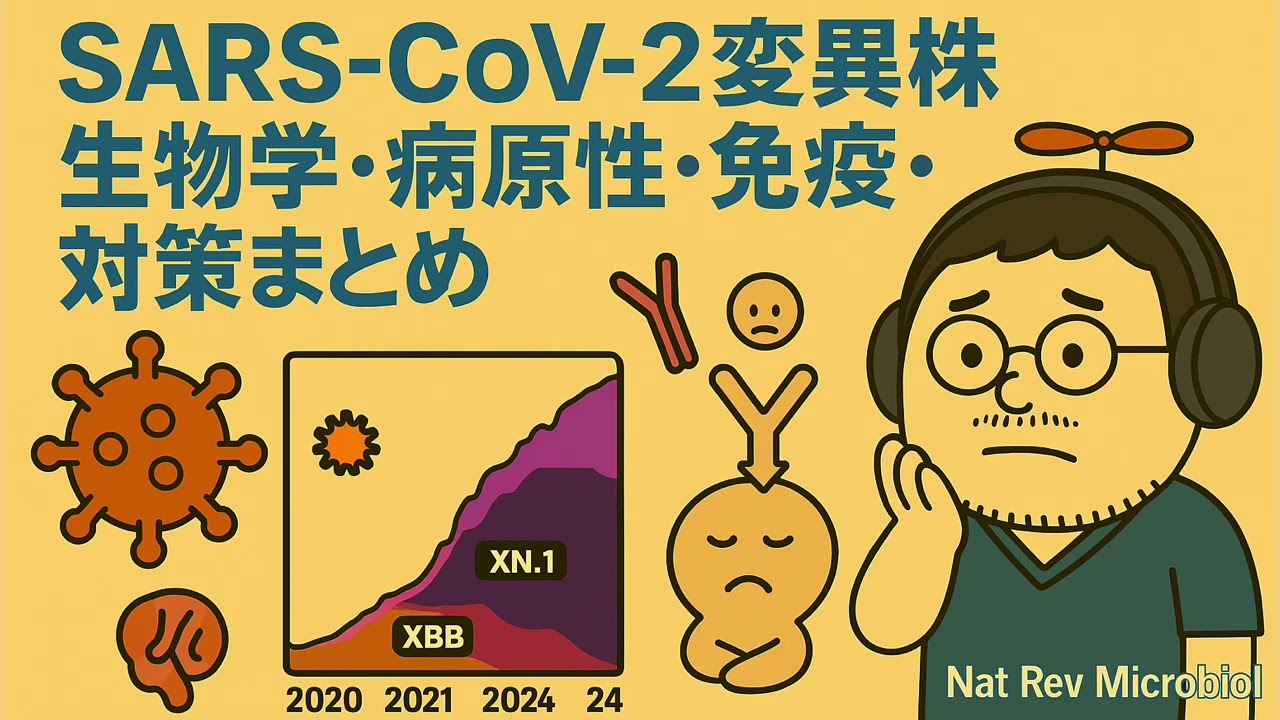新型コロナウイルス変異株:微生物学・病原性・免疫 Nat Rev Microbiol
皆さん、こんにちは。クオレディオです。 こんにちは。 この番組は複雑に入り組んだ感染症領域に鋭いメスを入れ、様々な謎や疑問を徹底的に明するポドキャストです。 はい。 それでは皆さんご一緒にせの 靴オレディオ。靴オレディオ。 さて今回皆さんと一緒に深掘りしていくのはえっと 2019年末に登場してからもう 5年以上ですか? そうですね。もうそんなになりますね。 未だに僕たちの世界に影響を与え続けている新型コロナウイルスサーズ COV2です。 はい。 で、手元にですね、その進化の奇跡をまとめた、ま、かなり読み応えのある科学レビュー論文がありまして、 ええ、 このウイルスがこうどうやって次から次へと姿を変えて僕たちの免疫とかワクチンから逃れてきたのか。その巧妙なサバイバル戦略の裏側ですね。 はい。はい。 その生物学的な仕組みからじゃあ僕たちはこれからどうすればいいのっていう未来の話までじっくり見ていきたいと思います。はい。 では早速なんですけどこの論文を読んでまずあなるほどなと思ったのがウイルスの進化を突き動かしている 2つの力という考え方で、 ええ、 これはつまり感染力を強くしたいっていう力とあとは免疫から逃げたいっていうこの 2つがあるってことですよね。まさにその 2つの力の、ま、攻めぎ合いがこの 5 年間のウイルスの歴史そのものなんですよ。 ほうほう。 考えてみればパンデミックの本当に初期ってウイルスにとって 1 番大事だったのはとにかく効率よく人から人へ感染を広げることだった。 ああ、なるほど。 なぜなら当時僕たち人類は誰もこのウイルスに対する免疫を持ってなかったわけですから。 確かに。 言ってみればウイルスにとってはもう無防美な土地がどこまでも広がっているようなそんな状態だったわけです。 なるほど。だからわざわざ免疫から逃げる必要がまだなかったと。 そういうことです。だから初期の D614G っていう変異は純粋に人の細胞にくっつく能力を高めるそういうタイプのものでした。 はい。はい。 でもワクチン摂取が始まったり感染から回復する人が増えたりして状況はもうガラっと変わります。 ウイルスにとって僕たちの免疫が育手を妨げるこう巨大な壁として現れたわけです。 その壁を乗り越えるためにウイルスが取った次の戦略は何だったんですか?ここでいいわゆる懸念される変異株 VOCが出てきますよね。 ええ、特にβ株とかガ株で見られた 484K っていう変異。これが象徴的でしたね。 E484K。 これウイルスにとって最初の本格的な変装だったと言えるかもしれないです。 変装ですか? この変異を持つことでそれまでのワクチンとか感染で作られた交代がウイルスを認識しづらくなったんです。交代という名のま、警備員の目をごまかす匠な変装術を身につけた後。 なるほど。 ここがウイルスが感染力一変から免疫へと進化の火事を切り始めた大きなターニングポイントでしたね。 変装術ですか。すごく分かりやすいですね。でもその次に出てきたデルタカブは変装というよりもっとこう凶暴なイメージがありました。 ああ、そうですね。 とにかく感染力が桁違いだった。あの強さの秘密は一体何だったんでしょう? デルタカブの戦略は変装じゃなくて破壊力の強化でしたね。 ロンドンが指摘している P681Rっていう変異がその鍵です。 P681R。 これがですね、ウイルスの膜融合能を劇的に高めました。幕有融合能っていうのはウイルスが細胞に侵入する力、そして中で増えたウイルスが隣の細胞に乗り移っていく力のことです。 ほう、ほう。なるほど。 ちょっと車で例えるなら初期のウイルスが普通のファミリーカーだとしたらデルタカブは円も足回りも極限までチ運アップした F1マシン。 F1マシン。 ええ、細胞のドアをこじ開けるのも早いし、細胞から細胞へ移動するのも早い。この圧倒的なスピードとパワーで他の変株を全部周回遅れにしちゃったんです。 それは強烈ですね。 でも僕たちがこれで打ち止めかなんて思ってたら今度はオミクロン株が登場して世界中がまたひっくり返りました。 いや、あれは衝撃でしたね。 デルタ株とはまた全然違うタイプだったんですよね。 全く違いました。デルタが F1 マシンへのチーンアップだとすればオミクロンはもはやク空飛ぶ車の登場ぐらいのインパクトでしたね。 クートぶ車。 専門的には光原シフトと呼べるほどのもう劇的な変化です。 ウイルスの顔であるスパイクタンパク質にいきなり 30 個以上の変異を持って現れたんですから。 30 個以上?それはもう僕たちの免疫システムから見たら、え、誰です? そうなんですよ。誰ですかってなりますよね。 かってなりますよね。全くの別人に見えたわけだ。 まさに明の警備員たちが持ってた指名手配写真とはもはや似ても煮つかないかおつきになっていたんです。 はあ。 で、さらに面白かったのがその戦術の変化です。 論文によるとデルタ株までは主に TMPRS 2 っていう構酵素を使って肺の奥深つまり動で感染を広げるのが得意だった。 ええ、 ところが初期のオミクロン株はそれとは違うエンドソーム経路っていうルートを好んで鼻とか喉といった蒸気道で増えるようになったんです。 感染する場所を変えた。 なぜそんなことを? これが 巧妙なところで戦場を体の入り口である蒸気道に移したことで重症化のリスクは下がる傾向にあったんです。 ああ、なるほど。 弱らせてしまうより軽い症状で済ませてその分外で動き回ってもらってもっと多くの人にウイルスを広めてもらう。そういう薄り場戦略に切り替えたのかもしれない。 うわあ。 ウイルスの生存としては極めて合理的ですよね。 聞けば聞くほどしたかですね。 でもそんなにウイルスがコロコロと顔とか戦術を変えてくると僕たちの免疫も混乱しそうです。 ええ、そうですね。 論文にあった免疫インプリンティングという言葉が気になったんですが、これはどういう現象なんですか? ああ、これは僕たちの免疫が持つ記憶力の、ま、ちょっと厄介な側面の話ですね。 厄介な側面。 私たちの免疫システムって最初に戦った敵の顔をものすごく鮮明に記憶するんですよ。 はい。 例えば最初に打った武漢株ベースのワクチンですね。この最初の記憶がいば張り込みインプリンティングとして強く残る。 それ自体は良いことのように聞こえますけど。 良い面もあるんです。もちろん。でもその後におクロン株みたいな顔が全然違う新しい敵が来た時にちょっと問題が起きる。 はい。 免疫システムはよし、新しい敵用の武器を 1 から作るぞとはならずに、つい昔の記憶に頼って、確かこんな顔のやつにはこの武器が効いたはずだ。て、武漢株用の古い武器を引っ張り出してきちゃうんです。 えっと、じゃあおミクロン株体用のブースターワクチンを打っても体の中では部漢株用の交代もたくさん作られちゃってるということですか? そうなんです。実際に研究で示されています。これが一丁言ったんでしてね。 ほう。 良い点は古い武器が新しい敵にもそこそこ効くことがある。つまり交差反応性が生まれて防御が広がることです。 なるほど。 一方で新しい敵に 1 番よく聞く、ま、特攻薬的な交代が作られにくくなるという欠点。もしこの古い武器が全く通用しないようなとんでもない変異株が現れたら ああ、 この記憶力の良さが耐えて僕たちの弱点になりかねないと論文は継承を鳴らしています。 なるほど。記憶が良くも悪くも僕たちの体を縛ってしまう可能性があるわけですね。ではウイルスの今ってどうなってるんでしょう?進化はまだ続いてるんですか? はい。 残念ながら論文が書かれた時点ではオミクロン株の子孫である JN.1 系統が世界を接してさらにそこから KP53.1.1 とかXFG とか孫やひ孫子の世代が次々と生まれています。 はあ。 しかも最近のウイルスはまた新しい技を覚えてきてるんですよ。 新しい技? ええ、グリカンシールドという技です。 スパイクタンパク質の表面を塔の鎖でコーティングして交代の攻義から身を隠すんです。 身を隠す。 まるで工学迷彩をまとった透明マントみたいに T22NN っていう変異なんかがそれに当たるんですが変装したりアップしたりするだけじゃなく今度は姿を消す術まで身につけようとしてる。 透明マントまで 本当に進化の終わりは見えませんね。 もういちごっこというか SFの世界ですね。 それはそんな相手に僕たちはどうやって立ち向かっていけばいいんでしょうか?何か未来の戦略は? そこで論文が非常に有望なアプローチとしてあげているのが警備ワクチンです。 鼻から吸タイプのワクチンですか? その通りです。考えてみてください。ウイルスって鼻とか喉の粘膜から侵入してきますよね。 はい。 今の筋肉注射のワクチンはいわば敵が城の中に侵入してから戦うための城の変を増やすようなものなんです。 ああ、なるほど。 それに対して警備ワクチンはウイルスの入り口である年膜つまり白門そのものに兵士を配置する戦略です。 なるほど。玄関口でブロックする とまさに年膜には分泌型 IGA 交代というま、粘膜専門の交代がいるんですが、これを警備ワクチンで協力に誘導できればウイルスが体内に侵入すること自体を防げるかもしれない。 感染予防そのが期待できる。 ええ、これは今のワクチンでは難しいゲームチェンジとなりうるアプローチとして非常に期待されています。 それは希望が持てる話ですね。 ウイルスの進化の歴史から未来の戦略まで非常にクリアになりました。ただ最後に論文を読んでいて 1つずっしりと思いが心に残ったんです。 はい。 それは個人の治療と社会全体の安全という話です。 ああ、免疫付不全の患者さんの治療に関する部分ですね。これは非常にデリケートで重要な問題です。 ええ、免疫の働きが弱い患者さんがコロナに感染するとウイルスが体内で長期間増え続けることがあるんですね。で、その患者さんを救うために高ウイルス薬を長く投与するんですが はい。 その間にウイルスが役から逃れる術を学習して薬剤体制を獲得してしまうことがあるんです。 つまり1 人の患者さんを救うための最善の医療が結果として社会全体を脅かす可能性のある新しい体制ウイルスを生み出すゆり加護になってしまう可能性があるということですよね。 そういうことです。目の前の命を救いたいという医療の使命と将来の未知の脅威から社会全体を守りたいという公衆衛生の使命。この 2つがここでは衝突する可能性がある。 うん。 どちらが絶対的に正しいという簡単な答えはありません。 個人の命を救う医療と社会全体を感染症から守る公衆衛生。この 2 つの時に反するかの知れない価値のバランスを僕たちの社会はこれからどう取っていくべきなのか。 ええ、これはウイルスが僕たちに突きつけている生物学を超えた非常に思いだと思います。是非皆さんも一度考えてみていただければと思います。 そうですね。 大阪医学部付属病院感染症内科ではフェローそして大学院生を激しく募集しています。 都え、大阪大学へ お待ちしています。
元の論文
SARS-CoV-2 Variants: Biology, Pathogenicity, Immunity and Control
Citation
Uraki R, Korber B, Diamond MS, Kawaoka Y. Nat Rev Microbiol. 2025; published online Nov 2025. doi:10.1038/s41579-025-01255-x.
要約
本総説は、SARS-CoV-2の進化、生物学的特性、病原性、免疫逃避、そしてワクチン戦略の最前線を包括的に整理している。2019年の出現以来、ウイルスは感染性と免疫逃避のバランスを保ちながら進化し、アルファ、デルタ、オミクロンなどの主要変異株を経て、2025年現在はJN.1系統から派生したXFG、NB.1.8.1などが主流となっている。これらの新系統はACE2結合能を高めつつ免疫回避を強化しており、特にL455S/F456L変異が鍵である。オミクロン株以降はTMPRSS2依存性が低下し、上気道感染への適応とともに病原性は低下したが、感染力は維持された。臨床的には、重症化率は低いものの、免疫低下者や高齢者では依然として重篤化リスクが残る。ワクチンはJN.1またはKP.2株を抗原とする単価型が推奨され、免疫刷り込み(original antigenic sin)が変異対応ワクチンの効果を制限する可能性が示唆された。今後は、経鼻型ワクチンやT細胞免疫誘導型ワクチンの開発が課題であり、長期的にはインフルエンザと同様に定期的な株更新と予測モデルに基づく抗原選定が必要とされると結論づけている。
大阪大学大学院医学系研究科 感染制御学講座では
・感染症専門家の育成
・感染症研究
・正しい感染症情報の発信
・医療機関や高齢者施設などへの感染対策支援
のためにご寄付をお願いしております。
ご寄付は以下のHPよりお申し込みいただけます。
https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/hp-infect/donation