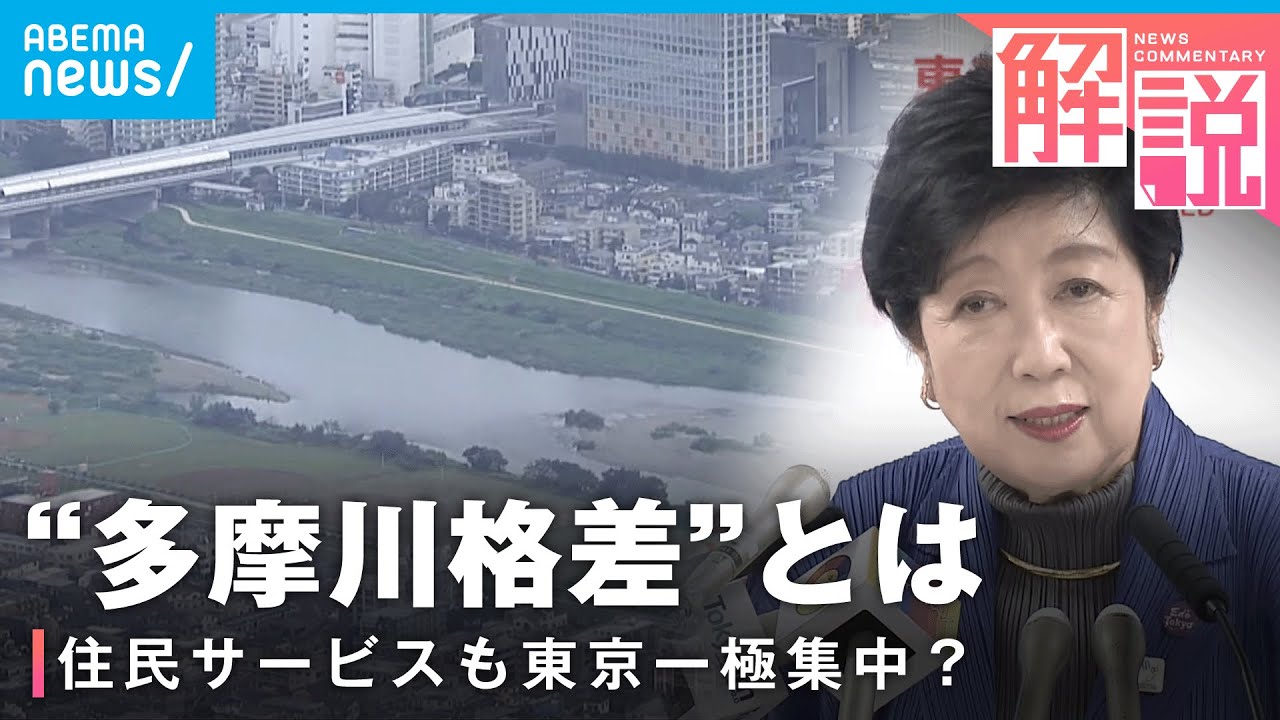【記者解説】東京はお金が余っている?“多摩川格差”が生まれるワケは…神奈川・千葉・埼玉知事ら怒り|経済部 佐藤美妃記者
今日は玉川格差という言葉について考えて いきたいと思います。 ま、近年人口が増え続けている東京、そしてその隣にある神奈川県の間を流れているのが玉摩川なんですけれども、この神奈川県と東京の間で格差が生まれているのではないか、玉摩川を隔立てて格差が生まれているのではないかという現象をさす言葉がこの玉摩川格差なんですけれども、この言葉から東京 1 局集中のことでしたり、また地方格差の辺りを考えていきたいなという風に思います。え、テレビ朝経済部の佐藤記者に話を伺ってきます。佐藤さんよろしくお願いします。 よろしくお願いします。お願いします。 いきなりなんですけど、私その東京から川を 1個隔立てた川崎市出身なんですね。 で、 言うてみれば玉摩川格差っていうのは昔からありました。 はい。 もう それもずっと感じて生きてはきましたけど、もう近年よく聞くワードだなってすごくよく聞くようになったっていうのでやっぱり 実際にこう感じてる人は うん。 いるんですよね。 うん。そうですよね。うん。 切実に感じてる人がいます。 そうですね。 あの、特に最近ですね、東京都がやっている様々な政策っていうのがありまして、これが多分その格を感じやすくなってる、ま、 1 つの要因かなというのがあります。ちょっと一例を見てみますね。 え、ま、主に子育て世帯への支援が多いんですけれども、例えば東京都ですと保育ですね、 1 人目のお子さんから保育量が無償化されていますし、あとは学校給食、ま、これ公立の小中学校ですけれども、え、学校給食費が無償になっていますし、あとは私立、私立の高校の授業、こちらも実質無償化 で、これもうほとんどあの所得制限もなく、ま、どんなに高所得の世帯でも受けられる うん。そうですけの水道の基本料金この夏無償化されていましたしあとは小エネのエアコンなどを購入すればこの支援っていうのも受けられます。ま、これ全部やってるのが東京と いうところで、ま、この辺りが都民が恵まれてるんじゃないかというのが都民の方以外は の方はやっぱりちょっと感じるみたいですね。例えば同じクラスにあのお子さんが行った行ってる。 きいますので、ま、この辺たりがこう玉摩川と言われるようになった遊縁ですね。 立高校では確かに東京やろんなところから集まってるわけですよね。その中でも負担が違う人がいると。 うん。はい。 同じ授業を受けていても、あの、住んでるところで、ま、何十万円も差が出てくるっていうところがやはりこう感じてしまいますし、ま、実際その川崎市の、え、議会の中ではこの問題あの議論されていまして、え、一主市議がこの議会の中で証言されてるんですけれども、例えばですね、年収 600万円から700 万円の世帯でお子さんがお 2人いる場合、0歳から2 歳までにかかるあの費用っていうのが保育利用量と ううん。 えっと、 そうですね、えっと0歳から2 歳までの保育利用量と、え、効率小中学校の給食費、え、これがかかってきますと 385万円の費をなりますね。 で、これが東京都であるとこの辺り全部無償化されているので 0円とでさらにですね 018 サポートというのが始まっていて、これも所得制限なしでもらえるんですけれども 0歳から18歳まで子供お子さん 1人当たり月5000円。 ま、1年間にすると6 万円もらえますので、ま、子供 2人で計200 万円もらえるということで、あの、議会の中で話があったと。 うん。 でもこれやっぱり不幸感は感じますよね。 そうですよね。ま、このね、実際に子供 2 人を育てた場合っていう、ま、ケースではありますけれども、川崎氏だとこのね、この表だけだと、ま、出ていくものがあって、で、東京都はもらえるものがあるという、この、ここの差はどうしても感じてしまう部分があって、ただこの格差についてはこれ神奈川だけじゃないですよね。これ 東京の周りの都道府県はやっぱり感じる部分っていうのはありますよね。 そうですね。 体でもそれぞれのサービスだけを見るとやってるところは実際あるんです。 うん。 でもそれを全部受けられるのが東京都だけていうところで言うとやはり格差は感じますし、ま、ただ一方で、私東京都民なんですけども、ま、東京都に住んでると、ま、家賃も高いですし、ま、物価も全体的に、ま、スーパー行っても野菜の値段 1 つ取っても高いというところを考えると、ま、ト民からすれば、あの、出てくお金も多いんだから、ま、もらえるものがあってもというのはあるんですが、ま、これもまたトの中でも差が実はあるなという風に感じう ていて、ま、私は子供がいない家なので、あの、そういう過程だとこういう子育て世帯向けの支援っていうのは特にないですし、ま、そうなるとそのもらえる人、もらえない人っていうのは、ま、東京都の中でも、ま、あるなっていうのはちょっとありますけれども、確かに。でもこれ見てるとやっぱりお子さんがいる人たちに感じるその格差のことをすごく感じるかなと思うんですけど、やっぱりその自分の暮らし方によってね、感じ方も違うんでしょうね。 でも、あの、私この夏、あの、その電気屋さんでね、 エアコンの補助っていうのを見た時にト民って書いてあった時にああ、東京だけなんだなってすごい思ったんですよね。 ま、これも精度の問題という部分もあって、 なんかそういう差でやっぱり、ま、子供がいなくても うん。 あ、さ、差はあるんだって、格差はあるんだってのは切実に感じました。 あ、そうですね。 なんか実際、ま、あの、東京都に住んでると何がこう私たちだけが受けられるサービスで何がそれ以外のあの方を受けられないかっていうのが分からないので、ま、意外と感じてないこともたくさんあると思うんですけど、でも、ま、やっぱりこの東京都とそれ以外の周囲の件ですね、千葉、神奈川、埼玉、この辺りの、え、ま、周辺の件で今すごくこの差が問題になっています。うん。うん。 これに関して、ま、千葉県、そして神奈川県、埼玉県の知事がですね、ま、それぞれこういう風なコメントをしているということで、ちょっとご覧いただきたいと思います。都会ですね、え、住民サービスに大きな差が、あ、さらに集してるという状況になります。 え、さらにですね、あの、医療、介護、 保育、ま、こうした形で人材を確保する ために東京都産がですね、え、今年度だけ でも1100億円予算を計上しておりまし て、まさに、え、それぞれの地域が育てて いる人材を、え、東京都が全部こう抜いて いく、ま、そういう状況になってきており ます。 東京都は金が余ってしょうがないように 見えちゃうですね。これ東京都がやってる ことについてクレームをつけてるわけで ございません。東京はそれができるだけで の財源があるということですね。明らかに 東京都だけは特別だということ。ま、これ を今日今回はアピールさせていただきまし た。昨年から今年にかけてのこの1年で 考えると2つの大きな変化があったのかな と思っているのは1つはあのイコマンスの 進展であります。あの、インコマスについ ては、多く進展していますけれども、え、 その多くは例えば埼玉や神奈、え、使って 買ってもですね、本社の東京に税金が 落ちるこそういった傾向がます進展してい て、東京だけに集中する。 ま、この神奈川、千葉、埼玉の知事がです ね、ま、こういうことを話てるわけです けども、佐藤さん、これどういう風に見 ましたか?そうですね、これすごく慰例の ことなんですね。 これあの総務大臣のとに産の知事が申し入れに来たんですけれども、ま、そもそも知事ってめちゃくちゃ忙しいのでその 3 人が日程を合わせるというのはかなり大変だったと聞いています。で、そこまでしてなぜ来たのかっていうところなんですけれども、ま、背景にあるのがこれまでその東京都の 1 人勝がちっていうのは元々ですね、知事会で、ま、そもそもあの問題にはなっていたんですよね。 うん。 で、ただこうどう見えてるかと首都とそれ以外いう感じで、ま、どちらかというと千葉、埼玉、神奈川東京よりと うん。 いうに、ま、言われてきたんですけれども、ただここ何年かですね、先ほど申し上げましたように、東京都でそのお金を配るようなサービス、ま、て世帯向けのサービスが充実してきたというところで、ま、それぞれの県微の方からですね、どうしてうちではできないんだと、ま、知事としては付き上げを食らうわけなんですよね。 で、ま、そういったところでやっぱりこう各自治体隣の、ま、県といえどもやっぱりそこの差が如実になってきたというところで今回あの慰例の申しれになったと。 あ、ですから知事会の中では元々は首都首都権他の地方っていう構図があったけれども今はと東京 vs そのね、周りの件がちょっとこう地方よりの考えという風な立場になってきたという部分もあるということですね。 そうですね。この3 つの件からすればもっとちゃんと見てってことですよね。 そうですね。あの首都権で括らないで全然東京とうちは違うよっていうことをしかもこれ 3 人が並んでいうことでまたちょっとこれ意味がね重くなってきますよね。 そうですね。 やっぱりその隣だからこそ隣合ってるからこそ普段のこう接する機会もあの住民同士も多いですからそこの差がどうしても目立ちやすいていうところがま、今回の申し入れにつがったと思うんですけどもこれ実際ですねお金っていうところもその今ですね都が独自に使えるお金とかこの 3件で使えるお金っていうのもう 結構差が実際あるんですよ。 そうですね。 なぜこれだけ格差が出てくるのか、財源ってどうなのか、この辺りちょっと聞いてみたいですね。 うん。そうですね。ちょっと、ま、この今独自に使えるお金見てみるとこの 2010年代の半場と、まあ、 2025 年度で、ま、それぞれ伸びているんですけど、東京都の伸びがやっぱり大きいですね。すいですか、これ。 そうなんですよ。 埼玉って意外と別にそんなに使えるお金が多いわけではないっていうのもありますので、ま、この辺りがあの、ま、背景にあるんですけども、じゃ、なぜこれだけ東京だけと伸びてるのかっていうのを東京都のちょっと税収で見てみたいんですが、 あの、ま、最近のですね、東京都の税収、その全国の中において東京都の税収のシェアというのを、えっと、グラフにしてると思うんですけれど、 ラフにしてみたんですが、ま、パみそんなに急に増えてるわけじゃないかなというところはあるんですが、そもそもですね、東京都の人口って全国の 1割強なんですよ。 なのに地方法人2税がもう2 割を超えていますし、個人住民税も少ずつとはいえ増えている。 で、固定資産税も増えているというところでやっぱこう東京都の税収っていうのは増えているなと。 うん。 この地方法人税は要するに法人税って考えたい。 そうですね。あの、法人住民税と法人事業税っていうのが、ま、正確のところですけれども、そうですね、いわゆる企業から上がってくる税収です。 はい。うん。なるほど。ま、ただそうそうな、このね、シェアはあの 20% ま、そこまでこう極端なことが出ていないのに実際格差が出ている。ま、 これはどういう風に考えたらいい? ですね。 ここはやっぱりちょっとこう、なんて言うんですかね、構造的な問題と言いますか、制度的な問題と最近のその経済、日本経済のあり方っていうこう大きな背景があるので、ちょっとそれを見てみたいと思います。まずちょっと制度のところを見てみますが、少しちょっと勉強みたいになってしまうんですけども、これ今のその国の制度としてお金持ちの自治体とそうでない自治体のこう不近衡を鳴らすための制度というのがあります。 で、それをこの図にしているんですけれども、これあの点があるがありますよね。これ何かって言うと、それぞれの自治体が標準的な行政サービスていうのをするのに必要な額、ま、これ実際あの県都道府県によって違うんですけれども、それが決められています。 うん。 で、そこに足りない分、自税の税はあるんだけれども、足りない分ていうのが出てくる とそこの部分は地方交付税というので補われます。ま、これは国からもらえる分なんですがでこれをもらっているところを交付団体、 もらっていないところを不幸府団体と言いますが、今この都道府県で不幸府団体って東京だけなんですね。 で、まずそれが前提にあります。 で、最近税収が増えてます。 うん。 で、そうすると地方税の税は増えるんですが、 は地方税が増えてもそれが全部その自分たちが自由に使えるお金ではなくてそれだけ地方交付税が減っちゃう、 もらえるお金が減っていうのがこう今の制度なんですね。 うん。はい。 で、一方で不幸府団体の東京は地方税が増えたらそれがそのままその余ってるお金が増えるということになるので使えるお金はそのままあの増えるというところのこう制度のまず問題があります。 なるほど。 ま、これ分かりやすく、そのすごく平たい言葉で言うと、その元々地方、え、自治体を運営するためにこれだけのお金が必要ですよってキャップがもう決まっていて、で、そのキャップに足りない分を地方交付税と補うので、税金が、ま、増えたとしても地方交付税がちょっと圧縮されると他の団体はでも必要な基準よりも東京もう上回っちゃってるからそこ地方税が増えた分はそのままちゃうよ、東京はっていうことですよね。 そうなんです。 だから東京だけがこの税金地方税の税収が増えた分の教授できていると。これはこれ東京だけなんですね。 東京だけです。あの歩道府県で見た時にはそういう風になっているので、 ま、正確に言うと交付団体も全部その自分たちで使えるお金にならないわけじゃなくて、一定はあの使えるお金になるんですけども、でもそのほとんどがこの地方交付税の圧縮分になってしまうので、 ま、なかなか税収が増えてもじゃあいろんな独自サービスやろうってしてもできない。 というのがこうまず制度的な限界ですね。これはやっぱ制度の限界としてある意味仕方ないところ。地方不正っていう考え方自体があの足りないものを補うっていう風なところから出発してしまってるのでこうなってるようには見えますけれどもね。うん。そうですね。ま、そこのところがまず 1つあるっていうのと、ま、もう 1 つですね、その先ほど申し上げた経済のあり方が変わってきてるっていうところなんですが、ま、そもそもですね。 ね、東京都今大規模な企業ほど東京に集中してきています。これ中小企業も含めてなんですけども、やっぱり東京にあの本社を置くような企業が増えていますし、特にですね、あの規模の大きい企業、例えば資本金 50 億円以上とかそういった大きな企業ほど東京都に今集中してきてるんですね。 うん。 で、そうなれば当然、ま、税収も多いっていうところがありますし、あとですね、あの、もう 1 つ東京都のみに農税する企業っていうのが結構増えていて、その税収が多くなってるんですけども、例えばその経営コンサルとかあとはネットショッピングとかの EC サイトを運営しているところ、こういったところは東京都にしかあの会社がなくてあ、視点があったりするわけじゃないし、 東京以外にはなかったりすると結局視点がな ば税収はそこには上がらないので。 そうか。 もう東京都にばっかりこう税収が入ってしまうんだけれども利用する人、お金を払ってる人は東京都以外の方が利用してたりとかするわけなので。 そうですね。大阪とか名古屋であの人が EC サイドを買ったとしてもその会社が東京にあれば東京の会社が儲けたことになると。 そうですね。 その拠が地方になそこに収がなかなか入らないということになってしまうので、ま、そういう構造的なところもありますし、ま、あとはフランチャイズっていうシステムもそうですね、コンビニとか、あの、ま、飲食業とかでもありますけれども、ま、フランチャイズって結局ロイヤリティと言われるその収益の、ま、結構な部分を本社に収めるっていうことになりますので、ま、地方のお店であってもあの東京の方にどうしてもこう収益が行ってしまうと、 ま、そうなると地方から見たら商店の数は減るわ。 で、お金も入ってこないわっていうところでなかなかこう厳しい状況になっていきますし、逆に東京からすると、ま、どんどん集まってくるという結構これは構造的な問題ですね。もう 状況がすぎる。 難うん。ちょっと難しいですね。 なんかいいコマス。その EC サイトとかだったらそれこそ東京じゃなくてもいいじゃんって思っちゃったりしたんですけど。 ね、ま、その企業の考え方としてサイトじゃ軸にやっていくんだったら別に東京じゃなくてもいいっていう考え方もできるしでも実際の店舗とのやり取りとかじゃあ観光長とのやり取りって考えたらじゃ東京にやっぱ本社あった方がいいよねとか なるしね。だからやっぱ便利だからこそ東京にあるのは分かりますけどでもこれをこのこの動き流れをどこかで立ち切らないと全部東京になっちゃうってことですよね。 そうですね。 え、これは逆にじゃ、東京都はどういう風に言ってるんですか?これに関しては 東京都はですね、ま、実はこれ東京都がその元々な何て言うんですかね?強いっていうのが、ま、昔からあるので問題になってきていて、ま、何度もその東京都の富を各地域に配ろうっていうような、いわゆる変在事と言われますけど、偏りを直すための制度っていうのが取り入れられてます。 はい。 で、その結果、ま、東京都してはですね、毎年 1.5兆円 国に、ま、言い方召し上げられてると。 なんでこういうこう国の不合理な制度の見直しで本来都民のために使われるべき税が奪われてきたというのが、ま、東京都があの総務省とかに対してこう説明してる言文です。 うん。 うん。 なるほどね。 ま、これに関しては、ま、もうね、あの、地方からもちろん自分たちが住んでるところが、あの、もちろん良くなってほしいっていう両者の意見はもちろん分かるんですけど、じゃあこれが国が出てこなきゃいけない問題なのかなっていう気がするんですが。 そうですね。そうなんですよね。なんだ からそうなるとやっぱこの制度のあり方を どうするかっていうところを考えていか ないといけないんですけれども、ま、そう いったところで今ですね、あの総務省が あの有識者の方々を集めた検討会っていう のをやっていまして、ま、7月以降特に この問題に特会して議論をしています。 で、ま、実際どうしてこういう格差が東京都とそれ以外に出てきてしまってるのかというのを、ま、今日ご説明させていただいたような内容も実は検討会でまさに議論されているところで、ま、この辺りが今後どういう結論出していくかっていうところにはなってきますね。 うん。でもね、あの、なんか 諦めてたんですよね。なんかその東京と比べたってどうせ無理じゃんってどっかで思ってるんですけど、やっぱ自正できるものなんですかね。その検討すれば。うんうん。そうです。 これ是正しないといけないという指摘がまさにありまして、あの総務省のその検討会にもメンバーでもいらっしゃって、地方の税財政に詳しいあの関西学院大学の上村と期教授にお話を伺ったんですけれども、これやっぱ税収の話にとまらない問題なんですよね。 で、どういうことかと言うと、ま、放置すると東京にどんどんこう人材が集まってしまうとで、ま、東京からすれば別に地方から来てもらったらいいじゃんて思うかもしれないんですけど。 そうすると今度地方の方の人材がいなくなってしまう。 で、そうなると東京に来てくれる人もいなくなってしまうということになると、ま、そもそも東京自身もあの持続可能ではなくなってしまうということで、やっぱり東京都にとってもこのまま放置するっていうのは長期的に見たら決して良くはないという指摘があります。 はい。うん。 そうか。東京にとってもこのままでは良くないということなんですね。そうなんですよね。 うん。 ま、ただこの地方付税のあり方っていう風なところから先ほどグラフで説明していたように、あの、これ構造的にキャップがついてしまってるんで、圧縮されてしまう。この問題をなんとかしないと いつもでもその税収が地方税が増えても東京ばっかり儲かるみたいなことになってしまうような気がするんですが。 そうですね。 で、ま、そか難しいと、ま、あの、度やっぱり措置してきて、今の地方付税も含めてですけども、すごく密に制度設計されてるんですよね。これをなんとかするっていうのはそんな簡単な問題じゃない。 あっちを触ればこっちが苦しむとかそういう風に今なってきてますし、ま、東京都からすれば確かにその自分たちで使えるはずのお金が使われるっていうのは納得できないっていう感情的なところももちろんあると思うんですけど、ま、そもそもやっぱり首都としてあのインフラをきちんと整備しなきゃいけないとかそういったところにその財政が必要だっていうところもありますし、かなりやれることっていうのは、ま、だいぶあの限界と言いますか、制限はあると思うんですがう ただこまでやっぱり取材してきていろんなところでお話を聞いているとその今後のその方向性としてどうなるかっていうところで言うとやはり何らか制措置は必要だろうと。ま、つまり東京都の税収をあの他のところで、え、再配分できるような仕組みっていうのを、ま、さらに入れる方向にはなりそうです。 はい。 ただ、あの、これ、ま、ちょっと時間かかる非常に複雑な生徒設計なので、で、もう 1 つで言うと、ま、さらに別の全く今なかった。 仕組みを取り入れるっていう方法もあります。 で、これ例えば今固定資産税も東京都増えてるんですけれども、ま、地下が上がってあの増えていくんですが、この固定産税って実はこう変在是その偏りをなくす仕組みっていうのが今はないんです。そこにそれを こう入れる。 はい。 で、例えば韓国のソルですと、一定の基準を超えた不動産に対してその税をかけて、ま、いわゆる富裕税ですかね。で、これを地方に配分するということをやっています。 ま、それで全てが解決するわけではないかもしれないんですけれども、そういった形で新しいその仕組みっていうのを導入するていうのも 1つの方法です。 はい。ま、これもちろんその国の財政って いうのの一般的な考えはあるところから 取ってないところに分配する再分配の考え 方というのがもちろん基本になってるわけ なのでそれをじゃあ国レベル、その地方 実写レベルに考えた時にやっぱりお金が ある東京から他のところに、え、お金を こう配分していって東京じゃない地域の 暮らしを、ま、いや、さらに良くすること で、ま、人口、東京局集中、これもちろん 問題になってるわけですから、解決するに はやっぱその方法がまず1番近いんじゃ ないか という風に直感的に思いますけどもね。 そうですね。 やっぱりそれがの、ま、東京もそうですけど、その日本全を見たには必要ですし、で、やっぱりその、ま、平成 20年、あの、2008 年以降ですね、いろんな制度の見直しはあったんですけど、やっぱりその時々によって経済の状況っていうのも変わりますし、そのあり方っていうのも変わっていくので、それに応じたどんどんこう、やっぱり制度の改正と言いますか、見直しっていうのは必要だと思うので、まさに今それが考えるべき時期に来ているのかなというところがありまして、 ま、実際その今月中旬にはですね、総務省の検討会があの分析結果を公表するので、まずそれでそのこの格差の原因っていうところどういう風にこう踏み込んでくるのか、その分析結果っていうところにも注目していきたいですし、またこの年末にではですね、あの税のその制度のあり方を議論する与党の税制改正の、え、議論もありますので、その中でもこの問題取り上げられると見られますから、それの議論とか、ま、国としても 今まさに議論をしているところなので、それはそうですね、監視を持って東京都民であってもなくてもはい。見ていく必要があると思います。 あの、今日のテーマは玉摩川格差という言い方してましたけども、東京とその周りの 3 件の問題っていうのはこれを大きくしてくとやっぱり東京と地方てもっと大きな視点でその東京の一局集中ってどうなんだろうかってことにつなげて考えるべきだと思うんですよね。 だからこの、ま、ちっちゃいて言い方がしいかから、このと東京の関係からここの入口にしてやっぱりもう 1歩踏み込んだ こと考えなきゃいけないんですよね。 うん。ま、東京は東京で当たり前ですけど自分たちの自治体住みやすくしたいわけじゃないです。そうですね。 で、でも地方は地方で自分たちのところにこれ以上人口が減ってはまずいっていう危機感はもっとあるわけで、ま、っていう風にもちろん理害がこうやってぶつかるわけですから、ここはやっぱり国が出てきて調整をしないといけない。 ま、そういう時期に今人口減ってますから日本全体行くと差しかかっているっていうことが今日のこの玉摩川格差ていうのをきっかけにちょっと日本全体ことを考えるきっかけになりましたよね。 はい。 え、ここまで佐藤記者に解説をしていただきました。佐藤さんありがとうございました。 ありがとうございました。 最後までご覧いただきありがとうございます。安ニュースキャスターの辻ゆです。これおきに是非チャンネル登録よろしくお願いします。
.
◆ABEMAで無料視聴
▷https://abema.go.link/cPj9f
◆過去の放送回はこちら
【大相撲】34年ぶりロンドン公演 現地の様子は?ファンに囲まれる横綱・大の里と豊昇龍も…【SUMO】|ANNロンドン支局 立田祥久
▷https://youtu.be/xNN0EL0sf0g
【林芳正】「“旧岸田派”を足場に…結束は抜群」ギター&作曲 多才な“文化力”で外交も【自民党総裁選】|政治部 小手川太朗記者
▷https://youtu.be/zuqKh_PnnsI
◆キャスト
矢島 悠子(テレビ朝日アナウンサー)
辻 歩(ABEMA NEWSキャスター)
佐藤 美妃記者(テレビ朝日 経済部)
「倍速ニュース」
平日よる7時 アベマで生放送中
#格差 #東京 #多摩川 #解説 #アベマ #ニュース
————————————————————
◆ニュース公式SNS
アベプラCh:https://www.youtube.com/@prime_ABEMA
X(旧Twitter):https://twitter.com/News_ABEMA
TikTok①:https://www.tiktok.com/@abemaprime_official
TikTok②:https://www.tiktok.com/@abemaprime_official2
◆ABEMAアプリをダウンロード(登録なし/無料)
iOS:https://abe.ma/2NBqzZu
Android:https://abe.ma/2JL0K7b
※YouTube動画には一部ミュート(消音)の部分がございます。
※YouTube動画には掲載期限があり、予告なく掲載をおろす場合がございます。ご了承ください。
————————————————————