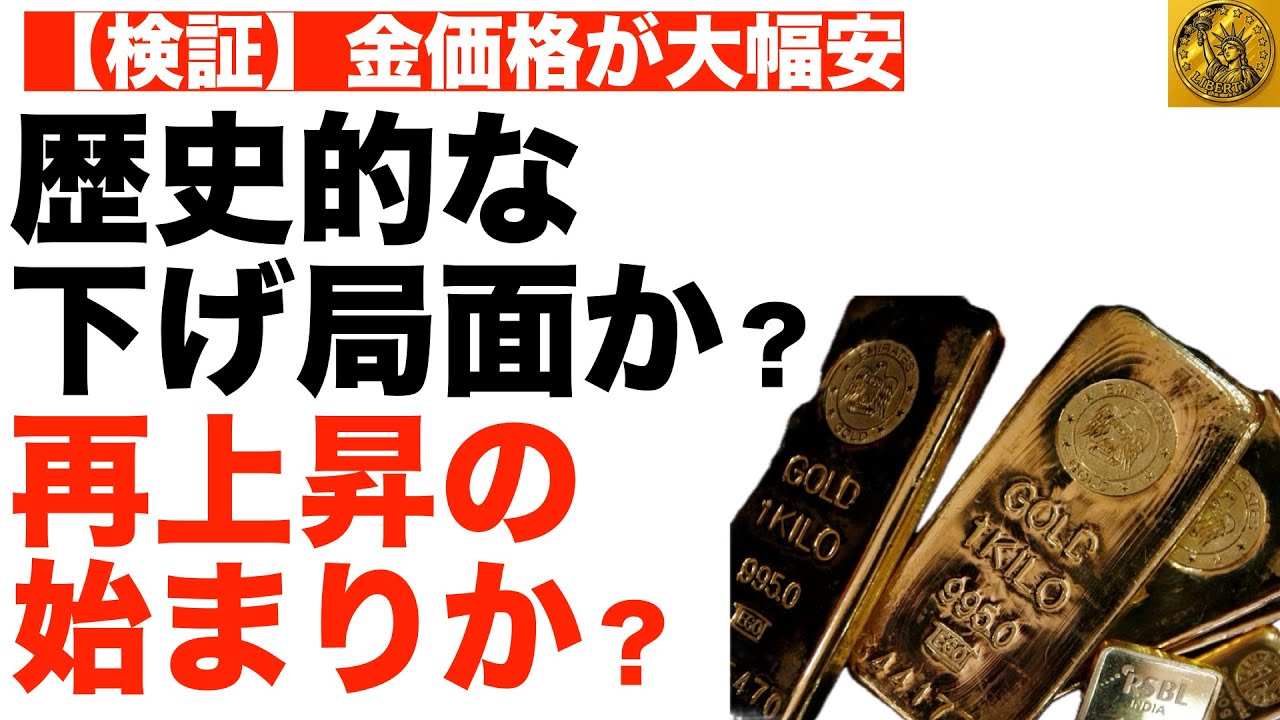【検証】金価格が大幅安 歴史的な下げ局面か、再上昇の始まりか 過去のケースと比較検証
経済ライターの木村貴です。金(ゴールド)の価格が先週、大幅安となりました。国際 指標であるニューヨーク先物の中心限月は21日、前日比250ドル安の1トロイオンス 4109ドルに下げ、1日の下落幅としては過去最大を 記録しました。前日に4398ドルの史上最高値を付けたばかりでした。 市場では「バブルが崩壊する可能性は高まっている」との声も聞かれます。金は歴史的な 下げ相場に入ったのでしょうか。それとも、これは新たな上昇局面への起点にすぎない のでしょうか。過去の下落局面をヒントに探ってみましょう。まず、金相場の「前史(それ 以前の歴史)」を簡単に振り返ってみましょう。第二次世界大戦後の国際金融の枠組みと なった1944年のブレトン・ウッズ協定に基づき、ドルは「金1オンス(およそ31グラム)=35ドル」の比率 で金との交換を保証されました。これを金・ドル本位制といいます。金価格は1オンス 35ドルの固定相場となったわけです。戦後の混乱した国際経済のなかにあって、 アメリカは飛び抜けた経済力をもち、国際流動性(国際的通用力をもつ決済資金) が不足するなかで、ドルは金よりも強いとさえいわれました。このような経済力とドルの 圧倒的優位が、ドルを基軸通貨とする国際通貨体制を生み出しました。しかし、アメリカ から西側諸国への経済援助や軍事援助、ベトナム戦争などによる軍事支出を通じて、 ドルが世界中にばら撒かれると、アメリカの対外債務は金準備を上回るようになりまし た。対外債務とは、外国から借りている債務(借金)のことをいいます。外国がもつドルは アメリカの対外債務となります。一方、金準備とは、ドルとの交換に応じるために準備 している金のことです。金準備が足りなくなった結果、ドルへの 信用不安が高まり、各国政府はドルを金と交換したため、アメリカ国内から大量の金 が流出して「ドル危機」と呼ばれる事態が発生しました。こうしたなか、1968年3月、 金の公定価格は形だけ残すものの、自由市場での金価格は自由に変動させるという、 金の二重価格制度が導入されました。これ以降、金は一般の商品と同じように、変動相場 の時代に入ります。ドルが事実上、金の裏付けをもたない不換紙幣となり、金価格が自由に 動き始めた1968年以降、大きく下落した局面は過去4回あります。1回目が 1974年半ば〜76年半ば、2回目が1980年初め〜85年春、 3回目は長期にわたるため前後に分かれ、前半が1988年初め〜93年半ば、 後半が1993年〜2001年。そして4回目が2011年9月〜16年2月 です。これら4回の歴史的な下落局面には、ある共通点があります。国際金融 エコノミスト、ブレンダン・ブラウン氏の分析によれば、それはいずれも、ドルを好き勝手 に増やせる不換紙幣体制が健全な方向に改革されるという、楽観論の高まりが きっかけになったということです。それらの楽観論は結局、期待外れに終わりましたが、 金価格を一時急落させる一因となりました。具体的に見ていきましょう。1回目の 急落局面は、アメリカが金とドルの交換体制(金本位制)を完全に廃止した1971 年のニクソン・ショックの後、1970年代半ばに始まりました。バーンズ議長 率いる中央銀行FRB(アメリカ連邦準備理事会)が遅ればせながら実施した金融 引き締めは深刻な不況を招き、消費者物価指数の伸びも低下しました。 同じ頃、ドイツとスイスはともに、お金の供給量を絞ることで物価を抑え込む マネタリズムの考えを取り入れて成功し、これがアメリカにも波及するとの期待が 高まりました。実際、アメリカ議会では与野党双方から改革に支持が集まり、1977 年の連邦準備制度改革法が成立しました。これによってFRBは、雇用の最大化と並んで 物価の安定というデュアル・マンデート(2つの使命)を課されることになり、議会への 定期的な報告を義務付けられました。次に2回目の金価格急落は、ボルカーFRB議長が 金融引き締めに動いた1980年初めから85年春先にかけて起こりました。不換紙幣 体制の下であってもマネタリズムの手法を取り入れることで、インフレは退治できると いう楽観論が広がったためです。ただし、長くは続きませんでした。すでに1984〜 85年にかけての冬、ボルカー議長は大規模なインフレ政策へと舵を切り 始めていました。このボルカー氏によるインフレ政策は、レーガン政権下でベーカー財務長官が 主導した85年9月のプラザ合意に象徴される、ドル安政策を後押しするものでし た。金価格は87年の株価暴落(ブラックマンデー)あたりまで上昇を続けます。3回 目の下落は1988年初めに始まりました。前年のブラックマンデー直後、FRBは 異例の資金注入を実施しましたが、88年に入ると市場は金融引き締めの可能性を 察知しました。実際、グリーンスパン議長率いるFRBは89年に引き締めに動き、 その結果、世界的な資産価格の高騰が下落に転じました。とくに日本では土地・株式バブル が崩壊に向かいました。金価格は93年に一時回復するまで、大幅に下落しました。 ここまでが前半期です。それに続く後半期、金価格は2001年 まで再び下落しました。この後、2000年代半ばから2008年のリーマン・ショックに 至るまでの間、株式や債券など資産価格の変動幅が低下し、市場全体が安定する 「グレートモデレーション」をもたらしたとして、グリーンスパン氏は「マエストロ(巨匠)」と 称えられることになります。FRBが不換紙幣制度を管理する新たな能力を発揮したと の楽観論が広がる一方、水面下ではマネーの膨張が進み、IT(情報技術)革命と グローバル化による供給力の高まりで物価上昇の圧力が覆い隠されていました。 1990年代半ばから後半にかけて、クリントン政権の下でアメリカ政府が財政黒字に転じた ことも、金相場の下落を誘いました。将来、財政赤字をドルの発行で穴埋めする「財政 ファイナンス」のリスクが小さくなることを意味したからです。そして、今のところ最後 の歴史的下げ相場である4回目は、2010年の中間選挙で保守的な草の根運動である ティーパーティー運動が盛り上がり、共和党が下院の支配権を奪った後に訪れました。 下院は上院、オバマ政権と政府支出の削減で合意に達しました。FRBがQE(量的緩和) から撤退する議論が高まり、その後実行に移されました。2008〜11年の金 ブームの際に強まった、不換紙幣体制が揺らぐという悲観論は後退しました。さて、もし 5回目の金の下げ相場が起こるとしたら、やはり不換紙幣体制に対する楽観論の再燃 がきっかけになるとみてよいでしょう。現在、コロナ対策を口実とした財政の膨張や、 ドルを武器代わりにした経済制裁などにより、ドルに対する不信感は、過去のどの金ブーム時 よりも大きいとみられます。逆に言えば、その反動も大きくなる恐れがあります。 下げ相場の引き金となりうる出来事として、ブラウン氏は3つを挙げています。第1に、 FRBによる大幅な金融引き締めです。2026年も消費者物価が上昇した場合、次期 FRB議長が中間選挙の後にでも実質的な引き締めに着手する公算があります。 第2に、大規模な財政支出削減の実現です。政治情勢が変化し、大規模で計画的な支出削減 が可能になるかもしれません。第3に、一段の物価高とそれに対する市民の不満を背景 に、超党派の議員グループが通貨健全化に向けた改革案を練り始める可能性があります。 そのうえでブラウン氏は「5回目の下落は必然ではない」と付け加えます。つまり、金価格は もはや大きな下げ相場を迎えることなく、上昇を続ける可能性があるということです。 なぜなら、ドルを健全な通貨に戻す改革は、もはや合理的に期待できる域を超えている かもしれないからです。過去の金下落の引き金となった通貨改革に向けた楽観論は 「永遠に消え去ったと言えるかもしれない」とブラウン氏は冷ややかに述べます。もし そうだとすれば、足元の金価格急落は、下げ相場の始まりではなく、新たな上昇相場の 起点となる可能性があります。そのとき、かつては金より強いといわれたドルをはじめ、 円を含む不換紙幣の価値が根本から問われることになるでしょう。最後までご視聴 ありがとうございました。このチャンネル
はリバタリアン自由主義者の目線で経済、 政治、歴史などについて分かりやすく解説
します。特に人気の高い動画を選んでその 内容を電子書籍として出版しています。
またお金の価値がなくなるインフレを中心 テーマに無料の経済勉強会も開いています。説明欄から是非チェックしてみて ください。それではまた次の動画でお会い
しましょう。
金(ゴールド)の価格が先週、大幅安となりました。金は歴史的な下げ相場に入ったのでしょうか。それとも、これは新たな上昇局面への起点にすぎないのでしょうか。過去の下落局面をヒントに探ってみましょう。
<動画が電子書籍になりました!>
特に人気の高い動画を選び、その台本を本文として収録しました。電子書籍だけの特徴として、それぞれの本文から重要なキーワードを選び、解説を付けてあります。興味のある方はぜひ、アマゾンのサイトからダウンロードしてみてください。
【最新刊】
* ドイツのハイパーインフレ 破滅した人、大儲けした人 https://amzn.to/46EWjXU
* 預金封鎖サバイバル術 https://amzn.to/48FeizX
* 金が買われる本当の理由 https://amzn.to/42g8069
<勉強会のご案内>
お金や経済についてもっと知りたい人のためのオンライン勉強会です。入退会自由、無料です。商材の勧誘などは一切ありません。こちらの説明動画をご覧ください。
<関連動画>
<関連/おすすめ本>(Amazonアソシエイト・プログラムを利用)
『政府はわれわれの貨幣に何をしてきたか』ロスバード、岩倉竜也訳(きぬこ書店) https://amzn.to/45boBZr
『金100パーセントのドル』ロスバード、岩倉竜也訳(きぬこ書店) https://amzn.to/3UF682k
『連邦準備制度反対論』ロスバード、岩倉竜也訳(きぬこ書店) https://amzn.to/4lT6COm
<参考記事>
金価格が大幅安 歴史的な下げ相場か、再上昇の始まりか 過去のケースと比較検証(木村貴の経済の法則!)
https://moneyworld.jp/news/05_00190268_news
What Will the Next Gold Bust Look Like? | Mises Institute
https://mises.org/mises-wire/what-will-next-gold-bust-look
<チャプター>
00:00 オープニング
00:50 固定から変動相場へ
03:00 過去4回の下げ局面
04:15 マネタリズムに期待
06:23 悲観論が後退
08:44 次の引き金は?
11:11 エンディング
<略歴>
木村 貴(きむら・たかし)
経済ライター。1964年熊本生まれ。1987年から日本経済新聞社で記者として主に証券・金融市場を取材。その間、スイスの金融街チューリヒに駐在。業務のかたわら、リバタリアン(自由主義者)の政治思想や、政府の経済介入を批判するオーストリア学派経済学を学ぶ。現在はグループ会社でライター兼エディターとして勤務し、個人としても記事・動画コンテンツを発信する。
『反資本主義が日本を滅ぼす』(コスミック出版) https://amzn.to/3DMgsk8
『教養としての近代経済史』(徳間書店) https://amzn.to/404IezB
『世界金融 本当の正体』(執筆協力、サイゾー) https://amzn.to/3Pr8ak2
『デフレの神話』(Kindle個人出版) https://amzn.to/4236wfV
『サンデル教授、ちょっと変ですよ』(同) https://amzn.to/3PqPFwg
『自由主義者かく語りき』(同) https://amzn.to/3Pq9UtS
X(旧ツイッター) https://x.com/libertypressjp
ブログ「リバタリアン通信」 https://libertypressjp.blogspot.com