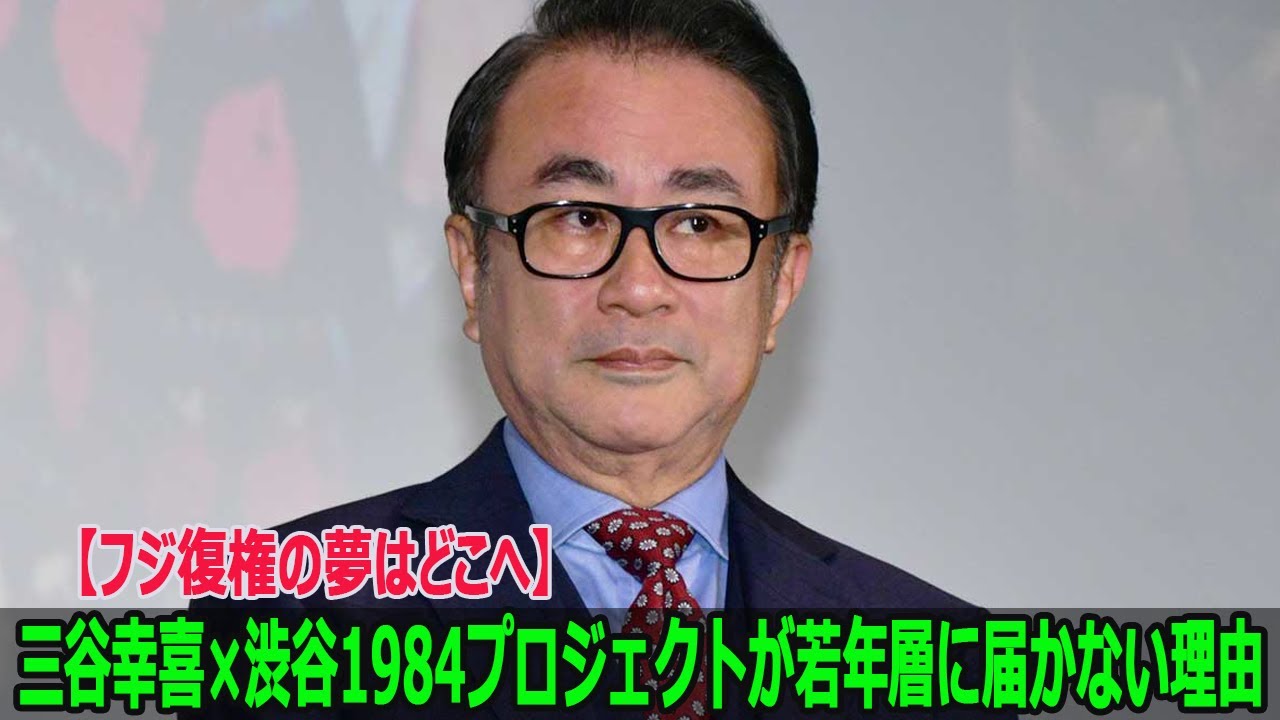【フジ復権の夢はどこへ】三谷幸喜×渋谷1984プロジェクトが若年層に届かない理由
フジテレビが満を持して送り出した連続ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』が、初回視聴率5・4%という厳しい船出を切った 脚本は三谷幸喜、民放GP帯での連ドラは実に25年ぶりという触れ込みだった 主演は菅田将暉、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波、菊地凛子、小池栄子、市原隼人、井上順、坂東彌十郎、小林薫と超豪華 冒頭ナレーションは渡辺謙、主題歌は世界のYOASOBIという盤石の布陣だ それでも数字は伸びなかった 理由をひとつに絞るのは難しいが、若年層に刺さる導線が見えにくかったのは確かだ 舞台は1984年の渋谷、三谷の自伝的要素を含むオリジナル青春群像とされた 巨大なオープンセットまで建て、当時の空気を再現する投資は相当だった 民放プロデューサーの見立てでは初回のギャラだけで1500万円規模とも語られる 今期のフジはこの一本に賭けたと受け止められても不思議ではない 一方で他枠のキャスティングは相対的に地味で、編成の重心が『もしがく』に偏っていたのは明白だ 月9『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』はSeason5とはいえ主演は沢口靖子で、長期シリーズの安定枠という構図だ 火曜21時『新東京水上警察』は海猿の二番煎じ的と揶揄され、主演は佐藤隆太 木曜22時『小さい頃は、神様がいて』は北村有起哉が連ドラ初主演で挑む 人材の層は厚いが“豪華”と断じるのは難しい そこへ『もしがく』は大看板を勢ぞろいさせた 「三谷作品だから集まった」という評価は的を射ている 『振り返れば奴がいる』『古畑任三郎』『王様のレストラン』『総理と呼ばないで』と、かつての三谷は視聴率20%超えを量産した 大河でも『新選組!』『真田丸』『鎌倉殿の13人』を成功に導き、映画『THE 有頂天ホテル』『清須会議』もヒットを記録した ゆえに役者はかけ声ひとつで馳せ参じる オープニングで大写しになるカセットテープ、昭和59年の渋谷スクランブルの映像は、ノスタルジーを直撃する演出だ エンディングの【映像協力 チ・ン・ピ・ラ】が示すように、84年公開の名作からの抜粋が随所に織り込まれている 同作の製作者にフジの前相談役・日枝久の名が並ぶ因縁も匂わせる しかし若い視聴者にとって1984年は歴史の彼方だ “記号としての渋谷”は分かっても、肌触りまでは共有できない ここに第一の距離感がある 物語は、アングラ小劇場にありがちな熱血で横暴な演出家を菅田将暉が演じ、彼が追放されるところから始まる 舞台がWS劇場に移るとダンサーの小池栄子が踊り出し、場末の熱と混沌が噴き上がる この匂いが昨年7月期の『新宿野戦病院』を想起させたという声もある 渋谷の裏町と歌舞伎町という舞台の違いはあっても、湿った空気感はクドカン的な肌合いに寄った さらに菅田が吐く昭和の暴言は『不適切にもほどがある!』の余韻を連想させる 参照される記憶が多層に重なり、初見の若年層には入口が狭くなった 配役の“豪華さ”も諸刃の剣だ 菅田と二階堂のツートップに加え、放送作家モデルに神木隆之介、巫女に浜辺美波とスターが続く 浜辺の父で神主に坂東彌十郎、踊り子にアンミカ、用心棒に市原隼人、ジャズ喫茶のマスターに小林薫が並ぶ 客引きに井上順、テレビに映る芸人役で堺正章という“ザ・スパイダース”の名コンビまで差し込む さらに冒頭でシェイクスピアの名言を語るのは渡辺謙という重さ 主題歌はYOASOBIで、パッケージの格はもはや日曜劇場級だ だが情報量が過密になれば、主人公の心の動線は霞む 序盤から“誰を追えばいいのか”がぼやければ、若い視聴者はスマホのタイムラインに戻ってしまう VIVANT級のスケールをテレビ文法で見せるには、視点の一本化が要る それが初回では贅沢な賑やかさに埋もれた 数字の側面でいえば“ご祝儀で二桁、最低でも7〜8%”は取りたかったはずだ だが現実は5・4% この落差が示すのは“豪華=高視聴率”という古典の失効だ 思い返せば三谷の民放連ドラ前作『合い言葉は勇気』は初回15・9%から第6話で7・4%まで下げた すでに25年前の時点で民放の数字は伸び悩んでいた 三谷がその後、NHK大河に軸足を移したのは自然な流れだった 大河は全50話、民放の1クールはおおむね全10話 三谷自身が「大河の5分の1で、勝算のあるテーマを考えた」と語ったように、短距離走への最適化は意識されていた ただし民放GP帯は視聴率の世界であり、途中経過の点検が命だ “視聴者がついてきているのか”を逐一チューニングする執拗さが必要になる ブランクの25年は、その勘を鈍らせるには十分に長い 加えて三谷は22年4月から『情報7daysニュースキャスター』の総合司会を務めている 作る側が出る側に回るとスタンスが狂うことがあるという指摘は鋭い 相撲取りがバラエティで人気者になり、土俵で負けが込む比喩は痛烈だ “演出家”が“演者”になると、現場のリズムに微妙なズレが生じる瞬間がある 『もしがく』の台詞にも気になるフレーズがあった 「笑いなんか必要ないなんでわかりやすい方向に行きたがるのか!」という檄 「芝居はわからなくていい理解しなくていい、感じてくれれば」という宣言 これは作り手の矜持であると同時に、若年層の“ながら視聴”と真っ向から衝突する思想でもある “わからなさ”をあえて残す芸は、深夜や配信では熱狂を生むが、GP帯初回ではハードルになり得る 渋谷1984のディテールは濃密で、当時を生きた世代には芳香剤のように効く だがZ世代にとっては匂いの元ネタが共有されていない 映像協力の由来も、映画史やフジの系譜に通じる者だけが拾えるサインだ メタ参照の多さが、入口の狭さとして働いた可能性は高い では、どう“届く物語”へ舵を切るか 視点を絞り、菅田と二階堂の関係線に観客の体温を集中させること 群像の濃さは残しつつ、各話の“感情の出口”を一つに定めること 1984年の小道具は背景に退き、今の若者が自分の痛みを代入できる“現在形の痛点”を手前に置くこと 豪華キャストは“顔見せ”から“物語の推進力”へ移行させること YOASOBIの主題歌は世代横断の鍵になり得る “歌で掴み、物語で離さない”配置を整えること 数字は冷酷だが、物語はここから変えられる まだ初回が終わっただけだ 『もしがく』は回を重ねるごとに、賑やかさの奥にある“ひとり”の震えを見せられる 三谷の帰還にふさわしい“現在地の名台詞”が、次の週に用意されているかもしれない 1984年の渋谷という記憶の街で、今の観客が自分の居場所を見つけた時、数字は後から追いつく 若年層に届かないのではなく、まだ届いていないだけだと信じたい 初回5・4%という現実を起点に、第二話以降のチューニングが大胆であることを期待する 過去の栄光を参照するのではなく、いまの観客のスピードに作品側が追いつくこと その一歩を、次の放送で見せてほしい 動画をご覧いただきありがとうございます最新の動画や関連トピックの情報をご覧いただくには、チャンネル登録をお願いいたします
【フジ復権の夢はどこへ】三谷幸喜×渋谷1984プロジェクトが若年層に届かない理由
フジテレビ渾身の連ドラ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』が初回視聴率5.4%で苦戦。脚本は三谷幸喜、民放GP帯の連ドラは25年ぶり。1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇として大きな話題を集めたが、若年層への浸透は鈍かった。
菅田将暉、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波、小池栄子、菊地凛子、小林薫、坂東彌十郎ら超豪華キャストに加え、渡辺謙のナレーション、主題歌はYOASOBI。巨大オープンセットや当時映像の引用など、初回だけで1500万円級の投資もうかがえる。
一方で序盤から登場人物と情報が過密で、モデル化された放送作家や巫女など多彩な脇役が物語の焦点を散らし、昭和の暴言やメタ参照の多さもハードルに。1984年のノスタルジーは刺さるが、Z世代には“入口”が狭く、ながら視聴の離脱を招いた。
かつて『古畑任三郎』『王様のレストラン』で20%超えを量産し、大河や映画でも成功した三谷だが、民放での25年のブランクは大きい。視点を菅田×二階堂に絞り感情の出口を明確にすれば、賑やかさの奥の“ひとり”が立ち上がり、巻き返しは可能だ。
#もしがく, #三谷幸喜, #視聴率5.4%, #1984年渋谷, #豪華キャスト, #YOASOBI