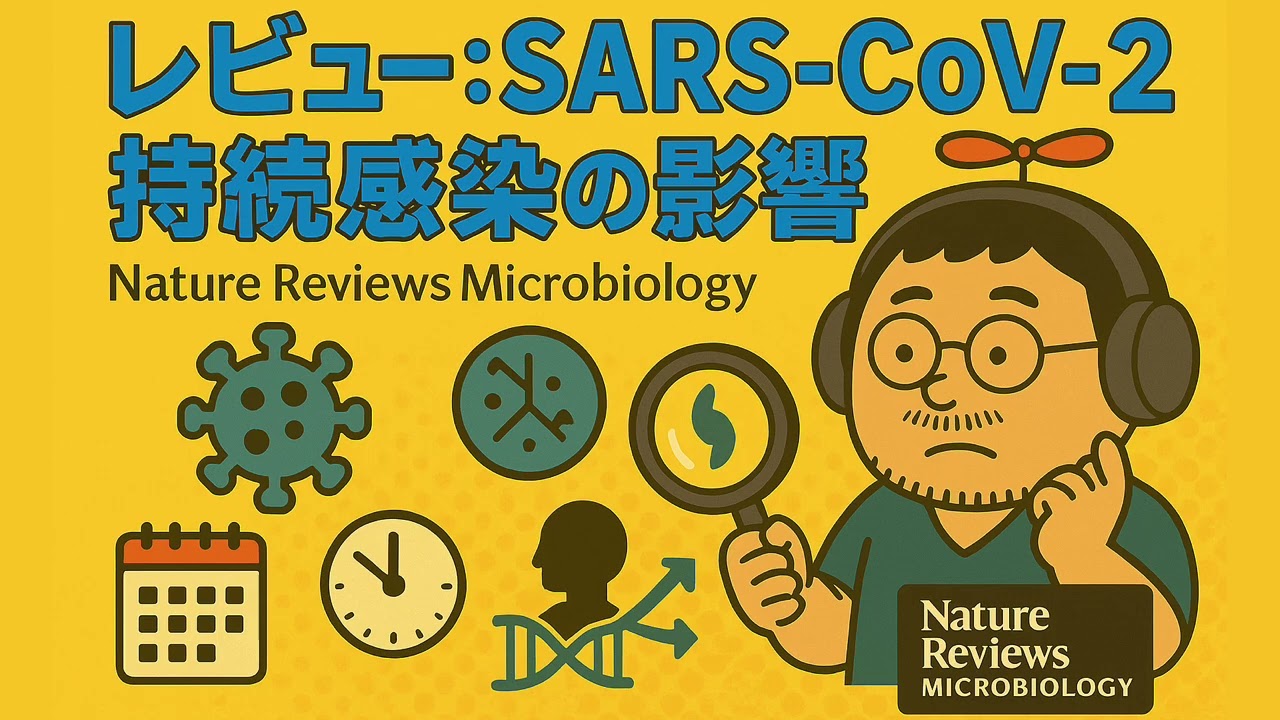【医療者向け・音声のみ】新型コロナウイルス「持続感染」の真実:変異株の起源とロングコビットの謎を徹底解明 Nat Rev Microbiol
皆さん、こんにちは。靴オレディオです。 この番組は複雑に入り組んだ感染症領域に 鋭いメスを入れ、様々な謎や疑問を徹底的 にするポッドキャストです。それでは皆 さんご一緒にせーの靴をレリオ。さて今回 皆さんと一緒に深く掘り下げていくのは 新型コロナウイルス サーズ物の話です。はい。 特にですね、なぜ一部の人たちの体の中でこのウイルスが、えっと、数ヶ月列とかなり長い期間しつこくわり続けるのかという点に注目したいと思います。 え、重要なテーマですね。 で、手元にあるのはNature ReviewMICRDIY オジー氏の最新レビュー論文 consequencesofSARS CF2withinhost persistance はい。 これを元に、ま、ウイルスが持続する仕組みとか、それがウイルスの進化。 特に次々出てくる変異株にどう影響してるのか、あとはやっぱり気になるロングコビッド行為症との関係。この辺りを皆さんと一緒に解き明かしていきたいなと。 ええ、是非。 さあ、早速ですが中身を見ていきましょうか。まず基本からサーズコブ 2 の持続感染。これって具体的にはどういう状態なんですか? はい。えっと、普通新型コロナにかかっても、ま、大体は 1 ヶ月以内にはウイルスは検出されなくなるんですね。 そうですよね。 ですが、それを超えてもまだウイルスが検出される状態、これを持続感染と、ま、定義しています。 なるほど。 特に免疫が普通に機能している方ですと、 1 ヶ月以上も例えば鼻とか喉からウイルスが見つかるっていうのはこれかなり稀れなことです。 ふむふむ。当初はあの制の呼吸機感染症だって考えられてたわけですが、どうも長引くケースがあると。 ええ、そういうことが分かってきたんですね。 で、この論文によれば持続感染には大きく分けて、ま、 2つのパターンがあるとされています。 ほう、2つですか?1 つは免疫の働きが、ま、なんだかの理由で弱っている方のケース。 はい。 で、もう1 つは免疫は見たところ正常なんだけれども、それでもウイルスが長引きかもしれないというケースですね。 うん。 ちょっと性質が違うんです。 なるほど。では、その1 つ目、免疫が弱い方、免疫付不全状態での持続感染について詳しく教えていただけますか? はい。えっと、こちらのメカニズムは比較的、ま、分かりやすいかもしれません。 はい。 体がウイルスを得意的に攻撃して排除するためのシステム、これを適用免疫って言いますけど、この働きが十分じゃないんですね。 適用免疫。 ええ、特にウイルスを直接無力化する、ま、中和交代という武器がありますけど、これを作る能力が低いとウイルスをなかなか効率よく排除できない。 ああ、武器が足りないと。 そういうことです。具体例としては例えば HIV 感染症が進行してしまって免疫の指令灯である CD4要請T 細胞が非常に減ってしまった方 はい。 あるいは自己免疫疾患とか癌の治療で B 細胞っていう交代を作る細胞をこう上去する治療、利き島とかですね、そういうのを受けて免疫が抑えられている方々。 なるほど。 こういった方々が挙上げられます。で、実際にそういう方々の鼻とか喉からウイルスが長期間検出されると、しかもそのウイルスを採取して実験室で用するとちゃんと増えるんです。 つまり複製能力を持っている生きたウイルスだということが確認されているんですね。 へえ。ちゃんと増えるんですね。 え、で、これはサーズ鉱物だけの特別な話かと言うとそうでもなくて、例えばインフルエンザとか MPXV、M トックスですね、あとはノロウイルスなんかでも免疫が弱っているではウイルスが長期間持続するってのはよく知られています。 他のウイルスでもあるんですね。 そうなんです。だからサーズコーブ2 でも、ま、同様の現象が起きてるんだろうと考えられるわけです。 ふむ。 じゃあどれくらいの人がこのリスクを抱えているのかっていう話ですけど、米国とか英国のデータからの推計になりますが、世界人口の大体 4%から7% くらいが何らかの理由で免疫付全の状態にあるんじゃないかと。 4 から7%結構な数ですね。 ええ、で、中でも特にリスクが高いと考えられるのが進行した HIV 感染者の方々。世界で約人以上いると推定されてます。 [音楽] 400万人。 あとは先ほど例に出した B細胞除去療法を受けている方も 2012年時点でも100 万人以上いてさらに増える傾向にあると。 うーん。うん。 これらを考えると持続感染のリスクを、ま、潜在的に持っている人々っていうのは世界中で少なくとも数百万人の単位には登るだろうと。 数百万人記ですか?それは無視できないですね。 ええ、 なるほど。免疫がうまく働かないとウイルスがわってしまうというのはよくわかりました。ではもう一方の免疫は正常に見えるのに持続感染が疑われるケース。これはどうなんでしょう?あのロングコビッドとの関連でよく聞く話ですよね。 はい。そこが非常にこう興味深くてかつ複雑な点なんです。 ほう。 免疫が正常な方の場合、先ほどの免疫不全の方とは状況がかなり違います。普通は感染しても鼻や喉気道からはですね、長くても大体 1 ヶ月以内にはウイルスは検出されなくなるはずなんです。 ええ、通常はそうですよね。 問題はその後なんです。 その後 はい。呼吸機からはウイルスがいなくなっ たように見えても、例えば消化感とか体の 他の部位からですね、ウイルスの遺伝情報 であるRNAとかあるいはウイルスの かけらタンパ質ですね。これが感染から 数ヶ月場合によっ検出されることがあると いう報告がこう相ついるんですね。 えっと、呼吸機以外でそんなに長くですか? ええ、 でもそこで1 番気になるのはその検出されたものって本当に生きてるウイルスなんですか?それともなんていうかウイルスの残骸みたいなものなんですかね? まさにそこが最大の疑問点であり、今の研究のこう焦点になってるところです。 はい。 で、結論から言ってしまうと、現時点ではですね、免疫機能が正常な方で呼吸機以外の場所から長期間検出されるウイルス成分について用に成功したという、つまり生きて増殖することを確認できたという確実な報告はまだないんです。 ああ、まだないんですね。 ええ、ただ状況証拠のようなものはいくつか積み重なってきています。 例えばなった方の体を調べるポケ研究では旧世紀にウイルスが消化とかリパ説寝脳といったかなり全身に広がってる可能性が示唆されています。 全身に ええ、あとは生きている方の組織を一部取って調べる政権研究ですね。これだと感染から数ヶ月ある報告ではもう 2 年近く経っても消化間の年膜とか人造肝臓なんかでウイルスの RNAとかN タンパ質が見つかったとされています。 2年近くもですか? はい。弁の検査でも感染後 4ヶ月経っても約13% の方で弁の中にウイルスRNA が検出されたという研究例もありますね。 ふむふむ。 さらにちょっと面白いのが地域の下水ですね。ここから非常にたくさんの変異を持ったまるで隠れた系統クリプティックリネージと呼ばれてますけど、そういうス配列が見つかっていて、これがもしかしたら地域にいる持続感染者から排出されたものなんじゃないかと考えられているんです。 Sから色々なところに痕跡は残る可能性はあると。 そうなんです。 でもそれが活動中のウイルスだって断定はできないわけですね、今のところは。 まさにその通りです。注意点もあって、例えばその政権研究の対象になった方々は元々消化機系の症状があって検査を受けているというケースも含まれている可能性があります。 ああ、なるほど。 そして何より重要なのは繰り返しになりますけど、ウイルスとかタンパ質の断片が見つかることとそれが感染力のある完全なウイルス粒子であることを意味するわけではないということなんです。 はい。 先ほどの用の話、つまりウイルスが生きて増殖できるかどうかの決定的な証拠がこのケースではまだ得られていないというのが現状です。 うん。なるほど。 じゃあロングコビッドとの関連はどうなんですか?ウエルスが残ってるのが原因だみたいな話もありますけど。 ええ、それについてはウイルスの持続あるいはその構成要素の残存があの長引く検体感とかブレインフォグといった症状の原因になってるんじゃないかという仮説はかなり有力視されています。 はい。 ただそのメカニズムはまだ全然分かっていないんです。 もしウイルスが原因だとしてもそれは微量 ながら複製を続けているウイルスなのか、 それとも残ったRNAやタンパク質がこう 慢慢性的な炎症を引き起こしてるのか、 あるいは免疫系のバランス自体がおかしく なっちゃってるのか、または体内に潜在 た別のウイルス、例えばEBウイルスとか が活化してるのか 色々な考えられるわけですね。ええ、本当 に様々な議論されていて、まだ結論は出て いません。 ちなみに他の感染症、例えば地空ユニアネスとかインフルエンザなんかでも感染後に長く症状が続くケースがあることは知られていますね。 なるほど。ロングコビットの原因解明はまだまだこれからということですね。 そうですね。 さて、話を少し戻して持続感染そのものについてですが、このウイルスが体内に長くいること自体が何か別のこう重要な影響をもたらす可能性ってあるんでしょうか? ええ、そこがもう1 つの非常に重要なポイントになります。 と言いますと、 あのですね、持続感染がウイルスの進化を加速させる可能性があるんです。 進化を加速 はい。 持続感染している患者さんから時間を追ってウイルスを採取してその遺伝子配列を調べてみると驚くべきことが分かってきました。感染初期のウイルスと比べて数ヶ月後にはもう複な数の変異を蓄積していることがあるんです。 ほお、そんなにですか。 ええ、これはその人の体の中でウイルスがその環境、つまり祝の体の中で急速に適用するように進化していることを示しています。 多様な変異を持つウイルスの集団。専門的にはクアジースピージーズって言いますけど、わば変異の組むみたいな状態を作り出しているんですね。 体の中で進化が加速する。普通に人から人へ感染していく場合と比べてなぜそんなに早く進化が進むんでしょう? はい。理由は主に2つ考えわれています。 1 つは電波時のボトルネックがないことです。論の図 2を見ると分かりやすいんですが ボトルネック ね。 通常の制感染だと体内に新しい変異が生まれても次の人に感染するのはごく一部のウイルス粒子だけですよね。 はい。はい。 これをボトルネック効果と言ってく有利な変異が生まれても偶然その変異を持たないウイルスだけが次の人に伝わってしまうということがよく起こるんです。 ああ、選ばれないと伝わらない。 そうです。 ところが持続感染の場合、ウイルスはずっと同じ体の中で増え続けますから、有利な変異が到されずにどんどん増えていって集団の中で優位になるための十分な時間があるわけです。 なるほど。電波のいわばくじ引きがないから有利な変異が生き残りやすいと。 そういうことです。で、もう 1 つの理由は持続的な免疫からの圧力です。 免疫のプレッシャーですか? ええ、制感染だと体が本格的に免疫で反撃し始める頃にはもう感染の終わりが見えてますよね。 まあそうですね。 でも持続感染の場合はたえ免疫の力が弱かったとしても長期間にわって交代などから逃げようとする圧力がかかり続けるわけです。 なるほど。 ですから免疫を解するような変異がより 選択されやすい環境にあると言えます。 実際に持続感染中のウイルスの進化 スピードを計算してみるとこれも図2Bに ありますが、あの世界中を騒がせた アルファとかオミクロン株といったされる 変異株BOCですね。これらが出現する に至った進化のスピードに匹敵するか場合 によってはそれを上回るほどの速さで進化 していることが示唆されています。え、 BOC並れ以上。 はい。ただしこれは注意が必要で多様なウイルス集団から平均的な配列、コンセンサス配列っていうのを読み取って比較しているので、実際の個コ々のウイルスの進化はもっと早い可能性もあるという点は竜保が必要ですけどね。 いやいや、でもそれはすごい話ですね。個人の体内で世界的のパンダミックを引き起こした変異株レベルか。それ以上のスピードでウイルスが進化してるかもしれないってことですよね。 ええ、そういう可能性が示唆されているわけです。 ということはですよ、もしかしてあのアルファとかデルタ株、そしてオミクロン株みたいなものすごく変異した株って実はこういう持続感染していた誰かの体内で作られたものだったなんて可能性もあるんでしょうか? まさにその可能性が有力な仮説の 1つとして考えられています。 やっぱりそうですか。 変異株がどうやっと生まれるのかについては主に 3つのシナリオが考えられています。 1 つは多くの人の間で感染が繰り返されるうちに徐々に変異が積み重なっていくパターン。 はい。2 つ目は人から感染した動物の体内で返異してそれがまた人に戻ってくるパターン。動物リザーバー経由ですね。 ああ、動物から。 そして3 つ目がこの持続感染した個人の体内で一気に変異を駆するというパターンなんです。 うーん。でもちょっと待ってください。 普通に考えると特定の人の体の中で特別に適用したウイルスってむしろ他の人には感染しにくくなったりしませんか?なんか HIV の研究とかではそういう話を聞いたことがあるような気がするんですが。 ああ、良い指摘ですね。確かに一般的にはそう考えられます。祝の体の中で増えやすくなるための変異と人から人へ効率よく電波するための変異っていうのは必ずしも同じではないんですね。 ですよね。 縮に特化しすぎると帰って電波能力が落ちるなんてこともあり得るわけです。 うん。 そこがこの仮説のま、興味深くもあり、少し意外な点でもありました。 ええ。 しかしサーズコブ 2 の変異株の出現の歴史を振り返ってみるとどうもこの持続感染由来説を指示するような証拠が見えてくるんです。 ほうというと、 例えば初期に出てきたアルファブ、これは感染力とか電波力を高める変異。 例えばスパイクタンパ質の N501Y変異とか6970 消出とかですね。あとは体の初期防御である自然免疫を交わす異、 NSP6 という部分の血出とかそういうのは持っていたんですが交代から逃れる変異は少なかったんです。 ふむふむ。 これはまだ集団の大部分が免疫を持っていなかったデミック初期の状況と会いますよね。 なるほど。免疫がないから逃げる必要もあまりなかったと。 そういうことです。で、次に出てきた株。 これは細胞にくっつく能力を高める変異A 701Vに加えて一部の交代から逃れる ための変異K417NとかE484Kこれ も持ち合わせてましたワクチンとか過去の 感染によって少しずつ集団の免疫レベルが 上が期の現 はい そして皆さんの記憶にも新しい オミクロン株最初 のBA1系統ですね ええありましたね これはもう明らかに交代から逃れる能力が拡段に上がっていまし 特にスパイクタンパ質の中でも重要な細胞にくっつく部分 RBDにたくさんの変異がありました。 ありましたね。変異が多いって。 ええ、それに加えて電波しやすく増えやすくなるような変異 H55Y とかまた出てきましたけど 69ダ70ケ出NSP6 決出とかそういうのも合わせ持っていた。 これはワクチン摂取や過去の感染によって集団の免疫レベルが非常に高くなった状況で登場しました。図を見るとその関係がよく分かれます。 免疫レベルと変異のタイプが連動してる感じなんですね。 そうなんです。 で、ここで本当に注目すべきなのはこれらの変異株で見つかった変異の多くが実は持続感染している患者さんの体内でも独立して繰り返し進化によって生まれていることが確認されているという点なんです。 えっと、同じ変異が持続感染者の中でも ええ、そうです。 論文の補足表1にリストがあるんですが、 例えば交代回避に関わるN440K、E 484A、Q493R、Q498R といった変異、あるいは感染力電波力に 関わるNSP6、69-70ケ、N 501Y、P681Rといった変異。 これらは変異株と持続感染の両方で見つかる進化の例と言えるんですね。 終練進化。別々の場所で同じような進化が起こるってことですね。 そういうことです。つまりパンデミックの時期団免疫のレベルによって有利になる変異のタイプは変わるわけですけど 13 シャ持続感染という環境はまるで変異の実験上のように様々なタイプの変異を生み出し続けている可能性があると。 うわあ、なるほど。 変異株で見つかった特徴的な変異が持続感染者の体内でも独立して生まれているっていうのはこれはかなり強い状況証拠ですね。 ええ、 持続感染が変異株の製造工場になってるかもしれないっていう仮説にぐっと説得力が増しますね。 そうですね。そしてその製造工場がもしかしたら特に集中しているかもしれないと疑われている地域があるんです。 え、そんな場所が? それが南アフリカなんです。 南アフリカ。 はい。 実際先ほど名前が出たベータ株とかオミクロン株の最初の BA1、BA2 系統さらにその後に出てきた BA2.86 といった特に変異の数が多い株の多くが世界で最初に南アフリカで検出報告されているんですね。図 4シ。 なぜ南アフリカでたまたま見つかっただけということではないんですか? もちろんその地域のゲノムサーベイランス体制、つまりウイルスの遺伝子を監視する能力が非常に高いということも早期発見につがっている大きな理由の 1つです。これは間違いありません。 はい。 しかしそれだけではない可能性も指摘されています。 1 つは免疫不全状態のある人の割合が他の地域に比べて高いことです。 特に治療を受けていない、あるいは治療がうまくいっていない進行した HIV 感染者の数が多くてですね、南アフリカだけで約 80万人に登ると推定されています。 80 万人も。 ええ、そしてもう1つの可能性として HIV 感染者の免疫状態の多様性が関係しているのではないのかとも考えられています。 免疫状態の多様性。 はい。HIV感染者の免疫抑制の度合と いうのは治療状況なんかによって本当に人 それぞれなんですね。 中にはウイルスを完全に排除するには至らないけれども、ウイルスに変異を促す路のなんていうか、中途半端な免疫圧力がかかっている状態の人がいるかもしれないと。 ああ、完全に抑え込めてはいないけどプレッシャーはかかっているみたいな。 そうです。このような状態がウイルスにとっては変異を重ねて進化するのに帰って都合の良い環境を提供してしまっているのではないかというわけです。 なるほど。 免疫不全のさとその免疫状態のグラデーションみたいなものが結果的に変異株を生み出しやすい土上を作っている可能性があるということですか?うーん。これは非常に考えさせられますね。 [音楽] ええ。 では実際に持続感染している方の症状とか治療というのはどうなってるんでしょうか? はい。持続感染している方の症状はですね、元々持っている病気基礎疾患に大きく左右されるので本当に様々です。 思い尾と19の症状が出る方も いらっしゃいますし、一方で特に免疫党 自体が非常に弱っている進行HIV感染者 などの場合症状が出ない全くの無症状と いうケースも報告されています。無症状の 場合もあるんですか?ええ、免疫が十分に 戦わないので症状も出にくいということ ですね。なるほど。 治療はどうなんですか? 治療に関してはまだ確立された方法というのはなくてですね、少報告レベルでの思考錯誤が続いているというのが現状です。高ウイルス役、レムデシビルとかパキロビットとかですね。これを長期間使う方法がありますが、やはり薬が効きにくい体制ウイルスが出てくるリスクも指摘されています。 ああ、体制の問題が。 ええ、なので高ウイルス役と交代とか回復した人の決晶みたいな免疫を利用した治療を組み合わせたり、あるいは HIV感染者の方であればまず HIV自体の治療、ART 療法をしっかり行うことが重要だと考えられています。 なるほど。基礎疾患のコントロールも大事なんですね。 はい。非常に重要です。 では今回の探求で分かってきた重要なポイントを最後にまとめていただけますでしょうか? はい、承知た。 まず抑えておくべきなのはサーズコブ 2 は特に免疫の働きが低下している方において数ヶ月という長期間にわって体内度増え続ける持続感染を起こし売るということです。 はい。 次にこの持続感染という状況は祝の体の中でウイルスの進化を劇的に加速させ免疫から逃れる変異と感染力を高める変異の両方を生み出す変異の音症となり得るということです。 変異の症。 ええ。 そしてこれが最もインパクトのある点かもしれませんが、特に多くの人が免疫を持つようになった状況ではこのような持続感染がオミクロン株のような高度に変異した新しい変異株の機嫌となっている可能性が高いということです。 機嫌になっている可能性が高いと。 はい。一方で免疫が正常な人で見られるウイルスの痕跡の長期残存とロングコビッドとの間にはまだ明確な因果関係。 特に生きたウイルスが持続しているという証拠は確立されていないという点も重要です。ここは区別して考える必要がありますね。 なるほど。いやあ、実に実に興味深い話でした。この少数の特定の個人の体の中で起こるウイルスの長期潜伏と進化がもしかしたら世界全体のパンデミックの要素を一変させてしまう可能性がある。 ええ、 このある種の偶然性がもたらす影響の大きさというのはこれから先新たに出現するかもしれない変異株を予測したり、あるいは日常の病気、フード病となったサーズコブ 2 とどう付き合っていくかを考える上で一体どんな意味を持つんでしょうかね。 うーん。そうですね。 そしてこのメカニズムは将来現れるかもしれない全く新しいウイルスにももしかしたら当てはまることなのかもしれない。非常に深く考えさせられるですね。 皆さんも是非この点についてちょっと考え てみていただけたらと思います。大阪大学 医学部付属病院の感染症内科ではフェロー 、短期研修生、入局者、そして大学院生を 激しく募集しています。都え反対へ。
元の論文
The consequences of SARS-CoV-2 within-host persistence
Citation
Nat Rev Microbiol. 2025;23:288–302.
要約
本総説は、SARS-CoV-2が一部の免疫不全患者で長期持続感染を起こす仕組みと、その意義を整理している。免疫不全例(進行HIVや抗CD20抗体療法など)では、ウイルス排除が不十分となり、数カ月に及ぶ持続感染が報告されている。これらでは高ウイルス量が維持され、抗体回避や細胞親和性増大をもたらす変異が急速に蓄積し、変異株出現の温床となり得る。免疫正常例では、消化管など呼吸器以外の部位にウイルスRNAや抗原が長期間検出されるが、複製能のあるウイルスが存在するかは未解明である。疫学的には持続感染は稀(0.01–0.06%)と推定されるが、一部はAlphaやOmicron BA.2.86のような大きな進化枝の起源となった可能性がある。さらに、長期にウイルス抗原が残存することがlong COVIDの一因かどうかも議論されている。治療においては延長抗ウイルス療法や免疫療法の有効例があるが、耐性リスクも報告されている。著者らは、持続感染の理解がCOVID-19の病態解明および次のパンデミック備えに不可欠であると結論づけている。