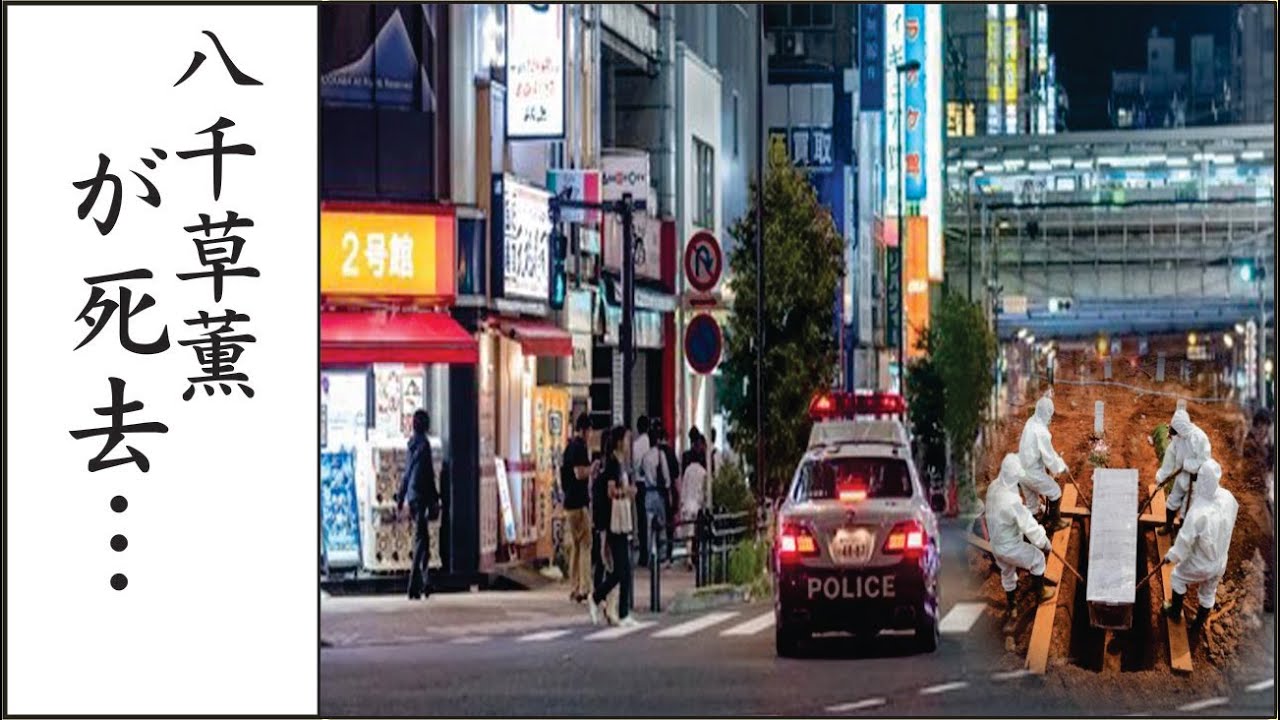八千草薫の最期の予兆に涙が止まらない…八千草薫の息子を襲った病気の真相に一同驚愕!
八草香るという存在はまるで静かな面に 移る月の光のように決して小高かに事故を 主張することなくそれでいて誰の心にも 深く染み込んでいく不思議な力を持ってい た。宝塚過激団に入団した頃から彼女は他 の誰とも似ていない雰囲気をまとっていた 。 華やかで堂々と舞台を支配する娘役もいれ ば強い光で観客を圧倒するスターもいた。 しかし八草はそのどちらでもなかった。 彼女はひっそりと立たずみ微笑みほんの 一言柔らかな声を響かせるだけで舞台全体 の空気を変えてしまう。 観客は気づかぬうちにその世界に引き込ま れ彼女が去った後の余因に酔いしれるの だった。の世界に飛び込んだ八草カおはる 清楚という理想を対現するかのように スクリーンに現れた。 戦後の混乱から立ち直ろうとする人々に とって彼女の姿は未来への希望の象徴だっ た。黒沢明監督の隠しでの三人で彼女が 放ったマ志は権や陰謀が渦まく物語の中で 一際住んだ光を放っていた。その光は作中 の登場人物だけでなく観客1人1人の胸に 差し込み暗い現実をほんの少しでも照らし てくれるようなぬくもりを持っていた。時 が流れ、若い頃のカレンさが成熟へと 変わると八草は母祖母の役を演じるように なった。だがそこに漂う気品は決して失わ れることなく、むしろ彼女の言葉の1つ1 つに重みがまし、視聴者は自分の母や祖母 もこうであったならと願わずにはいられ なかった。画面の向こうで微笑えむ八草は もう女優という存在を超え、人々の心に 住みつく理想の家族となっていた。 プライベートでは建築家の家にとぎ芸能人 らしい派手さから距離を置き、ひたすらに 性質な生活を貫いた。だがそのしけさこそ が彼女を輝かせ、作品に映し出された時に 生きた真実身を与えていたのだろう。周囲 の人々はかおさんはいつも変わらないと口 を揃えた。置いてなお背筋を伸ばし優雅に 歩き柔らかな声で語りかける姿は時代が うろっても人間の品とは何かを教えて くれるようだった。 晩年彼女が病に犯されながらも女優である ことをやめなかったという事実は多くの 人々の胸を打った。カメラの前に立つこと は彼女にとって生きることそのものだった のだろう。最後までリとして誰よりも静か にしかし確かに輝きを放ち続けた八草香る 。その存在は消えることのない星のように 日本人の心の夜空に明かり続けている。 彼女が歩んだ道を振り返ると、それは まるで1本の長い小道のようで、春の花が 先にれる季節もあれば、夏の日差しが 眩しく降り注ぐ瞬間もあり、秋の夕暮れの ような物寂しさや冬の厳しさもあった。 しかし八草香という人はどの季節にあって も決して足を止めることなく、その時々の 景色を受け入れ、穏やかな笑を称えて前に 進み続けた。宝塚の少女だった頃、彼女は 自分はスターにはならないだろうとどこか していたとも言われるが、だからこそ舞台 に立つ度に1つ1つの役を大切にし、観客 にとって忘れがい印象を残した。 スクリーンに進出した後も同じで、派手な 演技や過剰な自己主張とは無縁であり ながら、その透明感溢れる存在は見るもの の心を静かに支配した。の銀幕で彼女が 放った光は戦後の混乱を経て希望を探して いた人々の心にとってどれほど大きな支え になったことだろう。黒沢作品で権の影を 切り裂くようなマ差しを放ち、現代劇では 家庭を包み込むぬくもりを漂わせ、時代劇 ではイニシエの女性の毛高さを対現した。 どの時代、どの作品であっても八草香は そこにいるだけで世界を完成させる旧な 女優であった。家庭に入っても決して女優 という道を捨てず、むしろ私生活で培った しけさや深みが役柄に厚みを与えていった 。母親役を演じれば見るものは自分の母を 思い出し、祖母役を演じればこんな祖母に 抱かれたいと胸を熱くした。若い頃の家差 が老に差しかかるとともに気品へと変わり 、彼女は女性が年を重ねてもなお美しく あるとはどういうことかお自らの生き方で 示して見せた。やがて時代が平成を迎え、 芸能界の空気が変わっても八草はその波に 流されることなく性質な気配をまとい続け た。 彼女の声を聞けば人は安らぎに姿を見れば 配金を正された。 ある時共演した若い女優がカオルさんの隣 に立つと自分がそやに思えるとこぼしたと いうがそれは彼女の持つ独特の気品がただ 外見ではなく人としてのあり方から滲み出 ていた証にほならない晩年病を抱えながら も作品に挑む姿は観客だけでなく共演者や スタッフの胸にも深い印象を残した演じる という行為が単なる仕事ではなく彼女に とっては呼吸と同じ生きることそのもの だったのだろう。 最後まで現役であり続けたその姿はまるで 夕暮れに輝きを増す星のように時間と共に 帰って強い光を放っていた。静かに膜を 閉じた後も彼女が残した映像や言葉は今 なお人々の心に生きづいている。 八草香は単なる1人の女優ではなく、日本 人の心に刻まれた理想の女性像として永遠 に語り継がれるに違いない。八草香が晩年 に差しかかってもなお人々を引きつけ続け た理由は彼女が単に女優として優れていた からではなく、その存在そのものが時代を 超えて生き方の美学を対現していたからで あった。彼女の歩みは華やかな舞台や銀幕 だけでなく静かな日常の積み重ねにも輝き が宿っていた。ある冬の朝、雪が庭先に 降り積もり、白く覆われた世界を窓越しに 見つめながら彼女は小さく綺麗と呟いたと いう。何気ないその一言に言わせた人々は 八草香という女性が人生の最後の瞬間に 至るまで目の前の小さな美しさを見逃さず 慈しむ心を持ち続けていたことを知り深い 歓明を受けた。な言葉も派手な書作もなく 、ただ日常を大切に生きるその姿勢こそが 多くの人の心を静かに揺さぶったのだ。病 の影が忍び寄ってからも彼女は決して弱ね を吐かず、むしろ周囲を気遣い現場では スタッフ1人1人に丁寧に声をかけ続けた 。 ある撮影現場で彼女は体調が優れないにも 関わらず長時間の待機を黙って受け入れ、 若いスタッフに寒くないと微えんだという 。その姿に言わせた者たちは胸を熱くし、 誰もがこの人のために最善を尽くそうと心 から思った。 彼女にとって演じることは自己表現では なく、人と人をつぐ行為であり、カメラの 前で役を生きることで観客に希望や安らぎ を届けることだったのだろう。晩年の インタビューで彼女はどんな役でもその人 の人生を生きているつもりで演じたいと 語った。 その言葉通り彼女の演技には一点の偽りも なく観客はいつも真実の人間を見い出した 。八草香が亡くなった時、多くの人々が 喪失感に包まれたが、それは単に1人の 名女優を失ったという以上の意味を持って いた。彼女の存在は日本の人々にとって 気品とは何か、優しさとは何かを移す鏡の ようであり、その光を失ったことで世界が 少し暗くなったように感じられたのだ。 しかし同時に人々の記憶の中で彼女は今 なお行き続けている。 古い映画を再生すればそこに変わらぬ笑が あり、ドラマの再放送を見ればまるで家族 の一員のように寄り添ってくれる。彼女の 存在は過去に閉じ込められたものではなく 、未来へと受け継がれる遺吹きなのだ。 ある若い女優は八草さんのように年を重ね たいと語り、ある視聴者は彼女を見ると心 が穏やかになると言った。そうして1人 また1人と彼女の生き方を胸に刻む人々が 増え、八草かは時代を超えて行き続ける。 春の桜の下を歩けば太彼女の柔らかな笑が 思い浮かび、秋の夕暮れに染まる町を 眺めればその佇まいが蘇える。八草カお 女優としてだけでなく人としてどう生きる かを示してくれた。 彼女の人生は1本の映画のように幕を閉じ たが、その余因は観客の心の奥深に流れ 続けているのである。八草香の人生を物語 として語り継ごうとすれば、そこにはいつ も光と影のコントラストが浮かび上がる。 彼女は表部隊では清楚で優雅な女優として 人々に愛されてきたが、その裏には静かな 葛藤や孤独が隠されていたとも言われる。 幼少の頃から人前に立つことを宿命付け られたように舞台の道へと進み宝塚で 華やかに羽いたが、その華やかさの影で 自分はどう生きるべきかという問いを抱え 続けた。人気の過中にありながらも彼女が 決して奢らず、むしろ控えめに振るまった のは常に自分を見失う前とする心の防波堤 だったのかもしれない。スクリーンに移る 姿は確かに清らかで柔らかかったが、役を 終えて1人になった時、彼女は静かな部屋 で台本を抱きしめるようにして、この役を 生きることで私は少しでも人に寄り添えた だろうかと自問していたのだろう。 やがて映画黄金機を駆け抜けた後、テレビ ドラマという新たな舞台に立つと彼女は母 祖母と言った役柄を通じて多くの家庭に 理想の家族像を届けた。視聴者は画面を 通して彼女に励まされ、時に涙出し時に 微えんだ。 ある老夫人は晩年の彼女を見て八草さんを 見ていると昔なくした母に会える気がする と語ったという。その言葉は八草香という 女優が役柄を超えて人々の人生に寄り添う 存在であったことを物語っている。家庭で は建築の名門にとぎ表には決して出さない 性質な時間を大切にした。庭に咲花を眺め ながら夫と語らう時間。台所に立ちながら 明日の献立てを考える時間。どれも舞台と は無縁のように見えて実は女優としての 彼女を支えていた。日常を大切にすること で演じる役に本物の温かさを吹き込むこと ができたのだ。だからこそ彼女の母親役に は作り物ではないぬくもりがあり、ぼ薬に は心からの優しさがあった。人生の晩年に 病が訪れても彼女は決して悲想感を漂わせ ず、むしろその姿にリとした美しさを宿し た。撮影現場で休憩中にそっと鼻ガめの花 を直しながらこれで少し華やかになったわ ねと微笑んだ彼女を見てスタッフたちは涙 をこえきれなかったという。誰よりも弱っ ているはずの人が誰よりも周囲を思いやる その姿に人間としての真の強さがあった。 やがて彼女の最後の時が近づくと関わった 人々は不思議と恐怖ではなく静かな安らぎ を感じたという。八草かは自らの塩も1つ の美しい舞台の幕として受け入れていたの だろう。彼女の枕本源には障害大切にして きた台本や花が置かれていたと伝えられる 。その最後の微笑みは長い人生を慈くしみ 愛し抜いた人にしかできない穏やかなもの であった。 そして彼女が息を引き取った瞬間、多くの 人が涙を流しながらも八草さんらしいと口 にした。彼女は最後までヤぶカオルであり 続け、優雅で気品に満ちたまま静かに去っ ていったのだ。 だがその存在は決して失われない。 スクリーンや映像の中で、あるいは人々の 記憶の中で彼女は今も生きづいている。さ が叫ば彼女の柔らかな笑顔を思い出し、 秋風が吹けばその落ち着いた声を思い出す 。 八草香は1人の女優を超え、人々の心に 永遠に行き続ける美しき生き方の象徴と なった。八草香の人生をさらに深く書こう とするならば、それは1つの電気を超えた 長大な女児師のようになっていく。彼女は 決して自らを誇張して語らなかったが、 その静かな歩みの中に実は多くの秘密や 小さな奇跡が宿っていた。宝塚に入団した 若き日の彼女は舞台袖で何度も不安に駆ら れたという 華やかな光の中に立つと自分が溶けて消え てしまうのではないか。そんな恐怖を抱き ながらも舞台に出ればその存在は確かな光 を放ち観客の心を掴んで話さなかった。 彼女は自分を大きく見せることを知ら なかったが、だからこそ観客は彼女の自然 体の美しさに心を寄せたのだ。映画の世界 に入るとその魅力はさらに際だった。戦後 の人々が未来に夢を託そうとしていた時代 八草香の透明な微笑みはまだ日本には希望 があると信じさせる力を持っていた。 黒沢明監督の現場では厳しい演出の中でも 彼女は1度も顔を曇もらせることなく紳摯 に役と向き合った。カメラが回っていない 時も役の心を生き続けるその姿に周囲の 俳優たちはカオルさんの旗に立つと自分も 配金が伸びると感じたという。 やがて時代がり変わり映画からへと活躍の場が広がると八千草おは想の母理想の祖母としてに親しまれた。その裏側で彼女は演じるに相と現実の間に揺れていた。実の程は時に複雑で必ずしも穏やかではない。 それでも彼女は役を通じて人の心に優しさ を灯せるなら、それは私の使命と信じ、 画面の向こうにいる視聴者のために全身 前例を注いだ。 撮影現場で若い俳優がセリフに詰まると 彼女はそっと横に立ち、大丈夫よ。 ゆっくりでいいのと支いた。その声に救わ れた俳優たちは数知れず、彼女の優しさは スクリーンを超えて人の人生に触れていた 。晩年病が彼女を蝕ばみ始めた時でさえ その品は失われなかった。点敵を受け ながらもお化粧はきちんとしなくてはねと 微笑み、みりを整えることを忘れなかった 。その姿は美しく生きるということが 単なる外見の問題ではなく、最後まで自分 を大切にする心のあり方であることを示し ていた。彼女の最後の日々は静かで穏やか だったと伝えられるが、そこに寄り添った 人々は皆カおさんの周りには不思議と 温かい空気が流れていたと口を揃える。死 を恐れるのではなく、まるで次の舞台へ 向かう準備をしているかのように彼女は 微笑みを絶さなかった。 そして幕が降りた後も八草香の存在は消え なかった。古い映画を見る人々はその 微笑みに励まされ、ドラマの再放送に涙 する人々はまるで家族に再開したようだと 語った。高い女優は年を重ねても八草さん のようでありたいと夢を抱き、観客は人生 の最後まで優雅でありたいと心に誓った。 八草かはもはや1人の女優ではなく、生き 方そのものが人々の指針となったのである 。彼女が歩んだ小道は静かで控えめだった が、その後には春の花が先乱れ、秋の木々 が色づき、冬の雪が清らかにツもっている 。 彼女の人生は一ぺの歌のように今も人々の 心に読みつがれ、語り継がれていく。草 香るという存在はまるで静かなに移る月の 光のように決して小高に事故を主張する ことなくそれでいて誰の心にも深く 染み込んでいく不思議な力を持っていた。 宝塚過激団に入団した頃から彼女は他の誰 とも似ていない雰囲気をまとっていた。 華やかで堂々と舞台を支配する娘役もいれ ば強い光で観客を圧倒するスターもいた。 しかし八草はそのどちらでもなかった。 彼女はひっそりと立たずみ微笑み、ほんの 一言柔らかな声を響かせるだけで舞台全体 の空気を変えてしまう。 観客は気づかぬうちにその世界に引き込ま れ彼女が去った後の余因に酔い知れるの だった。映画の世界に飛び込んだ八草 カオルは時代が求める清楚という理想を 対現するかのようにスクリーンに現れた。 戦後の混乱から立ち直ろうとする人々に とって彼女の姿は未来への希望の象徴だっ た。黒沢明監督の隠しでの三人で彼女が 放ったマ志は権や陰謀が渦まく物語りの中 で人際は住んだ光を放っていた。その光は 作中の登場人物だけでなく、観客1人1人 の胸に差し込み、暗い現実をほんの少しで も照らしてくれるようなぬくもりを持って いた。時が流れ、若い頃のカレンさが成熟 へと変わると八草は母祖母の役を演じる ようになった。だが、そこに漂う気品は 決して失われることなく、むしろ彼女の 言葉の1つ1つに重みが増し、視聴者は 自分の母祖母もこうであったならと願わず にはいられなかった。画面の向こうで 微笑む八草はもう女優という存在を超え、 人々の心に住みつく理想の家族となってい た。ライベートでは建築家の家にとぎ 芸能人らしい派手さから距離を置き、 ひたすらに性質な生活を貫いた。だがその しけさこそが彼女を輝かせ、作品に 映し出された時に生きた真実身を与えてい たのだろう。周囲の人々はカおさんはいつ も変わらないと口を揃えた。相手なお背筋 を伸ばし優雅に歩き柔らかな声で 語りかける姿は時代がうろっても人間の 品異とは何かを教えてくれるようだった。 晩年彼女が病に犯されながらも女優である ことをやめなかったという事実は多くの 人々の胸を打った。カメラの前に立つこと は彼女にとって生きることそのものだった のだろう。最後までリとして誰よりも静か にしかし確かに輝きを放ち続けた八草香る 。その存在は消えることのない星のように 日本人の心の夜空に明かり続けている。 彼女が歩んだ道を振り返ると、それは まるで1本の長い小道のようで、春の花が 先にダれる季節もあれば、夏の日差しが 眩しく降り注ぐ瞬間もあり、秋の夕暮れの ような物寂しさや冬の厳しさもあった。 しかし八草香という人はどの季節にあって も決して足を止めることなく、その時々の 景色を受け入れ、穏やかな笑を称えて前に 進み続けた。宝塚の少女だった頃、彼女は 自分はスターにはならないだろうとどこか 達感していたとも言われるが、だからこそ 舞台に立つ度に1つ1つの役を大切にし、 観客にとって忘れがい印象を残した。 クリーンに進出した後も同じで派手な演技 や過剰な自己主張とは無縁でありながら その透明感溢れる存在は見るものの心を 静かに支配した。昭和の銀幕で彼女が放っ た光は戦後の混乱を経て希望を探していた 人々の心にとってどれほど大きな支えに なったことだろう。黒沢作品で権の影を 切り裂くような、マ差しを放ち、現代劇で は家庭を包み込むぬくもりを漂わせ、時代 劇ではイニシエの女性の毛高さを対現した 。どの時代、どの作品であっても八草か香 はそこにいるだけで世界を完成させる急な 女優であった。家庭に入っても決して女優 という道を捨てず、むしろ私生活で培った しけさや深みが役柄に厚みを与えていった 。母親役を演じれば見るものは自分の母を 思い出し、祖母役を演じればこんな祖母に 抱かれたいと胸を熱くした。若い頃の家差 が労に差しかかるとともに気品へと変わり 、彼女は女性が年を重ねてもなお美しく あるとはどういうことかお自らの生き方で 示して見せた。やがて時代が平成を迎え、 芸能界の空気が変わっても八草はその波に 流されることなく性質な気配をまとい続け た。 彼女の声を聞けば人は安らぎに姿を見れば 拝金を正された。 ある時共演した若い女優がかおさんの隣に 立つと自分がそやに思えるとこぼしたと いうがそれは彼女の持つ独特の気品がただ 外見ではなく人としてのあり方から滲み出 ていた証にほなならない晩年病を抱え ながらも作品に挑む姿は観客だけでなく 共演者やスタッフの胸にも深い印象を残し た演じるという行為が単なる仕事では彼女 にとっては呼吸と同じ生きることそのもの だったのだろう。 最後まで現役であり続けたその姿はまるで 夕暮れに輝きを増す星のように時間と共に 帰って強い光を放っていた。静かに膜を 閉じた後も彼女が残した映像や言葉は今 なお多くの人々の心に生きづいている。 八草香は単なる1人の女優ではなく、日本 人の心に刻まれた理想の女性像として永遠 に語り継がれるに違いない。八草か晩年に 差しかかってもなお人々を引きつけ続けた 理由は彼女が単に女優として優れていた からではなく、その存在そのものが時代を 超えて生き方の美学を対現していたからで あった。彼女の歩みは華やかな舞台や銀膜 だけでなく静かな日常の積み重ねにも輝き が宿っていた。ある冬の朝、雪が庭先に 降りツもり、白く覆われた世界を窓越しに 見つめながら彼女は小さく綺麗と呟いたと いう。何気ないその一言に言わせた人々は 八草香という女性が人生の最後の瞬間に 至るまで目の前の小さな美しさを見逃さず 慈しむ心を持ち続けていたことを知り、 深い歓明を受けた。な言葉も派手な書作も なく、ただ日常を大切に生きるその姿勢 こそが多くの人の心を静かに揺さぶったの だ。病の影が忍び寄ってからも彼女は 決して弱ねを吐かず、むしろ周囲を気遣い 現場ではスタッフ1人1人に丁寧に声を かけ続けた。 ある撮影現場で彼女は体調が優れないにも 関わらず長時間の待機を黙って受け入れ、 若いスタッフに寒くないと微えんだという 。その姿に言わせた者たちは胸を熱くし、 誰もがこの人のために最善を尽くそうと心 から思った。 彼女にとって演じることは自己表現では なく、人と人をつぐ行為であり、カメラの 前で役を生きることで観客に希望や安らぎ を届けることだったのだろう。晩年の インタビューで彼女はどんな役でもその人 の人生を生きているつもりで演じたいと 語った。 その言葉通り彼女の演技には一点の偽りも なく観客はいつも真実の人間を見い出した 。八草香が亡くなった時、多くの人々が 喪失感に包まれたが、それは単に1人の名 女優を失ったという以上の意味を持ってい た。彼女の存在は日本の人々にとって気品 とは何か、優しさとは何かを移す鏡のよう であり、その光を失ったことで世界が少し 暗くなったように感じられたのだ。しかし 同時に人々の記憶の中で彼女は今なお生き 続けている。 古い映画を再生すればそこに変わらぬ笑味 があり、ドラマの再放送を見ればまるで 家族の一員のように寄り添ってくれる。 彼女の存在は過去に閉じ込められたもので はなく、未来へと受け継がれる遺吹きなの だ。 ある若い女優は八草さんのように年を重ね たいと語り、ある視聴者は彼女を見ると心 が穏やかになると言った。そうして1人 また1人と彼女の生き方を胸に刻む人々が 増え、八草かは時代を超えて行き続ける。 春の桜の下を歩けば太彼女の柔らかな笑が 思い浮かび、秋の夕暮れに染まる町を 眺めればその佇まいが蘇える。八草香は 女優としてだけでなく人としてどう生きる かを示してくれた。 彼女の人生は1本の映画のように膜を閉じ たが、その余因は観客の心の奥深くに流れ 続けているのである。八草香の人生を物語 として語り継ごうとすれば、そこにはいつ も光と影のコントラストが浮かび上がる。 彼女は表部隊では清楚で優雅な女優として 人々に愛されてきたが、その裏には静かな 葛藤や孤独が隠されていたとも言われる。 幼少の頃から人前に立つことを宿命付け られたように舞台の道へと進み宝塚で 華やかに羽いたがその華やかさの影で自分 はどう生きるべきかという問いを抱え続け た。人気の過中にありながらも彼女が 決して奢らず、むしろ控えめに振るまった のは常に自分を見失う前とする心の防波堤 だったのかもしれない。スクリーンに移る 姿は確かに清らかで柔らかかったが、役を 終えて1人になった時、彼女は静かな部屋 で台本を抱きしめるようにして、この役を 生きることで私は少しでも人に寄り添えた だろうかと自問していたのだろう。 やがて映画黄金機を駆け抜けた後、テレビ ドラマという新たな舞台に立つと彼女は母 祖母と言った役柄を通じて多くの家庭に 理想の家族像を届けた。視聴者は画面を 通して彼女に励まされ、時に涙出し時に 微えんだ。 ある老夫人は晩年の彼女を見て八草さんを 見ていると昔なくした母に会える気がする と語ったという。その言葉は八草香という 女優が役柄を超えて人々の人生に寄り添う 存在であったことを物語っている。家庭で は建築の名門にとぎ表には決して出さない 性質な時間を大切にした。庭に咲花を眺め ながら夫と語らう時間。台所に立ちながら 明日の献立てを考える時間。どれも舞台と は無縁のように見えて実は女優としての 彼女を支えていた。日常を大切にすること で演じる役に本物の温かさを吹き込むこと ができたのだ。だからこそ彼女の母親役に は作り物ではないぬくもりがあり、ぼ役に は心からの優しさがあった。人生の晩年に 病が訪れても彼女は決して悲想感を漂わせ ず、むしろその姿にリとした美しさを宿し た。撮影現場で休憩中にそっと鼻ガめの花 を直しながらこれで少し華やかになったわ ねと微笑えんだ彼女を見てスタッフたちは 涙をこらえきれなかったという。誰よりも 弱っているはずの人が誰よりも周囲を 思いやるその姿に人間としての真の強さが あった。やがて彼女の最後の時が近づくと 関わった人々は不思議と恐怖ではなく静か な安らぎを感じたという。八草かは自らの 塩も1つの美しい舞台の幕として受け入れ ていたのだろう。彼女の枕元には障害大切 にしてきた台本や花が置かれていたと伝え られる。その最後の微笑みは長い人生を 慈くしみ愛し抜いた人にしかできない 穏やかなものであった。 そして彼女が息を引き取った瞬間、多くの 人が涙を流しながらも八草さんらしいと口 にした。彼女は最後まで八ぶ草カオルで あり続け、優雅で気品に満ちたまま静かに 去っていったのだ。 だがその存在は決して失われない。 スクリーンや映像の中であるいは人々の 記憶の中で彼女は今も行きづいている。さ が叫彼女の柔らかな笑顔を思い出し、秋風 が吹けばその落ち着いた声を思い出す。 八草香は1人の女優を超え、人々の心に 永遠に行き続ける美しき生き方の象徴と なった。八草香の人生をさらに深く書こう とするならば、それは1つの電気を超えた 長大な女児子のようになっていく。彼女は 決して自らを誇張して語らなかったが、 その静かな歩みの中に実は多くの秘密や 小さな奇跡が宿っていた。宝塚に入団した 若き日の彼女は舞台袖で何度も不安に狩ら れたという 華やかな光の中に立つと自分が溶けて消え てしまうのではないか。そんな恐怖を抱き ながらも舞台に出ればその存在は確かな光 を放ち観客の心を掴んで話さなかった。 彼女は自分を大きく見せることを知ら なかったが、だからこそ観客は彼女の自然 体の美しさに心を寄せたのだ。映画の世界 に入るとその魅力はさらに際だった。戦後 の人々が未来に夢を託そうとしていた時代 、八草香の透明な微笑みはまだ日本には 希望があると信じさせる力を持っていた。 黒沢明監督の現場では厳しい演出の中でも 彼女は1度も顔を曇もらせることなく紳摯 に役と向き合った。カメラが回っていない 時も役の心を生き続けるその姿に周囲の 俳優たちはカオルさんの旗に立つと自分も 配金が伸びると感じたという。 やがて時代がり変わり映画からへと活躍の場が広がると八千草おは想の母理想の祖母として人々に親しまれた。その裏側で彼女は演じるに想と現実の間に揺れていた。実の程は時に複雑で必ずしも穏やかではない。 それでも彼女は役を通じて人の心に優しさ を灯せるなら、それは私の使命と信じ、 画面の向こうにいる視聴者のために全身 前例を注いだ。 撮影現場で若い俳優がセリフに詰まると 彼女はそっと横に立ち、大丈夫よ。 ゆっくりでいいのと支いた。その声に救わ れた俳優たちは数知れず、彼女の優しさは スクリーンを超えて人の人生に触れていた 。晩年病が彼女を蝕ばみ始めた時でさえ その品は失われなかった。点敵を受け ながらもお化粧はきちんとしなくてはねと 微笑み、みりを整えることを忘れなかった 。その姿は美しく生きるということが 単なる外見の問題ではなく、最後まで自分 を大切にする心のあり方であることを示し ていた。彼女の最後の日々は静かで穏やか だったと伝えられるが、そこに寄り添った 人々は皆カおさんの周りには不思議と 温かい空気が流れていたと口を揃える。死 を恐れるのではなく、まるで次の舞台へ 向かう準備をしているかのように彼女は 微笑みを絶さなかった。 そして幕が降りた後も八草香の存在は消え なかった。古い映画を見る人々はその 微笑みに励まされ、ドラマの再放送に涙 する人々はまるで家族に再開したようだと 語った。若い女優たちは年を重ねても八草 さんのようでありたいと夢を抱き、観客は 人生の最後まで優雅でありたいと心に誓っ た。 八草香はもはや1人の女優ではなく、生き 方そのものが人々の指針となったのである 。彼女が歩んだ小道は静かで控えめだった が、その後には春の花が先乱れ、秋の木々 が色づき、冬の雪が清らかにツもっている 。 彼女の人生は一ぺの歌のように今も人々の 心に読み継がれ語り継がれて
Please support me by subscribing to the channel. To see the latest videos ! . If you like it, please like and share. If you have any questions, please comment below! Thank you so much !love you !