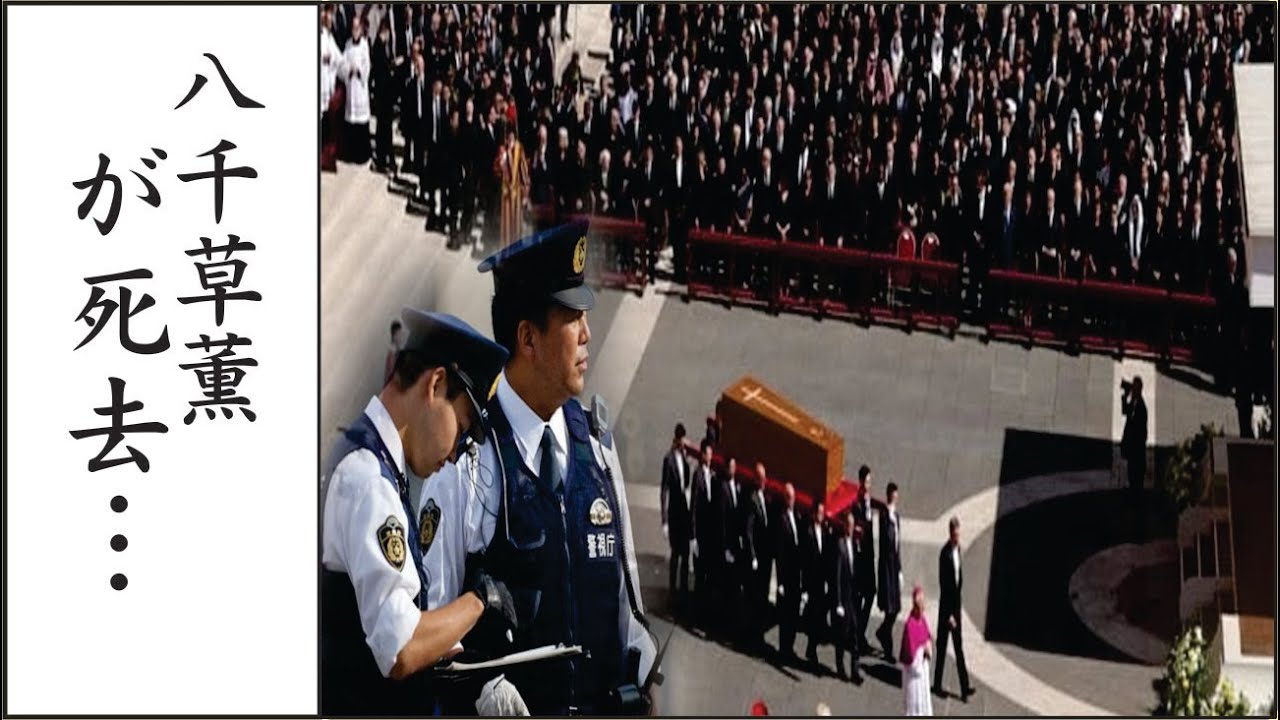八千草薫の旦那の本当の“死因”や残した遺産額に言葉を失う…八千草薫が“豪邸売却”した理由…
八草が香るその名前を耳にしただけで 柔らかい日差しが差し込む午後の縁側や 静かに湯気を立てるお茶碗のような ぬくもりが胸に広がる。彼女は1931年 の冬昭和初期の空気がまだ冷たく張り詰め ていた時代に生まれ、宝塚過激団という夢 の舞台で羽き、やがて日本映画会テレビ会 に欠かせぬ存在となった。小柄で決して 派手な美貌ではなかったが、そのマざしの 奥に宿る真の強さと言葉をかわす人の心を ふっと和ませるような優しさは金膜を通し ても画面越しにも確実に伝わった。少女の ような透明感を持ちながら母として妻とし てまた成熟した女性としての深みを年齢と 共に積み重ねていった彼女はまさに永遠の 家という表現にふさわしい女優だった。 宝塚時代の彼女は舞台の大林の花という よりもに咲くすみれのような存在感を持ち 、観客の目を引きつけるのではなく、太め にした人の心に残る光であった。映画館に 飛び込んでからもその印象は変わらない。 セ次郎 といった巨匠に愛されたのは彼女の中に 飾り立てぬ誠実さとどのような物語の中に も自然に生きづける人間らしさを感じ取っ たからに他ならないバ花に移る彼女の美償 は赤い花の燃えるような色彩とは対象的に 一際は穏やかで性質な光を放ち見るものの 胸に長く残った家庭を舞台にしたテレビ ドラマの全盛期彼女は母親役やつ役を演じ ながら画面の向こうの誰もが自分の家にも こういう母がいてくれたらと思わせる存在 になった。岸部のアルバムでの演技は日本 のテレビ氏に刻まれる名場面であり家庭の 崩壊と再生という思いテーマの中でも彼女 が放つマ差しにはどんなに壊れても人は また歩き出せるという優しい祈りのような 響きがあった。 彼女は観客に絶望を突きつけるのではなく 、絶望の中にそっと差し込む党を示す女優 だった。市生活では映画監督谷口吉地と 結ばれ師ともに互いを支え合いながら生き た。芸能界という華やかで時に激しい荒波 の中でも2人の姿は穏やかな湖のように 見えた。 外ではスター女優でありながら家に戻れば 夫を思い、静かな日常を大切にする妻でも あった。そのたまいそのものが彼女の演技 の根源となっていたのかもしれない。晩年 に至るまで彼女は女優という仕事を手放さ なかった。80歳を過ぎてもなお現場に 立ち、若い俳優やスタッフに笑顔で声を かける姿はまるで長い旅を続けてきた母 なる存在のようであり、誰もが自然と拝金 を伸ばした。病が彼女の体を蝕ばんでいた 時期でさえ彼女は役を演じられる喜びを 決して失わなかった。 最後まで女優であり続けるというその姿勢 に多くの人が静かな感動を覚えた。 2019年彼女が88歳でこの世を去った 時、日本から惜しむ声が寄せられた。早々 のニュースに触れた人々は彼女の残した 作品を思い出し、かつてテレビの前で家族 と並んでみた時間や映画館で心を振わせた 瞬間を追い体験した。八草香るという女優 はただのスクリーン上の存在ではなく、 人々の人生の記憶そのものの中に寄り添っ て行き続けていたのである。その微笑み、 その声、その気配は今も作品の中で 生きづいている。彼女の演じた母は妻は 少女は決して過去の映像ではなく、見る人 の心の中で今も生き優しく問いかけ続けて いる。あなたは大切なものを忘れていませ んかと。八草香の生涯は1人の女優の物語 であると同時に日本人の心に刻まれた永遠 の記憶であり昭和から平成そして令和へと 続く時代を結ぶ光そのものであった。 彼女の人生を語ろうとするとまるで静かな に石を落としたかのように次から次へと 記憶の波紋が広がっていく。八草香る本名 を松田み子と言い、1931年の冬の朝に 生まれたその少女は当時の日本にありふれ た庶民の家庭に育ち、周囲の誰もが少し 大なしくて人前に出るような子ではないと 思っていた。 しかし、幼い頃から心の中にはどこか住ん だ光があり、その光は彼女自身にもまだ 見えていなかったが、やがて人々の目に 移り、舞台やスクリーンを通して永遠に 輝くこととなる。 宝塚音楽学校に入ったのは10代の終わり 。少女から大人へと移り変わる揺らぎの 季節だった。の少女たちが同じ夢を追い 歌い踊り、そして競い合う世界の中で彼女 は派手さや夜で突き抜けるタイプでは なかった。ただひたすら稽古に向き合い 自分なりに与えられた役を大切に演じる時 に周囲から地味と表されることもあったが その浸きさと清らかさこそが後に彼女の 最大の武器となる。舞隊で初めて大きな 拍手を浴びた時、八草は心の奥底で私は人 の心に寄り添うことができると知った。 華やかさではなく観客の胸の奥に柔らかな 塔を灯すこと。それが自分の使命だと感じ た瞬間だった。 映画会にスカウトされ、東方の専属女優と なったのは自然な流れのようでありながら 、当時の彼女にとっては大きな決断だった 。金膜の向こうに映し出される自分は舞台 の上の自分とはまた違う。映画のカメラは わずかな表情の揺れや視線の奥にある思い までをもらえてしまう。だがその繊細さ こそが彼女には合っていた。悲願で見せた 美少。女の中にいる他人で浮かべた複雑な マ志し。それらは全て演技というよりも 彼女の生き方そのものの延長だった。 日本映画会が黄金機を迎え数えきれない ほどの名雄監督たちがスクリーンを彩る 時代に八草香は永遠のカ連という題名詞で 語られるようになった。だが彼女はその 呼び名に甘んじることなく年齢と共に役柄 を広げていった。 な娘役から妻、母、そして追いをしった 女性へ。岸部のアルバムで見せた母親の姿 は見るものにとってあまりに生々しく、 まるで自分の家庭を映し出されているかの ような痛みを伴った。家庭が崩れていく 悲しみの中でも彼女の存在は最後の砦手の ように温かく視聴者はその姿に涙を流し ながらも救われる思いを抱いた。生活では 映画監督谷口吉地と結婚し、夫婦としての 年月を重ねる。谷口は映画会の刺激であり ながらカオルにとってはただの夫であり、 彼女は謎女優でありながら妻としての日常 を何よりも大切にした。2人の暮らしは 華やかな社交の場とは対象的で穏やかで 静かなものであった。 タオルは撮影現場から帰るとエプロンを身 につけ、夫の好きな料理を作り、遊気の 時間を大切にした。その小さな日常が彼女 の演技に真実を与えていた。スクリーンの 中の母妻が観客にとって本当にいそうだと 思わせたのは彼女が自らの生活の中でその 役を生きていたからだ。 80歳を超えてもなお彼女は現役であり 続けた。若い俳優たちが次々と登場し、 時代の流れが早く変わっていく中でも八草 かが現場にいるだけでその空気はどこか 落ち着きを帯びた。 彼女の周りには自然と人が集まり、その 穏やかな笑顔に励まされる水癌という 厳しい病に犯されてからも彼女は役を 演じる喜びを最後まで手放さなかった。 教室でも台本を手にし、セリフを口にし、 心の中で観客に語りかけていた。 2019年10月24日、彼女が静かに この世を去った時、日本の人々はそれぞれ の記憶の中にある八草香を思い出した。 ある人にとっては初恋いのような淡い存在 であり、ある人にとっては母のような ぬくもりであり、またある人にとっては 理想の妻像であった。 彼女は銀幕の中で行き続けるだけでなく 人々の人生そのものに寄り添い共に歩んで いたのだ。彼女の残した作品を見返すたび 観客は再びあの優しい声とまざしに触れ 時代を超えて生きることのたっさを 思い出す。八草香るその生涯は1人の女優 の物語であると同時に日本人の心に刻まれ た永遠の風景である。春の桜のように甘く 美しくそして潔ぎよく散ってもその記憶は 毎年の季節と共に蘇える。 彼女の名はこれからも語り継がれ、 スクリーンの中で、テレビの中で、そして 人々の心の中で決して色わせることなく 輝き続けるのだ。彼女の物語をさらに深く 掘り下げていくと、そこには1人の女性が 歩んだ昭和から平成。そして令和へと続く 長い道のりが鮮やかに浮かび上がる。八草 香が生まれた1931年はまだ戦争の影が 人々の暮らしに忍び寄る前の時代であった が幼少期の記憶にはすでに不安や混乱が 色濃く刻まれていた。集方の彩電、窓の外 に見えた炎の色、母の手のぬくもり、そう した断片的な記憶が彼女の心に残り、人の 命のはなさや温かさを幼い頃から体感した ことが路地の演技に深い影を落としたのか もしれない。 少女はやがて宝塚音楽学校の門を叩く。 多くの夢見る少女たちが集まるその場所で 彼女は決して1番目立つ存在ではなかった が、その瞳に宿る光は教師や仲間たちを 驚かせるほど清らかで、どんな役を与え られても自然さと誠実さで観客の心を打っ た。 夏部隊で浴びた拍手の音は彼女にとって ただの完成ではなく人と心を通わせること ができるという確信となりその後の人生を 導く新番となった。映画館へ移った彼女は カメラの前に立つことで新たな挑戦を 始める。クリーンに移し出される自分は 舞台の上での大きな動きや表情とは違い、 本の一瞬の瞬きや息使いまでもが観客に 伝わってしまう。その緊張感の中で彼女は 嘘をつかない縁にお身につけた。おや次郎 監督の悲願における柔らかな美少は観客に とって作られた表情ではなく、まるで隣に 座る女性が見せる自然な仕草のように移っ た。なるセ夫の作品における彼女の姿は 苦悩や迷いを抱えながらも既然と 立ち向かう女性像そのものであり多くの 女性たちが自分を重ね合わせた彼女の演技 には押し付けが増しさがなく見るものに私 も生きていけるという勇気を与えた。 テレビドラマの黄金時代が訪れると八草香 は家庭の中の母や妻を数多く演じるように なる。特に岸部のアルバムでの母親役は 人々の記憶に深く刻まれた。家庭が崩壊し ていく家庭を書いたそのドラマで彼女は ただ悲にくれる母ではなく揺れながらも 必死に家族を見守る人間の姿を演じた。 そのまましには壊れても人はまた 立ち上がれるという希望が宿り、視聴者は 涙を流しながらも心の奥で救われた。彼女 はテレビの前に座る無数の家庭の中に 入り込み、同じ食卓を囲み、同じ痛みを 分かち合う存在となった。 私生活においても彼女は常に静かで誠実で あった。映画監督谷口吉地との結婚は彼女 にとって大きな支えであり、華やかな芸能 界の中で彼女が決して浮き足立たなかった 理由でもある。 仕事を終えて家に帰ればそこには夫がいて 2人だけの静かな時間が流れていた。 パオルはスターでありながら家庭では普通 の妻であり、夫の健康を気遣い、食卓を 整え、共に穏やかな日々を過ごした。 その日常の積み重ねが彼女の演じる妻や母 をさらに信じ罪のあるものへと変えていっ た。やがて時は流れ、彼女は年齢を重ねて もなお現役として輝き続ける。80歳を 超えても台本を手にし、現場に立ち、若い 俳優たちに優しい言葉をかける。撮影現場 で彼女の姿を見るだけで誰もが背筋を 伸ばしそこに流れる空気が柔らかく変わっ た。病を抱えながらも演技を続けた晩年の 姿はまさに最後まで女優であることの証で あった。彼女は自らの命が限られている ことを知りながらもその瞬間瞬間を観客と 共に生きることを選んだ。2019年10 月、彼女が静かに息を引き取った時、日本 の人々はそれぞれの記憶の中にある八草 カオルを思い起こした。 ある人にとっては青春時代に憧れた銀幕の ヒロインであり、ある人にとっては子供 時代にテレビで見た理想の母であり、また ある人にとっては晩年の優しい語り口に 癒された存在だった。 彼女はただの女優ではなく、人々の人生に 寄り添い喜びや悲しみの記憶そのものを共 にしてきたのだ。彼女が去った後もその声 や微障は作品の中で行き続けいるものの心 に静かに問いかけてくる。あなたは本当に 大切なものを忘れていませんかと。八草香 の生涯は1人の女性が時代を超えて愛され た理由を示している。華やかなスターで ありながらも最後まで人間らしく生きた こと。 その姿勢が多くの人の心を捉えて話さない 。彼女の名はこれからも春の桜のように 人々の心に淡く美しくそして確かに咲き 続けるだろう。私は八草香本名は松田み子 。昭和6年の寒い1月に生まれた少女だっ た。その心着いた頃から私の周りには戦争 の影が色濃く広がり、幼い胸に刻まれたの は遊びよりも不安や祈りの記憶だった。 暴空号へと急ぐの手のぬくもり、夜空を 切り裂くサイレン、燃える町の匂い。 それらは恐怖そのものでありながら人が人 を思いやる力の強さを私に教えてくれた。 だからこそ私はいつしか人の心に寄り添う ことを生涯の軸にして生きるようになった のだろう。 少女時代の私は特に目立つ子ではなかった 。静かで声も大きくなく華やかな場に立つ ような性格ではなかったはずだ。しかし なぜだろうや歌に心を惹かれた。ただ重大 のある日、宝塚音楽学校の門をくぐった 瞬間、私はまるで新しい呼吸を覚えたよう な気がした。 そこには全国から集まった夢見る少女たち がいて厳しい稽古、厳格な起、夢と競争が うまいた。私は決して1番ではなかった けれど、与えられた小さな役に全身で挑ん だ。地味だと言われても構わなかった。 大切なのは役を通して誰かの心に届くか どうか。それだけだった舞台で初めて浴び た拍手の音が今も耳に残っている。あの時 私は確信した。私は人と心をつなげられる のだと。その瞬間が私の運命を決定付けた のだと思う。やがて映画館へと誘われ、 東方の専属女優として銀幕に立った。舞台 と違い映画は一瞬の表情までも切り取ら れる。視線の揺らぎ息を飲む音言葉になら ない感情。嘘は通じない。だからこそ私は 自然であること誠実であることを心情にし た。安次郎監督の願花での1場面静かに 微笑んだあの時私は観客に自分の心を 丸ごと差し出すような気持ちでいた。 観客が演技とは思わず1人の女性として私 を見てくれたならそれが私の最大の喜び だった。女優として歩む年月の中で私は 数多くの女性を演じたカレンな娘強い母 揺れる妻時に孤独を抱える老女 岸部のアルバムで演じた母親役は私自身の 心を深く揺さぶった家庭が崩れていく 悲しみを抱えながらもなおも家族を見守る 母そのまざしには私が幼い頃に母から 受け取った祈りのようなものが宿っていた のかもしれない。 視聴者が涙を流しながらも救われたと言っ てくれた時、私は演じることは人を癒す ことでもあると知った。私生活では谷口 先吉という判例を得た。監督であり、夫で あり、時に父のような存在でもあった。 彼と過ごす日々は表に出る華やかさとは 対象的に穏やかで静かなものだった。 仕事を終えて帰宅すると、私はエプロンを つけ、夫のために夕食を用意した。スター 女優であろうと家庭の中ではただの妻。 そうした当たり前の日常が私の演技をより 真実のあるものにしてくれた。スクリーン の中の私が本当にそこにいる女性として 観客に移ったのは日々の暮らしを大切にし ていたからだと思う。やがて時代は 移り変わり、若い俳優たちが次々に登場 する中でも私は役をいただける限り現場に 立ち続けた。80歳を超えてもなお台本を 開くては震えず、役を生きることの喜びが 心を満たした。病を抱えながらも私は最後 まで女優であることを手放さなかった。 水像癌と診断された時、恐怖よりも先に もう少し演じたいという思いが胸に湧いた 。台本を読みながら私は観客とまだ繋がっ ていると感じた。 2019年の秋、私は静かに幕を下ろした 。だが私の歩みはそこで終わったわけでは ない。金幕やテレビの中で私は今も生きて いる。ある人にとっては憧れの少女として 、ある人にとっては母のような存在として 、ある人にとっては静かな祈りを込めた声 として、 人々の記憶の中で私は生き続ける桜の花が 毎年春に咲き、人々の心に淡い喜びを 呼び覚ますように、私の名もまた時代を 超えて思い出されるだろう。私は八草香る 女優であり、1人の女性であり、そして 観客の人生の中に寄り添い続ける小さな としびである。例え姿は消えてもその光は 消えることなく人々の心の奥で静かに揺れ 続けるだろう。私は八草香る昭和という 時代に生まれ、平成を生き抜き、令和の 始まりと共に静かに幕を下ろした1人の 女優である。 思い返せば私の人生は1冊の長い物語の ようであり、決して派手な冒険端では なかったけれど、人と人の心が交わる瞬間 に満ちていた。幼い頃に見た戦下の記憶は 私の中で消えることなく、いつも人は 生きるために寄り添い合わなければなら ないという確信を残した。 だからこそ女優という道を選んだ時、私は ただ自分が光を浴びるためではなく、見て くれる人の心に小さな安らぎや勇気を灯し たいと思った。宝塚音楽学校で過ごした 日々は夢と苦しみが同居する時間だった。 朝早くから夜遅くまで続く稽古。厳しい 起立。仲間でありライバルである少女たち との切磋琢磨。やかな舞台の裏には汗と涙 と孤独があった。それでも私は逃げ出さ なかった。なぜなら舞台に立った瞬間観客 の拍手が全てを報いてくれるからだ。 初部隊の幕が上がった時の光景は今もまぶ に焼きついている。観客席に広がる無数の 瞳が私を見つめ、私の小さな動きや声に 反応する。その瞬間、私はここが私の居 場所だと確信した。映画館に進んだ時、私 は再び新しい世界に飛び込んだ。 スクリーンは舞台以上に冷鉄でごまかしが 効かない。カメラは私の内面までをも 映し出す。安次郎監督と出会い日願花に 出演した時、私はただの役柄ではなく1人 の女性として存在することの意味を知った 。ほむ涙を浮かべる視線を落とす。その1 つ1つが観客の心に届く演技を超えた 行きざが映るのだと悟った。セミキお監督 の作品では人間の弱さや複雑さを格約を 通して私は自分自身の心の奥深を 見つめ直すことになった。 人は弱いけれども弱さの中にこそ強さが ある。その真実を私は役を通して学んだ 時代が進みテレビドラマの時代がやってき た。岸部のアルバムで演じた母親は私の 人生の中でも特別な役となった。 家庭の崩壊を書くその物語で私は母として 妻として揺れる心を全身で表現した。撮影 の合間に胸が苦しくなることさえあった けれど、あの作品を通して私は母という 存在が持つ深さを改めて知った。 放送後、多くの視聴者からあなたに救われ ましたとの声が寄せられた時、私は女優で あることの意味を改めて強く感じた。 演じることは単なる仕事ではなく、人の 人生に触れ支えになることなのだと。 市生活では谷口先吉という判出会い、共に 歩んだ。彼は映画界の巨匠でありながら私 にとってはただの夫であり、穏やかな生活 の相棒だった。仕事を終えて家に戻れば私 は台所に立ちかれの鉱物を作った。食卓を 囲みない会話をかわす時間が私にとっては 何よりの幸せだった。華やかな芸能界の外 には静かで温かな日常があった。その日常 が私の演じる妻や母に血を通わせてくれた のだ。 やがて年齢を重ねても私は役をいただける 限り演じ続けた。80を過ぎても現場に 立ち、若い俳優たちと共に芝居を作ること ができるのは私にとって最高の喜びだった 。病に犯されてもその思いは変わらなかっ た。 水造ガと告げられた時恐れもあったがそれ 以上にもう少し演じたいという願いがあっ た。台本を手にすると私は再び若き日の 少女に戻ったように胸が高なった。そして 2019年10月私の命は静かに終わりを 迎えた。しかし私が歩んだ道はそこで 終わりではなかった。人々の記憶の中で私 は生き続ける。金幕に移る私、テレビで 微笑む私、母として、妻として、少女とし て、それらは過去の映像ではなく、見る人 の心の中で今も生きづいている。 ある人にとって私は初恋いのような存在で あり、ある人にとっては母のような安らぎ であり、ある人にとっては人生を共に歩ん だ友人のような存在なのだ。八草香という 名前は春に咲くの花のように淡く美しくは なくしかし確かに人々の心に残り続ける 時代が移り変わっても人は彼女を思い出し その優しさと強さを胸に抱くだろう。私は 女優であり、1人の女性であり、そして 何よりも人々の人生に寄り添い続ける 小さなと知りである。 私は八草香として生きた年月をこうして 振り返ろうとするとどの瞬間も1つの舞台 の幕合のように鮮やかに浮かび上がって くる。昭和の始まりに生まれ、幼い頃に見 た戦争の記憶は今でも心の奥に生々しく 残っている。 暴空棒に走る時、母の手をギュっと 握りしめた感触。空に響き渡るサイレン。 闇を赤く染める縁。それは少女の心に恐怖 だけでなく人は互いを支え合うことでしか 生きられないという心理を刻んだ。その 思いがやがて私を女優という道へと導いた のだと思う。華やかな世界に憧れていた わけではない。ただ人の心に寄り添い 寄り添われるそのぬくもりを表現したいと 心の奥で願っていた。宝塚音楽学校に入学 した頃、私は自分が特別な存在だとは思っ ていなかった。むしろ数多くの少女たちの 中で自分は埋もれてしまうのではないかと 不安に思っていた。しかし厳しい稽古の 日々の中で私は次第に理解した。 目立つことよりも自分なりに誠実に役を 生きることが大切なのだと。やかな踊りや 派手な歌声で観客を魅了する仲間たちの 傍原で私は与えられた小さな役を丁寧に 演じることに心を注いだ。その姿勢が やがて評価され、観客の心に清楚で華連な 娘役として映るようになった。初めて観客 席から大きな拍手が湧き上がった時の感覚 は今も体に染みついている。あの瞬間、私 は人と心をつなげられるのだと強く感じ、 人生をかけるべき道が定まった。やがて 映画会に誘われ、東方の専属女優として 銀幕に立った時、私は再び試練に直面した 。舞台と違って映画は一瞬の表情を 切り取る。目の揺らぎ、息き遣いの変化。 ほんの一瞬のためいさえも観客に伝わって しまう。 が通用しない世界で私はただ自然である ことを選んだ。演じるのではなくそこに 生きること。小や次郎監督の悲願で見せた 美償は私自身の心から溢れたものだった。 観客が女優の演技としてではなく、隣に いる女性として私を受け止めてくれた時、 女優としての喜びが全身を駆け抜けた。 セ瀬ミキお監督の作品に出演した時も同じ だった。人間の弱さ、矛盾、孤独を抱え ながらも前に進む女性を演じることで私は 人間そのものの美しさを学んだ。テレビの 時代が到来すると私は母妻を数多く演じる ようになった。岸部のアルバムでの母親役 は私の人生にとって大きな天気だった。 家庭が崩壊していく中でなおも家族を 見守り続ける母。その苦しみと愛情を 演じることは自分自身の心を削るようでも あったが、同時に人間の強さを見つめ直す 機会となった。放送後、多くの人々から あなたの姿に救われたという声を頂いた時 、私は深く実感した。 演じることはただの仕事ではなく人の人生 に寄り添う行為なのだと女優という存在が 人を支え人を生かすことがあると知った。 市生活では映画監督の谷口吉地と出会い共 に暮らすようになった。 彼は映画会の巨匠でありながら私にとって は優しく厳しい伴侶であった。家に帰れば 私はエプロンをまとい彼の鉱物を用意し、 共に食卓を囲む。華やかな世界の外には 穏やかで温かな日常があった。 その日常が私の演じる妻や母に弱肉を与え てくれたのだ。家庭での私の姿と銀幕の中 の私が重なり合い、観客に本当にそこに 生きていると思わせる力を産んだのだと 思う。年齢を重ねても私は現場に立ち続け た。 80を過ぎてもなお役をいただけることは 喜びであり、若い俳優たちと共に芝居を 作る時間は掛け替えのない宝物だった。 撮影現場で私が笑顔を見せると空気が 安らぎ緊張が解けると若い人たちに言われ た。 私はただ自然でいただけだが、その自然さ が人を安心させたのなら、それは女優とし てではなく、1人の人間として最も嬉しい ことだった。水道癌と診断された時もまだ 演じたいという思いが勝っていた。台本を 手にすると心が若返り、まだ自分は舞台に 立てるのだと確信できた。そして2019 年10月、私の命は静かにを閉じた。 しかし人生の幕は降りても物語は終わら ない。 私の演じた役は今も人々の記憶の中で 生きづいている。ある人にとって私は 初恋いの人であり、ある人にとっては母で あり、またある人にとっては人生を共に 歩んだとのような存在だ。人は作品を通し て再び私に出会い、私の声に耳を傾け、私 の微笑みに安らぎを感じるだろう。八草が 香るその名は春に咲くのように淡く美しく はなく、しかし確かに心に刻まれ続ける。 昭和から平成そして令和へと時代が 移り変わっても人々の記憶の中で私は生き 続けるだろう。女優であり、1人の女性で あり、そして何よりも人の心に寄り添い続
Please support me by subscribing to the channel. To see the latest videos ! . If you like it, please like and share. If you have any questions, please comment below! Thank you so much !love you !