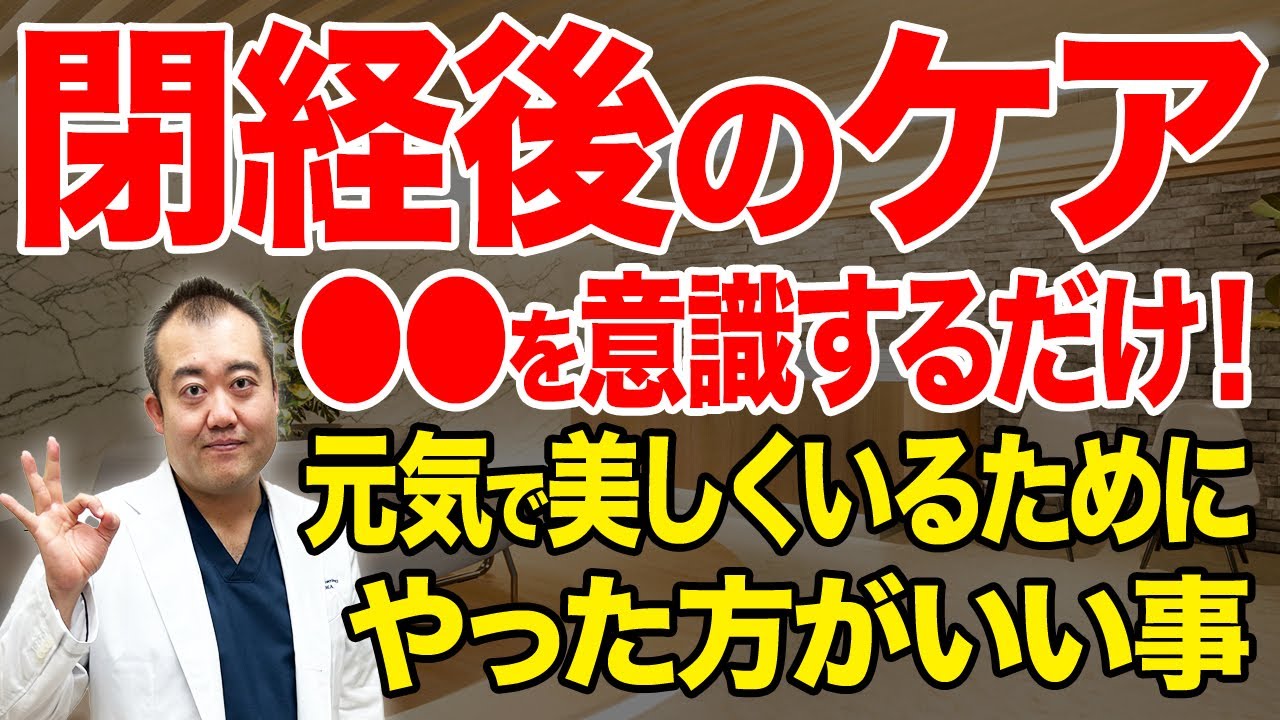【更年期後期】閉経後の体調と心の安定を保つ為に試してほしい事を産婦人科医が徹底解説!
高年期の後をどれだけ元気に快適に 素晴らしく生きれるか高年期後の症状を 良くするために治療をするっていう考え方 もあります。 皆さんこんにちは。今日もドクター ヨッシーのレディ学のチャンネルをご覧に なっていただき本当にありがとうござい ます。今日はたけっぴンさんとずっきん さん来てもらってます。よろしくお願いし ます。お願いします。はい。今日は何を 話せばいいですか?はい。 今日はですね、経験に関するコメントがどうしても圧倒的に多いんですけど、高年期の症状が辛い。そういった方がすごくコメントで経験を残していただいてるんですけど、今日は平形後にやってみるといいよっていう平後のケアについて三個人会目線でお話ししていただきたいなと思って持ってきております。 [音楽] これはですね、高年期の時期をどう過ごすかによって決まります。これがどうやって過ごすかによって変わるっていうこと。 [音楽] そしてどう変わっていくのかってことを話していきたいと思いますので、今高年期になってる方もその先になってる方も実はその前の方も皆さんに適用してくる話だと思いますので是非最後までご覧いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 お願いします。 はい。 まずね一般的な話として携っていうのは何でしたっけ? 1 年間整理が止まること。 そうですね。その止まった時に1年前の ところを見直した時に平形ですよって言っ ていいってことになってます。ここがね 平形なんじゃないかっていう風に おっしゃる方がいたんですけど ガイドラインとか日本産婦人家のホーム ページとか見てもこっちですよってことに なっててどうもこっちっていう2つ産婦人 家の先生がいたと思うんです。あんまり こういうことを3婦人会って細かく気にし てなかったりするんでちなみに僕もこう いうのやる前はあんまり気にしませんでし た。今参加不人家学会っていう学会でも それは出してますね。この平形の前後 5年から5 年のことを高年期っていう時期として言います。これは期間の話ですね。この高年期に起こる症状のことを 高年期症状 そうですね。高年期症状と言ってさらにこの高年期の症状が日常の生活を壊してしまうぐらい悪い場合には何でしたっけ? 高年期障害。 そうですね。高年期障害という風に呼になってましたね。 そして特に高年期症状とか生涯で重要の ことは他の病気を否定してあげ るっていうことが何よりも重要でしたよね 。高年期の症状は他の病気でも出やすい です。ま、例えば目舞いとか言っても他の 病気でも出るわけですよね。皆さんこう いう高年機の話をしていたりネットで見 てると目前やったからもう全部高年期だっ ていうまた1対1対応になっちゃうんです けどそうじゃなくて他の病気でも目前 起こります。例えば耳の病気でも目前 起こるし、頭になんかできてしまったとし ても目前起こりますし、そういうような いきなり高年気少女って言っちゃいけない ということになります。疲れやすい。これ も出やすいですね。これもいきなりじゃ 疲れやすいからイコール私は50歳だから 高年期っていう風に言っちゃいけなくて 例えば疲れやすいんだったらもしかしたら ガが隠れてるかもしれないし成立がひどく て量が多くて生理の量が多いから疲れ やすいとかねそういうこともあるので他の 病気をしっかり否定してあげるということ が重要でしたっていう話になります。特に この高年期の症状が出る時期っていうのは かなり皆さんにも理解されるようになって きたし病院でもこれで困ってるか来ますっ ていう人はいます。 じゃあその時に何を見るかって言うとホルモンでしたね。女性ホルモンが下がってると平形っていう診断になって高年気症状だよねってことを言っていいわけなんですけれども、じゃその時治療しますかって言うとあんまり困ってないんで大丈夫ですよみたいな話はよくあります。つまり心配をしてるんだけど治療やだなっていう人が多いってことなんですね。もちろん治療早くしたいですって人もいます。汗がだラだラ出ちゃって困っちゃう。 電車に乗っていて1人だけ汗になって とにかく周りの目が気になっちゃう。だ から治療してください。こういう人もい ます。でもなんか困ってんだけど我慢 できるからやんなくていいです。これ多い んですよ。もちろんねこれを絶対やん なきゃいけないってわけではないです。 ただ今の症状を良くするっていう目的も 治療にはあるんですけれども、それ以外に も実はこの先ですね、高年期の後をどれ だけ元気に快適に素晴らしく生きれるかに かかってくるのが高年期後の症状を良く するために治療する考え方もあります。 そこ重要です。考え方としてね。うん。 それは知らなかったですね。知らなかっ たっていうことありますよね。はい。 じゃ、これなんでなんだっていう話をするんですけど、そもそもこの高年期後に起こる第 1 フェーズとしてはまずは内科的な病気が起こりやすくなります。高年期が終わった後、ま、一般的には 55歳ぐらいの女性ですね。 お2人の中で55 歳ぐらいの女性のイメージありますか?どんな感じですか? はい。私は母親がその辺りなので 母がすぐ お母さんとかお友達とか兄弟とかどういう感じのイメージですか? ちょっと体がいるか? そうですよね。ま、福な人が増えるっていうのは間違いないと思うんですよ。これでも別にみんななりたくせになってるわけじゃないと思うんですよね。 ま、そういうようないろんなことが起きて くるわけなんですけど、特にこの福女って ところはすごく重要で、さっきも話した けど、みんながなりたくてなってるとか、 集団的にそれを目指してるわけではない ですよね。でもそうなっちゃうわけなん ですよ。若い自分たちの年代の女性を 考えると、例えば福力な人の割合いって 多くはないじゃないですか。この高年期後 の時期の人を思い浮かべるとどうしても 福岡の人が多くなってくる。そしてその上 になってくると、もっともっとその割合は 増えてくるっていうのはなんとなく分かる と思います。これはなんでかって言うと、 女性ホルモンなんですよ。そもそも女性 ホルモンが落ちてきちゃう。これはどうし ても女性としては起きなきゃいけない現象 の1つになっちゃいます。ただしそれが 起きることによって太りやすくなって しまう。これはキーワードとして非常に 多く上げられます。ま、よくあるこの年代 の方の悩みとして太りたくないんだけど 太ってしまったとか、今まで通り食べてん だけど痩せにくくなったとか。これはなん でかって言うとホルモンのせなんです。 ホルモンが落ちてくるからのこともあるし とかも出てきちゃうしっていうことになる んですね。そしてその原因結果として 起こりやすいのが内的な病気が起こり やすい例えば糖尿病になりやすいとか脳の 病気になりやすいとか脳中になりやすいと か心臓がおかしくなっちゃうとか一般的に は男性では多いですよね。そうですね。僕 の年代になるとそういう人が増えてきます 。学生の時には劇的に痩せててかっこ よかった人が20年ぶりにあったら めっちゃ太っててあれ誰でしたっけみたい なことっていうのはイメージ湧くと思うん ですよね。これ男の人あるですけど女の人 もこの年代の後になってくるとそういう ことが起こってくる。これが後年記号の 特徴になってきます。じゃあこの内画的な 病気をどうやったら直せるのって言うと 高年機を実はどう過ごすかによってこれに なりやすいかというのことが決まってき ます。ホルモンが減ってくることに対して ホルモン補充とか高年機の治療をやって いただいた方はこういう病気が実は減り ますってことが科学的に医学的に実は 明らかになってます。これはなかなか知ら ない人も多いんではないでしょうか。 ガイドライっていうところにもこの駅の 治療やった人は内科的な病気が減りますと 予防することができますって言われてます ので脳中になっちゃったりとか糖尿病に なっちゃったりとか真金高速になっちゃう その年代の人が急に元気がなくなっちゃっ たりそれを景気に元気がなくなっちゃっ たりりってことは多い病気の1つです。 しかしながら高年期を整するものは高年期 後も精になるわけですね。それが非常に 重要ってことになります。まずこれが1点 目ですね。そしてもう1 つは骨の問題になってきます。骨がもろくなっちゃうっていうのは聞いたことありませんか? はい。母の友人が骨折することが増えたって。 そうですよね。今まで皆さんの年代で骨折する人あまりないっすよね。 スキーに行っててジャンプして折れました。それは折れます。だけど年気後の人は普通に歩いててつまづいただけで骨が落ちてたりするんですよ。それって普通じゃないじゃないですか。 [音楽] そうです。 これもなんでかって言うと実はホルモンが下がってくることによって骨がスカスカになっちゃうていうことで起こる現象になります。じゃあこれもどうすればいいのかって話になるんですけどこれも実はホルモンの治療とか高年機の治療をどう過ごしてきたかってことによって予防することができますしが落ち着いてたりホルモンの治療することで骨がスカスカになりにくいんだよっていうことも目指すことができます。 実は今女性は長意気ですね。男性よりも約 8年ぐらい長意生きすると言われています 。一方でその裏側では生きているんだけど ネタきりの人がめちゃくちゃ多い。これ どうですか?ネタきりだったら生きてても なかなか自由が効かなくて楽しくないです よね。ですから元気に長生きするためには 骨のこともすごく考えなきゃいけない。 そしてそれを良くする方法として高年期の 治療もあります。もちろん骨を強くする ようなお薬素症の予防薬としてあるんです けどそれと共に高年機をどのように過ごす かによっても骨の強さを保つことができる 骨折がしなくなる元気で長気でき るっていうことにつがってくるという ところが非常に重要になってきます。とし て骨を強くする方法としては高年の治療も あるんですけれどもビタミンDを多く取っ てもらうとかカルシウムを取ってもらうと いうこともありますしそしてビタミンDを 活性するには日光にしっかり当たって もらわなければいけないので外でしっかり 運動するっていうことが重要になってき ます。 なかなか女性だと気に当たるのが嫌だとか、日焼けが嫌だとかっていうことになるかもしれないんですけど、骨を保つにはそうやって外で運動してもらったり、しっかりした食事を取ってもらう、これが非常に重要になってくるのも間違いないと思います。 確かに私結構朝方するんですけど、公園に行くとちょっと年配の方が 2 個を浴びながら愛情体操とかしてて、そういう方だって元気だなってすごいね。太陽のおかげなんですかね。 そういうこともあると思います。 そういう方たちは多分ちゃんとやってるんですけど、ほとんどの人は家にいる人が多いと思うんで、より出ていっていただけるといいんじゃないかなと思います。 実際私の母の場合だと主婦をしながらハートに行っていたりするかなと思っていて、そうするとやっぱり運動の時間を取るのが難しかったりすると思うんですね。ただ今ビタミンを取るのも重要って同じだったので、それをサプリメントで沖縄っていうことでも問題ない。 そう、もちろんそれはいいと思いますよ。 サプリメントでビタミンDとかを取って もらう。カルシウムを入ってるような サプリメントを取ってもらう。もちろん これもいいと思いますし、運動する時間 っていうのが取りにくい人はバイトに行く 時間を運動に当てちゃったりとか、駅3 個乗るんだったら帰りは1個歩いてくると かね。した工夫でそれもできるんかなと 思います。ありがとうございます。はい。 吉川さん、 変形された方って産婦人化に行きにくいとかあるかなって思うんですけど、それは行っても全然大丈夫です。 もちろんです。献心で来てもらってもいいし、おネきの治療をしたいってことで来てもらってもいいですし、僕なんかは骨のお薬をやったりとか、コツの予望とかもやってますので、そういうことで来てもらうのはいいと思います。特にね、今若い方が産婦人家に来ることが多くなってきて、待室はほとんどが若い方なんですね。 だから逆に年齢が上の方が着にくいとか 行きにくいとかいづらいとかそういうこと をおっしゃる方は実は多いんですよ。私が 来ていいのかなって一言言ってから入って くるみたいな人多いんですけどでも別に 若い人から行って55歳の人60歳の人が 3風人に気になります。気にならない全く ならないですよね。そんなに気にする必要 ないですよね。そうですね。 で来てる方も多いので、お母さんはこの治療、娘は劇のちょっと治療とかそんな感じで来てもらってもいいし、なんで毎回一緒に来んのかなっていう親子もいるぐらいで、ま、でもそれでもなんか炎としていいなと思っちゃうんですけど、全然気にならないよとは思います。 はい。高年期の症状が辛かったらもう病院に行って治療するのが高年期後を生するっていうことです。 高年期の症状が辛かったらじゃなくて高年 機をする人が高年期構成するので症状が 強くなくてもやっとくことが重要だよねっ てことになるんですよね。症状があって あんまり強くないからやらないって人も今 の症状だけじゃなくてその10年先を見て てとか5年先を見てやってもらうのもいい よねってことになります。 今日は平後の症状について色々お話をし ました。年気特に起こりやすいのは内科的 な病気、骨の病気ってことになります。 そして高年機の治療、特にホルモン療法を やることによって内科的な病気を予防する ことができるってことは言われてます。 そして骨に関しても骨折しにくくなったり 強くなったりってことができますのでの 治療やっとくこともいいですし、手屋とし て運動したりとか日光を浴びたり、 ビタミンのサプリを取る、タルシムの サプリを取る、そういうのもいいと思い ます。そんなことでより良い女性の送って いただければと思いますので、是非そう いうことを理解していただければと思い ます。今日もドクターヨッシーのレディの チャンネルをご覧になっていただき本当に ありがとうございます。今日のお話が 良かったという方是非高評価、チャンネル 登録を入れていただければと思いますし、 あんなことあった、こんなことがあっ たってことがあればコメント欄に入れて いただければと思います。そしてLINE 登録も入れていただければと思います。 どうぞよろしくお願いします。 [音楽] 皆さん、公式LINEを作りました。公式 LINEへの登録本当にありがとうござい ます。今後はこの公式LINEを使って チャンネルをもっと大きくしていきたいと 思います。そして皆様相談を個別でされ てる方いますが、順次返信をしていきたい と思いますので、少々お待ちいただければ と思います。今後はですね、さらにこの コミュニティを大きくして患者さん同士 そして女性同士で相談できるような場所を 作っていきたいと思いますので、是非 チャンネル登録を入れていただければと 思います。さらにその中から出演をしても 良い、動画に出てもいいという方は是非 LINEの中からスタッフの方に連絡をし ていただければ調整をさせていただきたい と思います。出てくれた方には得典として ドクターヨッシーの書いた人家全般の方も プレゼントさせていただきたいと思います 。どうぞよろしくお願いいたします。さん でした。 今日のテーマは平後のちょっとご高の方のお話だったと思うんですけど、お肉を食べる方の方がなんだか元気なイメージなんですけど、喧嘩関係あるんですか? そもそもやっぱりそういうのを元気で食べられてるっていうこと自体が元気でないと食べられないんだと思うんですよ。元気がない人が 80 歳でステーキ食べられるかつうとなかなか難しいと思うので元気である証拠として結果としてそういうのが食べられるんじゃないかなっていうのは思いますね。 ちなみに岡さんはお肉好きですか? はい。あ、お肉は好きですね。結構食べたい方のものになります。 牛派ですか?豚さん派ですか? ああ、どっちかっと牛の方がいいですかね。 今度焼肉牛お願いします。 お願いします。 あ、ああ、分かりました。じゃあ今度あれですね。 300g にぴったりだったら持ち帰れるみたいな、そういう企画にしましょうね。 お肉を。 そうですね、矢沢ミートさんから仕入れた 2kg のお肉ですみたいなカットしましょうみたいなね。 300gみたいなしてますかね。あれなんかついつい挑む時見ちゃったりするんでそんなこと思い増えましたけどそんなね元気な方が増えるようにお肉食べてくださいって感じですからね。ありがとうございました。 ありがとうございました。 [音楽]
婦人科医の吉岡範人です👀
皆さん、今日もご視聴ありがとうございます✨
本日は、閉経後のケアについてお話しました‼️
Dr.ヨッシーオススメの更年期・閉経の動画はコチラ↓
↓公式LINEのご登録はコチラ↓
https://page.line.me/733gftdq
このチャンネルでは、女性特有のからだの悩みや不安を解消し、パフォーマンスを上げていくことができる情報を発信していきます!
からだの不安が安心に変わり、明日の自分が好きになれるように一緒に頑張りましょう!
↓チャンネル登録はコチラ↓
https://www.youtube.com/channel/UCpEYXNbZyRCA99PmVZOuNQQ
=======
◆吉岡範人のプロフィール
【経歴・実績】
聖マリアンナ医科大学卒業後、2003年同大学の初期臨床研修センターに配属。婦人科腫瘍を専門とし一般産婦人科に加え救命救急、内科、外科、小児科を学ぶ。
2013年カナダ・ブリティッシュコロンビア大学への留学を経験。
2019年つづきレディスクリニック理事長に就任。
東京オリンピック競技大会の水泳競技に救護ドクターとして参加。
東京2020パラリンピック競技大会にて、水泳競技のドクターボランティアとして参加。
創刊100周年を迎える週刊エコノミストにて、2023年を牽引する26人の経営者の1人として理事長の吉岡が選出。
https://www.weekly-economist.com/recaward2023/
婦人科の治療法は一人ひとりの生き方の違いや年齢、その時々の生活の状況などによって変わるものです。
診察では説明をゆっくり、わかりやすく、時間をかけて行い納得していただいてから治療することを心がけています。
女性がいつまでも若々しく・活き活きと暮らしていけるお手伝いができるレディスクリニックを目指しています。
【書籍】
『女性が体の不調を感じたら、まずは婦人科へGO この本を読めば10年後のあなたが変わる』
https://amzn.asia/d/6kXy8eo
『フェムテック 女性の健康課題を解決するテクノロジー』
https://amzn.asia/d/6pLSovS
🎥運営担当:株式会社STAGEON
YouTube運営に関するご相談がある方はこちらから
→https://share-na2.hsforms.com/1AmHtcup8RDqfbzA-ep-FSg408bva?source=Dr.-tj1bg
#婦人科 #医学 #閉経