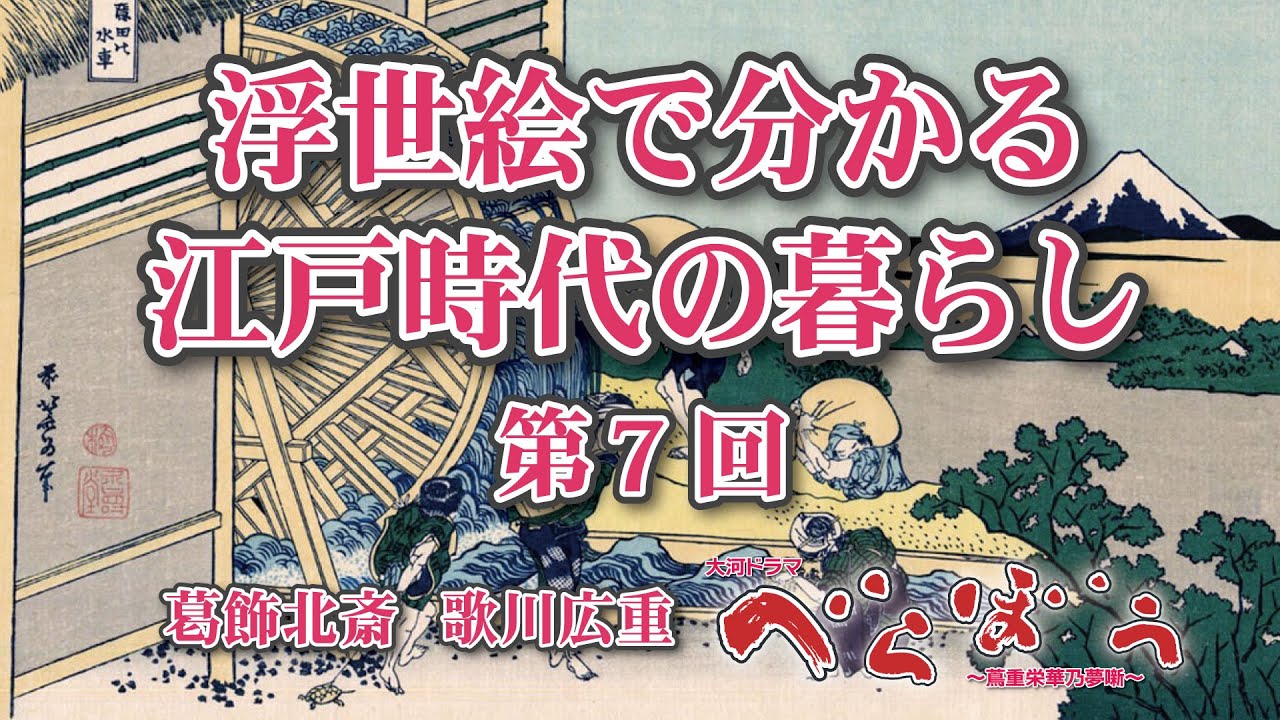NHK大河ドラマ べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~解説 浮世絵で分かる江戸時代の暮らし 第7回
NHKタイガドラマ ベラボスタジュエガの夢話 解説浮いで分かる江戸時代の暮らし第7回 2025年のNHK大画ドラマ ベラボスタジュエイガの夢話は デド時代を舞台にその時代の文化や人々の 生活を鮮やかに描き出しており、多くの 視聴者から関心を集めています。今回は そんな江戸の町に暮らす人々の生活を浮を 手がかりに探っていきたいと思います。 猫のお部や作者不傷 明治17年1884 江戸っこは皆お風呂が大好きだったと言わ れています。しかも仕事前と仕事終わりの 2回お風呂に入っていたそうです。世界で も稀れな綺麗好きだったようですね。江戸 には水道毛が引かれていましたが、さすが に水はまだ貴重で、燃料の焚きも高価な ものだったため、各家庭にお風呂があった わけではありません。 一般家庭はもちろんのこと合の家、そして 宿屋にもお風呂がないことが多く、人々は ユやと呼ばれた先頭に通っていました。 江戸時代の後木にはなんと湯の数は600 件もあったそうで、 しかも料金は格安で8から10問くらい だったそうです。 奥にはザクと呼ばれる小さな入り口があり 、 そこをくぐると虫の中に 小さく浅い浴草が作られていました。 蒸気と湯の両肩で熱効率をよくしよう特風 された形です。 湯の温度はかなり高かったそうで 浴草はあくまで体を温めるだけの目的で さっと浸り、 体を洗い上がりを浴びて帰るというのが 当時の戦闘スタイルでした。 江戸時代には欲が普通でした。 空気が乱れるとして江戸幕府から 何度司令も出されましたが 婚欲の家屋は数多く残っていたと言われて います。 建物の改築など費用面での課題も大きかっ たことから 徹底がされなかったのではないかと考え られています。 男女だけでなく家に来るのは様々な身分の 人がいるので マナーも保たれていました。 例えば入る時には 冷えもんでござい冷えた体で入りますから 体が当たったりしたらすみませんなどと声 をかけ お互いに気遣ったそうです。 冬層向けの追加サービスともあります。 三介がその1つです。入り口で追加料金を 払うと サスという職業の男性に背中を流して もらったり、 肩のマッサージまで受けることもできまし た。 そしてイヤの2階には男性専用の娯楽室も 用意されていました。 追加料金はかかりますが、お茶やお茶菓子 などが用意され、 男性たちは世間話、 将棋などに教ていたそうです。 利用は男性の身に限定されていましたが、 社交としての役割も果たしていたようです 。 タシ北斎 富学36系温の水社方1年1830 青山温田村は現在の渋谷区神神宮前 いわゆる原宿あたり 当時は至るところで水車が見られるような 電園地帯でした。 渋谷川から引き込んだ水流を利用した 水車小屋の周りで 洗い物をする女性や粉引きをするための 穀物を運び入れる男性。 亀を連れて遊ぶ子供など地域住民の 暮らしぶりが伺えます。 本殿とは新たに開根した神殿で 幕府から念具の長臭をま抜かれるために 女将に隠れて作った水電を言います。 現在も温殿神社として長残っています。 遠くに見える森は代々木8万です。 兵は金料理が集まる場所でもあり、 その名残りでしょうか?毎年5月には金運 アップの 近魚祭りが開かれています。 田上を待つ諸家の風景ではないでしょうか 。 北斎は賑やかに働く人々の動き。 激しい水流によって半ト計周りに大きく 回る水車の丸い形と [音楽] 静寂な電園地帯にそびえるここの富士の形 との退避を 楽しんでいるかのようで北斎の観察力に 驚くばかりです。 温の水車を復言した模型が 渋谷区率神宮前小学校内に設置されてい ます。 歌川広げ 名称江戸百系京橋竹橋安静 [音楽] 江戸時代東海道の起点日本橋から京都に 向かう場合に 最初に渡る橋なので京橋と名付けられたと 言います。 橋は江戸幕府がかけたご入り要求で 親柱には奉仕方の装飾希望士が設置されて いました。 これは重要な橋の証で江戸では城へ渡る橋 以外には 日本橋、京橋、新橋だけに義防が飾られて いたと言います。 は京橋とその下を流れる京橋川沿いの 竹橋の 満月の夜景として描いています。 昭和30年代にプラスチックが広まるまで 江戸時代竹は生活に欠かせないものでした 。 割って編んだり、箸や竿のようにそのまま 使ったり、 竹の川は食べ物を包んだり、竹を燃やして 作った竹は 薬品としての価値もありました。 そのため江戸庶民を支えるためには大量の 竹が必要で 北関東各地からイ田に組んで運ばれ、 京橋の竹菓で土産げをしていました。 大量の竹で京橋は竹の要塞だったようです 。 京橋近くの時町に住んでいたと言われる 広げにとっては 見慣れた風景だったでしょうか? 川沿いにぎっしりと立てかけられた竹を 美しい法で描き、手前の橋を見事に 浮き立たせています。 の経営とされているので 中旧暦8月15日の満月かと思いますが 橋を渡る男たちが大山参りから持ち帰った 梵天を担いでいるので この満月は7月15日頃だという説もあり ます。 旧暦7月15日といえば裏ボンの中日に 当たるので 男たちはそれに間に合うように 大山参りから慌てて戻ってきたのかもしれ ないですね。 橋の上で月を眺めている人もいます。 月のではクレムッツ午後6時頃です。 奥に見える橋は3年橋、さらに奥は 白うお橋。 さらに奥は八丁橋と続きます。 今回はこれにて 次回も浮えで分かる江戸時代の暮らし第8 回を お楽しみください。 [音楽]
NHK大河ドラマ
べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~
解説 浮世絵で分かる江戸時代の暮らし 第7回
NHK大河ドラマを応援しよう‼
2025年の NHK大河ドラマ
『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は
江戸時代を舞台に その時代の文化や人々の生活を
鮮やかに描き出しており
多くの視聴者から関心を集めています
今回は そんな江戸の町に暮らす人々の生活を
浮世絵を手がかりに探っていきたいと思います
—–猫のおぶうや 作者不詳
明治17年~(1884)頃作
江戸っ子は皆 お風呂が大好きだったと言われています
しかも仕事前と仕事終わりの2回
お風呂に入っていたそうです
世界でも稀なきれい好きだったようですね
江戸には水道網が引かれていましたが
さすがに水はまだ貴重で
燃料の薪も高価なものだったため
各家庭にお風呂があったわけではありません
一般家庭はもちろんのこと 豪商や武士の家
そして宿屋にもお風呂がないことが多く
人々は「湯屋」と呼ばれた銭湯に通っていました
江戸時代の後期には何と湯屋の数は600件もあったそうで
しかも料金は格安で8~10文(約96~120円)位だったそうです
#NHK大河ドラマ #べらぼう #蔦重栄華乃夢噺 #あらすじ解説 #蔦屋重三郎 #吉原 #北尾重政 #歌川広重 #葛飾北斎
このチャンネルのメンバーになって特典にアクセスしてください:
https://www.youtube.com/channel/UCsaVsGk60LQcmrCOoVxF1tQ/join