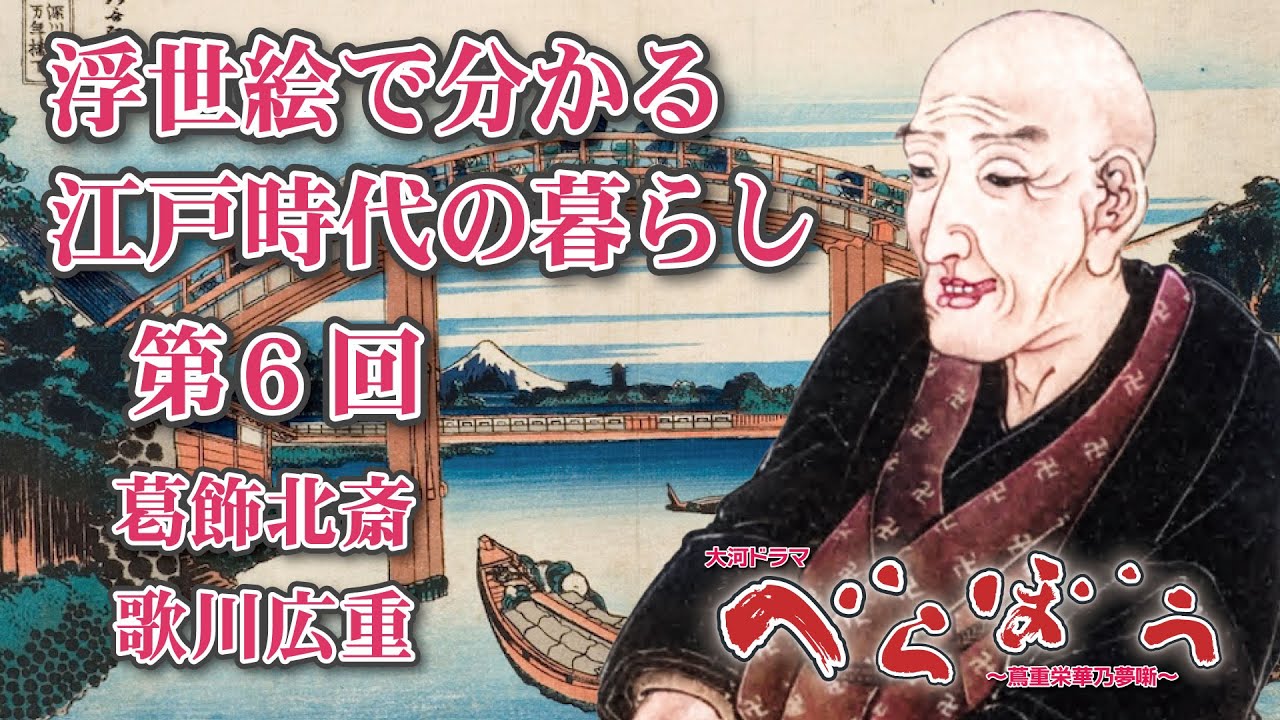NHK大河ドラマ べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~解説 浮世絵で分かる江戸時代の暮らし 第6回
NHKタイガドラマ ベラボスタジオ映画の夢話 解説浮いで分かる江戸時代の暮らし第6回 [音楽] 2025年のNHK大画ドラマ ベラボスタジオ映画の夢話は 江戸時代を舞台にその時代の文化や人々の 生活を 鮮やかに描き出しており、多くの視聴者 から関心を集めています。 今回はそんな江戸の町に暮らす人々の生活 を 浮を手がかりに探っていきたいと思います 。 北川 と名所神田妙人5年1834頃作 と名所シリーズとは初代疑川浩が 市野豊ひの没により美人から風景画を制作 するように転 その出世作であり代表作でもあるのがと 名所シリーズです。 1834年方5年から5年間ほどの間に 描かれたと名所シリーズの神田妙人東坂 広げは東坂としていますが 現在の名前は男坂です。 神田明人は高台に立っており、 江戸時代には湯島天人同様の調合を 誇っていたことがわかります。 画面右下がその男坂で江戸でも評判の9 階段でした。 別の絵があります。 この9階段東坂を上がって北を向けば 上野浩寺や上野の社代が眼下科に広がり ました。 ちなみに神田妙人あたりで 開罰20m内外の大地となっています。 経験的に自盤が固く津波などの危険がない 。 武蔵の大地の上に自社が購入されたことが 分かります。 坂の上には大い町があり、 あはかずさの暴走半島からやってくる。 船のりの目印になり、逆に坂上からは海を 眺めたと言います。 この坂の下に銭型兵事が暮らしていたと。 銭型兵事取物控えの作者野村古藤道は想定 したようです。 車電によると延長2年1309 天業の欄で討伐された平の正戸の霊を 沈めるために 大手町の首塚正門塚近くの神田に平の 正か門を祭りました。 成長5年1600天下分け目の関ヶ原の 活戦を前に 徳川イエア安は神田明人に先を祈願 の関ヶ原活戦の日は 旧暦9月15日で神田祭りの日でした。 以降徳川将軍家より神田祭りは 演利の良い祭例として奨励され、 やがて独歩こたちから妙人様と呼ばれ 商売繁盛の神様として現在に至ります。 5月に行われる神田祭りは江戸時代には 出しが将軍ジラのために江戸城中に入り 将軍家ジ乱の転下祭と言われた英あるもの 祭り深川祭りと共に 江戸三大祭りにも数えられています。 徳川は家康の関ヶ原の戦いの勝利をしして 盛大に行われるようになったとも 江戸時代には三納祭りと確念の交代で行わ れていたため 今でも偶数年に本裁が行われています。 北川広げ ト名所高川26や町の図方 12年1841頃作 26山町とは 毎年7月26日の夜に夜ふまでお年物を 唱え 26日目の細い月を拝むと 網田様観音様子菩薩様 三ゾがお月様に乗って月の光と共に登ら れるのをお待ちした。 特別な夜で願い事が叶うという言い伝えが あったことから この月身を目当てに 月の名所高縄に多くの人が集まったよう です。 絵を見て興味深く感じたのは 屋台で売られている食べ物です。 寿司、そば、天ぷら、イカ焼き、田んぼ、 シルコ、 そしてスカなどの果物を見ることができ ます。 江戸時代に食されていたものは今も身近に あり、 日本人の食欲のレベルにも当時と大差は ないと思われます。 月のでは夜明け近くなのでそれまで屋台で グルメを楽しみ お酒を飲んだり夏の名残りを惜しんだよう ですね。 江どっこたちの飛びっきりの夜遊びでした 。 高川は当時海岸線でした。 今は山手線が走っています。 沖合いに諸国からの物資を運んだ大型の 日垣線が描かれています。 江川沖に物資を運ぶ小さな船も生きってい ます。 勝鹿北斎 富学36系深川満年下方 2年1831頃作 見事な曲線を描いた橋が目に飛び込んでき ます。 万年橋は東西に流れる小川と南北に流れる 住田川の合流地点にかけられた橋で 現代の東京都高区に当たります。 開罰の低かった深川では洪水対策のため 川の両騎士の石を高くしていたとされて おり、 この石炭の上にかけられた橋は周囲よりも 高い位置から 富士を望める絶好の見物スポットだったの かもしれません。 9時は橋の間にひっそり描かれていますが 、 そこに視線が向くようにとの思いか、 水上の船は富士にへ先を向けて浮かんでい ます。 本作の構図は川村民が明年1771に観光 した。 百富士に登場する橋下から着走を得たと 考えられており、 北斎は40代後半の時に制作した反が高橋 の富士で 洋風表現の思考と共にその構図を採用して います。 また同様の構図は後年の不学100系2編 一覧の富士でも採用されています。 絵の右下橋の田元には松尾馬が晩年を 過ごした。 場所案がありました。1686年の春に 開催された。 使いで古池や川ず飛び込む水の音を読み ました。 また場所の弟子がこの家の庭に南国の場所 を植え、 そこから配合を場所にしたとされます。 多少はバナナとどうかの植物です。 この絵が描かれた100年以上も前に 松場弟の空がここから船に乗り 住田川を登りきた千住の宿場から 奥の細道の旅に出発しました。 勝を分かっていてあえて絵に入れたそう です。 橋の向こう岸は今で言う日本橋、浜町、 水天宮のある辺りです。 満電橋は川の流れが穏やかで魚が集まる 絶好の釣り場でした。 楽観は北斎 室必とあり、 イツ時代や時は憲法発からの4年間とされ 、 生涯のうちで最も浮い半に軽中した時期と されています。 今回はこれにて 次回も浮えで分かる江戸時代の暮らし第7 回を お楽しみください。 [音楽] [音楽] [音楽]
NHK大河ドラマ
べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~
解説 浮世絵で分かる江戸時代の暮らし 第6回
NHK大河ドラマを応援しよう‼
2025年の NHK大河ドラマ
『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は
江戸時代を舞台に その時代の文化や人々の生活を
鮮やかに描き出しており
多くの視聴者から関心を集めています
今回は そんな江戸の町に暮らす人々の生活を
浮世絵を手がかりに探っていきたいと思います
—–歌川広重
東都名所 神田明神 天保5年~(1834~)頃作
東都名所シリーズとは 初代・歌川広重が
師の豊広の没により美人画から風景画を制作するように転身
その出世作であり 代表作でもあるのが東都名所シリーズです
1834(天保5)年から5年間ほどの間に描かれた
東都名所シリーズの神田明神東阪
広重は東阪(東坂)としていますが
現在の名前は男坂です
神田明神は高台に立っており
江戸時代には湯島天神同様の眺望を
誇っていたことがわかります
#NHK大河ドラマ #べらぼう #蔦重栄華乃夢噺 #あらすじ解説 #蔦屋重三郎 #吉原 #北尾重政 #歌川広重 #葛飾北斎
このチャンネルのメンバーになって特典にアクセスしてください:
https://www.youtube.com/channel/UCsaVsGk60LQcmrCOoVxF1tQ/join