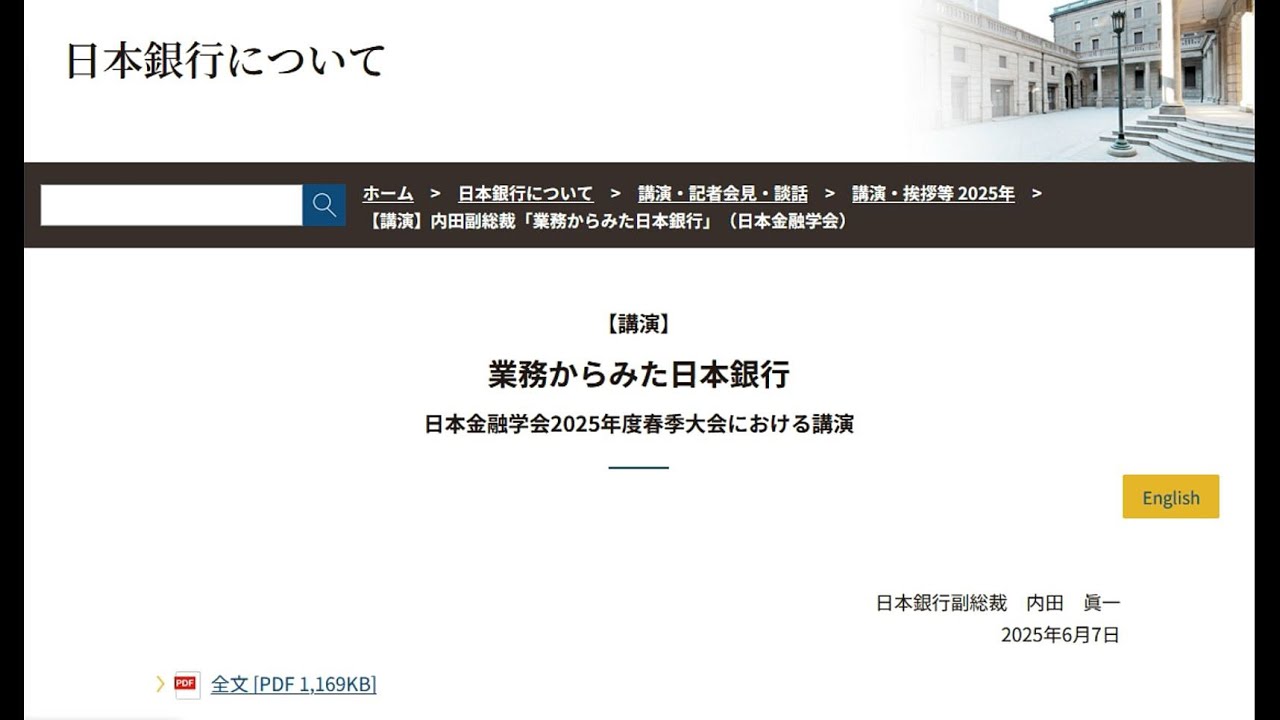2025年6月7日日本銀行公式掲載 「銀行業務からみた日本銀行」資料のご紹介 第1弾!! (通し読み上げ のみ)
公演業務から見た日本銀行日本金融学会 2025年度春期大会における公演日本 銀行副総裁内田新一2025年6月7日1 に日本銀行の内田でございます。本日は 日本金融学会2025年度春期大会にお 招きいただき大変公栄に存じます。私から は業務から見た日本銀行というタイトルで お話申し上げます。足元のマクロ経済や 金融政策運命といったことから少し離れて 日本銀行の業務の面に光を当てて中央銀行 というものを改めて考えてみたいと思い ます。中学の社会化では日本銀行は発見 銀行の銀行政府の銀行であると教えられ 高校にかけて金融政策や物価の安定 あるいは最後の過手や金融システムの安定 について学んでいきます。私自身店長をし ていた頃は中学校の退でお金とは何かの 出前授業をしたりしました。ただこれらの キーワードを有気的に結ぶこと、例えば なぜ中央銀行は菩薩を発行して金利を上げ たり下げたりしインフレやデフレに責任を 持つのかまとめて整合的に説明することは 大人にとっても意外に難しいことです。 中央銀行の政策と業務は一体不分のもの です。通常それは政策を実現するための 手段としての業務という順番に語られます 。今日の私の試みは逆の順番、つまり業務 を出発点にして政策につなげていこうと いうものです。私は昔からこうした視点を 大切なものだと思ってきました。実は 私自身が関わったものを含めて同じような 試みは過去にもいくつかあるのですが、 時折りこうしたことを繰り返していかない と忘れられがちなテーマですので今日の この場をお借りしたいと思った次第です。 2発見銀行流算高 3つの機能のうち発見銀行から始めます。 日本銀行に入行すると視点ではまず発見 業務を経験します。私も松山視点の発見で 手作業の監査を教えてもらい40年前の ことなのでソロ番で近庫内の銀行権の残高 を計算しました。銀行は日本銀行の金庫に あるうちはただの紙ですが取引先の金融 機関に払い出された瞬間に日本銀行の負債 となり強制通用力を有する通貨になります 。図票2をご覧ください。現在市中に流通 している銀行は120兆円でこのうち金融 機関の店舗やATMにある部分は10% 程度です。図表3をご覧ください。900 年以降の銀行権発行高の対GDP費です。 2回の例題を除いてほぼ全ての期間で 10%ゼの水準にあります。決済手段とし ての銀行権の特徴はどこでも支払いに 使える一方で利息がつかないことです。 ある程度高額の支払いには銀行振り込みや クレジットカードが使われることが多い ですが、日常的な支払いに必要な現金の額 は時代を問わず経済規模に比例している ようです。例外の2回のうち1回は第2次 対戦前後でこれは経済と下幣価値の混乱に よるものでしょう。もう1回が1990年 代半ばから現在に至る期間で直近では対 GDP費は20%と通常の2番以上の銀行 が日本銀行の外で流通しています。この1 つの要因は定金利環境が続き人々がこなめ に預金しに行かなくなり手元に現金を置い ておくことが増えたことです。インフレの 際の修レザーコストの逆のような現象と 言えます。この点昨年からの3回の利上げ によって政策金利は0.5%普通預金金利 は0.2%程度になっています。これは 2007年2月から2008年10月まで の約1年半と同じ水準ですが、この時は 銀行健残高のトレンドは変化しませんでし た。この先の金利がどうなるかは本日の 公園の趣旨を外れますので置いておくとし ましてどの程度の金利がどの程度の期間 続くと人々が保有する現金が減るのか先見 的にはははははっきりしません。今後の 同向をよく見ていきたいと思っています。 3政府の銀行国業務と電子化次に政府の 銀行としての機能についてお話しします。 この機能については各国で様々なやり方が ありますが、ほぼ共通しているのは政府が 中央銀行に預金口座を持っていることです 。日本銀行にも政府の預金講座があり、 国金の出入りを管理しています。またこれ に加えて日本銀行では会計項目ごとの整理 や国際発行などの事を行っています。こう した機能を果たす上で全国の金融機関が 日本銀行の代理店あるいは歳入代理店と なってネットワークを形成しています。 日本銀行には本天と32の視点があります が、納税の際に日本銀行の本視点に行くの は一般的ではありませんし、国の館長は 日本銀行の本視点所材地から離れた場所に もあります。この代理店等と日本銀行の間 で情報と資金のやり取りをすることで最終 的に日本銀行にある政府預金の入出勤が 完了します。以前は代理店頭が個人から 受け付けた納付書類を日本銀行の本視点に 郵送して日本銀行で集計することで国業務 が行われていました。私も40年前には 地点で入金の調表をめくりながら加算期 レジのような機会です。で、集計作業を やっていました。図表6をご覧ください。 現在では国業務の電子化は相当進み、年金 の支払いなど国からの支払いについては 99%が電子化しています。一方、納税 など国が資金を受け入れる方向の事務は 収める国民の皆様の選択による部分が 大きいため、電子化の比率は7割程度です 。中央銀行と政府の取引銀行は国金の管理 に付随して政府の資金繰りの実務も担って います。収入と支出のタイミングの常に よって政府預金の残高は上下しますが短期 的な資金の不足は国個短期証券の発行に よって賄えます。これは公募入札で金融 機関等に売却されますが例外的に募集残額 が生じたり国に良きせざる資金需要が生じ た場合には日本銀行が引き受けることが できます。その場合には次回以降の公募 入札の代金で召喚を受けることになってい ます。また日本銀行が金融市場調節など 自らの必要のために買った国際の召喚期限 が到来した場合国短期証券で借り替える ことができるようになっています。これは 乗り換飛級受けと呼ばれ日本銀行側では 政策委員会が金融市場調節上支障がない ことを確認して議決する必要がある。ほ、 政府側では財政法第5条の例外として国会 の議決が必要になります。以上細かい説明 になりましたが、これらの業務は政府に 対する信用協にあたり、政府と中央銀行の 関係を考える上で重要な論点を含んでい ます。このため日本銀行では対政府取引に 関する基本容量を定め、基準や手続きを 明確にしています。またこうした政府の 銀行としての業務とは別に金融政策目的で の国際の買入れがあります。現在の日本 銀行のバランスシートの資産サイドで最大 の項目は国際です。これは2013年から の大規模な金融緩和において2%の物価 安定の目標を実現するため金融政策の必要 性から買入れ保有しているものです。政府 による財政資金の調達を支援するための ものではありません。ただしこの問題は 中央銀行が金融政策目的であって財政 ファイナンスではないというだけで完結 するとは思っていません。出口を含めた 緩和政策の全プロセスにおいて経済物価と の関係で適切な金融政策を行い、これを 財政状況への配慮によって曲げることは ないという結果が必要です。その意味で 今後の日本銀行の政策運営を持って示して いくべきことと考えています。4銀行の 銀行決済と最後の貸して機能中央銀行の 歴史は国によって多少の違いはありますが 歴史的な原型の1つであるイングランド 銀行を含めて多くの中央銀行が銀行間の 資金決済を司さどる銀行の銀行として 始まっています。銀行館の資金決済のため には当然各銀行が中央銀行に預金口座を 持つ必要があります。また決済を円滑に 行うためには中央銀行の信用共有与が必要 になるのが普通です。その際には古くは 商業手方のように昇流の裏付けがある資産 を担保として健全な銀行に一時的な流動性 を強与していました。その後も担保の中心 が国際に変わった点を除担保でソルベント な銀行に対して流動性を強与するという 基本的な構造は今に至るまで同じです。 こうした機能を有する中央銀行の多くは 設立当初からあるいはその歴史の中で金融 システムを守る公的な役割を付与され最後 の貸しとして機能しています。その際有 担保の通常の貸し出しに加えて無担保の 貸し出しやソルベントでない金融機関への 信用共用を行うかは預金保険制度など他の セーフティネットとの役割分担の問題とも 絡んで各国で様々です。また時期によって も信用教与の携帯や手続きなどの面で編成 があります。また近年2008年の グローバル金融機器などを経てこの最後の 貸して機能は広がりを見せ最後の グローバルな貸してGLLRや最後の マーケットメーカーMMLRと呼ばれてい ます。一例としてはグローバル金融機器の 際に作られた先進国中央銀行館のスワップ モとそれを利用したドル資金供給スキーム があります。各国中央銀行は時国通貨は無 制限に発行できますが他国通貨は持って いる分しか供給できないので時国の金融 機関の外下流動性の不足に対しては最後の 貸し手になれません。このスキームは先進 国間でスワップを作ることで他国の通貨を 供給できる余地を広げたもので近年では コロナ禍の2020年ドル資金調達の コストが急上昇した際のバックストップと して有効に機能しました。このことは本質 的にドメスティックな存在である中央銀行 にとって中央銀行間の協力関係が非常に 重要であることを示しています。短期金利 の操作こうした最後の貸しの機能は例外的 なケースで発揮されるものですが、通常時 においても銀行間の決済を完了させるには 何らかの形で中央銀行が流動性を強与する 必要があります。冒頭お話ししたように 銀行権は取引先の金融機関に払い出すこと で流通を始めるわけですが、少なくとも 金融機関はそのための原子となる預金残高 を日本銀行の口座に持っている必要があり 、その資金は元を正せば日本銀行がどこか の金融機関に信用共与を行ったか国際など を買った代金を払ったことによるはずです 。伝統的には中央銀行は銀行権の受け払い や政府との資金のやり取りを勘案した上で 準備を金制度上要求される最低限の残高を 積むために必要になる義務学を金融機関へ の貸し出しや国際の売買などを通じて供給 します。その際の金利などの条件によって 短期の金利が決まるという仕組みです。 従ってかつては中央銀行のバランスシート の大きさも概行権発行残高と準備預金の 義務額で決まっていました。図票7はその 頃98年度末のバランスシートです。当 預金への振りトのインプリケーション。 しかし現在では多くの中央銀行がバランス シートの大きさと短期金利の操作を 切り離しています。当預金に金利をふすと いう金利操作の方法が導入されたためです 。日本銀行も2008年に保管当制度を 導入し、超準備当預金のうち準備預金制度 に基づく所要準備を超える部分に対する ふりができるようにしました。当初は臨時 措置として導入されましたがその後高級化 されました。金融機関は余った資金を日本 銀行の当に置くか市場に放出するかの選択 がありますので最低行動により市場の金利 は日本銀行がふりしている水準に近い水準 に誘導されます。現在で言えば不利金利は 0.5%市場における短期金利は 0.48%程度です。このことはその後 技術的な金利操作の手段という意味合いを 超えて大きなインプリケーションを持つ ようになりました。1つは金利操作と 切り離してバランスシートの大きさを決め られるようになった結果、資産サイドを 使った政策を大規模に行うことが可能に なったことです。非伝統的金融政策の中心 手段の1つはいわゆる両的間はすなわち 国際の買入れによって長期金利を 押し下げることですが、これを実行するの にはバランスシートの大きさとは無関係に 短期金利をコントロールできることが前提 になります。この点両的緩和を実行して いる間は割り切ってしまえば金利を コントロールできなくても0金利でも良い と考えることもできなくはありません。 しかし両的緩和からの出口プロセスに時間 がかかることはあらかじめ分かっているの でその時に大きなバランスシートを抱え ながら短期金利をコントロールできること が保証されていないとこうした手段は採用 できません。バランスシートの大きさと 短期金利の操作が切り離されたことのもう 1つの期決は短期金融市場の参加者と中央 銀行の取引先の範囲が必ずしも一致しない ことで起こる流動性の変在への対応が可能 になったことです。取引先と取引先が混在 する状況で伝統的な短期金利操作によって 所用順病均残高ギリギリの水準しか供給し ないと金融市場の多様なに必要な流動性の 量に足りないということが起こってしまい ます。この問題は米国FRBのように法律 で当座預金取引先の範囲が基本的に預金 取り扱い金融機関に限られている国では 以前からあったのですが、近年は各国で ノンバンク金融仲会機関NBFI、 保険会社、年金基金、各種ファンドなどの 存在感が拡大し、その影響が短期金融市場 に及んでいます。この状況に対応するには 中央銀行がふりを使って短期金利を操作し ながら市場に必要な量の流動性を供給 できることが重要です。現在各国の中央 銀行はバランスシートの縮小を進めてい ますが、その多くは伝統的な金融調節方法 に戻ることはないでしょう。市場の求める 流動性に見合ったバランスシートを維持し ながら当への振りによって短期金利操作を 行うことになるだろうと思います。52つ のキーワード人々が安心してお金を使える ようにすること図標8をご覧ください。 ここで1度これまでの話をまとめるキー ワードを2つ提示したいと思います。人々 が安心してお金を使えるようにすることと 支払い完了性のある決済手段を提供する ことです。これまで述べてきたような様々 な業務を行うことで日本銀行が果たすべき 目的について日本銀行法第1条は銀行権を 発行し通貨及び金融の調節金融政策を行う こと及び資金決済の円滑の確保を図りもっ て信用秩序の維持に指することと否定して います。そして第2条では金融政策の理念 として物価の安定を図ることを通じて国民 経済の健全な発展に指すると定めています 。法律要用語なので目的や理念などの け明けがありますが、こうした日本銀行の 役割を一言でまとめるとすれば人々が安心 してお金を使えるようにすることです。 日本銀行に関心を持ってくれる学生の皆 さんなどにはそう説明しています。銀行権 がクリーンで偽造権がないようにすること やお金の価値すなわち物価が安定するよう にすることはまさにその具体化です。また 人々がお金という時持っている現金だけで なく銀行に預けてある預金残高も早期する でしょうから金融システムの安定を図る ことも重要になります。支払い完了性の ある決済手段そして中央銀行がこうした 使命を追求することができる厳選は業務面 で支払い完了性ファイナリティのある決済 手段を提供できることにあります。まず この支払い完了性の意味ですがある個人が 別の個人や店舗に銀行権を渡せば支払いは 完了します。金融機関同士や政府との資金 の決済は日本銀行の当座銀行座の受け払い で完了します。日本銀行権と日本銀行当は 共に支払い完了性があり、他の決済手段に は同じ意味での完僚性はありません。中央 銀行が最後の貸してになれるのも支払い 官僚性のある決済手段を提供できるから です。中央銀行の貸し出しは相手方の金融 機関の口座に資金を起調し、中央銀行の 負債の増加、貸し出し債権を取得する中央 銀行の資産の増加で実行できるので無制限 に実行可能です。また先ほどの別通り金融 政策における金利操作も決済に必要な資金 が向上的に不足することを前提として中央 銀行が銀行間の決済を完了させる手段を 供給できる唯一の存在であることを利用し て資金をやり取りする短期市場の条件金利 を決めることができるという仕組みです。 として支払い官僚性のある決済手段を無限 に供給できる中央銀行は信用共有与を含め て政府の資金繰りを完結できるのですが これがデリケートな問題を含み極端な場合 には物価の安定とのをむことは歴史的な 事実です。先ほど述べた非伝統的な金融 政策としての国際会入れはその現代的な 現れと言えます。財政ファイナンスかどう かの引きについて私は財政への配慮で適切 な金融政策を曲げることがないという点に あると考えていますが、支払い完了性の ある決済手段の使い方としてより手前で 予防線を引くべきという考え方もありえ ます。グローバル金融機器以前の中央銀行 の常識にはこの点の自主規制があったよう に思います。この辺の事情は別の機会4に 論じましたので今日は省かせていただき たいと思いますがグローバル金融機構の非 伝統的な金融政策の交際は中央銀行公開 全体の課題だと思っています。日本銀行権 と日本銀行当日本銀行の負債です。以上の ことをまとめると日本銀行はその負債とし て支払い完了性のある決済手段を供給する ことで人々が安心してお金を使うことが できるようにする役割を負っているという ことができます。6デジタル社会の中での 決済システムと中央銀行業務決済の デジタル化図表級をご覧ください。ここ からは後半パートに入り、日本銀行の業務 と政策がデジタル化などの環境変化によっ てどう変わるのか、あるいは変わらないの か考えてみたいと思います。我が国は キャッシュレス比率が低いと言われます。 この点は各国で定義も異なり厳密な比較は 難しいのですが、我が国の場合銀行口座で の引き落としの他振り込みの割合が大きい のが特徴です。これは1973年から稼働 している全銀システムによってこれらが 極めて便利にできていることが背景です。 また冒頭でご説明したように我が国の銀行 健算残高は低理になる前で比較しても他国 よりも多くなっています。これには現金を 持ち歩いても安全であることやその元で コンビニエンスストアを含めてATMが 発達しているという背景があります。元々 人々がどのような決済手段を使うかはその 人の自由です。最も日々の買い物を含めて 経済のデジタル化が進展する中で人々に とって便利で安全な決済手段を選択できる ようにそれにふさわしい決済手段が提供さ れることは重要です。として決済システム が全体としてデジタル社会の中で高い安定 性と効率性を発揮するために中央銀行が どのような形態の支払い完了性のある決済 手段中央銀行負債を提供すべきか設計して いく必要があります。中央銀行デジタル 通貨この点に関連して中央銀行自身が デジタル通貨中央銀行デジタル通貨 CBDCを発行するというプロジェクトが 各国で進められています。欧州では欧州 中央銀行ECBが2023年にデジタル ユロに関する調査フェーズを完了し、準備 フェーズに移行しています。また イングランド銀行はデジタルポンドについ て設計フェーズの進捗レポートを公表して います。中国では国内26都市や香港で デジタル人民源のパイロット実験を実施中 です。一方、米国では2022年から23 年にかけてCBDCに関する市中協議を 行いましたが、銀行協会などから強く懸念 する声が寄せられました。またトランプ 大統領は今年1月CBDCの発行等に 関する政府機関の取り組みを停止禁止する 大統領例に署名し、FRBのパウエル議長 も2月の議会証言で自身の在任中の CBDCの発行を否定しています。我が国 では2020年に日本銀行が中央銀行 デジタル通貨に関する取り組み方針を公表 し技術的な検証を進めています。23年 からはパイロット実験に移行し、実験用 システムの構築と検証を実施するとともに 民間事業者の技術的な地見を活用するため CBDCフォーラムを設置し、幅広い関係 者に参加いただいて様々なテーマで議論し ています。政府においてもCBDCに 関する関係不省庁日本銀行連絡会議が設置 され、制度設計の応枠の整備に向けて検討 が進められています。GBDCはデジタル 社会の元での我が国の決済システムの将来 像を決める重要なインフラになりるもの ですから、これを発行するかどうかはこう した内外の情勢を踏まえた上で国民的議論 の中で決める必要があります。ご説明した 通り各国の対応も分れています。ただ CBDCを発行するにせよしないにせよ デジタル社会の中で現金のような支払い 完了性のある決済手段を誰がどのように 提供するのが決済システム全体の安全性と 効率性につがるのか考えていくことは必須 です。具体的な仕組みとしてはまず必ず 必要になる個人との接点インターフェイス の部分はいずれにしても基本的に民間の 事業者が担うべきだと思います。個人の 多様なニーズに答えることは公的機関で ある中央銀行には難しいからです。その中 で利用者にとって便利なインターフェイス やそれを生かしたイノベーションが 生まれるのだと思います。その上で考え られるバリエーションには結構大きな幅が あります。決済手段というものはその ほとんど全てが最終的には中央銀行に つがっています。全てと言いきらない理由 は最終省で述べます。問題は人々が現金と 同じような機能を持つと認識する決済手段 はどの程度直接的な支払い完了性を有する 必要があるのかその支払い完了性をどう 担保するのかということです。この点 CBDCは中央銀行の負債ですので現金と 同等の支払い完了性があります。GBDC を発行しない場合には民間が提供するその 決済手段と中央銀行負債をどう結びつける のかまた現金のようにいつでも受け渡し 可能であるようにオペレーションの元検性 や後半なり可能性をどう確保するかなど 技術的な側面を含めて検討する必要があり ます。国際的な視点決済の未来像を考える 上では国際的な視点が欠かせません。実を 言えば現在の国際的な決済システムには 多くの不満が寄せられており、これを いかに便利で安全なものにしていくかは 未来の問題というより現在の喫金の課題 です。例えば各国では外国からの労働者が 母国に送金する際の手数料の高さや時間の 遅さが問題になっており、2020年以降 G20のアジェンダにはクロスボーダー 送金の改善が掲げられてきました。この点 は既存のコルス銀行を中心とするシステム の運用を改善していく方向性として決済 システムの稼働時間の拡大国際総電分 フォーマットの標準化などの法策が検討 実施されている。ほ、新たな可能性として 例えば各国のリテールの即事送金システム ファストペイメントシステム日本では全銀 システムやことらがこれにあたりますの 相互接続といったことも模索されています 。また金融機関間の資金決済や貿易に かかる決済などより大口の資金決済の分野 では先進国のグループや新国を中心とした プロジェクトなど様々な試みが進行し成果 を競い合っています。その1つBISが 主催し、多くの民間金融機関と日本銀行を 含むつかの中央銀行が参加している プロジェクトアゴラでは運産大腸技術 DLTを使った共通プラットフォーム上に 商業銀行預金と中央銀行預金の量を載せて それらを組み合わせて安全かつ効率的な クロスボーダーの決済を行うという新しい タイプの決済インフラが構想され実験 プロジェクトが始まっています。こうした 国際的な決済システムを巡る取り組みが 競そうように進展していることは経済安全 保障の観点と切り離せません。ロシアの ウクライナ進行を受けて各国で経済制裁が 発動されその実行性を担保するため スイフトなど国際的な決済ネットワーク からロシアの銀行を排除する動きになった のは記憶に新しいところです。またやや 異なる観点ですが、サイバー空間には国境 はありませんので、サイバー攻撃が大規模 か組織化されるもで、一国の決済システム の安全をどう守っていくのか、その際の 中央銀行を含めた公的部門の役割は何か? 考える必要は年々大きくなっています。 例えばデジタル通貨が発行された場合、 中央銀行が発行するにせよ、民間が提供 するにせよサイバー攻撃の対象になり やすいと考えられます。これに対抗する ためには総合のコストと技術を集める必要 があります。米国は基本的に民間の イニシアティブで進めていく方向に見え ますし、欧州は官民でCBDC エコシステムを構築する計画です。PCB がCBDC発行の理由としてユロエリアの 戦略的自立性ストレートジック オートノミート通貨主権モネタリー サーブレTを高めることユロ決済における 非欧州系の民間決済事業者プライベートの ヨーロピアンペイメントプロバイダーズへ の依存度を下げることとはっきり述べて いることはこの問題が国内内的な事情を 超えて経済安全保障的国際競争的な側面を 持っていることを示唆しているように思い ます。7非連頭的な金融政策と中央銀行の バランスシート非伝統的な金融政策の効果 資産サイドと負債サイド後半パートの2つ 目のテーマは非伝統的な金融政策と バランスシートです。非伝統的な金融政策 はその名の通り伝統的な業務運営を超えて 中央銀行業務を拡張することで金融政策の 効果を追求するものです。これはしばし バランスシート政策と呼ばれます。中央 銀行が支払い官僚性のある決済手段を負債 として供給することはその裏側で資産を 持つことを意味しています。理論的には 支払い完了性がある負債はいくらでも提供 できるのでどんな資産をどれだけ持つかが 制作のパラメーターになり得るのです。 図標10をご覧ください。現在の日本銀行 のバランスシートです。非伝統的金融政策 として長期国債を買った場合資産サイドで 長期国債が増加し負債サイドでは相手方の 金融機関の当預金が増えます。その制作 効果は資産サイドで国際を買いることに よって市中から金利リスクを吸収し、 タームプレミアムを押し下げる効果、 いわゆるストック効果が中心であると分析 されています。一方、負債サイドの当座 預金残高やマネタリーベースあるいは バランスシートの大きさには資産サイドの ような直接的な効果があるわけではあり ませんが、一定のアナウンスメント効果は 持つ可能性があります。大きなバランス シートを急激には縮小できないことは市場 も分かっているのでしばらく緩和を続ける というメッセージになり得るということ です。2000年代の初め頃、川瀬市場 などで中央銀行のバランスシートの大きさ の比較が材料になったことがありました。 この点リミアな関係を導くことは無理です が、緩和スタンスのプロキシーとして緩い 関係を見い出すことは不可能ではなく、 あとはケインズの美人島を表に機能したと いうことでしょう。バランスシートの大き さを明治的に使ったコミュニケーションと しては日本銀行は2016年9月に イールドカーブコントロールを導入した際 に消費者物価指数生産食品の前年費上昇率 の実績値が安定的に2%を超えるまで マネタリーベースの拡大方針を続けると いうコミットメントオーバーシュート型 コミットメントを行いました。先ほどのべ た通り短期金利の操作とバランスシートの 大きさは切り離し可能なものなのでこの コミットメントは強いものではありません 。より直接的なコミットメントとして、 例えば消費者物価が2%を安定的に超える まで長の金利目標の水準短期は-0.1% 、10年金利は0%程度を続けると約束 することも論理的にはあり得ました。ただ これではフォワードガイダンスとして強 すぎ将来の柔軟性を犠牲にする恐れがあり ましたのでバランスシートの大きさに 紐付けたということです。一般的に バランスシートの拡大を続けながら利上げ をするというのはイメージしにくいので 緩和を続けるというスタンスは伝わる一方 でオペレーション的には業務面から考えれ ばバランスシート縮小QTの前に売上を 始めることは可能でその余地を残したもの です。この辺りの事情はフォワード ガイダンスという自分を縛って効果を得る 政策の微妙なバランスを示しています。 効果と自由度のバランスを取るために明治 的に例外エスケープクローズを入れておく という例もありますが、業務の要素を絡め て対応余地を残すという方法もあるという ことです。日本銀行を含めて各国の中央 銀行は当然こうしたことを分かった上で バランスシートと政策金利の運営、そして そのシークエンスを考えコミットメントを 実施してきました。こうした意味でも中央 銀行にとって政策と業務は不可分のもの です。非伝統的な金融政策と中央銀行の 収益。中央銀行は平常時にはバランス シートの構造上収益が上がるようになって います。もう1度増標7をご覧ください。 98年度末え伝統的な金融市場調節を行っ ていた当時のバランスシートです。負債 項目の多くを占める発行銀行貢献は無理 です。当預金も無理でした。この時点では 不利制度は導入されていませんでしたし、 仮に導入されていたとしても準備預金 ギリギリの水準で調節を行うのであれば ほぼ無理です。一方で資産サイドの国産や 金融機関への貸し出しには利息がつきます 。この差額は通過発行権を持つことに伴う 収益シレッチであり支払い完了性のある 決済手段を負債として独占的に供給できる ことによるものです。この関係は非伝統的 な政策によってバランスシートが大きく 拡大すると変化します。まず非伝統的な 制策を行っている間は収益は大きく拡大し ます。短期金利は0%ないしマイナスです ので負債サイドの利払いは基本的には 生じることはありません。資産サイドから はバランスシートが大きい分だけより 大きな収益が得られます。日本銀行の場合 、当金を三層構造とし、マイナス金利部分 を最小限に抑える一方、プラス金利部分も あったため、ネットで利払いが発生しまし たが、資産サイドの方がずっと大きな効果 を持ちました。図表11をご覧ください。 実際大規模緩和前の日本銀行の経常利益は 平均して6000億円程度でしたが、大 規模緩和を行っていた時期には毎年数兆円 の収益を計上していました。これが出口に なると当預金のふりによって売上を行う 一方で資産サイドは金利が低い時に買った 国際で固定されているため薬が発生します 。この点日本銀行のスタッフが シミュレーションを行っています。図表 12をご覧ください。その結果は短期金利 、長期金利のパス、バランスシート縮小の ペース、さらには冒頭でご説明した銀行権 の残高がこの先どうなるかなど複数の要因 に左右されます。前提条件として昨年9月 時点で市場が折り込んでいた金利未投資の 通り金利が動くと仮定した場合青い実践の ようになります。この前提では収益は減少 しますが赤字にはならないという結果でし た。ただ金利がより急激に上昇するなどの ストレスをかけるとシャドウのように一時 的に赤字になる場合があります。ただ どちらのシナリオでもその後は負債サイド で当預金が減少し資産サイドで国際が高い 金利のものに入れ替わっていくに従って 収益が回復していきます。このように収益 や自己司法の資産は前提条件次第で変わり ますが、いずれにしても中央銀行の バランスシートの状況によって物価の安定 が既存されることはありません。皆様には ご説明するまでもないことですが、管理 通貨制度のもで通貨の森認は中央銀行の 保有資産によって担保されるものではなく 、適切な政策運営によって物価の安定を 図ることを通じ確保されます。またそうし た指名追求のための政策遂行能力に財務 状況が影響を与えることもありません。 一時的に赤字や極端な場合債務聴化になっ たとしても収益や資本は信列による将来の 収益で復言されますし、支払い完了性の ある決済手段を自ら供給できるため支払い は常に可能です。実際にFRBやECBを 含めて多くの中央銀行が現在赤字を計上し ており、その一部は債務聴化になってい ますが、業務や政策の運営に支障は生じて いません。それでも多くの中央銀行は自己 資本など一定のバッファーを有しています 。日本銀行も自己資本を有している。か、 大規模緩和の家程では収益の上ぶれ分の 一部を引き当て金として流保し、出口で 損失が発生した場合に備えています。本来 中央銀行の財務構造を理解していれば問題 ないことであったとしても、例えば赤字や 債務超などが発生した時に市場が中央銀行 が財務リスクを気にして適切な政策の実施 を躊躇するのではないかといった疑念を 持つようなことがあれば政策効果の波及が 阻害されます。そうした技疑念を弱期さ せることのないよう、適切な政策運営を 行うという大前提のもで、上気の引き当て 金など可能な手段を通じて財務の健全性に も配慮していくことは大切です。8中央 銀行業務と決済システムの未来像銀行権の 未来。最後に中央銀行業務と決済システム の未来像について思考実験を行ってみたい と思います。デジタル化が大きく進む中で 銀行権はどうなるでしょうか?この点まず 申し上げたいことは日本銀行は現金に 対する需要がある限り現金の供給について 責任を持って続けていくとコミットして いるということです。中央銀行が現金供給 に責任を持つ中で銀行の視点や コンビニエンスストアを含めたATM網 など現金が流通する経路が維持され、人々 にとって現金を使うことが便利であり 続けることは重要でそれによって今後の 現金の使われ方は変わってきます。 スウェーデンでは現金流通残高の対GDP 比率が0.9%まで低下しています。これ はデビットカードや個人乾燥金システムが 便利だということが主院ですが、銀行の 店舗などの関係で現金の利用が不便になっ たことも一員と言われています。このため 2021年には金融機関は現金の引き出し や受け入れ拠点を整備しなければならない という趣旨の法律が制定されました。こう した問題意識は他の欧州諸国でも見られ、 例えば米国では2023年の法令に基づき 財務省がATM等の配置に関する距離基準 を設定しています。スイスでは中央銀行と 財務省が金融機関警備輸送会社交理業界 消費者団体等を招いたラウンドテーブルを 共し現金を巡る課題と共に現金は将来に わって必要であるという認識を共有しまし た。さらに欧州諸国はそうではありません が、偽造などによって銀行権を使うことの 便利さや安全性が低いことが キャッシュレス化が進む要因になっている 国もあります。一方、当然のことながら 現金の供給体制の維持にはコストがかかり ます。現金供給には日本銀行だけでなく 金融機関、コンビニエンスストアなどの リテール事業者現金を運ぶ警備輸送会社 など多くの関係者が関わっています。この 体制を維持していくためにはこれらの関係 者にとって銀行権の供給がそれぞれの顧客 のニーズに答えてサービスを維持していく メリットがあるものであり続ける必要が あります。この顧客ニーズという点では私 は決済には経路依存性があり、現金は対面 での決済としてとても便利なので現金に 対する需要は簡単にはなくならないと思っ ています。日本銀行としてはそうした ニーズがある限りいかに安全かつ効率的に 現金級の体制を維持していくか責任を持っ て考えていきたいと思います。デジタル化 やキャッシュレス化は社会経済の効率性を 高める効果を用ちうるものだと思いますが 、そのプロセスは利用者の自由な選択の中 で進むのが望ましいと思っています。架空 の世界、現金のない世界、銀行権が存在 するのであれば仮に決済に占める比率が 低下したとしてもこれまでお話ししたよう な中央銀行の業務のやり方や政策の メカニズムは変わりません。支払い官僚性 のある決済手段の唯一の提供者として資金 供給などの業務によって金利操作を行い 日々の決済を完結し、最後の過として機能 します。このメカニズムが変わる可能性が あるのは以下のような2つの構造変化が 起こった場合です。いずれも架空の シナリオです。こうしたことが起こると 予想しているわけではありませんが、架空 の世界を想像してみることは現在をより よく理解する上で有益です。1つ目は現金 が全く存在しなくなる場合です。く CBDCが発行されればマイナス金利を 吹すことができるので金融政策運営は 大きく変わると言われますが正確には少し 違います。まずCBDCが発行されても 現金が残る限り名目金利のゼロ制約は残り ます。マイナス金利をふされない下げ場が ある限りCBDCにマイナス金利をふす ことには限界があります。また逆に現金が なくなるのであればCBDCを発行して いるかどうかはあまり関係ありません。 民間が提供するデジタル通貨であっても何 らかの形で金融資産の裏付けがある以上、 中央銀行は金融資産の価格、金利に影響を 与えることで金利のゼロ制約を破ることが できます。例えば民間提供のデジタル通貨 が中央銀行の当に紐づいている単純な ケースでは当金の振り水準の変化によって 民間デジタル通貨にマイナス金利をすこと ができます。そうした意味でマイナス金利 を可能にするためにCBDCを発行すると いう発想は中央銀行にはありません。この 現金がない世界では金利のゼロ制約がない ためマイナス金利のふりに限界がなく従っ て政策金利の引き下げ余地の乗りを確保 する必要はなくなります。物価目標は バイアスのない物価指標であれば0%に なるはずです。金融政策の運営は大きく 変わります。それでも中央銀行として物価 の安定などの使命を果たすことができると いう点は不遍です。架空の世界円のない 世界もう1つの可能性は中央銀行としては 起こって欲しくないシナリオです。円で 表示されない決済手段が決済の主役になる ことです。取引の決済は双方が合意するの であればどんな手段でも可能です。それは 円で表示される資産に限らず金でも米でも 引っ越しのお手伝いでも片たき権でも双方 がそれで再権債務関係を消滅させることに 納得していれば構いません。デジタル社会 においては暗号資産がその対象となり得 ます。元々一部の暗号資産の同期には主権 国家に頼らないビバタリアン的な発想が あります。現在円で表示された銀行権や 銀行預金の振り込みが利用されているのは それがほとんど全ての人が納得する決済 手段として認識されているからです。その 前提の下で日本銀行には法律的にも強制 通用力が付与されています。ただしこれは あくまで円で表示された債権債務関係を 消滅させる弁載手段となるというだけで あって取引関係に入ることを強制される わけではありません。私は金でしか あるいは暗号資産でしか売る気はないと いうことは契約自由の原則により可能です 。こうした未来が訪れることは少なくとも 我が国においてはないと思います。縁に 連動しない決済手段について物やサービス との関係で価値を安定させる仕組みを作る ことは中央銀行の物価の安定と同じ機能を 独自に持つということですから簡単では ありません。中央銀行が価値を安定させて くれる縁に乗っかった方がずっと合理的 です。その意味で中央銀行がその使命を きちんと果たしている限り円以外の決済 手段が決済の主役になることはない でしょう。中央銀行がその使命をきちんと 果たしている限り9終わりに本日は日本 銀行の政策について業務に焦点を当ててご 説明しました。もう1度増標8をご覧 ください。中央銀行の政策の厳選は支払い 官僚性のある決済手段負債の提供とその 裏側で資産として何を持つかにあります。 日本銀行はそれを通じて金利操作を行い 最後の過手として機能します。非伝統的 政策はこうした業務やバランスシートを どのようにどこまで使えるのかを追求した ものとも言えます。政策を考える時に業務 に関する理解は不可欠です。それは業務と してできないことが制約になるといった 意味ではなく、むしろ中央銀行業務の持つ 可能性を知った上で政策のイノベーション につなげるという方が私には実感に合い ます。ただし支払い完了性のある決済手段 を独占的に提供できることの重みを しっかりと胸に刻んだ上でという自覚が 必須です。万能薬は使い方によっては モラルハザードを生むものです。として 何より支払い官僚性のある決済手段を与え られた目的は人々が安心してお金を使える ようにするためであるということを忘れて はならないと思っています。校舎の使命を 果たせない場合全車の手段は機能しなく なります。歴史は物価の安定が損われて あるいは金融システムが崩壊して自国通貨 が流通しなくなる国をたくさん運んでき ました。さらに将来に向けてはデジタル化 が大きく進展した社会で主権国家の中央 銀行が発行する通貨が一般需要性のある 決済手段として機能し続ける保障はあり ません。支払い決済手段を選ぶのは人々の 自由である。このことを胸に置いて中央 銀行の業務を運営していかなければなり ません。もちろん多くの関係者の皆様と共
こちらは今年2025年6月7日に掲載されたばかり。日銀副総裁の
「日本銀行の業務」を解説した資料の「通し読み上げ」動画で
す。(一部飛ばしている箇所もありますがほぼ通しております)
当初は、中身は難解なこともあり要点解説など編集してからアッ
プしようと考えていましたが、私ら国内有権者が「銀行実務内容」
を知るためには非常に貴重な資料だということがわかりました。
そのため、先行第一段としてシンプルに「通し読み上げ」動画
といたしました。
現在youtubeでは国会議論動画が隆盛ですが、国内貨幣の実務を
担当する「日本銀行の実務」中身を探るのが何より「芯」!!
まずは中身を確認してみてください。
公式資料ですし、ちまたで広がっている嘘情報是正へのソースと
しては最適。
この資料は私らにとって重要と分かりましたし、今後何回かに
分け、また繰り返し深堀りして解説編動画をアップする予定で
す。
周囲へ、この資料存在だけでも拡散して頂けるだけでも幸いです。
資料元 リンクコチラ https://www.boj.or.jp/about/press/koen_2025/ko250607a.htm