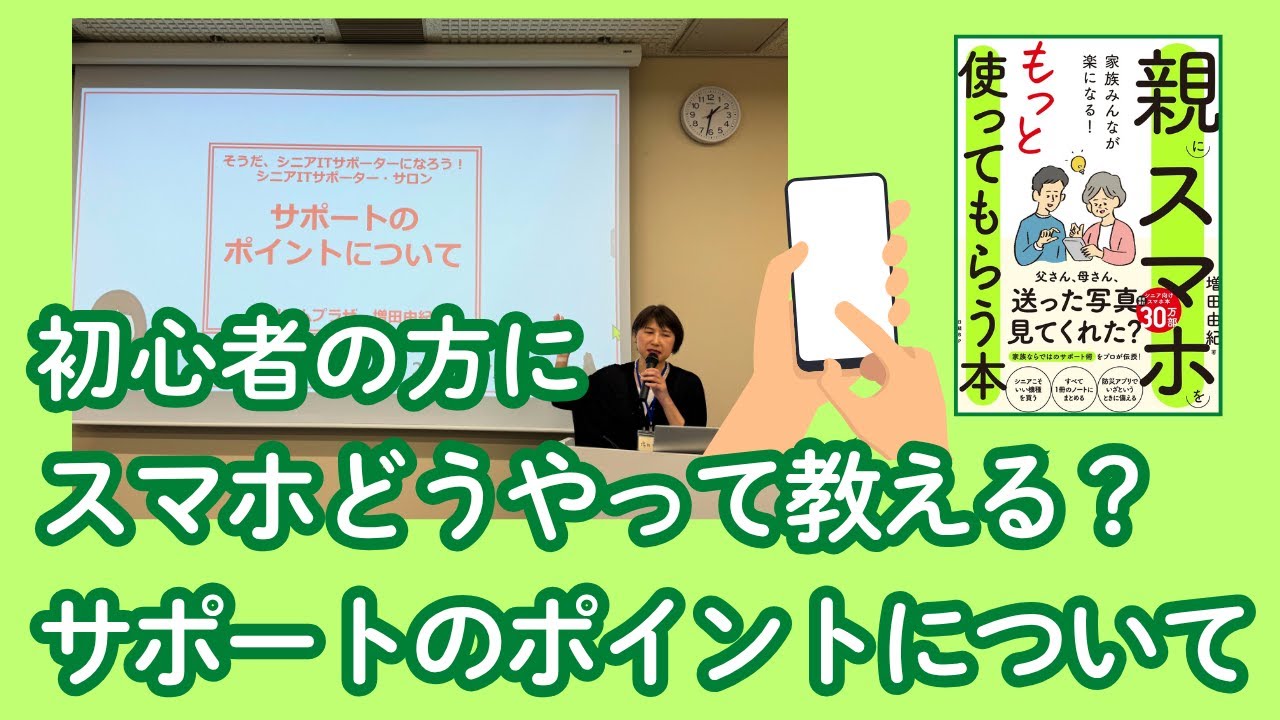現役講師が伝える・スマホ初心者の方へのスマホサポート術
こんにちは。 こんにちは。 え、初めましての方もいらっしゃると思いますけれども、私、あの、今多分スライド出てくると思いますけれども、え、今日は千葉県の安市から参りましたと申します。で、今日スライド、あの、いくつか出ますけれども、皆さんがあの、書き止めるの間に合わないなという時にはですね、あの、スマホでパシャって撮っていただいてもいいですので、ありがとうございました。 はい、ということでですね、私、あの、 民間と言いますか、え、仕事で教室をやっ ておりますけれども、こちらのあの、 シニアのITサポーターサロンということ ですから、私があの、日頃生徒さん60代 から90代の方に接する中で、あ、これの サポートのポイントになるのかしらって いうことを少しご紹介をできればなと思っ てます。え、私は今日のプレゼン資料を こちらをその後に入れてまいりましたので 、これでちょっとお話をしようと思います が、え、あの、お室をやってる方々ですね 、ま、あの、原疫講師ということもあり まして、最近はあの、本を書かせて いただくことがすごく多くなりまして、 70代からの、70歳からのスマホの 使いこなしと、それからこれがついました 2ということになりますが、え、こんな ようなお話をししております。で、あの、 私、あの、スマホ、ま、スマホ先生って 呼ばれることが多いんですけれども、最近 の私の身に起きたことで大変スマホが役に 立ったなということを最初にちょっとお 話ししようと思うんですけども、5月の5 日にですね、自転車であの盛大にすっ転で 左手を骨折しまして、人生初の、え、手術 入院ということで、今もちょっとこの リハビリですね、しておりまして、生徒 さんが要因がいが大変なのよと スケジュールが忙しいのよとおっしゃって いるのが非常によくわかり病院リハビリ間 を打って仕事みたいなすごい忙しいんだ なってことが分かりましたがこの入院に 関してですね本当に役に立ったなスマホ がっていうことがありましてまずあの私 こう自転車で倒れた時夫もおりませんで どうやって病院に行こうかととてもあの、 ぐったりしていて、もう純天堂大学の電話 番号を調べて、電話口に立って電話なんて できないなと思ったので、SIRがいる じゃないかと、ヘイシリーと言って準天堂 大学に電話をしてもらいました。それから 救急車を呼ぶって頭がなかったので タクシーだと。で、私のタクシーはですね 、タクシーにクレジットカードも割り付け てあるんです。で、そうしますと自宅から 順点って入れるだけでですね、お支払いも 終わりますから、もうあの崩れ落ちるよう にタクシー お支払いもなしというのも手がダメでお 財布が出せないんですよね。取るものも とりあえずっていうのもありました。それ からあのスマホ決済を使っておられる方も 多いかと思うんですけど お財布の着屈なかなか開けにくいわけです 。それで顔を見せるだけで決済ができると 病院の中でも結構あの使えましたのでこれ は便利だなと思いました。それからあの本 の締め切りが閉まってあの迫っていたと いうこともありですね。書かなきゃいけ ないということでパソコンについている 音声入力それからスマホの音声入力 めちゃめちゃ役に立ちましょう。そして あの痛めに埋めく時間もう何も見る気もし ない。でもあのポッドキャストですね。あ 、新一郎の日王天国を聞いて気を紛らして いたということで、こういうお話を生徒 さんでね、すごくあの身近に起きるかも しれないと自分にもで、今まであんなに クレジットカードを入れるのは嫌だと怖い と怪しいとおっしゃっていた方がタクシー にクレジットカードを割り付けてくと すごく便利ですよって言ったらですね、皆 さん授業の合間にクレジットカードを出さ れて入れたいということで、あ、こういう 誰かから身近に使った話っていうのを聞い てみたいものなんだなっていう風に思い ました。え、とてもですね、クレジット カード割り付けるのやだよってなんか騙さ れちゃうみたいに思う方多いと思うんです けど、あの生活に役に立つんだったらやっ てみようかなっていう方も多いのかなって 思いました。え、ここにですね、ちょっと グラフを持ってまいりましたけれども、 年々こうガーっと上がっていく数字でこれ がですね、えっと、こっちか2025年の 1月時点で98%の数字を示してると、 これ何の数字だと思われますか皆さん? 15年前は4.4%もこもう年々年々 上がってきて98ならほぼほぼほぼほぼみ なって感じだと思うんですけど、これは ですね、こちらにもあります。 NTTドコモのモバイル社会研究所1月、 今年の1月の調べになりますが、携帯で、 ま、っていうものを持っている方の中の スマホの比率ということになります。え、 世界ではどうでしょうか?携帯も持って ませんっていうお友達とかって いらっしゃいますか? 2つ折れ形態でさえ持っていないという方 がいたらあれですが、ほぼほぼみんなもう スマホになってるんだなということですね 。もうすごい数字が上がってると思います 。それからですね、同じ研究所の1月の 調べです。あの表をちょっと見ていただく と60代から80代までを太ったものです が、え、オレンジ色のところは8割の方が できるよって言ってることですね。メール やメッセージを送るのはこちら80代前半 の方でもま、できるということですね。8 割ですから。ですが、だんだんオレンジの 比率がこう下がってまいりまして、これ 後ろから見ると濃いオレンジと薄い オレンジって差が分かりますか?あんまり わかんないですよね。あんまりわかんない ですよね。ですがメールを見たり、カメラ で取ったり、電話帳に、ま、なんか登録し たり、レッド検索っていうのは、ま、 まあまあの方ができると。で、この辺り から来るとですね、ちょっとなんか怪しく なってできる人が減ってくるということで 、どんなことを皆さんちょっと苦手に感じ てらっしゃると思います。ここにまあ5つ ほど入ります。これはもしかしたら皆様が 誰かのサポートをする時に、あ、こういう の苦手なんだなっていう項目になるかも しれませんが、こういうことがやはりあの こうちょっとご年齢を重ねるとできにくく なると。これ見ていただくとですね、 アプリのダウンロード、Wi-Fiに つなぐ、あと受信拒否情報で、ま、 ちょっとコードな写真の加工と設定周りの ことがちょっと苦手なんじゃないかなって いう傾向が見えるんじゃないかなと思うん ですね。え、ネット見たりなんか写真撮っ たりはできるだけどちょっとご年齢を重ね ていくとこの辺り弱くなってそういうこと よく聞かれるんじゃないかなって思うん ですね。 え、もう1つ表を持ってまいりました。 これはですね、えっと、昨年の8月の調べ です。ただそんなに1年経って変わって ないかもねっていう数字です。60代の方 で男女を合わせてこれぐらいの、ま、比率 70代で男女合わせるとこれぐらいの方が そうだと言っている。80代になると数字 がまた上がると。 これは何の数字を表していると思いますが、スマホは普及してきてる、ま、基本的なことはまあまあできる人が多いとなった中でのこの赤い数字 セキュリティ設定 セキュリティ設定そういうのもあるかもしれません。セキュリティ設定も含めてかなと思うんですけども、どっちかていうとですね、体感みたいな感じ。 あの、何々っていう具体的なことじゃなくて、こう思ってます私みたいな言葉がここに入るんですけど、どんなことが 使いこせてない。 はい、ありがとうございます。あんまり使いこなせてないなあって思ってらっしゃる方がすごく多いみたいなんです。 こう外側から見たらいや使えてるじゃない ですかと思うんですがご本人はいやいや あんまり使いこなせてなくてとこれをです ね60代4割70代で6割80代で約7割 の方がどうも自分は使いこなせていないと 実感していらっしゃるようなんです。で、 ここはそのサポーターということをですね 、目的としていらっしゃると思うんです けど、いやいやそんなことないですよと 是非言ってあげて欲しいなと思うんです。 皆さんね、すごいご自身に高いハードルを 貸してらっしゃって、うちの教室の生徒 さんでももう10年以上、20年以上通わ れている方でもあんまり使えてなくて いやいや何をおっしゃいますかって感じな んですけど、みんな自分厳しいなって思う んですね。で、スマートフォンの普及に 行ってですね、やっぱりこのスマホを 使えるかネットを使えるかっていうことで 生活の、ま、質と言ったらあれですが、 生活のスタイルってかなり変わってくる だろうと。ここ都市部ではまだそんなに差 は感じられないかもしれませんけど、地方 の方で例えばJAさんの仕事でちょっと 地方の方に行ったりするとああ、まだある んだなっていうケースがすごく多いんです ね。これもう本当さいちゃうだろうなって いうことか。で、スマホの使い方を多分 聞かれることって皆様も増えてくるんじゃ ないかなと思うんで、今回中島さんから ですね、このお話いただいた時にですね、 すごくいいなと思ったんですね。そのIT スキルを先に身につけていらっしゃるここ ですね。中高年の方。もう同世代くらいの 方だと分からないところが分かるとか、 気持ちが分かるよとか、そういう方がです ね、地域でITのサポートをするって いうのはすごく意義があるなと中島さん私 は思った次第でございますよ。はい。それ でですね、ま、私も仕事があの皆さんのお 手伝いをしておりますけれども、ここの 方々ですね、サポートをするということに なりますから、あのうちの教室でもですね 、サポーター行政口講座っていうのやっ てるんですけど、皆さん最初参加されると その先生みたいに色々知らないから無理だ と皆さんおっしゃるんです。でも私は確か にこう資料ですけども、そうではなく サポートっていうのはですね、こう自分で できるようにお手伝いをすると自分も 分からないところがあるけどご一緒に メニュー見てみましょうかとそういうこと で全然構わないと思うんです。全部知って いなければ人のお助けができないという ことではないので、自分でできるところ まで寄り添ってあげるということとできる ようにしてあげるというよりもできる気が するようにしてあげるっていうのがすごく 大事。やる気だけはその方からしか 引き出してこれませんのでなんか私も サロンに通ってなんかちょっとできるよう な気になってきたっていうところをですね 、目指していただくのがいいんじゃないか なと思うんです。で、もしかしてこの中で サポートっていうその仕事と言いますか、 お役を初めてやりますという方も いらっしゃるかもしれません。もうやって ますよって方もいらっしゃるかもしれませ んが、私もいろんな講習会でこういう ところがなんかつまづいちゃうのかなって いうことがやっぱ顕著な例がいくつかあり まして、もしあの初めてサポートするの 初めてだよっていう方がいたらですね、 少し情報の共有ということになると思うん ですが、あの皆様が何気なくやっ てらっしゃるはい、そこタップしてくださ いっていう時のタップって初めての人が 100発着中できるかと言うと結構そんな ことないんですよ。で、このタップが ちゃんとできていないがためにもう何度も 何度もやり直しをするというシーンを多々 見ておりまして例えば知っている皆様が そこしてそこしたらもうゴールだよって いう2工程で住むところが押す場所が命中 しないんでいやいや違います。戻って ください。で、また押していや、そこじゃ なくてまた戻ってって何度もやってるうち に先生マホって難しいですねって言われる ことがんです。いや難しくないとタップが 命中してないだけだということすごくあっ て100発100中に近いぐらい確実に できるようにしてあげるっていうのは すごく大事。これ意外とこんなことぐら いって思ってらっしゃる方多いと思うん ですけど、すごく大事で冬場だったら はあってやるとかですね。すごい電車です 。あとですね、お店から帰ってきて何にも 設定しないと大体30秒画面がすぐ暗く なるというのを講習会でまた拝見すると ですね、もうすぐ暗くなっちゃってそのた にあれを4桁ペタを言えなきゃいけない からこれを解除して欲しいという方結構 いらっしゃいます。いや、解除はできない ですよ。やらない方がいいですよ。でも めんどくさいんだ。そうなるとこの短く なるまでの時間って伸ばせるんですよ。 ってなると、そうなのってなりまして、 こういうところも意外とお1人ではでき ないなと。あと、ま、サボみたいなとこに いらっしゃった方に例えば何かを聞きたく て来てる方はいいですけど、そうじゃない 場合ですね。何をなさりたいですか?て 聞いても何をって言われてもってなるん ですよ。何ができるか分からないのでなり ますので、何がやっていいかわかんない けど、こういう着てるところに来てみ たって方もいらっしゃるだろうと思うん ですね。あとはやはり文字入力にどうして も苦労してしまうというのが私ら何年やっ てもあまり変わらないな。初心者の方の つまづくところっていう風に思います。 それでもしこれをまじゃどうやってあげ たらいいのかなと思ったらですね。は やっぱり基本操作ではあるけれども、丁寧 にこんなことぐらいと思わずにもう100 発100中になるようにちゃんとこう最初 は大きいアイコンから徐々にメニューの 小さいところが選べるようになるまでこう 指の感覚をご本人に感触を掴んでいただく ことが大事ですし、暗くなるまでの時間は ですね、ま、ご本人が覚えなくてもこれも 別に良くて数分にしましょうかと。ま、 サポートをする方はですね、相手のスマホ をパッと取ってやってはいけませんから、 これできますけど、いかがいたしましょう かと言ってからですね、設定してあげると いいし、何からやったでいいかわからな いっていう方にもうどんどんどんどん 新しいアプリを紹介するのはそれはあまり 良くなくて、まずあるものでやってみよう と、もう十分入ってますよみたいな感じで 、まずはあるもの使ってみたらどうですか と。そして文字入力に関してはですね、 うちの教室はベコも早めに、え、も声入力 をご紹介をしています。あの、文字入力 ごときでつまつぐぐらいだったらもう スカスカ喋っていただいて所々直せる方が すごくあのいいなと思いますので、ま、 こんな解決法とは言いませんが、どんな風 に考えたらいいんだろうという時にこんな こともちょっとあのアイデアとして持って ていただくといいかなと思います。で、私 がいろんな講習会見てますとですね、この スマートフォンをな、何て言うんでしょう ね。親の敵のように叩くから言われてです よね。そんなに力も入れなくてもと思うん ですけど、この方は多分最初にそう教わっ たんだろうなと。で、もうそれに慣れて しまってのこう爪の立つ音がするけれども 、指の腹も柔らかいところでって言っても なかなか癖が治らないんですよ。最初なん だろうなってすごく思うんです。だから もしお初めての方がいらっしゃったらそう いうところをしっかりやってあげると すごくいいだろうな。そ、その方のスマホ ライフにとってすごく親切だろうなって 思います。あの、未来英語をお手伝いする ことはできない。その方がご自身でできる ようになるっていうことが大事ですので、 え、きっと最初のスタート地点間違わ なければそんなに苦労することなかったの になってことはすごくあります。で、うち のあの生徒さんたちにもですね、ま、皆様 がもうサポーターになられたとしても誰か に何かを伝えるというか、ま、教え るっていうことになると思うんですけど 生徒さんにですね、教えるのがうまい人 ってどういう特徴があると思いますかと 聞いたところ、大体どのクラスも似たよう な意見が変えてまいりました。皆様も ちょっと考えていただいて、あの人なんか うまいよねみたいな人はどういう特徴が あるでしょうかね。4つほどに集約できた と思うんですけど、性度がうまい人って どういう人だと思いますかと聞いたところ ですね。こんなようなことが返ってきまし た。まず説明がゆっくりな人はすごく聞き やすくてうまいなって思うというご意見。 それからポイントですね。どこが大事なの かをはっきり言ってくれる先生はすごく 分かりやすいと思う。それから自分もその 全てを説明できるわけじゃない。このこれ がこうでこうしてこうって言えない。ああ とかええとか言っちゃうんと。そういう時 に話をよく聞いてくれる先生だとすごい うまいなって思う。放射でこちらが もかしい言える気持ちをなかなか伝えきれ ない。これを分かってくれる人はすごく うまいと思いますというようなご意見が 返ってまいりました。で、もう1つ聞け ましょう。じゃ、これの反対下手とは言わ ないが下手とは言わないが教えるがうまく ない人ってどういう人ですかとお伺いをし ましたところです。やっぱ傾向ってあるん だなと思ったんですけれども、え、早口な のはダめよ、先生と。もう早口は誰で説明 がすごく丁寧に長々してくれたんだけど 結局何聞いたんだかわかんなかったって いう人もいるから買いにくい説明は ちょっとねあと高圧的にすぐ覚える おそらくこれはご主人のこと言ってじゃ ないかなとあるいはお子さんですねあの 教室の生徒さんはですね方が多いんです けれども教室に入るきっかけにになった夫 の一言というのがございまして、お前には 100万回言ったぞ。もう2度と聞くもん かと思って、もう自分でできるようになり たいって変えられた方もいるんですね。 それからお嬢さんや息子さんにすごく怒ら れて先生あんな言い方ってあると思います みたいなそういうことを想像し てらっしゃるんだと思うんですね。そして こう言いたい気持ちを分かってくれないと いう方ですね。結構この気持ちの面って すごくあるんじゃないかなと思うんです。 それでこの分かりにくい説明にはやっぱり 特徴があってですね、早い、長い、くどい 。これはどんなに丁寧にどんなに説明して あげてもです、やっぱり双方に残らないと 言いますか、え、分かりにくいのに入っ ちゃったなと。で、早いと何がいけないか ですね。はい。と、うん。はい。食べる方 は分かってるわけですよ。ゴールも見え てる。だけど聞いてる本はその手順の追え なくなってきたわけです。今どこになっ てるか分かりませんみたいなことになる わけです。そして長い。長いとですね、 この長さには特徴があって、あの文章を 喋られる時にですね、Aして、Bして、C して、Dして、Fしてくださいって言うと 分かんなくなっちゃうんですよ。途中で 迷子になってしまうという傾向があって、 どんなに丁寧に説明をしてあげても やっぱり使わないってことがあるんですね 。そしてくどい。くどいというのは くどくどくど説明してくれたんだけれども どこが大事か分からなかったと最後に言わ れ双方披露するとこんなに喋ったのに みたいなことがあってですね、やっぱり 分かりにくい説明には特徴あるなと思うん です。となれば少しでも分かりやすい説明 がしようと思ったらこれの逆を意識すれば いいわけですよね。最初からできる人はい ないけれども意識をすればいいと思います 。え、ゆっくり喋る。ゆっくり喋るという のはお相手も取り残さないというかついて いけるわけです。とりあえずゆっくりして ここまでどうですか?大丈夫ですかって 言いながらついていける。として1つの 文章を短くするとこれも私も生徒さんから 本当にたくさんのこと教えていただいて まして先生1つの文章カタカナが2個入っ たらもう私たちはダメていうですね2個 以上入れないようにしようって思うんです が1つの文章を言い切り型にする短めに するどうしても何々して何々して何々でっ て続けちゃうんですけれども短いと1分を 理解し安いってことが言えると思うんです ね。そして端的、あの、だらだら長く言う ということではなくてですね、ポイントを 明確にすると、ま、例えばさっきの暗く なるまでの時間を伸ばすのでしたらば設定 のここですよみたいなポイントを明確にし てあげると、そうすると相手も分かり やすいけど、こちらもですね、喋る時に 多分ですよ、サポートな方もなんだか今日 は疲れたなみたいな日があると思うんです 。こんなに説明したのにもういいです。 じゃあみたいな感じでさっぱり伝わら なかったなっていう時にですね。あ、少し こんなポイントを知ってると自分でも意識 しようって気持ちになるんじゃないかと 思うんです。で、もちろんこれらはですね 、私があの講師要請っていうかですね、 妖請なんかでこう3日間の講座なんかでお 話ししたりする内容ですから、それを ちょっとこう買りつまんで持ってきたん ですけど、皆様にもですね、ま、明日から でもあの取り入れていただけるっていう ことをですね、いくつか持ってまいりまし て、具体的にすぐ実践できるテクニックと しましてはですね、もう本当にね、 ゆっくり喋るってことなんです。思ってる よりゆっくりです。人に人を待たせていて 自分が喋ると早くなっちゃうんですよ。お 待たせしてはならない。こうやってなんか どうなるのかなって相手の人は聞いている 。えととか待たせちゃいけないと思って たタって喋りたくなっちゃうんですけど、 ゆっくり喋るっていうことをですねご自身 にも心がけるといいと思うんです。で、 これがなかなかできるようでできないん ですよ。ゆっくり喋るとゆっくり話す効果 っていうのがありまして、自分もゆっくり 喋ってますからとりあえず相手を観察でき ます。相手がこれ分かってんのかなって いう反応を観察できる。そして慌てている と自分も焦ってんですよ。やばいな、 やばいなとか思いながら自分自身も考えを 整理することができます。からなんか焦っ ていても立て直しをするともうあの坂道を 転がるように説明をする方いるんですよ。 もう早くですが焦っていても立て直せ。 そして少なからず人の前に立ちますとです ね、なんかあの、あのサポーターさん すごい焦ってかえみたいなことじゃなくて なんかもう余裕を持って振るまっていると なんとかすごくえみたいみたいな安心感を 演出することができますのでゆっくり話す 効果は絶大だなという風に思います。で、 皆様がですね、このゆっくり話すという ことを意識してていただくとですね、 ゆっくりとすごく象徴的、抽象的だと思う んですね。ゆっくり私はゆっくりだと思う けどなと。これはご自身が今を持ってる よりもゆっくり。あと見えりとか手振 りってあると思うんで、さしてくださいね とかここですね。なんていう時もわざと スローにすると。そして一応ですね、数字 で目指すとなりますと、1分間300文字 で、これはNHKのアナウンサーさんが1 分間300文字で読むという訓練をされて いるそうなんですが、1分間に300文字 という数字が分かったとしても、じゃあ どんなスピードってなると思うので、 ちょっと皆様でですね、実験をしてみよう か思うんです。皆様の時計にストップ ウォッチがあればそれを使っていただいて もいいし、こちらにも時計がございますの で、今から私は画面にですね、 ちょうど300文字ぐらいの文章をお出し したいと思います。で、300文字を1分 だと意識しながらその今から画面に出る 文章これね、みんなで喋ると多分あの ざついちゃうと思うのね。今日は心の声で 本当は目読だともっとスピード上がっ ちゃうんですけど、ちょっとわざと声には 出ないが声で喋ってるような感じで1分 300文字を1分を意識しながらちょっと 喋ってみていただければと思います。ご 準備は大丈夫でしょうか?時計をご自身の スマホを見ていただいてもいいし、あれで 各々がより良きスタートしやすいところ からで結構ですが、今から300文字の 文章を出してみたいと思います。見ながら 意識している時の300文字のスピード1 分ですね。じゃあ、スライドをめくります ので、で、1分ぐらい経ったら私またお声 をおかけしますので、ではよろしくお願い します。1分で300文字です。 いかがでしょう?これちょうど丸まで含めて多分 300 文字あると思うんですけど、チラチラ時計を見ながら 300文字を1 分間なんで、で、講師はこの 1分を2時間 ずっとキープをするっですね。最初の 1 分は結構できるんですよ。最初はゆっくりなんですよね。最後になるとどうしても早口になっちゃうんです。 で、今時計をちら見ながらしていただき ましたが、この300文字なんてもちろん 覚えられないし、ちょっと練習しようかな と思っても、ちょうど適義300文字 なんて文章なかなか身の回りにないと思う んですね。で、私がいつもやっている練習 がありまして、ああ、また私ちょっと早口 になってきたかなっていう時にペースを 戻す時の練習っていうのがありまして、ま 、日本人だったら多分誰でも知ってる でしょうねというお話を今から300文字 で画面に出します。え、それをですね、 今度は時計をなるべく見ずにまあ1分自分 がちょっとちらっと時計見て吉だって 初めて喋り終わって時計見ていただいて1 分なのか超えるのか短いのか次は試してみ ていただきたいと思いますのでまた300 文字もみんながよく知ってる話が出てき ます。 じゃ、時計のご準備はよろしいでしょうか?今度はチラチラ見るんじゃなくて 1 回スタート見たらとなるべく見ないでやってみてください。ではお出します。割とゆっくりだった今はみたいな。これをですね、時々やりました。私、ま、なんか今日早かったかもなんていう時には昔々昔しとこを作るんですね、自分で。 で、ゆっくり喋るというのは意識しないと なかなかできないんですよ。知ってること を喋るっていうのはどんどんどんどん早く なってしまいますので、ゆっくり喋 るっていうのはね、多分すぐできる テクニックに行くかなという風に思います 。え、他にもですね、こういうのあります 。1つの文章に指示は1つから2つと、 これも生徒さんから学んだことです。2つ 以上になるともうわかんないよって言われ てました。全員の方に同じことをやって いただこうと思ったら1つの中文章の中に 指示は1個か2個でゆっくり話しながらお 相手が進んでるかな大丈夫かなって確かめ ながら喋らないとこっちもあっちも疲弊 するんだなっていうことがあります。で、 専門用語は、ま、使わないとか文章と文章 の間を少し間を開けるとか、大事なことは 繰り返しますよっていうのは多分こうね、 あの、皆さんもよくご存知じゃないかなと 思うんですが、え、次にですね、ちょっと これも実践できるテクニックかなと思うの が、誰かのサポートをすると、すいません 、これがって言われた時に早く答えなきゃ 聞かれてるんだしみたいに思われると思う んです。で、それもですね、まずその説明 をあのしなきゃならないという意識から ちょっと1回遠いていただいて何か説明し なきゃというよりはまず聞くという体制を 心がけていただくといいと思います。あの 、誰だってすいません したくなっちゃうんです。それはですねと かちょっとしていただいていいですか? 説明したくなるんですけども説明するより まずお相手の話を聞くっていうのはすごく 大事。それは結局のところ解決の近道にな るっていうことがも多々あります。で、話 を聞く時に相手が質問をしているとさあ どうやって答えようかな。えっと、あそこ だったかな?設定のとか考えずにまずは 相手の話をですね、心を傾けて聞く時に この文字を使いますけど、例えば相手の方 が質問されて、それ絶対あれやってんな みたいに決めつけないで聞くと。それから いやいやそうじゃないですよ。そうじゃ ないですよって否定しないで聞くとそして あ、そうなんですねって寄り添って聞くっ ていうことが結局のところ早い解決に至 るっていうことはも何度も私も経験をして います。でとはいえ質問されてんだから 喋りなくなっちゃうわけですよ。そこで もう1つこれをストッパーをかけるという か、こういう意識を持っていただくといい のかなっていうのがですね、そで聞くとで 聞くとまずあの人の話を聞く時に頭の中に そという言葉を思い浮かべていただいて素 で聞くってなんだって言ったらですね自分 がそから始めてくださいねということです 。お相手がすいません。これなんとかなん とかでって言ってきた時もあ、それはです ね、設定のこことすぐに言わずに、あ、 そうなんですねとか、あ、そうですよねと か、あ、そうだったんですね。そういう ことですかという風にですね、説明したく なるかもしれないけど、まず相手の話を 聞こうと思ったらそという言葉がとても 便利だと思うんです。これはですね、相手 の発言を受けてから喋るのはそから始まる 。相手も何も言ってないのそうだったん ですねとは言わないですよね。相手が言う からこっちもそうだったんですねっていう わけですから。から始めるということを ちょっと意識していただくだけで、ま、 聞かなきゃ聞かなきゃでも相手の話はあ、 そうなんですねって聞いてみると相手の話 からヒントがもらえることってすごくあっ てああ設計じゃなかったんだな、これだっ たんだななんてね、分かることがすごく あるんです。それからですね、皆様はもし かすると、あの、たくさんこう質問を受け て何でもパパッと答えてくれる、もし じゃあサポーターさんなり代表さんなりが いたらあの人すごいな、あんな風になり たいなって思われるかもしれないんです けど、私もですね、講師として気をつけ てることがあって、もうすぐに答えて、 すぐに答える先生が親切なのかなと思っ たらそうでもないんですよ。もうすぐに 答えて失敗したってこといっぱいあります 。え、すぐに答えずに相手の方をよく見る ということをいつも心がけてます。これも もちろんすぐに答えないで相手を見る抽象 的だと思うんですが、え、テクニックが あるとするとですね、どいう言葉でも相手 の話を聞いてるわけです。私 すぐになんか説明したくなっちゃうんだ けどお話をまず聞いてどという言葉から スタートして考えております。そのドア なんだろうと思ったらですね、この方どこ でつまづい頼むんだろうなとか、どこが 分からないっておっしゃってるんだろうな とか、毎回なのかな、どんな時にそうなる のかなとか色々説明したけどでも最終的に はどういうことができればいいんだろう。 それだったらこんな難しいことをご紹介し なくてもこっちの方が簡単じゃないみたい なことがあってですね、何でも答えればい いってわけじゃないんだなと。このどと いう言葉をですね、相手の状況を知ろう しろうと思って心に浮かべている言葉なの で、このストッパーになるんじゃないかな と思うんですね。え、皆様がもしなんか あの説明しなきゃいけないとか急がなきゃ とかちゃんと説明しなきゃということが もしかしたらなんかこうサポーターになる のネックになってらっしゃるんだったら そんなにあの何でも聞かれたことは答え ますよって思わなくても大丈夫だと思い ます。お相手の話を聞いてどこが困っ てらっしゃるのかなっていうのを探 るっていうのも十分このサポーターの方の 仕事尊いお仕事かなという風に思います。 で、え、相手の話をまずよく聞いて、で、 どうやってそうなっちゃったんだろうとか 、どこがそうなってんだろうてよく挨拶、 あの、相手の方を観察して、ああ、これの ことですかとなったらようやく喋るという のが、あの、私も心がけていることですし 、サポーターの方にもこうだったら少し気 が楽になるんじゃないかなと思ってですね 。私、あの、講師の要請講座の時もですね 、この順番でお話になってくださいねと いう風に言っていますが、まず聞く、 そして見る。で、最後が話すということで 君はっていう順番で話すようになんか早 話さなきゃとか早く教えてあげなきゃ、 説明しなきゃって思わなくてもいいです よってお話をよくしています。え、ですの で聞いたことにすぐ答えてくれる人が本当 に先切なのかと言うと、意外とご本人が 説明しようと思ってる時間を奪ってしまっ たりとか本当はできたかもしれないの全部 それに被せて最初っから説明するとあの 相手にとって本当に親切な例えば今日は ここ人として見ましたけど私の場合だと 聞いたことにすぐ答えてくれる先生はいい 先生なんだろうかって考えた時に必種も そうじゃないだろうなっていうのがですね 、私のその25年の講師経験から最近は もうなるべく喋んなくていい事業がいいな と思ってんですよ。ま、なるべくもうこれ 経験があって生徒さんの話をよく聞いてる と私は何にも答えてないですよ。ああ、 そうなんです。うん。なるほどて言った。 あ、先生分かりましたってなって何も答え てないけどなっていう経験がすごく たくさんあるんです。その経験から何年も かんでもすぐ答えちゃだめだなと。ご本人 が持っているものをこう引き出すっていう のは仕事だなっていう風に思ってるんです ね。で、え、皆様がこのサポートにこの、 ま、サポーターのサロンに集ってくださっ て何かどなたの役に立てたらななんていう 時にですね、どんな年代であっても自分で できるなっていうことがすごく大事になる と思います。え、小さなことでも構わない 。自分でできるということが大事で、それ をサポートするのが多分サポーターのお 仕事だと思いますし、できる気になって もらわないとどんなにじゃあこれやってみ ましょうかやってみましょうかってなって もこれ劣等感というかどうした年できませ んしってなっちゃう。気持ちだけはご本人 があげてもらわないとできないんですよ。 もう本人が要無理だと思います。先生って 言われるのをあげるのすごい大変なんです ね。なんだなんか私もあのサロンに来てて な気がしますって言って書いていただくの はすごいいいことじゃないかなという風に 思っております。ですので、このお話を ですね、伺った時にですが、そのもう先に 先輩ですよね、相手へのスキルを身につけ ている先輩の、しかも年の近しい先輩の方 が地域でそのあんまりよくまだ分からない んだなっていう方のサポートをするのは すごくいい活動だなと高島さん私は思って いるわけで ということでですね、え、ちょっとお 預かりした時間をちょっと12分ほど消化 しておりますのが私が過市経験から、ま、 加工隊になられる方がこれぐらいのこと 知っておられると少し気が楽じゃないか なっていうことをお話をしてみました。 そしてですね、私、あの、最近本を書く 機会が多いので、え、ちょっと最後に新刊 のご案内をさせていただけますとですね、 こちら、あの、日経BPさんから7月の 18日に発売をされますが、タイトルが ですね、親にスマホをもっと使ってもらう 本ということで、どうしても親子は見解に なってしまうと、え、それをですね、もう ちょっとこういう風に言ってあげたら、 両親もスマホが使えるついてはご両親世代 がスマホが使えるってことはあなたの身に 帰ってくるんですよみたいなことを書いて おりますが、これはま、サポートをする方 にとってもあ、なんかこんな風に言えば いいのかなみたいなね、ちょっとこう エピソードとか参考になるかもしれないな と思いまして、最後にすいません。 ちょっと新刊の案内をさせていただきまし たけれども、え、私の話はここまでにさせ ていただきたいと思います。ありがとう ございました。 最後までご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録や高評価ボタンをお願い いたします。
20250706シニアITサポーターサロンにて、ゲストとしてお話ししてきました。
スマホの初心者の方に、スマホの使い方を教えるサポーターとして、サポートがしやすくなる心構えや、伝える時のコツなどをご紹介しました。
00:00 講師の自己紹介と本日のテーマ
01:36 講師のスマホ活用経験談
04:32 スマホ普及率の現状
10:16 シニアITサポーターの意義
11:46 初心者のつまずきポイントと解決策
16:56 教えるのが上手な人の特徴
18:37 教えるのがうまくない人の特徴
19:56 分かりにくい説明の特徴
21:25 分かりやすい説明の特徴
23:17 具体的にすぐ実践できるテクニック:ゆっくり話す
29:09 具体的にすぐ実践できるテクニック:1つの文は短く、指示は1~2つ
30:07 具体的にすぐ実践できるテクニック:説明するよりまず聞く
30:46 話をよく聞くためのポイント
31:39 具体的にすぐ実践できるテクニック:「そ」で聞く
33:15 具体的にすぐ実践できるテクニック:すぐ答えない、相手をよく見る
33:41 具体的にすぐ実践できるテクニック:「ど」で考える
37:09 「自分でできる」をサポートするまとめ
38:52 講師の著書紹介
この動画では、スマホ初心者の方をサポートする際のコツについて、私自身の講師経験から、さまざまな生徒さんとのエピソードを交えながら、具体的なテクニックをお話ししました。
「タップが難しい」「画面がすぐ暗くなる」といった初心者がつまずきやすいポイントから、「ゆっくり話す」「まず聞く」といったすぐに実践できるサポートのテクニックまでをご紹介しました。
こうしたポイントを知っていれば、シニアの方やそのご家族、そしてスマホのサポートに関わる方が、少し気が楽になるのではないでしょうか。
ぜひ最後までご覧ください。
【新刊紹介】7/18発売
「家族みんなが楽になる!親にスマホをもっと使ってもらう本」(日経BP)
https://amzn.to/3U4rxBG
————————————————
📖【70歳からのスマホの使いこなし術<2>】(アスコム出版)
★☆★大ベストセラー待望の第2弾!★☆★
「スマホを使わなければならない場面」の練習ができる!
それがこの本の特徴です。
シリーズ累計33万部を超えるベストセラーとなった
『世界一簡単!70歳からのスマホの使いこなし術』と
『70歳からのスマホのパスワード記録ノート』。
その著者で、1万5000人を超えるシニアにスマホを教えてきた講師が
お届けする、これまでにない「練習できる本」。
https://amzn.to/45NdHuU
📖【70歳からのスマホの使いこなし術】(アスコム出版)
シニア世代こそスマホを相棒として使ってほしい。スマホともっと仲良くなってほしい。という思いで書いた本です。スマホでいろいろできるのは知っているけれど、その「いろいろ」がよくわからない。スマホの使い道を知れば、もっとスマホが楽しくなります。
Amazonからご購入いただけます
https://amzn.to/3yeb7iU
📖【 70歳からのスマホのパスワード記録ノート】(アスコム出版)
スマホにまつわるパスワードを書いて記録する「書き込み式の本」です。
「パスワードがわからない」。
そんなお悩みの解決策は、「1冊のノートに記入すること」。
特に、70歳を過ぎた方にはおすすめの方法です。
◎メモのようにバラバラにならないから、紛失しにくい
◎パスワードを忘れても、このノートを見ればいいという安心感がある
◎〝もしも″のとき、大事な情報がまとまっている状態で誰かに見てもらえる
Amazonからご購入いただけます
https://amzn.to/4hsb980
📖【老いてこそスマホ】(主婦と生活社)
私の親世代にあたるデジタルアンバサダー牧さんとの対談形式で進む本です。こんな風にスマホを使ってほしいな、という実例もたくさん載っています。
Amazonからご購入いただけます
https://amzn.to/4f99V11
————————————————-
🔔チャンネル登録お願いします
「ゆきチャンネル」を登録していただくと、新しい動画を載せたときに通知が届くようになります
↓をクリック
https://www.youtube.com/c/yukinojo7ch
————————————————-
📣月1回のペースでウェビナーを開催中!
過去の動画はこちらから購入できます。
パソコムプラザオンラインショップ
https://snow.official.ec/
————————————————-
🍁ブログ「グーなキモチ」 https://www.masudayuki.com
🍁Amazon著者ページ https://amzn.to/2pEhNDo
🍁Facebook https://www.facebook.com/pasocomplaza
🍁X フォローはお気軽に https://twitter.com/yukinojo7
🍁Instagram https://www.instagram.com/yukinojo7/
🍁パソコムプラザってこんな教室です
————————————————-
👓全国どこからでもオンラインで学べる
初心者のためのスマホ・PC教室【パソコムプラザ】
https://www.pasocom.net/
047-305-6200
👓オンラインレッスン無料体験会開催中!
https://pasocom.net/onlinelesson/taikenkai/
————————————————-
📖パソコムプラザ代表・増田由紀の著書
「70歳からのスマホの使いこなし術」(アスコム出版)
「老いてこそスマホ」(主婦と生活社)
「いちばんやさしい60代からのiPhone」(日経BP)
「いちばんやさしい60代からのAndroid」(日経BP)
「いちばんやさしい60代からのiPad」(日経BP)
「いちばんやさしい60代からのLINE」(日経BP)その他多数
📖Amazon著者ページはこちら
https://amzn.to/3pefEKS
————————————————-
【ゆきチャンネルの人気動画】
🎤セブン銀行でPayPayにチャージしてみた – https://youtu.be/flA-d64YyGU
🎤新型コロナワクチン接種証明書アプリ入れてみた -https://youtu.be/XMmAm2ntgh4
🎤【LINE Pay講座】お金をいれてみよう「チャージ」 – https://youtu.be/5mfTkzK0Uzg
🎤NHKおはよう日本で紹介された講座の様子 – https://youtu.be/qyUKjI3ETM4
・シニア世代こそ推し活のススメ SNSの楽しみ方
・80代のChatGPT、生徒さんと授業での一コマ
・パソコンから突然警告音、絶対電話をかけないで
・強くて忘れにくいパスワードの作り方
・スペースなしで文字をきれいに整える~ある日のオンラインレッスンの様子~
・【超簡単】Zoomのバーチャル背景に使うとよいもの – https://youtu.be/VGmIE9U6fRc
・【LINE Pay講座】スマホでピッとお買い物 – https://youtu.be/vFft5SYOS2U
・HDMIを挿すところがもうない!そんな時はHDMI分配器 – https://youtu.be/U-vo9j6WEU0
#スマホ初心者 #サポート#スマホ先生 #ゆきチャンネル