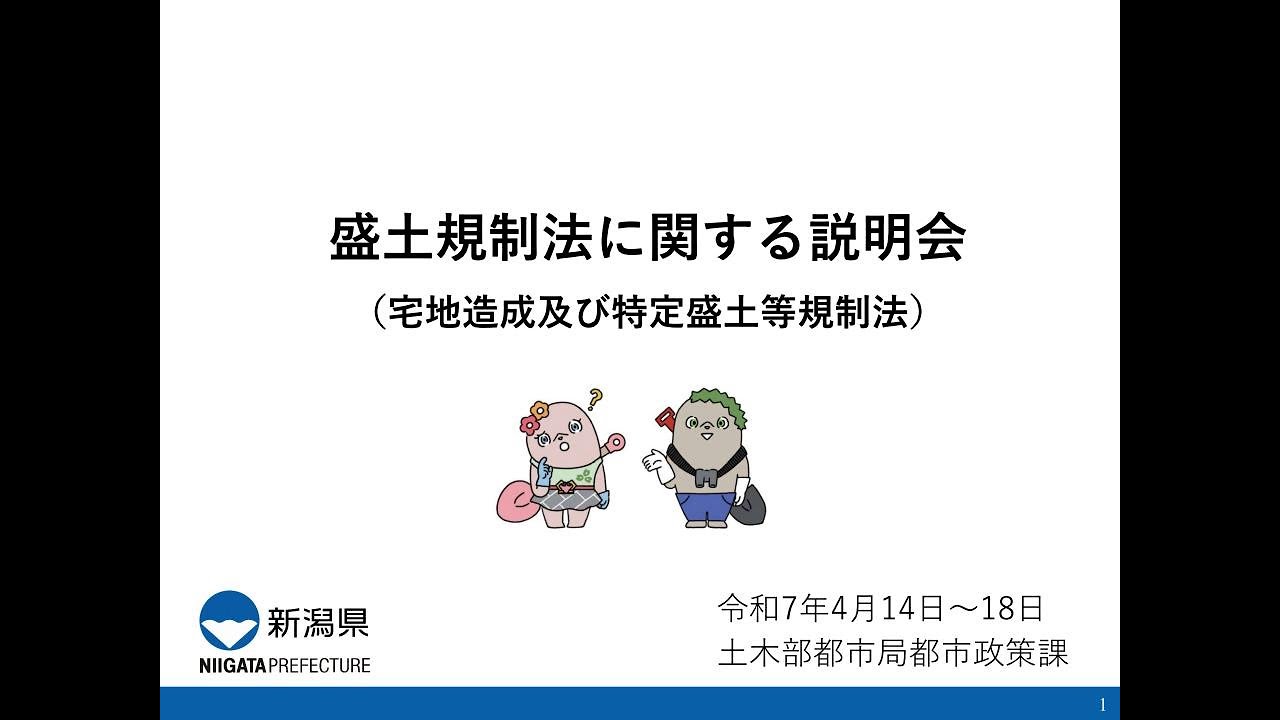盛土規制法に関する説明会(令和7年4月16日開催)
では始めに皆様にご案内したい3つの事項 についてご説明します 1つ目ですが新潟県では本年7月中旬に 規制区域の指定を予定しておりそれと同時 に森戸規制法の運用を開始します具体的な 指定日は決まり次第県のホームページ等で お知らせします 2つ目ですが本日の説明会は県民や事業者 の皆様に盛制法について広く知って いただくことを目的としています 時間の都合上と許可申請や技術の細かい 内容まではご説明できませんので詳細に ついては県のホームページで示す資料を ご覧いただければと思います 3つ目ですが森戸規制法の運用は 政令士である新潟市の区域は新潟市が担当 しそれ以外の県内29市町村の区域につい て件が担当しますそのため新潟市の運用等 についてはペット新潟市にお問い合わせ いただくようお願いします それでは3ページをご覧ください こちらは参考法令参考資料の一覧ですかこ の中には本日の説明でも用いるよ記載して います国の法令や技術国あ県の技術基準等 は必要に応じてそれぞれのホームページ から内容をご確認ください 次に4ページをご覧くださいこちらは説明 会の中でも出てくる用語の説明となります 用語の詳細についてはこのページでご確認 ください 次に5個ページをご覧くださいとこちらは 本日の説明の内容です内容は1森戸規制法 の概要2規制区域について3規制内容に ついて4申請手続きについて5技術記述的 基準について6事例紹介7不法森度につい て8その他となります まずは森規制法の概要について説明させて いただきます 7ページをご覧ください 森戸規制法が改正された背景ですが令和3 年に静岡県熱海市で発生した土石流災害が あります これまでの法制度では宅地や森林農地など の各法令で個別に森戸等を規制していまし たがこれにより法の隙間が生じ森戸の規制 が十分ではないエリアが存在していました 熱海の土石流災害もこの法の隙間を狙った 森戸が原因となっていました これを踏まえ国はこれまでの宅地増規制法 を抜本的に改正し宅地や森林農地などの 土地の用途に限らずと危険な森戸を全国 一立の基準で規制する各地増特特定モド等 規制法通称度規制法を令和5年に施行し ました 次8ページをご覧ください 森度規制法のポイントは大きく4つあり1 つ目は規制間のあ失礼しました隙間のない 規制です具体的には検知時等が森戸により 人等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に 指定することができこれにより規制区域内 で行われる森戸等は許可の対象となります 2つ目は森戸等の安全性の確保です この中で森ド等を行う際に必要となる許可 の基準が設定されましたまた施工状況を 適切に把握していくため定期報告や中間 検査等を求めることとなります 3つ目は責任の所材の明確化です法の中で 森戸が行われた土地について土地所有者等 が常時安全な状態に維持する責務を有する と明確化されました また必要な時は土地所有者だけでなく工事 施行者などの原因行為者に対しても是正 措置を命令することが可能となります 4つ目は実行性のある罰則の措置です無 許可や許可申請違反のあ許可申請手続きの 違反技術基準の違反等に対しては罰則が かかりまして最大で懲役3年以下罰金 4000あ失礼ました1000万円以下の 以下となりますまた法人の場合はこれに 3億円以下の罰金が加えられますので 手続きにはご注意いただきたいと思います 次に森戸規制法に基づく規制区域について 説明します 10ページをご覧ください森ド規制法の 運用を行う際は規制区域の指定が必要と なりますこの規制区域には2種類あり1つ 目は赤で示している宅地増工事規制区域 通称卓造区域で特に市街地やその周辺を 指定しますもう1つは緑で示している特定 モドと規制区域通称特森区域で市街地等 からは離れているものの地形条件等を 踏まえて指定するエリアとなっています いずれの区域も森戸等に規制がかかり特に 赤の区域ではより厳しい規制がかかると いうように捉えていただければと思います 11ページをご覧ください 先ほどご説明した2つの規制区域の指定は 検知時が行います 新潟県ではそれぞれの規制区域についてと 以下の条件で設定を行いました まず赤の区域悪区域は都市計画区域のうち 市街化区域用途地域また人口集中地区等の 区域上村あ市町村長が必要と認める区域 上期に隣接近接する土地の区域から設定し ています 次に緑色の えっと徳も区域については土石流土石流等 で人に被害を及ぼし及ぼすと想定される 渓流の上流域のエリア等を対象に設定して います新潟県では剣度全域について卓域 または特森区域のいずれかを指定すること としていますなお政霊市である新潟市は ベッド区域を定めています 次に12ページをご覧ください こちらはこれまでの基礎調査や関係市町村 との調整を経て整理した新潟県の規制区域 図となりますピンあピンクの区域が卓区域 緑色が特森区域となります県内各市町村の 小サイズについてはこちらのQRコード からご覧ください 新潟市の規制区域については新潟市の ホームページをご確認ください 次に13ページをご覧ください こちらは規制区域の指定の流れとなってい ます このフローに示しているように令和5年5 月に盛ド規制法が施行され令和6年令和6 年度には県で基礎調査を行い規制区域案を 作成したところですまたこの3月には規制 区域案を公表しパブリックコメントで県民 の皆様から意見を募集しました 今後関係市町村との意見聴収等を経て本年 7月中旬に規制区域の指定規制の開始を 行う予定としています 次に規制の内容についてご説明します 15ページをご覧ください 実際にどのような規模の森戸や切り戸が 規制の対象となるのかイラストで示したの がこちらの図となります まず厳しい規制のかかる卓区域についてご 説明します卓造区域ではこちらに記載の 規模の森戸について全て許可が必要となり ます森戸には2つの区分があり1つは宅地 造成などの土地の形を変更するものもう1 つは土砂の仮置きなどの一時的な土石の 体積です とそれぞれについて見ていくとまず土地の 形出変更では例えばあの丸1番森戸で高さ が1mを超える崖を生ずるものはと規制の 対象となりますここで崖とは30°を 超える角度の乗り面となります30°は 大体1対1.8となります 次に一時的な土石の体積では例えば丸6番 の通り最大時に体積する高さが2mを 超えるものあ2mを超えかつ面積が 300平米を超えるものが許可が必要と なります 次に16ページをご覧ください おも区域で許可届けでおる工事の希望に なります 特森区域では青字で示した比較的小規模な 森戸は届けで赤字で示した森度は許可が 必要となり先に説明した卓区域とは手続き が異なる部分がありますのでご注意 ください 許可や届け同様する工事の規模については 記載の通りとなります 次に17ページをご覧ください 等の規模によって必要な手続きが異なり ますので表にまとめたのがこちらです表の 上段は卓造区域下段は特森区域の場合です の色は森戸の規模を示しておりピンク色の セルは比較的小規模な森戸オレンジ色の セルはピンク色のセルよりも規模が大きな 森戸となっています 先ほど説明した通り白造区域では届け手の 手続きはなく赤枠で囲んでいる小規模な 森度も含めて規制対象となる森度は全て 許可が必要となります 一方で特森区域では許可体小規模の森と当 のうち赤枠で囲んでいる比較的小規模な ものは届けで手続きこれにより規模あそれ よりも規模の大きなオレンジ色のあ オレンジのセルの森度は許可の手続きが 必要となります また中間検査や定期報告は卓像区域匿森 区域のどちらにおいてもオレンジ色で示し た規模の森戸が対象となります 次に18ページをご覧ください こちらは新たに工事を行う際の申請手続き の 容判定の不ローとなります許可申請の 手引きから抜粋したものです 1番上の公共施設用地内または災害の発生 する恐れのない工事から進んでいくと最後 に許可を受けたと見なすもの許可申請が 必要なもの届け出手が必要なもの申請や 届け出手が不要なものと判断されます 実際に手続きを実施される際は参考になる フローズかと思いますのでご活用 いただければと思います 次に19ページをご覧ください こちらはその他届けを要する工事の一覧 です対象となる工事は3つあるのですが 特に重要なものは1番上に示している規制 区域の指定をまたぐ工事に関するものです 対象工事はと7月中旬の区域指定の際に すでに行われており許可届けを要する規模 に該当する工事でこれらの工事について 区域指定があった日から21日以内に 届け出を行う必要があります 届け出の期限が非常に短くなっております 法律で罰則の対象にもなってきますので 適正に手続きいただきますようお願いし ます その他2つの届け出については溶の除去を 行った場合施設用地の点用を行った場合と なります内容については申請な手引きの方 ご確認ください 続いて20あ失礼しました20ページを ご覧くださいここから5ページほど無理 規制法で許可を用しない工事を上げていき ますスライドの20ページから24ページ までをセットでご覧ください まず20ページですが公共施設用地におけ る工事は法の規制対象となり許可や届けで 等の手続きは不要となります 公共施設用地の具体的な定義はこちらに 記載していますが例えば国または地方公共 団体が管理する道路公園や河線などがあり ます不明点があればいつでもご相談 ください なお今後のスライドでもこの黒枠に囲まれ た表記がいくつか出てきます記載内容に ついて詳しくは説明いたしませんがと法律 の詳細部分を記載した箇所ですので後ほど お読み取りいただければと思います 次に21ページをご覧ください このページはその他法の対障害となる行為 の説明です 法律ではプチ利用のために土地の形を維持 する行為は災害の危険性を増大させない ことから法の規制対象とされています うちの形を維持する行為として具体的には 枠内に記載していますが1つは農地等に 行わ地等等において行われる通常の栄能 行為例えば後期や成地兵度の補充などが 該当しますもう1つは土地利用のために 土地の形出を維持する行為例えばえっと グランド等の土砂者の引き慣れし等が該当 しこれらの行為は規制の対象外となります 次に22ページをご覧ください こちらは災害の発生の恐れがないと認め られる工事も 法の規制障害となります具体的には砂利法 の砂利の採取土地改良法の土地改良事業 森林の制御を実施するために必要な作業路 の整備に関する工事モド等の高さあ失礼し ました森度等の厚さが30cmを超えない 工事土砂を当該工事の現場内またはその 付近に体積する工事などが規制体障害と なります 次に23ページをご覧ください こちらは法律の中で許可の特例として記載 されている事項になります 規制区域の指定後に都市計画法の開発許可 を受けた案件は森規制法の許可を受けた ものと見なすという特例がありこれは みなし許可と呼んでいます 都市計確保の審査の中で森戸の部分につい てもチェックしているため改めて森度規制 法としての許可の申請は不要という考え方 になります なし許可については後ほどまたご説明 いたします 次に24ページをご覧ください ここまでのスライドではえっと緑色の矢印 で示しているようパターンCのように規制 区域の指定後に工事着手あ工事着手する 場合に必要な手続きについて説明させて いただきましたこれから24ページと25 ページについては黄色の矢印のパターンB のように規制区域の指定前に工事に着手し 指定日の時点で工事中の場合について説明 いたします このパターンBの場合折り規制法の許可は 不要となりますが帰をまたぐ工事の届け出 というものが必要になります詳細について は届け出手での手引きの方をご確認 ください 区域指定日をまたぐ工事の届けでは 区域指定日の日から21日以内となります のでと繰り返しとなりますが事業者の皆様 にはご留意いただきますようお願いします 次に25ページをご覧ください こちらはクイックステ備をまたぐ工事の 届け出について対象となる工事の規模を 示した図となります 赤字青字で示した規模の工事はいずれも 届けの対象となります特に青子の規模の 工事の場合届け出手に図面の添風が必要に なりますこちらのも参考にご覧ください 規制区域の内容について説明は以上となり ます 26ページからは申請手続きについてご 説明します 27ページをご覧ください えまず申請の窓口についてです え事前質問もありましたが許可申請やその 他の手続きについて県庁の都市政策家森戸 対策係かりが全ての窓口となります市町村 や地域振興局に窓口を設けない形となり ますが相談等がある場合はオンラインでの 打ち合わせも実施いたします不明点があれ ばお気軽にお問い合わせいただければと 思います 次に書類の提出方法です各種申請届けで等 はできるだけ電子申請システムをご利用 いただきたいと考えています 電子申請システムのURLは現在準備中 です準備が出来次第ホームページに掲載 いたします これによる提出が難しい場合は申請書一式 を県庁都市政策家まで自賛または郵送 いただくこととなります え28ページをご覧ください こちらの表は許可申請の標準処理期間です 土地の警出変更に関する工事の許可は30 日土席の体積に関する工事の許可は14日 としています この期間には不等を補正する期間や県庁の 休日は含みません 続いて29ページをご覧ください 許可申請一見あたりこちらの表の通りの 手数料を徴収することとなります 額は森戸等をする土地の面積や工事の種類 によって区分されますなお変更の許可申請 等を行う場合も手数料が必要となります 金額は変更の内容によって異なりますので 詳細は申請手引きをご覧くださいなお 届け出手の場合は手数料不要となります 次に申請手続きの流れについて30ページ と31ページでご説明します 申請手続きには許可申請前許可申請法事 施工工事完了の4つの段階がありますまず 許可申請前の段階です 申請者の皆様から許可権者である新潟県に 対して電子申請システム等で事前相談を 行っていただけます その後県から事前相談の回答をします えまた申請者から土地所有者等全員の同意 をいただきますまた事業を行う周辺の土地 の住民への周知も実施いただきます 次に許可申請の段階ですまず申請者から 電子申請システム等で許可申請書を提出 いただきますその後資料の修正等の対応を 行いながら審査を実施し審査完了後に許可 通知書を件から申請者に交付いたします 許可後には県のホームページで許可内容を 一部公表します え続いて31ページです えこちらでは工事施工と工事の段階の流れ を示しています まず工事施行の段階です許可を得た工事に ついて申請者から現場に標識を設置して いただきますその後中間検査に該当する 案件については申請者から検査申請書を 提出いただき県が中間検査を行い合格書を 送付しますまた定期報告に該当する案件に ついては3ヶ月に1度申請者から県に対し 定期報告を実施いただきます 最後に工事完了の段階です全ての工事に おいて工事が完了した際には完僚検査申請 書を申請者から提出いただき県が完僚検査 を行った後検査済み症を交付します これが許可申請前から工事までの一連の 流れとなります 続いて32ページです 先ほどと似ている図となりますが都市計画 法の開発許可を受けたみなし許可の場合の 不ローとなります 開発許可の多くは市町村が許可権者となっ ていますそのため開発許可の申請や官僚 検査はこれまで通り申請者と市町村との間 で事務のやり取りを行っていただきます ただし皆の案件は赤線の森規制法の事務も 適用されます 森規制法の事務は県と指政策化が実施し ますのでこちらの赤枠部分の中間検査や 定期報告については申請者は件とやり取り をしていただくこととなりますご不便をお かけしますがよろしくお願いいたします 33ページは申請申請等の際に必要な資料 を一覧にしたものです え許可申請の場合は左側に記載の許可申請 書や工事の視力信用の確認書類各手が必要 となります また16ページや17ページで示した徳森 区域内での小規模な森戸に関する届け出で は右上に示す通り工事の届け出書や各種 図面の提出をお願いします 24ページでご説明した区域指定日を またぐ工事に関する届け出では右下に示す 通り届け出書や写真図面を提出して くださいこれらの必要資料の詳細について は件の手引きを参照お願います え続いて34ページですでここから15 ページ程度先ほどフローズでご説明した4 つの段階に区分してご注意いただきたい ポイントをご説明します まず許可申請前の段階ですがえ工事の許可 申請を行う前にできるだけ必要書類を準備 し事前相談をお願いしますこれにより結果 的に許可までスムーズに手続きができる ものと考えています また電子申請システムをご使用いただくと 必要事項が漏れなく記入されスムーズな 相談が可能となりますのでこちらをご活用 ください電子申請システムには県のホーム ページの森規制法メインページからも アクセスできます また森性森時規制法以外の法令についても 手続きを要する場合が多いかと思います森 規制法の事前相談に合わせ関係法令につい ても事前に調整をいただきますようお願い します 次に35ページをご覧ください 申請前の段階では土地所有者等の同意取得 が必要となります 森戸等の工事を行う土地について権利を 有する方全員の同意が必要となります 工事の計画について十分な説明を行うよう お願いいたします え次に36ページをご覧ください土地所有 者の同意と合わせてあかじめ工事を行う 土地の周辺の住民に工事内容を周知する 必要があります 周知の方法は説明会の開催や書面の配布 現場及びインターネットでの掲示があり ますのでいずれかの方法を取ってください ただし軽流等において高さ15mを超える 森動行う場合は工事内容をより詳しく周知 する必要があることから説明会の開催が 必須となります 周辺住民の周知にあたっては影響が大きい 隣接地等の住民に対して個別に説明を行う とともに周辺住民や自治会に対しても十分 な説明を行うと工事に対して理解が得 られるよう努めてください え続いて37ページですこちらの表は事業 の周知範囲の考え方をまとめたものになり ますので後ほどご確認ください え続いて38ページからは許可申請の際の ポイントについてご説明します 許可の基準としてまずはこちらに記載の 工事の技術的基準に合致している必要が あります 技術的基準については複数の項目があり ますがこの後の5章で詳しく説明します 39ページをご覧ください 審査では設計者の資格について確認が必要 な場合があります以下の工事の設計は資格 を有するものが実施しなければならないと されています具体的には高さ5mを超える 溶森戸等の面積が1500米を超える土地 における排水施設の設計があります必要な 設計者の資格はこちらの囲みの通りです 次に40ページをご覧ください 工事主の視力信用についても審査を行い ます 工事主が工事を完成するために必要な視力 や信用を有しているかをこちらの囲みの 資料によって確認します 続いて41ページをご覧ください 工事の施工者の工事完成能力についても 確認する場合があります 森戸等を行う土地の面積が1ヘクタル以上 の場合や溶を設置する工事においては工事 施工者が工事を完成するために必要な能力 を持っているか資料によって確認します 例として工事施工者の登期事項証明書事業 経歴書建設業許可証明書を提出いただき 確認することとなります 続いて42ページからは許可を受けた後の 工事施工についてポイントをお話しします まずは現場での標識刑事です許可を受けた 工事や特森区域における小規模工事の届け でを行った案件については許可を受けた 土地の見やすい場所にこちらに示すような 標識の掲示が必要となります えこちらについてはみな許可の案件でも 該当となりますのでよろしくお願いいたし ます え43ページをご覧ください え中間検査についてですこちらも見し許可 の場合も該当する内容となります 森度等を行う前の自盤面に暗排水等を設置 する工程が完了した段階で中間検査を 受ける必要がありますその後の工程は中間 検査に合格した後でなければ実施できませ んのでご注意ください また公前など検査が集中する可能性もあり ますので早めに検討な日程調整をお願いし ます なお中間検査の対象となる森戸等の規模は こちらの通りです 中間検査は自盤面に暗排水艦を設置する 工事のみが対象となることにもご注意 ください また検査の申請期限が排水艦の設置完了 から4日以内と非常に短くなっていること にもご注意ください 続いて44ページをご覧ください こちらは定期報告になりますこれも皆し 許可案件でも該当となります 定期報告ですが工事の規模に該当する場合 3ヶ月ごとに月末の報告を行っていただく 必要があります 例えば4月15日に許可を受けた案件に ついては第1回の定期報告を6月末に第2 回の定期報告を9月末に実施いただきます 定期報告を要する規模の森ド等はこちらの 表に記載の通りです 報告内容はその時点の森戸等の施工状況 です 45ページをご覧ください 次に計画変更についてご説明します工事を 実施していく中で計画が変更となることも あるかと思います許可を受けた工事の計画 を変更する場合改めて件の許可が必要と なります また変更の内容に応じベッド手数料を用し ますのでご注意ください 計画変更で提出が必要な書類としては変更 許可申請書計画の変更に伴い内容が変更と なる書類土地の土地等の権利者の同意書と なります なお警備な変更の場合は蒸気の変更許可 申請は不要ですが速やかにえ届けでしょう を提出する必要があります 警備の変更としては記載の通り法主等の 名称住所の変更及び法事の着手官僚予定 値費の変更が該当します 続いて46ページをご覧ください 工事が全て完了したら工事が許可内容に 適合していることを判定するため検査等を 実施します 申請者から提出いただく書類としては土地 の警出変更の場合は完了検査申請書土席の 体積の場合は確認申請書となります いずれも工事から4日内に申請が必要と なりますのでご注意ください 検査項目の例は囲みに記載の通りですが 森戸等や施設が計画通りに施工されている か土席の体積の場合は土席が撤去されて いるかを確認します その際工事内容の裏付けとなる写真等の 根拠資料が必要となりますので工事の段階 ごとに整理をいただくようお願いします 検査の検査の詳細は今後申請手引きの中に 追求していく予定です 47ページをご覧ください えこちらは参考となりますが都市計画法の 開発許可を受けたみなし許可の案件につい て森規制法としてどのような手続きが適用 になるか整理した表です 許可の案件には都市計画法の規定の他 オレンジで示している森規制法の技術的 基準中間検査定期報告監督処分標識の掲示 が適用となりますので該当する案件があり ましたらご注意ください 続いて48ページをご覧ください 許可で見なし許可が適用されるタイミング について規制区域指定の前後で複雑になる ことから運用イメージを説明いたします4 つのパターンがありますがこれらは全て森 規制法に該当する工事がある場合の話です のでその前提で聞いていただければと思い ます 青色は開発許可緑色は森時規制法に関わる 工程を示しています 真ん中の赤のラインが規制区域の指定日で 7月中旬から森戸規制法の運用が始まり ます まずかこ1は規制区域の指定前に開発許可 を受けすに工事に着手しているパターン です こちらは規制区域指定前の開発許可ですの で見なし許可にはなりません規制区域の 指定後も森戸農工事を続ける時は規制区域 指定後21日以内に届け出が必要となり ます 一方か2は規制区域指定前に開発許可を 受けたものの工事着手していない場合と なりますこの場合は工事着手が区域指定 より後となることから改めて森規制法の 許可を取っていただく必要があります 次にかこ3は規制区域の指定後に開発許可 を受けた場合です規制区域の指定後は森時 規制法の運用が開始しているのでこの場合 は見なし許可が適用されます 最後にかこ4は規制区域の指定後に工事 計画の変更をする場合です 具体的には規制区域の指定前に工事着手し ているもののその後の計画変更で霧戸や 森戸が増行し森戸規制法の許可対象の規模 になったというケースです この時当初の開発許可は見なし許可が適用 されていないので計画変更の際は開発許可 の変更許可と森時規制法の許可の両方が 必要となります えここまでご説明してきた中で特にかこ2 のケースは開発許可と森時規制法の許可が ダブルで必要となってしまい申請者側の 負担も大きくなってしまいますそのため このパターンの可能性がある場合は現場 着手を早期に行うとこのパターンを避け られるよう対応していただければと思い ます 個別に相談がある場合は都市作家までご 連絡願います 続いて49ページをご覧ください こちらも参考となります件では許可届け出 があった案件について情報を件のホーム ページで公表する予定です公表する情報は こちらに記載の通りです 公表方法については現在検討中ですが規制 区域指定日以降県のホームページをご確認 いただければと思います え続いて50ページをご覧ください こちらも参考となりますが県の森戸条例と 森戸規制法の運用イメージを示したです 県では現在森戸を規制する条例として新潟 県森戸等の規制に関する条例通称条例を 有しています ただしこの森戸条例は森戸規制法の運用が 始まる7月中旬に廃止する方向で検討して います 手続き等のタイミングによりいくつか対応 パターンが考えられますのでここで内容を ご説明しますなおここでは森戸条連の 手続きを黄色で森ド規制本の手続きを緑で 示しています か1は規制区域が指定される今年の7月 中旬までに森戸条例の許可を受け工事着手 まで行うものです この場合規制区域指定後21日以内に森戸 規制法の届け出手続きが必要です 括には規制区域の指定までに森戸条例の 許可を得たものの現場の着手に至らなかっ たものです この場合規制区域指定後に改めて森規制法 の許可申請が必要です かこ3は規制区域指定後すぐに工事着手し たいという場合です モニド条例は標準処理期間が90日となっ ているため今後申請を受け付けたとしても え許可の事務手続きが困難となりますその ため今後は森戸条例ではなく森戸規制法で の対応が基本と考えています区域指定前で も自然相談を受け付けておりますので許可 を急ぐ場合はご覧ください この他個別の案件で不明点があればお 問い合わせをお願いします 52ページをご覧ください 技術的基準になりますがえ先ほども少しお 話をしましたけれども森戸規制法にはえ この技術的な基準が複数定められており ますえこちらは土地の形出変更の技術基準 を示したイメージ図になります例えば左上 にありますけれども軽流等における15m 超の森戸の場合は安定計算を義務付けです とか左下のえモド等で崖を生じる場合は 傭壁またはえ崖面崩壊防止施設の設置え などがありますえ森戸等の許可を得るため にはえこれらの基準を満たしていく必要が ありますのでご注意くださいえこの後え この技術的な基準に関しましてえポイント え8ページほどご説明をさせていただき ますえ詳しい中身は県のえホームページに え載せておりますえ技術的基準を後ほどご 確認いただければと思います53ページを お開きください こちらはえ森戸の乗り面の安定計算での ポイントとなります 土地の形出変更を行う場合にはえ以下の 場合に乗り面の安定計算が必要となります まず丸1ですがえ軽流のように水が集まり やすい地形ではえ森戸の災害がえ発生する リスクも高いということでえこの経流では 盛道を行う際の安定計算を求めますえ丸2 ですがえ乗り面の勾配が30°を超える 場合えこの場合は安定計算または溶の設置 をえ設置が必要となりますえまず3番 乗り面の勾配は30°以内でえ以下に該当 するとしましてえ15m以上の高さの森戸 え傾斜の森戸や谷間を埋めるモドえ南弱 自板やつり地におけるえ住宅に隣接して いるモドえこれらは安定計算が必要となり ます 54ページをご覧ください こちらはえ森戸の施工上のポイントになり ます え敷き鳴らし締め固めではえ森戸の安定性 をえ確保するために土砂の巻き出し圧えを え30cm以下としていただいて一層ごと の締め固めをえ行ってくださいまたえ官業 検査で必要となりますので森戸の締め固め 状況をえ段階ごとにこう確認できるような え写真の管理を徹底いただくようお願い いたします につきましてはえ字山の勾配が15°え 以上ある場合にまこちらも森戸の安定性を 確保するためにえこちらに示しているよう な施工実施をお願いいたします 55ページをご覧ください こちらは洋壁の設置におけるポイントと なります オド等を行い生じた崖にはえ原速として溶 の設置が必要となります 溶の設置にあたりましてはえ背後の地下水 をスムーズに排水できるように水抜き穴等 をえ適切に設置をお願いいたしますまた 一定のえ値入れ深さの確保もお願いいたし ますえなおえ傭壁についてはえ国土交通 大臣が認定した癖えいわゆる認定癖を使用 される場合はえ森度規制法のえ技術基準に ついてはあの適用を受けないこととなり ますけれどもベッドあの認定の状況が 分かる書類を提出いただく必要があります またこちらは参考になりますけれどもえ スライドの右下の方にはえ壁の設置が必要 な崖あるいは不要な崖について歴をして おりますのでえ参考にご覧ください 続いて56ページご覧ください こちらは崖面崩壊防止施設になりますえ 施設のイメージとしてえ加護枠ですとか 補強壁等の写真を載せておりますえこれら の施設はえ以下のように傭壁の適用に問題 がある場合に傭壁の代わりに設置をする ことがえ可能となっておりますえ具体的に はえ自盤の指示力が小さい場合え地下水等 を排除する必要がある場合自盤の変形を 許容できる場合となりますただしえ住宅等 のえ自盤の変形が許容されない土地にはえ 使用ができませんのでご注意いただければ と思います 続いてえっと57ページをご覧ください えこちらでは排水施設についてご説明し ます これまでえ発生してますえ森戸崩壊の原因 の多くが自山からの有水ですとか地下水と なっておりますえそのため森戸の中に浸透 した地下水等についてはえ排水の施設に よってえ速やかに排除するということが 重要となります 排水施設の種類をえ参考にこちらに載せて おりますがえ赤枠で囲んでいる暗排水行に ついてはえ先ほど出てきました中間検査の 対象となりますのでえご注意くださいまた え地下排水の標準的な仕様についてもえ表 に記載しております参考していただければ と思います 次にえ58ページをご覧ください こちらはえ崖面以外の地標表面にえ構図ル 措置のポイントとなります 崖以外の地表面についてはえ基本的に新食 等によって森戸が不安定化しないようにえ 食成功等のえ乗り名保護が必要となります えただし以下のような場合はえ保護保護は え不要となりますえ具体にはえ排水勾配を ふした森戸またはティリドのえ上面えもう 1つは道路の路面の部分などえ地標表面を 保護する必要がないことがえ明らかな部分 もう1つえ農地等で植物の正がえ確保さ れる地表面となります乗り名保護えまた 上壁等の設置が必要な箇所については こちらの表にも整理をしておりますのでえ 参考としてください 次にえ59ページをご覧ください こちらはえ土石の体積のポイントとなり ます 土石を一時的に体積する場合はえ以下の 基準を満たす必要がありますえイメージと 合わせてご覧いただければと思いますがえ 具体には丸1え土地の最大勾配を1/1 以下とすること丸2え所定の幅の空地え スペースを設けること丸3え柵等等を 設けること丸4え速攻等のえ地方水を排水 する施設を設置をすることとなります 60ページをご覧ください え先ほどのえ基準を満たさない場合はえ こちらの候報を採用することができますえ まず十分な空の設置が困難な場合なんです けれどもえ1つはえ土席の高さを超える 公板え等の設置によって空地の確保が不要 となりますもう1つはえ体積した土砂の 乗り面勾配をえ緩やかにしてえ防水シート 等で覆ったりするということでもえ空地 スペースの確保が不要となります え次にえ自盤の勾配が1/1を超える場合 なんですけれどもえこのようなえ広大を 設けることで土石の体積が可能となります 続きましてえ6番の事例紹介としてですね よくあるご質問とえその回答をえいくつか ご紹介をさせていただきます 62ページご覧ください えよくある質問としましてえくぼ地で行う 盛ドはえ規制の対象になるのかというもの がありますえこれについてえ以下の場合は 森戸規制法の規制対象外となりますえ 例えば左側の図のようにえ司法を道路え ですとか宅地などで囲まれた低い農地が ありえこれを周囲と同じ高さまで理動する ような場合は許可不要となります えまたえ右側の図のように元々のくぼちを 周囲の土地より少し高く盛り度するえよう な場合えこれもえ基準面からの盛ドの厚さ が30cm以内であれば許可不要となり ますえただしえ赤字でも記載をしており ますがえ前後の自盤の標高差え森戸のま 厚みがえ30cmを超えると面積に応じて 姿勢の対象となりますのでえご注意 ください 続いて63ページをご覧ください えこちらはえ薄い森戸は姿勢の対象となる のかという質問ですが森戸前後の自盤の 標高さ森戸の厚さが30cm以下の場合は え規制の対象外となりますえ例えば工事例 の丸1ではえ森戸の厚みが30cm以下と なっていますのでえ面積がま500平米を 超えているんですけれどもえ知性の対象外 となります え赤字の部分は繰り返しになりますが森の厚みが 30cm を超える場合は面積によってはえ規制の対象となりますのでご注意をお願いいたします 続いて64ページをご覧ください 許可申請のえ対象面積ですがえこのような 森戸があった場合森戸の乗りから乗りまで のえ森戸等を行う土地の面積でえ算定を することとなりますこの赤字の部分になり ますまたえ申請の手数料についてもえ こちらの面積で判断をすることとなります のでえご注意ください 続いて65ページをご覧ください こちらは工事の現場内で土砂をえ一時的に 仮置きする場合の例となりますえ以下の ように工事の現場やえその付近においてえ 本体工事と一体的にえ森戸が安全管理され ているというあ失礼しましたえ一体的に 安全管理をされている火用機度については え規制の対象外となりますえ具体的にはえ 工事現場の考え方としましてはえ右側の イラストのようにえ工事が行われている 土地やえ工事現場から離れていても施工 計画書にえ工事現場として位置づけられて いる土地などについてはえ規制の対象外と なります 現場の付近の考え方ですがえこちら右下の イラストのようにえ工事現場に隣接してい てえ本体工事と一体的な安全管理が可能の 範囲可能な範囲えがえ該当しますえこちら についても規制の対象外となります 続いて66ページをご覧ください こちらはえ先ほどと関連した内容な内容に なりますがえやを得ず本体工事の期間後も え現場やその付近で土席の体積をえ継続 する場合の扱いについてですえ例えばえ 残度処分上やえ流用先の工事との法定調整 等によりやず工事のえ期間後も土席の体積 を継続する場合え許可不要として扱います え図のように森戸の工事があるとしてえ 森戸の一時工事ではえ現場付近にえ土席を 借り置きしており665ページ前のページ の通りですねえその場合は許可不要となり ます えその1次工事が完了した後にえ2次工事 の予定はあるのですがえ工事がない期間が 生じた場合え点線のところになりますこの 場合でも先ほどご説明した通り現場付近等 のえ土席の体積についてはえ継続して許可 不要となりますえただしえ森戸の管理の 状況を客観的に確認できるようえ本体工事 の管理者等に置かれましては管理体制等を え記した看板の掲示が必要となりますので えご留意をお願いいたします 次にえ67ページをご覧ください
はい こちらはえプラント等の敷地内における土席の体積となります え土席土席というえ言葉の定義については えこちらの資料の4ページにえ記載をして おりますがえ土砂もしくは岩石またはこれ らの混合物となっておりましてま一般的な え土え岩石に加えて海業度や再生えこれら も土石に含まれますえプラント等での土席 の体積はえこちらに記載の不ロによってえ 規制対象のをえご判断いただければと思い ますえ特にえその向上で製造されている 商品が土席に該当するかどうかという ところがえポイントとなりましてえ例えば コンクリート工場ではえ土席の体積は規制 の対象外となりますがえ開業度あるいは 再生再籍等の向上ではえ規制の対象という ことになりますえ1番下に米で書いてあり ますがあのまた規制区域のえ指定の時点で ですねすに運用されているプラント向場等 につきましてはえこちらも21日以内の 届け出が必要となりますのでご意をお願い いたします 続いて68ページをご覧ください えこちらは森戸の一体性の判断について ですえ例えばえ既存の森戸と接する新規の 森戸を増成するという場合にえ対象となる 森戸の規模をどのように考えるかという点 になりますえこれについてはえ個々の ケースによりえ判断することとなりますが え一体的な盛と判断される場合はえ規制の 対象となります え一体的な森であるかどうかというところ はえ以下のえ考え方によって総合的に判断 をいたしますえ具体的にはえ森戸のえ事業 者の同一性森戸の物理的な一体性機能的な 一体性え時期的な隕性となりますえこれら について不明点がありましたらえご相談を いただければと思います 69ページをご覧ください こちらは映能の関係となります評度の補充などの行為はえ規制対象となるのかというえ質問についてですが え30cm以内の度の補充などえ通常の能 A能行為の半疇であればえ規制の対象外となります 通常のAの行為としては例えばえ左側に イラストがありますけれどもえ農地の後期 定地京の新設ですとか表度の補充などが 上げられますえ一方でえ規模によって規制 の対象となる行為としてえ右側のイラスト のように補上の大区画化え森道を伴う電波 転換え濃動の整備などが上げられますえ ただしこちらについてあの22ページでも お話をしている通りえ米メ印にもあります が土地改業法に基づく土地改良事業はえ 規制の対象外となります え通常の栄行為の半疇範囲についてはえ 判断が難しい場合もあるかと思いますので え不明点があればえご相談をお願いします ここまでえいくつか事例をご紹介させて いただきましたえこれらあの一例ですので これ以外に判断迷うようなえ案件があり ましたらお気軽にご相談いただければと 思います 続いて7番のえ不法盛モ対になりますえ こちらではえ不法モドに関する事例のご 紹介ですとかえ皆様へのお願いをさせて いただきたいと思います71ページご覧 ください えまず事例の紹介になりますがえこちらは え福島県の西号村で行われたえ不法森道と なります令和5年のわずか数ヶ月の間にえ 関東から大業の建設弾度が持ち込まれえ 民家の脇に大きな森戸が増成をされて しまいましたえ福島県はこれに対してえ 森度規制法の違反としてえ行政大執行に よる土砂の撤去を行ってえ先日撤去工事が 完了したところですえ撤去に用した費用は 1億5000万円程度という風にえ聞いて おりましてえ建設弾度を持ち込んだえ自動 車にえ今後請求されるとえいう風に伺って いますなお自動車はえ森地規制法の違反で 刑事告発されております モド規制法ではえ規制区域の指定後にえ このような無許可モドですとかえ監督処分 の命令違反えあるいは技術的基準のえ規定 違反等の場合にえ3年以下の懲役または 1000万円え法人においては3億円え 加えて3億円以下の罰金となりますのでえ ご注意をお願いいたします 72ページをご覧ください こちらはえお願いとなります先ほどの写真 の通りあの不法森道というものがあまされ ますと一気にえ増成されて大きくなって しまうためえ早期の発見というものが非常 に重要となっておりますえ皆様におかれ ましてはえ不法と思われる森道を発見され た場合にえ是非通報にご協力をえお願い いたします怪しい盛ドとしましては例えば え現場に標識のないえま大規模な森道夜間 に行われている森戸え県外ナンバーの トラックの頻繁なデが考えられますえ通報 はえ県の都市政策家宛てにお電話いただく ようにお願いいたします今後え電話以外で の通報を受け付けるようなシステムについ ても導入を検討しております 最後に8番その他となります 74ページとなりますえここまでえ森戸 規制法の概要ですとか手手続きの概要に ついてご説明をしてきましたえ申請書のえ 具体な記載の方法あるいは届け出の方法え 技術的な基準等のえ具体な中身え等につい てはえ県庁都市政策家のホームページにえ 掲載をしておりますえこれらの資料をです ねえご確認いただければと思います 点え色々あるかと思いますけれどもえあり ましたらえこちらにえ連絡先までお気軽に お問い合わせいただければと思います以上 で説明をあります
新潟県では、令和7年7月18日に県土全域を規制区域として指定し、盛土規制法の運用を開始します。
盛土規制法の運用を開始すると、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合に、許可・届出の手続きが必要になるほか、これまでに造成された盛土等についても、土地所有者等が常に安全な状態に維持する責務が生じることとなります。
つきましては、県民・事業者の方々に向けて、法の概要や、許可・届出手続き等に関する説明会を、令和7年4月に県内3会場(新潟・長岡・上越)で開催しました。
この動画は、令和7年4月16日(新潟会場)の説明会を録画したものです。
説明会後に資料を修正した箇所がありますので、修正版の資料は下記のページからご覧ください。
【盛土規制法に関する説明会を開催しました】
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/toshiseisaku/moridokisei-setsumei.html
【動画の構成(資料の目次)】
0:00:00~ 0.はじめに…p.2
0:02:21~ 1.盛土規制法の概要…p.6
0:05:07~ 2.規制区域について…p.9
0:08:24~ 3.規制内容について…p.14
0:18:30~ 4.申請手続きについて…p.26
0:41:13~ 5.技術的基準について…p.51
0:50:26~ 6.事例紹介…p.61
1:00:26~ 7.不法盛土について…p.70
1:03:10~ 8.その他…p.73
【盛土規制法に関する問い合わせ先】
新潟県土木部都市局 都市政策課 盛土対策係
電話 025-280-5932
メール ngt160010@pref.niigata.lg.jp