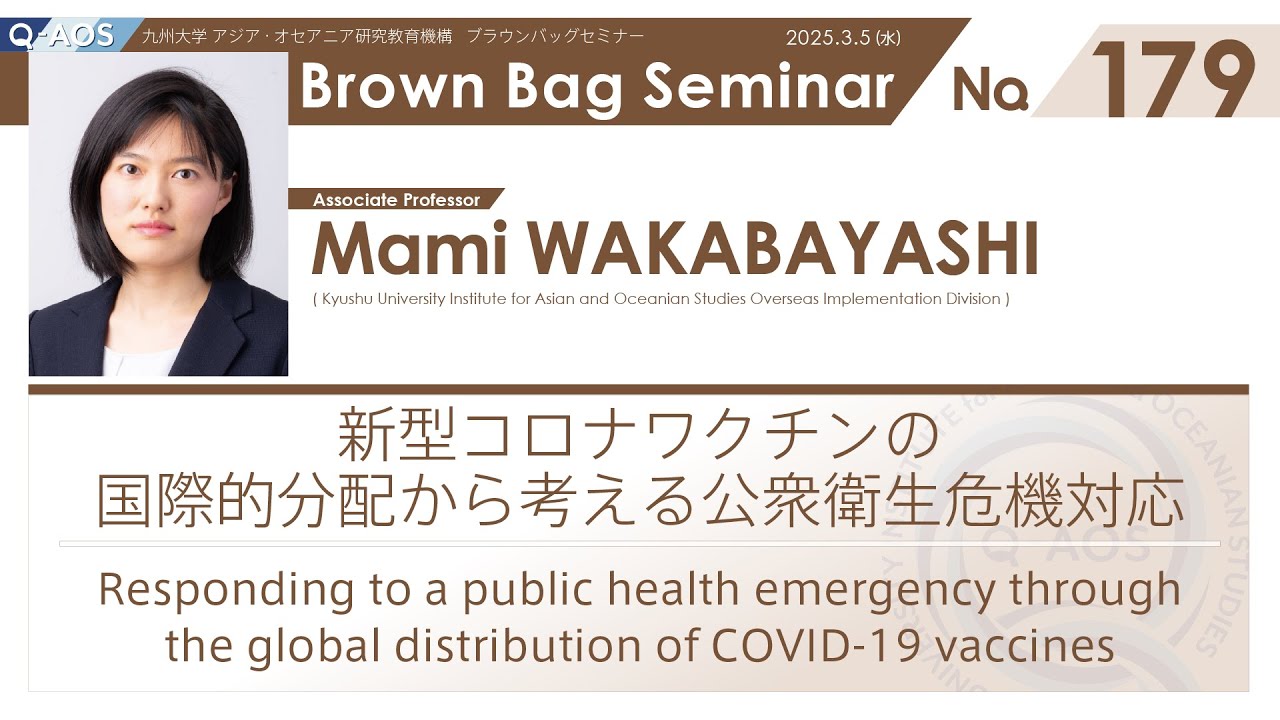Brown Bag Seminar No. 179 若林真美 准教授 「新型コロナワクチンの国際的分配から考える公衆衛生危機対応」
それでは実験となりますのでセミナーを 開始いたします本日殺長を包めますのは 九州大学オシエニア 県記菊教授です菊口先生よろしくお願い いたします はいありがとうございますえ皆様本日も バックセミナーにご参加いただきまして誠 にありがとうございますえ本日のMCを 務めますアジアオセアニア研究教育機構の 菊と申しますどうぞよろしくお願いいたし ますえこのセミナーはあ当期当期校の企画 としましてえ本学のアジアスアニャ地域 ですとかまSDGズに関係する研究活動を 多くの方に知っていただいてえま異分化 研究異分野研究ネットワークですとかま 交流のきっかけになる場を提供できればと の思いで開催させていただいておりますえ 発表者の方々のユニークな研究や活動がま 主張されてる皆様にとってえヒントになる ことをおでなりましたら幸いですのでえ 是非ご昼を取っていただきながらお気軽に ご参加いただければと思います はいえでは本日のスピーカーをご紹介 いたしますえ本日はあ アジアオアニア研究教育機構の若林ま美準 教授にご登壇をいただきますえ若林先生は グローバルヘルスを専門とされましてえ コビッドid19のパンデミックの時期に は外務省の国際保険政策専門としまして コバックスなどの国際的なワクチン供給の 活動にわりましたえこういった貴重な経験 を積まれておりますえ私自身もグローバル ヘルスの分野に携わっているのですけれど もまこのコビッドid19の時期にはま このグローバルヘルスの分野の課題と可能 性を改めて浮き彫りにしたなという風に 考えております若林先生のように実際に 国際的な枠組の中でま政策ですとか現場に 関わる経験をされたからのされた方のお話 というのは非常にあの貴重で下に飛んだ ものになると思います で本日のセミナーはえ新型コロナウイルス の国際的分配から考えるえ公衆衛生え衛生 危機対応というえタイトルでえコバックの 仕組みやその活動などですね先生自身のご 経験を振り返りながらお話しいただけると 思いますことと思います はいで本日お話しいただく若林先生の娯略 歴をご紹介しますえスライドにございます がえまず大阪大学にて看護学を学ばれまし てえ収支博士家程を終了されましたえその 後コンサルタントにてえコンサルとして 活躍されましてえ国際保険の分野で幅広い 経験を積まれてえいらっしゃいますえ外務 省ではま先ほども申しましたが国際保険 政策専門として勤務されてえその後国際 国立医療研究センターの方ではグローバル ヘルス政策研究センターの上級研究員を 務められましたまた直近ではUNISIF ブラジルの保険専門官としてえ国際的な 保険医療の支援に携わっておられますえ 長年にわり公的機関や国際機関え研究機関 の他方面でグローバルヘルスの政策や実務 に貢献されてきた先生ですはいえでは今回 グローバルあバックセミナー179回目と なりますがえ若林先生ご準備はいかが でしょうかよろしいでしょうか はい先生のご紹介いただきまして ありがとうございますえでは私若林の方 から発表をさせていただきたいと思います まずスライドを共有させていただきます はいスライド見えておりますでしょうか では発表を始めさせていただきたいと思い ます今菊先生からあの自己紹介いただき ましたので私の方から少しだけですねあの 補足としてえっとグローバルヘルスについ ての関わりについて少しご説明させて いただきたいと思います今ですねま グローバル化してない社会を想像するのが 難しいほどですね人物お金情報などがま特 を超えてえ様々な形で交流していますえ 健康課壇についてもですねま国境を超えて 様々な形でえ影響し合ってるというのはま 新型コロナあウイルス感染症のえ事例を とってもえ実感するところではないかと 思っておりますしえ日本のようなですねま あの海に囲まれたところですとまえ日本人 とその外国人そしてえ日本と日本以外と いうあの形で分けて考えることがまあのし やすいあの地域ではあるんですけどもそれ でもえたくさんのえ外国人の方が今日本に 来ておられてその方々のえ健康課題を 考えるといったようなえ日本における移民 の健康課題を考えるといったようなえ 新しい分野の研究もえますます活発になっ てきております私がねあの携わっている グローバルヘルスの課題というのはですね この中に見ますとえま国際協力国際機関 国際え期間を通してのえ援助といった形の えっとグロバルヘッツの課題になりますえ 特にですねこの分野についてさらに細分化 してあの考えてあの考えられた先生が いらっしゃるんですけれどもそこの分野で まどこをもう国ま低中所得国中え交所特国 どこをターゲットにしてどんなサービスを 提供するかということであの様々な触種と 関わり方というのがあります大体まこの 分野この国際協力の中の国際保険の分野で ま大体6万人ぐらいの方々があの関わって いろんなプロジェクトをされていると言わ れているんですけどもその中で私自身もま 皆さんからあの想像しやすい例えばですね 低ト部まアフリカなどの国に行ってえ炎上 緊急炎上という形で保険医療自治者として 携ええ従事してきましたけれどもそれだけ ではなくってえ保険の政策規範を設定し たりえ研究開発の投資を行ったりといった 分野のことにも携わってきました今回は ですねその一般としましてえコバックスと いって新型コロナのえワクチンをどのよう に分配するかという規範についてえ少し皆 様と一緒に考えていければなと思っており ます こちらが今日お話しさせていただくえもの ですけれどもまず背景としてコバックスに ついておめさせていただいた後特にですね 太平洋用国えその国々のえ新型コロナ ワクチンの摂取の事例を少し上げさせて いただいた後そこで起きた課題とえま今後 に向けた提言ということでそこを考える ことで次のまた新しいパラデミックにどう 対応していくのかということを皆様と一緒 に考えていければなと思います こちらま新型コロナワクチンに関してま あのどういう風な入手経路があるかという ことなんですけれどももちろん自分の国で え開発してえ生産というものができれば 各国それができればあのもちろんこういっ たあの分配するというような問題は起こら ないんですけどもですね日本においても 新型コロナウイルスのあワクチンがね開発 されてえま供給され始めたのはですね日本 独自のものというのは2023年の12月 と言ってまあの進学コロナのピークの時 から考えるとかなり遅れた時期となって おりますまそれまでどのように対応してた かと言いますとまいわゆる世界の大きな あのえ制約会社からえ独自で購入していた というのが現状ですただそういったま独自 のえルートを使って制約会社から購入 できる国というのはえ世界で見ても非常に 稀れな国でえ限られておりますじゃあでは どうしたら他のえ国々がえまいう公平にえ ワクチンをえ入手できるのかということを 考えて作られたのがコバックスとなって おります このコプクスというのはですねそのアクト アクセレと言いまして新型コロナウイルス 感染症対策に関する国際的こあ国際的 取り組みの枠組の大きな枠組の中の1つの え柱ですえこのアトアクセレターには ワクチン治療診断保険医療システム強化と いう4つの柱がありましてそれをえま各国 でえもっと強化していこうという風なえ 提案を日本を含めた8カ国のえ共同提案に よって立ち上がりましたえ各それぞれま ロゴがここに示されていますけれどもこれ らの国際的な期間がですね自分たちの本来 やってる業務の強みを生かしてえこれらの 柱をより強化していこうという風にしまし た中にもですね注目度が高かったのが ワクチンの柱なんですけれどもここに 関する製造開発調達供給規制調整といった 分野をえなってきたのが4つのえ国際国際 機関と国際的な組織でありますこのことの 枠組をえコバックスという風にえ読んで おりますでは国際的なえ期間がそれぞれ どのように役割分担したのかと言いますと まずまえセビというえ国際的な パートナーシップの期間があるんです けれどもここはですねそもそも医薬金 関する研究開発の資金を提供したりまその プロトコールに関する助言をアドバイスし たりというようなことをえやってた期間 ですのでそれを生かして新型コロナに 関するえ投資というものを促進させました 皆さんがご存知のまメーカーさんで言うと アストラジェネカのえワクチンであります とかあとはモデレーナといったMNの ワクチンもここのセにえよって支援をあの 受けていました そしてガディというのがまこの コフコワックスの中でもかなり1番中心的 な役割を担っていたんですけれどもえ コロナのえワクチンをえ制約会社とえ交渉 して購入したりあとはどんな国が参加する のかという参加での調整を行ったりという 事務局の役割を担っていましたえUNFは ですねあのもう戦後すぐからですね子供 たちのワクチンの供給という形でえ様々な ノーハウを持っているえ国際機関ですので 自動国際機関が中心となってまワクチンっ て結構あのすごく温度管理が重要だったり とかあのワクチンタブレットの薬ではない ので駐車機が行ったりとかえっとその他 諸々の付属品がいたり冷蔵庫を保管する ための冷蔵庫がいたりというああの ロジスティックの面がすごくあの非常に 複雑となっていますそういったノーハウを 使ってえその国からまいわゆる保険 センターにえ運ぶところまでの上行を UNFがえ行ったという風なえ経緯があり ますそしてWHOですね世界各国の保険省 と言われるま日本でいう厚生労働省の方々 が集まってまいろんな世界における規範を 作ったりすることをやっている期間ですの でその期間がえま新型コロナのえワクチン のどういう国々にま優先的に配布すれば いいのだろうかとかどういったその国に おいてどういった方々を優先して摂取す べきかあとは品質が保証されたま安全で 効果的ワクチンはどういったものがあるか というようなことをえエバあの認証したり といったことをえWAはえしておりました この4つの期間がえま共同してコマックス という風な枠組をえ運営していましたこの コマックスにおいてま特徴的だったのは2 つの大きな枠組がありますえ1つはですね ま高得国やあ集所得国向けの枠組でその 国々はま自分たちで資金は持っているので ワクチンを自分たちで買うことはあのでき ますでできるだけの資金がありますただ まあ2020年は新型コロナがあの活発化 にされていく中でまだどのワクチンが成功 するかっていうのが全く分からない状況 だったんですねの中でま成功確率が高い だろうと言われるえワクチンを選定して その会社と契約してえコバックスがま共同 でえワクチンを買ってその共同で買った ワクチンをま分配してあのえ公平にえっと ワクチンを配るというのが1つ目の枠組 これはですねま日本のようなあの交所特国 がですねワクチンを青互いと言いまして どれが成功するかわかんないけど成功し そうなワクチンを大量に買ってあのキープ してくというようなことをま抑をしようと したえあ1つの取り組みでもありますで もう1つの枠組としてはですねそのま そもそもワクチンを買うようなお金すら あのないであろう国というのをまドナー からのお金をプールしてその枠そのお金で えそのその国々にもえ平等にワクチンがえ 届けられるようにしようという枠組です その2つをえうまく回してえっとワクチン をあのできれば世界各国え全20億ローズ を供給することをえコバックスは目標とえ しておりましたで最終的にま2021年の 4月時点では191日国が参加してあの コバックスがえしたあの運営されていた わけなんですけれどもコバックスからあの ワクチンをするメリットとしてはこのよう なものが上げられます特にですねまあの 各国それぞれがあの制約会社と交渉して ワクチンを買うよりもですね大きなえま コバックスという単位で何億何兆というえ ワクチンをあのオーダーすることによって 制約にとってもですねあのま手間もはけ ますしこういうこれだけのあの需要が 見込まれるということであのまだワクチン はできてないけどワクチンができた時の 向上を拡大しで必要な整備を投資して おこうというようなことにもあのつがると いった形がありますしえ購入する側として はもちろん小さい国においてはそのえ集団 で購入した割引き価格でえ購入できますし あのま政治的な購入するお金はあっても 政治的なちょっとなんていうかパワー バランスによってあの購入が難しい国って 中特国とか交渉所でもあるんですねま1個 だけ例を上げるとすれば例えば台湾とか いう国はお金を持っていてもま政治的な 鑑渉によってあのなかなかあの購入が 難しいそういったような国もあのこういっ たコマックスからえ平等に降臨できると いうようなあのメリットがあると考えられ ております でじゃあこのコバックスを通じて初めて ワクチン供給が開始されたというのが 2021年のえ2月の24日となっており ますガーナという国民あの運ばれましたえ これは皆さんにとってどうですかねあの 早い時期ですかねえこんなに時間かかった のっていう時期ですかね 私個人のえ意見としましてはえっと比較的 早い時期にコバックスは初のワクチンを 供給が開始できたのではないかとしかも 低中所得に向けて開始ができたんじゃない かなという風に考えていますというのも 2021年のえ2月24日というのはです ねえ日本でもワクチン摂取がまだ開始され て1週間経ってない時期なんですねしかも 日本でワクチン摂取が優先されたのはえ 保険医療従事者の第1回目が始まったのが この1週間前ということになるのでそう いった意味ではあのコバックスは非常に 良いスタートが切れたのじゃないかなと いう風に考えておりますそしてその 2021年の2月24日からま約1ヶ月後 の3月31日との比較をした時にですね まだ2021年2月24日にはですね何の ワクチン新型コロナのワクチンを何もあの どこからもらってないし何も入手してい ないという国が81カ国あったんです けれどもそれがまあ3月の時点では37 カ国にまで減っていったこれは1つの コバックスの成果ではなかったかなという 風に考えておりますでこのようにま順調に コバックスは走り始めたかのように見えた んですけれどもあなかなかうまくかいか なかったということがあります実はですね まコバックス結論から言うとその目標には 立つ圧できなかった様々な要因があるん ですけれどもま1つはその2021年3月 以降にですねワクチンの供給最大国である インドであの新型コロナのえ感染的な感染 爆発まアウトブレイクが起きましてインド 政府はですね自分たちで作ったワクチン 自分の国でしか使わないという感じで輸出 規制をしましたあとヨーロッパの国々でも ですねあのえま他に優先する前に自分たち の国で輸出を規制するというようなことも ありましたえあとはですねあの供給料が 結構2022年になるとだいぶあの潤って きたんですけれどもえ逆にですねその ワクチン摂取え供給はできても摂取が なかなかあ摂取率が上昇しない摂取率の ド化というものが起きてきました下の コラブでもえっと特にですねあの低中所得 国の支援対象国となっている国々で初め はいよくあのワクチン摂取が進んでたん ですけどもやはり5月ぐらいになりますと 摂取率も上がらないもしくはワクチンの 摂取がえ10%未満の国がど全く減らない という状況がえ続いてきます ま特にワクチンのえ摂取率が低かった国が ですねまここにあげているような国々なん ですけれどもその中でも私はえ私が注目し ましたのはま太平洋国の1つであるパプア ニュージニアという国をにちょっと焦点を 当ててえ研究をあのさせていただきました この太平洋告というのはすごくあの新型 コロナウイルス感染症に対して非常に厳格 な あのみえっと対策を取っておりましてあの 驚くべきことに2022年の1月時点で ですねまだ感染者0という国もあの数多く ありましたえそんな中でまパパネジニアっ ていうのは非常にちょっと感染者数が 多かったというのはですねまインドネシア と国境が国であの陸続きで続いてるという ことやまあの先ほどはあのその国境風鎖と いう形であの感染者ゼロをしてる国が 多かったって言ったんですけどパパ ネギニアに関してはあの非常に早い段階で 国境をあの解放したりといったことがあっ たのであの非常に感染者数も大きくなっ っていましたしあの全体があの把握でき てるのかって言うとまこれのもっと多い あの感染者数がいたんじゃないかなという 風に予測されております でじゃあこの国々にまあの新型コロナ ワクチンをま分配してでワクチン精がどう いう風に結びついたのかをあの示したのが このグラフなんですけれどもえ大線グラフ がワクチンの摂取率で緑のオ来線グラフが ワクチンの摂取率でえ防グラフの方が ワクチンの供給率を示していますえ強制率 がま高くてワクチン接取率が高い国って いうのがもちろんいい国なんですけれども ま見ていただいて分かるようにえ右側の方 には供給していてもワクチン性率がそれに 追いついていない国々というのがあげられ ますの中の1つがですねまパパニアなん ですけども確かにワクチンの供給率も 7.4%と非常に低いんですけれども ワクチンの摂取率もそれの1/3以下と いう形で2.5%という形で非常に低く なっております 逆にですねまワクチンをま供給もっとし たいパパやニュキルニアにもっとしたいと いう国々はたくさんありましたし コバックスもワクチン摂取をえしてもらい たいのであのこの国を支援したいという 意向はあったんですけれどもなかなかこの 国にえっと支援を供給したとしてもそれが 接取りつかないという現状がありました その背景としてまいろんなことが考え られるんですけれども1つはまワクチン体 あの摂取体制の脆弱性というものがあり ましてそもそもの基本的な保険医療 サービスこの新型コロナのえっと危機的な 状況になる前からやはりこのあのパパニア というのは色々な保険医療サービスの脆弱 性があの指摘される国でありましてすごく あの難しいえ状況になっております保険 医療移住所の数も少ないですしそれが一気 にコロナになったから増えるわけにはなら ないのでそういった難しさというのがあり ますしあとはこういったあのワクチンに 関するまご情報といったま情報が流れてま 宗教に関連したデマなども流れましてあの こういったワクチンを打つことに関する 寄費感というものがあ高まったというよう な状況もあります 逆にまあの受益者との関係で言うと先ほど も申しましたようにこういった あのバーナブな国だからこそあのえ支援し たいというあのドナーはたくさんいますし 特にド内にとってはですねま人口のすごく 大きな国大きな国を支援するよりもですね こういった島国をあの支援する方が自分 たちの支援が貸視化されやすいって言った こともありますしあの近隣の諸国の オーストラリアミュージーランドにとって は時刻の感染対策にもあのつがることにも なっていきますので非常にあのこれらの 国々を支援する意義というのはありますし まああのワクチン摂取率の供給量も高くて ワクチン摂取率もすごく高い国っていうの はもうあのなんというかパートナー国がい てそこからあのワクチン摂取の支援をあの 非常に受けていたという風な形もあります そしてこれらの国々においてもですねその 厳格な国境風鎖によって感染予防をしてい たんですけれどもそもそも古らの国々が 外貨とかを獲得しているのが観光観光産業 なんですねなので観光産業を1刻も早く あのま再開したいそうでなければもう経済 的にかなり苦しいっていうような状況にも 追い込まれてましたのであのワクチン摂取 をあの進めていきたいというニーズはあの あったあですけどもなかなかあのま特定の 国特にパプアクニアでは進みにくい状況が あったという風に考えられていますその点 をま踏まえるとですねやはりあの1番え 今後のパンデミックに向けて強化していか なければいけない点というのは平事におけ るあの保険医療システムの強化をしていく ことがあの非常に大事になってきますし その平事の備えなくしてまこういった危機 的な状況に対応することというのが非常に あの難しいというのはあの皆さんもあの 感覚的にもあのご理解いただけるかなと 思いますそしてですねこういう困難におい てはですねコミュニケーションをどういう 風にあの取っていくかというのが非常に 大事になっていきますやはり政府に対する 信頼感というものが少し由来でいるま危機 的状況になった中で由来でいく中であのま 丁寧なというか初段からの コミュニケーション医療従事者とか例えば えま宗教関連のあの牧士さんからのことで あれば あのその言うことを信じてみようみたいな コミュニティ同士のま信頼関係がある中 そのそこの信頼関係をうまくの保険やこう いう対策にもあの生かしていくことでえま そういった危機的状況にもあのスムーズな コミュニケーションが取れるんではないか なという風にえ考えておりますこういった えことも今後あの話し合っていってあの次 のパンデミックに向けてしなければなら ないんですけれども実はこのパンデミック 次に向けての対策っていうのが今結構ト座 している状況になっております1つまあの 難しく状況を難しくしているあ事例として はえWHOではですねこのパンデミックを 受けてよりあのなんていうかえ対策を強化 していこうという形でパンデミック条約と いうのをま加命国全体でえ19国以上の 国々とえ結びたいという風に考えています がこの条約自体がまだまだえ締結にはええ ま あの締結期限を決めたんですけれども なかなかえ締結できず今延長という形で 話し合いが続いておりますその総点となっ ている点が1つはあの医薬品のアクセスま ワクチンを含めた医薬品のアクセスに 関するえ情報がかなりヒートアップした 議論になっていますえ日本もそうです けれどもこう所得国で自分たちでまあ言っ てしまえばワクチンを作れる可能性のある 国というのはですねあのやはりどうしても その制約会社のあの利益というのを守り たいという風な方向になりますので知的 財産の保護といったものをあの割と全面に 押し出すえ形であの考えてを進めています けども途上国においてえ特に提出所国自分 たちではあの開発まではできないんだけど もあの生産はできるというような国々は その特許をなくして生産する権利を欲し いっていう主張もできますしでもっと言低 所得国におきましてはまずそれをえっと 自分たちで作れるような技術移転を支援し て欲しいというようなあの要望があります その技術の支援っていうのは日本とかも ジャイカを通じてあの積極的にやられて いくあの部分だと思いますし私もそれ自体 はあのすごくあのいい方向の話し合いだと は思うんですけれどもなかなかあの先ほど 言いましたように保険医療システムのあの 全体の強化がえなされないとそういった 技術者っていうのも育っていかないので あの人筋でもう1年2年とかいう単位で あのすぐできるものではなくて10年20 年かけてしていかなければいけないあの 課題だなという風にえ感じておりますそう いったことがありましてあのますぐに次の パンデミが起きるというわけではないん ですけれどもこの兵士からのえ え保険義量システムの強化というものをし ていかなければえ第2第3のパンデミに 向けてあの対応していくことえ危機的な 状況に対応していくことというのは非常に あの難しい状況だなという風に考えており ますのでえ皆様と一緒にこういったえ機会 を持ってえ定のおけるま保険移動システム についても考えていければなという風に 思っております私の方からはえ今回の発表 はこれで終わりにさせていただきますご 成聴いただきましてありがとうございます はい若林先生ご発表ありがとうございまし たえ貴重なお話を聞かせていただきました でここからあの質疑応答の時間とさせて いただきますえご質問のある方はチャット 欄にご記入をくださいますようお願いし ますちょっと時間の都合上全ての質問にお 答えできない場合がございますがえご了承 くださいはいそれではえご質問お待ちし てる間にちょっと私の方から質問させて いただきたいと思いますえっと今回先生の あの森沢さんのお話でえま私自身あの コバックスの仕組みについてあまりこう あのまそれほどあの理解をしてるという わけではなかったんですけどもそういった 仕組みについてあの色々と教えていただき でまたあのそのま仕組みのメリットをです ねここについても色々と説明をして いただきましたそれからワクチン狂器の 流れですとかあ2021年の2月からあの 供給がちゃんとされてたんだっていう ところですとかあの非常に新しい新しいと 言いますかあの忘れてたこともこう 思い出させていただいて非常にああの有義 なあの発表だっだと思いますそれからあの 供給料と接取のギャップですねあのまそう いったあのま課題があったんだなっていう とこちょっと改めて知るところでしたしま パップはニュギアのニギアの例を1つ上げ ていただいてえま文化的なまあの考え方 背景などもこういったあの摂取にすごく 関係してるっていうところを改めてあの 感じる画面がございましたでまた次の パンデミックへのまあの働きかけとして 保険システムを強化していく必要があると いうことえただ一方でそれがちょっとし てるというちょっと若干不安な気持ちに なったりとかしながらあのなかなかこう WHOがあの質金があの出さないよと言っ てるあのま国もあったりしながらですね あの今後どうなってくのかなっていう次の パンデミックはどうなるんだろうっていう ちょっとあの不安も感じながらまでもあの 日本が例えば技術移転あのワクチン ワクチンの開発に向けての技術移転があの ま様々なあの開発と上国でできるかもしれ ないということでちょっとその辺りは何か 日本ができることがあるのかなということ であのちょっと明るい気持ちになりました はいあえでえっとちょっと早速質問が来て おりますのでえ よろしいでしょうかねえっとワクチン摂取 の格差に関する重要なテーマについてご 講演ありがとうございました 日本国内へのワクチン開発そして途上国への提供を強化するために今後のパンデミックに向けた具体的なロードマップえ例えば大学制約会社企業政府など検討されていますでしょうかというご質問ですがいかがでしょうか [音楽] はい質問いただきありがとうございます そうですねあの日本国内でのワクチン開発 については今回すごくま政府としても遅れ たというようなあの認識を持ってそのどう いう風な形で具体的にあのしていくかと いうロードマップもすでにできていますし そのロードマップに向けてあの大学やあの 制約企業へ働きかけをあのしているという のがありますでそしてそれを途上国にま 影響強化していくっていう段階がまま 繋がればよりいいんですけれどもあの やっぱりアウトブレイクの発端になる リスクが高いのは日本よりもそういった 途上国ですのでそういったところと強化し てまその言ったらウイルスの病原金とか そういったものをあのいかにま日本に提供 してもらって研究に生かすのかといった ところをま 話し合い特に東南アジア地域とのあの連携強化というのをあの中心に今行っている最中という風に認識しております [音楽] [音楽] ありがとうございます続きましてコロナワクチン廃棄率や副反応率などのデータはありますでしょうか?という質問が来ておりますがいかがでしょう はいえっと日本国内で言いますとその副ま 日本国内だけじゃなくて副能率については グローバルなものも含めてあの全てえっと あのWHOの本でも提供していますしあ WHOが認証したえっと役品に関しては そのフォローアップという形でえっと データ出ておりますしえ日本でおきますと その厚生労働省の本であのホームページで も副率のデータも随時あの更新あのされて いますでこのワクチンの廃棄率というのは ですねま普段でも約2割弱あるんです けれどもあのなかなかどういう風にあの 計算するかというようなあの問題もあって 私もまいわゆるあのま推定値という形で 推定させていただいたんですけれども なかなかにされているあのデータその ものっていうのはあのないというのが現状 となっています はいありがとうございますえっと続きまし てえご発表ありがとうございましたという ことでえと平等なあワクチンへのアクセス についてどういったことがあ求められると 思いますかとえ例えばまあのレイスですと かえボーダーですとか エコノミックコンディションなどをまそう いうものをに関わらずあの平等にアクセス するにはどういったことがあやられるべき だと思いますかという質問ですが ありがとうございますは日本語でいいん ですかね Icansaytheoneofthe most importantvalueofthe vaccineisprevention and theoneonesloganbig sloganisnooneissafe untileverybodyis safethat’sthemost importantsloganso thewetrytoemphasize theeverybodyshould betrytoprotect someofthe peopledu totheirallergy somethinglikethat butifthealmost90%of thepeoplevaccinated that’sthepopulation minorpopulationalso protectedbythe immunesystemsothat wayweneed toemphasizethe benefitofthe vaccinationbutof andallyeconomicis barfordistributing thevaccinationasI showthat todayasaJapaneseI buttheJapanalsotry togetthevaccinealot andthatcausedthe priceofvaccineis gettinghigherand theks tobuythevaccinein thebeginningvery earlybeginningthat kindofthingswas occursotheweneedto consideraboutthe integralizationand howwecanbecooperate witheachotherthatis verybutnowthemen菊先生 mentionaboutthekind ofpoliticalissue abouttheglob ありがとうございますあのまコバックスと いえばあのワクチン供給だけじゃなくてま 冷蔵保存のあの技術ですとかますごい低音 であのワクチンを保存しなきゃいけないと かあの輸送インフラの強化にも貢献し たっていうますごくいい部分もあったり 全くワクチンを大量購入するってことで もうワクチンをの価格を下げるって先生も おっしゃってたようなまそういうあの価格 交渉力も高まったっていうあのま背景は あったんですけどもでもあの一方でその あのままコバックスが掲げていたその持っ てるものも持ったざるものも平等にという あのそういう考えでま全ての国に20%の あのえ分の人口の20%分のワクチンを あの平等に提供しようっていうまそういう あのま狙いもあったと思うんですけれども また方で先生がおっしゃってたように先進 国ではそれぞれの国で開発したりワクチン を開発したりま独自のルートで手に 入れようとしたりとかまそういった流れも あってまそこにあの平等にこうああの配置 されたこワクチンが配置されたことであの 平等だけどなんか不成になってしまっ たっていうそういったこともあったかなと いう風に記憶しておりますがま例えば先生 のあのご同僚の方々の間でまそういった こう点に関するディスカッションとか なんかございましたでしょうかはい ありがとうございますやはりあの平等に 分配するのと公平に分配するのというのの 議論っていうのはつきないんですけれども やはり構成にあの分配しようという風にし ましたらやはり少しプロセスをクリアにし てどれぐらいどの国にっていうプロセスも 話し合うあのメカニズムっていうのがまた ベッド用意コバックスの中ではされてるん ですねでそれ自体があのなんていうか時間 がかかりすぎるというようなあのご批判を いただいたりとか逆にですねあのちょっと 今回はあの言及しなかったんですけど初め の提案国にですねま最大のグローバル ヘルスの最大のゾア国と言われてる アメリカは入ってなかったんですねでま それは政権の問題があったんですけども そういったま独自路線を行くというような あの国があのやっぱり出てくるとなかなか この連帯感というものがあの高まらずあの 公平にしようと思っても公平に仕組み自体 はあってもそれがうまく働かないという バリアがあのできてしまうなという風に あの感じていますのでそれに関しては すごく大きなあの懸念があああってあの 我々もなんなんか運次第なところが少し あるなというのはあの同僚とも話してい ましたしもうこのコバックスに携わってい た同僚自体はあの本当にあの一生懸命あの そのえもう寝ずに感じであのやっていたん ですけどもなかなかその大きなあのその 自分たちのコントロールを超えた力という のはなかなか難しいものがあるなというの は非感じましたあ本当にそうだと思います ありがとうございますちょっと最後になり ましたけどもあの先生あのこういった国際 機関ですとかまあの日本の象徴して海外で のあの活動いっぱいされてきてあのまそう いったあの海外での活動をこう目指してる 方々も今日聞いてくださってるんじゃない かなと思いますそういった方々に向けて 何かこうメッセージなどございましたら よろしくお願いいたしますはいありがとう ございます本当にあのまグロバルヘルス 大変なお話もいっぱいさせていただきまし たけどもまずはた楽しいというかいろんな 方々とそういうあの国境をこうやってあの 共同してあの何か1つのことを作り上げて いくというのがあの私自身は非常に楽しい なという風に考えていますのでまずあの 特にですねま私もまだまだですけどもその 若い方々が海外に出てそういった経験を あのしていただくということが非常にあ あの大事になっていくと思っていますので そういった相互理解がある上であの物事を 進めていくとこういった国際協力のあ全般 の世界をどんどんどんどんあの話し合いが スムーズにほその部分はあの一旦置いとい て人と人とで繋がっていけるんじゃないか なという風に考えていますので是非あの どんどんあの積極的に海外に出ていって 欲しいなと思います先生ありがとうござい ました 本当に本日あの大変しぎ飛んだそしてあの考えさせられるあの非常に良いあのお話を聞かせていただきました本日はどうもありがとうございましたではこれにてえ終了させていただきます ありがとうございました ありがとうございました菊口先生若林先生ありがとうございました 最後に事務よりご案内させていただきます まず次回のブラウンバグセミナーの内です は来週3月12 日水曜日12時10分より九州大学人間学 研究員投資建築学部門の 水広る教授より建設住宅主会峰の家と建築 学生が取り組む被災地支援 活動プロジェクトと 講演を実施いたします商材はホームページ をご覧ください
Brown Bag Seminar No. 179 Associate Professor Mami Wakabayashi
[Title] Responding to a public health emergency through the global distribution of COVID-19 vaccines
※講演資料:https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/events/events-bbs/2012/
※English Presentation Materials:https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/en/events/events-bbs/2016/
*Q-AOS ウェブサイト:https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/
*Q-AOS Website:https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/en/
*Q-AOS Facebook:https://fb.com/115565526935234
*Q-AOS Twitter:https://twitter.com/Q_AOS2019
*九州大学アジア・オセアニア研究教育機構:https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/
*Kyushu University Institute for Asian and Oceanian Studeis:https://in2fs.kyushu-u.ac.jp/en/
*プレアドミッション・サポートデスク (PSD):
https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/admission/pre-admission
*Pre-admission Support Desk (PSD):
https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en/admission/pre-admission
*List of Graduate Programs (taught in English):
https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/graduate/
*List of admission offices (in English):
https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/invitation/contact/
*Global Gateways:
https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en
#九州大学 #九大 #KyushuUniversity #Kyudai #KyushuUniv #アジアオセアニア研究教育機構
#InstituteforAsianandOceanianStudies #QAOS #qaos #ブラウンバッグセミナー #BrownBagSeminar
#BBS #公衆衛生危機#PublicHealthEmergency #新型コロナワクチン #COVID-19Vaccine #COVAX #国際
保健外交 #GlobalHealthDiplomacy