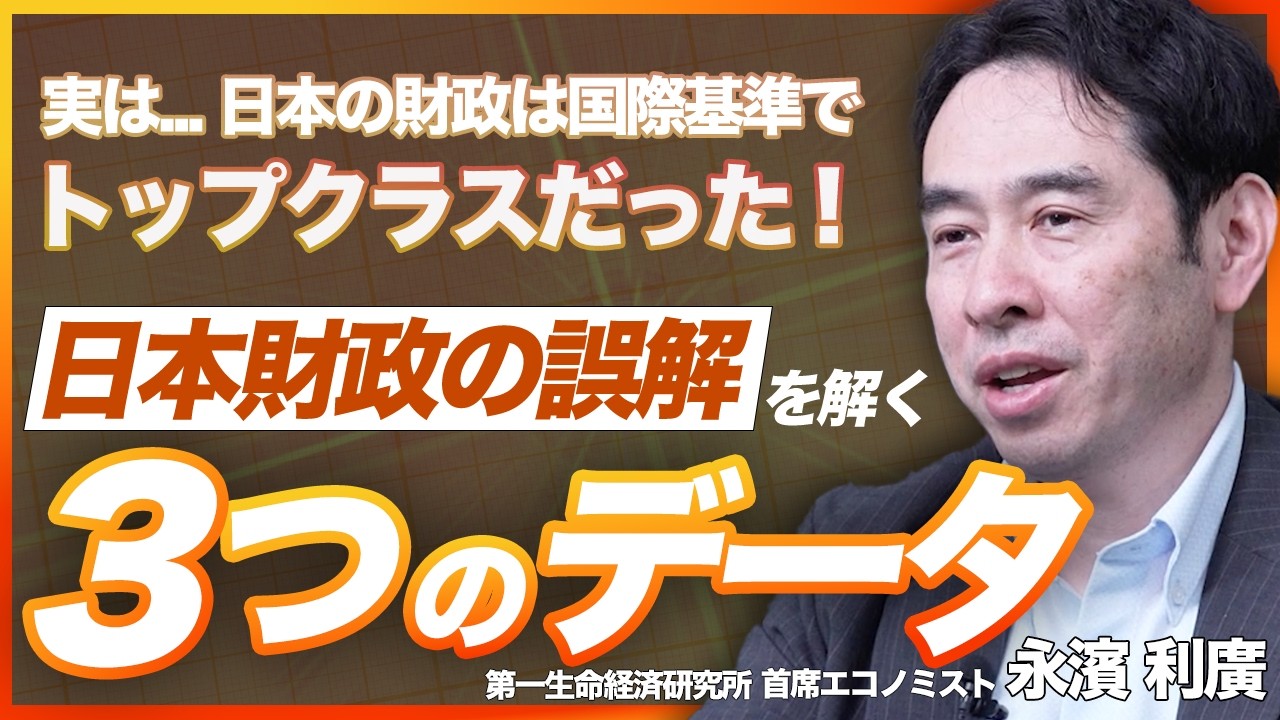消費減税 VS PB黒字化…なぜメディアは財政を税収のみで評価しようとするのか?今こそ国際基準に合わせるべき!(第一生命経済研究所 首席エコノミスト 永濱利廣)【ニュースの争点】
やっぱすでにもうあのマーケットで影響が 出てるんですけども、やはりアメリカ国際 の格下げと、ま、端的に言うとやはり、ま 、アメリカ売りのですね、え、状況になっ たとアップデートされた最新のそのマクロ 経済とか財政の考え方をですね、え、最近 市場の関係者の方がみんな理解してるかと いうと、ま、必ずもそうではないいうわけ ですよね。はい。 ま、今起きてることというのは何が起きてるかというと、実は国際の日本国際の、え、いわゆるデフォルトリスクが高くないにもかわらず実際に日本国際のですね、え、購入に関しては結構こう手る動きが出てきてるわけですね。 ま、一方でこう石橋総理大臣はこう日本の財政はギリより悪いという発言をしました。どのように受け止められました? はい。はい。プライマリーバランスの プロジっていうとも何で出てきたかって 言うと実は元々のう出発点っていうのは 政府債務残高GDPを下げるってところが 最初の起点だったです 。本日のニュースの総点は第1生命 経済研究所主席エコノミストらっしゃい ます先生をお招きし経済日本経済の問題を お聞きします。先生本日はよろしくお願い します。 え、早速なんですけれども、ま、まずアメリカが、ま、体中完税の引き下げを行いました。ま、これはやはりこう、ま、中国最大の貿易相手国でもありますから、やはりこう完全政策の、ま、限界みたいなところで仕方なくっていうところなのでしょうか。 はい。そうですね。やはり、ま、これまでの関税というのがですね、え、アメリカが中国の輸入費に対しては 145% で、ま、中国は逆に125%とうん。 ま、いうところなんですが、やはりかなりアメリカと中国というのはですね、え、未だにですね、え、貿易的なその経済の関係っていうのがありますから、やはりそれをそのまま、ま、続けていくとですね、え、そもそも、ま、アメリカ経済、さらには、あ、トランプ政権の有権者にもですね、え、ま、人大な、ま、経済への影響を及ぶと いうところで、え、ま、情報したのかなと。 ただそれでもですね、ま、115% ずつ下げられたとはいえですね、 え、中国からアメリカの輸入品には、ま、 30% の関税、え、で、中国から、あ、アメリカから中国に輸出するとこについても、完全 10%をかかるわけですから、 ま、そういった意味では、ま、影響は、 あ、ま、避けられなくてうん。ふん。 で、仮に実際にですね、あの、前回の 2018 年からですね、米中の追加完税が始まったわけですけども、あの、その時に実際にそのマクロ経済的には、あの、ま、どれぐらいのタイミングで、え、影響が出たかというのをですね、え、確認するとですね、え、実際にあの、非農業部の雇用者数なんかで見ると はい。ま、追加完税のおかけ前回、ま、3 月ぐらいから始まったんですけど、実際に雇用者数に明確な悪影響が出てきたので 7月分からなんですね。ふんふんふん。 すると、ま、今回もですね、え、足元ではまだそこまで明確な追加税の影響っていうのがアメリカには出てないわけですけども、ま、おそらく夏場以降ですね、 ま、かなり出てくるのかなと うなってくるとですね。え、ま、これからね、いろんな国とのその交渉も進んでいくと思うんですけども、 ま、実際あまりにも影響が大きくなってきたらですね、え、ま、中国以外の国に対してもですね、ま、少し情報の姿勢を示す可能性はあるんじゃないかなと思いますね。 うん。なるほど。はい。 なるほど。ま、そうした中でですね、ま、あの、アメリカの米国祭の格付けが、ま、下がるというニュースもありました。これはどういった影響があるでしょうか?はい。はい。ま、これすでにもうあの、マーケットで影響が出てるんですけども、やはりアメリカ国際の格下げという。 え、いうところで、ま、端的に言うと、やはり、ま、アメリカ売りのですね、え、状況になったと。 ま、具体的に言うと、え、株価が下落し、国際が売られ、え、ま、ドルが売られと、ま、いうことになったんですね。ただ、あの、ま、これに関してはですね、ある意味その財政関連のデータを見ると、 ま、格下げされても仕方がないのかなと いう状況だったと思います。 で、それなぜかというとですね、あの、こちらのグラフ見ていただきたいんですけども、ま、このグラフ何かというと、 2024 年の、え、G7 諸国の財政収支と経済成長率の関係を見たもので、特にご注目いただきたいのが横軸なんですね。これが 2024 年時点でのおG7 諸国の財政字のGDP を見たものなんです。はい。 で、これ見るとですね、え、1 番左側がアメリカになってるということはこれ 2024年の財字G7 でアメリカが、え、最も財産ア赤字がですね、え、大きかったと いうところなんですね。 で、一方で、ま、これ結構あの意外かもしれませんけども、これ見ると実は 2024年で1 番財政が少なかったのがカナダ うん。なんですけども、2 番目に少なかったのが日本なんですね。 日本は財政のGDP費、ま、2.5% ぐらいではい。 え、つまり2024 年時点で見て、え、アメリカの財産アジっていうのは日本の財政 GDPの3倍近かったと。 あ、そんなに違うんですね。 はい。いうことで、ま、非常に財政的に厳しかったわけですし、さらにまた別のデータで見るとですね、 え、これがですね、え、G7 諸国の政府債務残高、政府金融債務残高ですね。 え、のGDP費を見た。なんですね。 で、このグラフ見ると水準だけを見ると、ま、日本がダトで高いと、ま、いうことになるんですが、あ、直近期 204年はい。の変化を見ると ちょっとこれだけじゃ見にくいんですけど、実は、あ、 G7諸国で2024 年の政府債務残高GDP 費が下がった国というのは日本だけです。 他の国は全部政府金融債務残高のGDP 費は上がってるんですね。 ふんふんふんふんふんふんふん。 つまりこれどういうことなんでしょうか? うん。ということは、あの、2024 年のいわゆる国際基準で見た財政指標を見ると、え、やはり政府債務団高 GDPが上がったのが、 特に上がったのが財政が拡大したアメリカ うん。なので格下げになりましたと。 一方で、え、唯一改善した国っていうか日本なので、え、今足元で、ま、アメリカの国際の格下げなんかにも引っ張られて 日本の長帰国裁が上がってますけども、 え、これはどちらかというと日本の財政状況が悪化したというよりも、やはりアメリカの国際の格を通じて、え、国際的なその、え、債権市場の、え、ま、混乱を通じた、 ま、影響の方が大きいんじゃないかなということが言えると思います。 なるほど。 ま、こうしたこう格差下げっていう、ま、いわゆるこう、ま、国際の格付けで今回格下げですけれどもによって、ま、いわゆるこう国際マーケットは金融市場で、ま、影響あると思うんですけれども、ま、実際のこう財政運営を制限するわけではないですよね。こういったものが。 はい。 えっと、それアメリカ、 アメリカに限らず、ま、日本でもそうですけども、こういったこう国際の格付けっていうものが実際の政府の財政運営にこう制限をかけるような言論も見られるわけですけれども、実際運営上全く問題ないわけですよね。 はい。えっと、これがですね、結構微妙なところでして、 あの、短期的に考えるとですね、 え、それこう理論的に考えたら、あの、全く問題ないんですよね。うん。うん。うん。 特に日本に関しては、アメリカに関しては問題ありますけども。 あ、そうなんですね。はい。 え、ただですね、え、これやりそのいわゆるアップデートされた、あ、いわゆる最新のそのマクロ経済とか財政の考え方をですね、 え、最近市場の関係者の方がみんなに理解してるかというと うん。ふん。うん。うん。 ま、必ずもそうではないわけですよね。 はい。 で、実際に、ま、今起きてることというのは何が起きてるかというと、実は国際の日本国際の うん、 え、いわゆるデフォルトリスクが高くないにも関わらず はい。 実際に日本国際のですね、え、購入に関しては結構こう手替える動きが出てきてるわけですね。 うん。 で、それはなぜかというとですね、え、ま、具体的な財政とかはあまり意識せずになんとなくなんか、あ、各政党が消費限税を訴えているので、なんとなく財政やばそうだな。 うん。 なんとなくちょっと今の段階で国際買いにくいよね。 うん。ふん。ふん。うん。 ま、みたいな状況になってるということからすると、ま、全く問題ないわけではないのかなという風に思います。 はい。なるほど。 ただに、あの、じゃあ、あ、アメリカの国際が格下げされて、 ま、そのタイミングの後もやっぱ日本の特に調長期規なも上がってるんですけども はい。うん。 じゃあその辺のタイミングで、え、よくね、その各国の国際のデフォルトリスクを見る上で重要なん、 ソブリンCDSのデフォルト確率。はい。 ま、これを見てみるとですね、ま、こちらのグラフなんですけども、ま、これ国際の格が決まった 505 月の半ばぐらいのデータなんですけども、ま、これ見るとですね、え、デフォルト確率が 1番低いのがドイツうん。う、で、2 番目が日本ちょっと今足元ではイギリスによりも高くなってる可能性がありますが、まあ、 23位横イギリスと争ってる状況。 一方で、え、格差ゲになったアメリカはですね、やはりイタリア、イタリアについで、え、デフォルト確率が高くなってるわけですから。 うん。うん。 ま、そういった意味では、ま、アメリカの国際の格下げは国際金融市場的に見ても、ま、ある程度、え、ま、整合性があったとは思うんですけども、若干今の日本国際のですね、え、会が手えられてるというのはちょっと国際市場の関係者の過剰な反応の面があるのかなと。 で、もう1 つこれ、あの、実は別のデータで はい。 え、ま、興味深い動きがあるんですけども、 え、どういうことかというと、これね、ちょっと今日はグラフでは持ってきてないんですけども、え、 G7諸国のうん。 え、いわゆる長記載でも代表的30年の 利回りが、あ、4月以降上がってるかと いうのをG7諸国で、 え、比較をするとですね。 はい。やっぱ1 番上がってるのはアメリカなんですよ。 うん。 で、次に上がってるのが日本なんですね。 うん。ふんふんふんふんふん。 なんですけど、3 番目に上がってるのはどこかっていうと、カナダなんですね。 へえ。 カナダといえば、あ、G7 諸国の中でも、ま、資源国であって かなり財政があの健全な国と 言われているにも関わらず、うん。 はい。あ、3 番目に上がってるのはカナダです。 で、逆に、え、4 月以降長記載が、あ、下がってる国もあって、あ、ちなみにカナダの次に上がってるのはイギリスです。 あ、ふん。ふん。ふん。ふ、 アメリカ、日本、カナダ、イギリスが上がってる一方で、うん。 え、下がってる国どこか? なんと1番下がってるのがイタリアです。 財政が1番高いイタリア、イタリア、 フランス、ドイツの準ってですね。 へえ。なんかさっきの確率のずっとあんまり相関しないですよね。 そうなっておっしゃる。で、この関係はどういうことを意味してるかというと はい。 要はですね、いわゆる、ま、アメリカ国際が拡げされたことによってアメリカの金融市場と非常に関係性の深いアングロサクソンに近い国の国際が引きずられて上がって はい。はい。 一方で比較的アングロサクソン系の経済と若干関係が薄い うん。ふん。ふん。 地域の国際がの価格が下がってると いうことからするとこれはその各国の国際のリスクで、え、動いているというよりもいかに、え、アメリカの金融市場と、あ、関係が深いか薄いかによって うん、金利の上昇下落が決まってると いうことからすると、足元のアメリ、特に日本の長期載の利回りの上昇を通じて、確かに一部解する向きあるんだけども、 でもこれを持 日本の財政のリスクが高まっているかというと、ま、そういうことにならないんじゃないかと思いますね。 なるほど。こういった議論の時に私毎回思うんですけど、こう結局そのイールドカーブコントロールとかを日銀がやってたってことを考えると日本日本の国際に限って言えばですね、こう中央銀行が、ま、いわゆる金利もコントロールできるし うん。もしもとなったらこう国際買い取ればいいって思うんですけど、なんかこういろんな議論見てるとこう日銀にも なんて言うんですかね。 買う力はないとか誰が買うんだみたいな議論ってなんかこういつまでもあるわけですけれどもこの点いかがでしょうか? はい。はい。あの買うないのは間違いですね。それはなぜかついうと中銀行っていうのはですね、 え、いわゆるマネを供給できる はい。わけですから。だからないと でさらにま、これをいうのであればあの多分余力がないという意見のですね、背景にはおそらくマネの強しすぎるとま、円安になってしまうと。 うん。ふんふん。 え、いうう、ま、あの、考えもあると思うんですけども はい。 え、ただ足元についてはですね、ま、これ円安、円高出ればドリ安なのかもしれませんけどもう、 ま、そこで言うと一時期前に比べればですね、え、ま、円安に拍射ってしまうと、 ま、そういうリスクは、あ、ま、下がってきてると うん。 え、いうことからするとですね、え、仮にですね、これ長期の利回りがやっぱり市場が規模が小さいので、ま、結構やっぱりあの、ボラティが高いんですね。 うん。ふん。ふん。 うん。ただこういったところでその分市場が小さいので、え、仮に異常な動きをね、え、ある程度経済に応及すような大きい影響がお出てくるんであれば はい。 あ、それこそ中央銀行のオペであったりとか、 もしくは、あ、財務省の方がですね、 え、長の発行を減らすとかですね。うん。 ま、そういう対応をしてくればですね、え、そんな深刻なことにはならないんじゃないかなという風に思います。 なるほど。ありがとうございます。 ま、そうなるとやはりこうこうした、ま、なんて言うんですかね、長期金度き、国際マーケットの動きっていうのが、ま、財政運営上ですね、政府の財政運営上は特にこう日本の場合は制限かからないとは思うんですが、ま、一方でこう石橋総理大臣はこう日本の財政は議者より悪いという発言をしました。ま、どういう背景があるのかは分からないですけれども、この発言、ま、当然違うとは思うんですけれども、 どのように受け止められましたか? はい。はい。 ま、おそらくこれはですね、え、単純に政府債務残高の GDP費がですね、 え、ま、主要国で弾トに高いと うん。ま、ギリシャよりも高いと いうことでの出てきた発言だろうと思います。え、それで言うとですね、ま、先ほどもグラ見ていただきましたけども、まさに、 え、こちらのですね、図の4ですけども、 え、政府金融資産のGDP の水準だけで見るとうん。 日本は水準が高いわけですけども、一方ですね、こちらの図表の後でですね、これは逆にですね、 政府の金融資産高のGDP を見たものです。ほう。 えっと、基本的に資産とか借金とか見る時やっぱりトータルで見なきゃいけないわけですよね。 はい。 となると債務を見るってことは資産も見なきゃいけないと。 じゃあ資産を見たらどうかというと政府金融資産の残高の GDP 表見るとこれもですねトでトップなんですね。 そうですね。 はい。で、これで言うと分かりやすい比較で言えばですね、政府債務残高 GDP 費のGD はですね、アメリカと比較したら、ま、日本が 2倍弱ぐらい数字が高いわけです。 はい。あ、例えばアメリカであればですね、え、 100%超えてる状況で日本は200% 超えてるので、ま、2倍ぐらいあると。 そう。はい。 ただ政府金融資産のGDP 費を見ると日本はアメリカの5倍以上 うん。すごいですね。 持ってるわけですね。はい。 で、実際にその当然のことながら、あの債務はリバ来費が増えるわけです。 はい。 え、一方で資産からも利息収入が入ってくるわけです。 なるほど。 で、それトータルで考えなきゃいけないんですね。 はい。 となると政府の順利払費ってことで考えると確か今日本はカナダについて 2番目にいとうん。 で、さらにこれもよくやれる話なんですけども政府のリ払費がね はい。 すごい増えてから大変だという話があるんですけども、 金利ある世界みたいな話ですね。 そうです。 なんですけども、もう今で言うと、ま、多分年間やっぱり 9兆円ぐらいのロットで リ払が増えてるんですけども、ただ今国際の 約半日金銀が持ってるわけですね。 はい。と9兆円なら9 兆円こうリ払った分のもう半分近くがもう日品のからの国の納金で戻ってくるわけですね。 うん。うん。 だからそういったところまでのお金の流れを考えればですね、え、ま、日本の財政っていうのはそこまで、え、リスクは高くなくて、ま、それがソブリン CDSSの価格でも 反映されてますし、あとは例えば、あ、G 7 諸国でじゃあ資産と負債を合わせてみるのであれば純債務がいいだろうということで、この図 6 っていうのが政府準金融債務残のGDP です。はい。うん。 これなんであえて、え、金融、準金融債務にしてるかというと、金融にしてるかって言うと、よく実物資産はすぐ売れないとかって話があるので、 これ全部金融負妻負債と金融資産で企画してるんです。 で、これで見るとですね、実は、あ、政府純金融債務残高 GDP費、え、G7で1 番高いのはイタリアです。うん。 ま、次日本なんですけどね。はい。 ただこれ見ても分かる通り、え、改善度合を見ると実は日本だけ 4年連続で改善してます。 すごい伸び率ですね。 はい。え、あ、あとカナダですね。カナダと日本だけ 4年連続で改善してます。 他の国は悪化してます。 うん。ふんふんふんふん。 ってことからしても、ま、日本の財政っていうのは、え、物理的にはそこまで申告ではないんですが、ただこういったあの全倒なあ、財政理の考え方っていうのが日本の国際市場なんかにも十分浸透していないので、え、なんとなくなんか消費税が下がったら、あ、財政やばいかもという考えのもとなかなかあの国際があ、足元では消化されにくい状況になってるということだと思います。 本当に今のお話聞くと間違った現状認識で財政運営されてるっていうまさにその通りですよ。 あ、ま、これまではまあそうですね。はい。 なるほど。ま、実際ですね、ま、先生先日もこのチャンネルで消費税の限税の財源の話についても色々とお話していただきましたけれども、本当こうした話って財源論を出す人っていうのは はい。はい。認識するべき話ですよね。 ま、そうですね。ま、とはいえですね。 はい。 じゃあ全くを無視して政策が実現するかいうとですね、 それもなかなか難しいわけですよ。 うん。 となると、あの、私はやっぱり政策の実現可能性を考えるのであればですね、え、さすがにちょっとあの、プライマリーバランスっていう話になっちゃうとこれって日本だけしか出してないので、 それはさすがに難しいと思うんですが、国際標準的に考えてもですね、え、要は政府の債務残高自体が増えてもそれ以上に GDP が膨らんで政府債務残高のGDP 費が改善してればそれは財政は改善してるってことになるわけじゃないですか。 ってことを考えると、ま、足元のですね、え、政府の債務残高の GDP の改善ってやっぱりインフレで結構改善してますからっていう意味で私はあのある程度の規模であればですね、政府債務残高 GDP費をの下落下落方向を止めずに うん。ふん。 え、減税はできると思うんですね。 うん。なるほど。 なのでその範囲内での減税ということであればですね、ま、私はなんとかあのなんというか実現可能性は少し高まるんじゃないかなと。 ま、だってそもそも政府債務残高GDP 費をこうのが高いっていうのがそもそもの問題式だったわけですよね、日本って。 ああ、そうです。 でも下がってきてるわけですからね。でもあんまりこういう話って聞かないですよね。 そうです。そうですね。あのなぜかあのそもそもこれって世界標準的にもそうなんですけども政府債務高の GDP 費ってのは各国の経済状況によって適切な水準で違ってくるんですね。 うん。ふん。ふん。ふん。 例えばアメリカみたくアメリカって日本よりも企業部門が GDP費で2.5 倍も借金してる国なんですね。ま、そういう国だとやっぱりセフ債務残高の GDP ってそんなに増やせないんですけども うん。ま、 逆に日本の企業部門ってアメリカに比べたら債務をですね、借金をあの GDPで4 割ぐらいしかしてないわけですから。 うん。 ま、そういう国だと逆にその分政府債務残 GDP の水準っていうのはある程度適温領域として上げられる水準が高くて うん。 え、ただそれがね発散していっちゃったらまずいってことなんですけども、それは方向性が重要なんですけど、 ま、いくら水準が高くても、ま、方向性がね、改善しているっていう方向であればですね。うん。うん。うん。 ま、これでは別に財政の維持可能性としては担保されてるわけですからね。 ま、そういう考え方が、ま、重要になってくるのかなと。 ま、確か 本来はだから日本だと企業の貯蓄率が高い状態ですけれども、民間がこう企業が投資していれば はい。ま、あの政府債務残高GDP 費をま、もう少し閉める方向で考えてもいいけれども、ま、現在は 企業が貯蓄しているからちゃんとあの政府が財政出動するべきだよっていう安定ですけど本当にこう政府と家計と民間の本全体のバランスなわけですけれどもなかなかこういう話にならずに政府は政府だけはい。はい。 っていうことになりますよね。 はい。あ、そうですね。はい。 だ、そこの部分がやはりこれまで、え、ちょっと事実は、あ、マッチしてないような、 ま、政策が続けられてきた。うん。ま、1 つの要因で、で、おそらくその政府だけを 見て判断してきた最大の あの、ま、現象としてはですね、え、よく 政府債務がですね、あの、増えると増えれ ば増えるほど国際の供給が増えるほど、ま 、金利が上がるということがですね、 長らく言われてきたわけですけども、あの 、それに対して実は何が起きたかっていう と、政府債務残高が増えば増えるほど金利 が下がってきたことですね。で、それなぜ かって言うと、やはり政府部門だけの資金 受給だけでは金利は決まらないと、あ、 企業も家計も含めた民間問全体で、え、 決まってきて、で企業はそれなりに、あ、 政府はそれなりに、え、財政で、え、 いわゆる資金給迫していてもそれ以上に 家計と企業がお金を溜め込んで使わなけれ ば、ま、金利は上がらないとおまいことで さらに言えばあの金利が上がですね、それ 以上に名目成長率が高い人であればですね 必ずしも金利が上がったからと言って、え 、財政が悪化するとは限らないわけです。 で、それで言うと直近のデータで確認すれ ばですね、え、先般発表された、え、今年 13月の、え、GDPの経済成長率はです ね、え、これ確か実質4社期ぶりの マイナス成長ったわけですね。え、前期 年-0.7だったと思うんですけども、 なんですけども、え、前期年名成長で見る とプラ3%以上んですね。で、さらに、ま 、金利っていうのは、ま、1年前からどれ ぐらい利息が増えるかっていう意味で言う と、前年費が重要になってくると思うん ですけども、今の日本の長期金利が ちょっと上がってきて1.5%超えていて 、え、財政やばいて話になるんですけども 、じゃあ直近今年13月期のですね、名目 GDPの成長率前で何%伸びてるかと見る と5%増えてるんですよ。あ、そんなに 増えてるんですね。はい。 ってことからすると、あの、だから名目の金利よりも名目成長率が 3倍以上高いってことですね。 ってことからと、これってやっぱりかなりめちゃめちゃめちゃ財政が改善すると はい。はい。 いうことになるわけですから、 やはり金利財政話をする上ではしっかりとその名目成長率の水準感を見ないとミスリードしてしまうということだと思いますね。 その資産をなんかこういわゆるこう財性ま、特に財源の議論の時に特にこう最入と出語られるというかどうしても税収だけしか見てないような印象を受けるんですよね。 でも今の先生のお話を聞くと単に税収だけではなくてそうしたこう金利での収入とかもあるわけじゃないですか。 こうい、こういった話ってなんて言うんですかね。 こう議論の訴上に上がってこないんですか?実際のその政策、ま、国会運営ってかわかんないですけど。 え、いや、あの、ま、細かく予算を見るとですね。 はい。 ま、予算、補正予算、決算見るとですね、当然やっぱ税外収入とかも増えたりとか してるんですけども、 まだ残念ながらなんかメディアの報道ではそういったところには、あ、注目は集まらないですしうん。 え、ま、さっきから申し上げてる通り国際標準的には別にあの税収で全部馬な必要はなくて、え、要は政府債務が GDP 費が安定的に下がっていけばいいわけですから。 はい。 で、あれば、あの、いわゆる名目成長の拡大の範囲内のペースであればですね、え、債務残が増えても GDP比率下がってるわけですから。 はい。 ま、そういうですね、え、前提のもですね、ま、財運営をあった方が少し財線運営の柔度が拡大するで、実際に海外はそうやってやってるということだと思いますね。 となるとやっぱりこう新たなちゃん本当ちゃんきちんとしたマクロ経済運営する上での指標を政府が定めるということが、ま、多分 1番いいわゆるこうPB黒字ではなく はい。はい。 さっきおっしゃったように政府財務残高 GDP の現象の度合とかそれを見て判断するとかそういう指標を きちんと作るっていう議論を はい。 ま、今度選挙ですけれども、ま、そういった議論になっていかないとなかなかこう いつまでも財源の議論そうのにから抜け出せない。 特にその単年度中立過ぎじゃないですけども、 ま、どっかでね、え、減税するならでどっかで、え、財源が必要だと。 うん。うん。 なるとですね、え、それで結局トータルで減税にならないわけですよね。で、さらに言うとプライマリーバランスの黒字っていうともなんで出てきたかって言うと実は元々のうん、出発点っていうのは政府債務残高 GDP を下げるってところが最初の起点だったわけです。 なるほど。 で、じゃあその政府債務算残GDP を下げるためには必要な条件が2 つあって、ま、これがよく同条件って言われてるんですけども、政府債務残高 GDP 費が一定となる条件っていうのが1 つが名成長率とお金利が国際の利回りが一致する うん。ふんふんふんふ。かつもう1 つの条件がプライマリーバランスがあ、ニュートラル うん。ふん。 なんだけどもプライマリーバランスが導入されたもう 20 年以上前ですけどもこの時っていうのはディフレの状況でなかなかその名成長率があ金利を上回るっていう状況が環境は厳しかったので、 え、そういう中でも政府債務残高GDP 表下げるためにはプライマ最低でもプライマリーバランスを黒化しなきゃいけないというところでプライマリーバランスがあ、ま、あのこう日のみを見たというかうんっ てことなんですけども今ではもうインフレになってるわけです はい。 国際上りやすくなってるわけですかね。で あればなんかプライマリーバランスの黒字 が1人ありきするんではなくてそもそも 政府債務残高GDPっていうのが最終目標 として1番注目されてそれの部分的な要素 としてプライマリーバランスともう1つは 名目成長率と国際利回りの関係っていう形 でま、総合的に判断していくということが 重要でそういう判断をしていけばもう少し えま財政の改善を続けながら少しの余地が 出てくる ということになるのかなと思います。 なるほど。本当にもう今こそその切り替える絶好の機会はないっていうことですね。じゃあもうそうですね。状況変わってるってこと。 いや、おっしゃる。だから本当にここ数年で、え、ま、結果的にきっかけはロシアのウクライナ進行でしたけどもそれによって、え、日本企業の価格転換メカニズムというのは復活して、 え、で、かつ人手出手不足の状況もあったんで、え、まだ公循環まで行って、行ってないかもしれませんけど、物価と賃金がとりあえず上がるようになってきたと。 うん。はい。 で、そういうことになるとですね、え、ま、少なくともあの名目の成長率は金利も上がりやすくなるわけですね。 はい。 ただ残念ながら足元の状況を見るとあのぶ賃金以上にぶっか上がっちゃってるので 家に幸せが行っちゃってるわけですからとなると名目成長率が上がったことによる財政の改善度合の部分を一部財政の改善があ失われない範囲でえ割ってる家計の方に そ配分がいくようなうん、 ま、そういう政策が、ま、必要なんじゃないかなと思いますね。 ありがとうございます。 え、本日のニュースの送点は長浜俊先生をお招きし、世界経済、日本経済の問題についてお聞きしました。またこのような情報を広げるためにもチャンネル登録と高評価をお願いします。先生、本日はありがとうございました。 ありがとうございました。เฮ
ご視聴いただき、ありがとうございます。
ぜひチャンネル登録、いいねボタンとコメントをお願いします!
「ニュースの争点」では
・日本の将来に役立つ知見
・ニュースを見ているだけでは見えてこない社会の構造
を専門家の解説とともにお届けします。
他にも、テレビや新聞では聞けない専門家による
ニュース解説や特別座談会・対談コンテンツを配信中です!
↓↓永濱利廣先生出演回↓↓
【消費税減税は可能か?】反対派の意見に徹底反論!即効性がない?格差増?未来負担増?(第一生命経済研究所 首席エコノミスト 永濱利廣)【ニュースの争点】
【アメリカ景気後退か】トランプ大統領vs.FRB…日本への影響は?/-警戒ーマーケットは楽観的すぎる(第一生命経済研究所 首席エコノミスト 永濱利廣)【ニュースの争点】
↓↓オススメのコンテンツ多数↓↓
なぜ日本企業は世界から出遅れたのか?/日本人の足を引っ張るエリートの罪(中野剛志・施光恒・古川雄嗣・岩尾俊兵)【特別座談会Part1】
【丸わかり】トランプ政権ブレーンの脳内/PayPalマフィアが目指す世界とは?(思想史家 会田弘継)【ニュースの争点】
なぜ私たちは学問をするのか?/学者同士の争いが無意味なワケ/議論と論破の違いとは?(評論家 中野剛志×儒学者 大場一央)特別対談前編