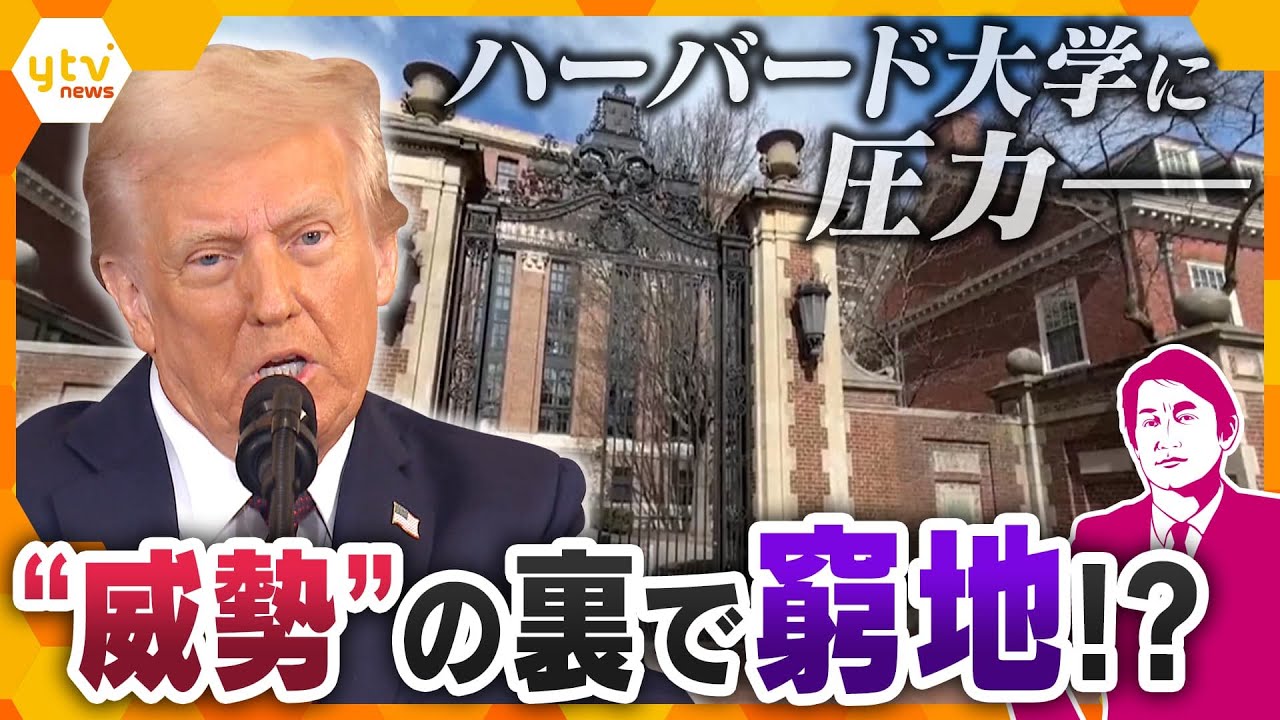【タカオカ解説】ハーバード大学などへ“圧力” トランプ大統領の頭を悩ます「学生の影響力」 問われる中間選挙までの「75週間」
高岡目線 トランプ大統領今度のまた揉めておりますが、え、揉めてる相手は有名大学でございます。 で、あの、もちろん日本にもね、あの、東大兄弟を、ま、筆としまして有名大学たくさんございますが、あの、実は米国はハーバードとか ね、え、スタンフォードだとかもう世界的に名知られた大学あるわけですが、そこと、え、トランプ大統領は補助金を打ち切るぞ。留学生多すぎるからもうビザ取り上げるぞ。結構圧力をかけて揉めております。 ただ怖いのはね、大学、特に世界の大学は世界につがる影響力を持っております。そこで今日のタイトルは最終的に追い込まれるのは大学側でしょうか?トランプ大統領でしょうか? どこまで本気なのかはね、分からないところではあるんです。 ま、ちょっとあの完税のように相手の国との交渉で解決するものではなくて私が見るにこの問題の方が世界的裾のが広いです。 ですので、どこかで着地点を探らないと、ま、ある意味帰り立を浴びるというような問題でもあります。え、助金をカット外国人の留学生もう出てってもらいたいというようなことを言い、大学は一歩も引かず、え、裁判所に訴えて憲法違反だということで、これあのハーマドに限りません。 え、ま、世界に直しられた大学ですけれど も、どの大学にもですね、いずれこの刃が 設向けられるとということで大学側は大変 な危機化を持ってるということなんですが 、さ、日本でも、え、やはり有名大学が ございます。え、東大もあります、兄弟も あります。私シリーズでも早稲田同士者と かね、こう色々ありますけれども、日本で もありますね。え、どこどこ大学のOB ですというOB会がありますけども、実は 、あ、米国あるいは世界の有名大学の出身 者ってのはそれを名乗るってことは実は 日本よりとても大事です。で、というのは ですね、あの貧しい国もあります、豊かな 国もあります。特にハーバーなんてのは 我が国の官僚も留学をしてます。 ですから、あの、大学にそれを受け入れるということはですね、え、どこどこ大子出ましたねということが世界共通の価値観にもなります。ちなみに我が国の公室はですね、留学をされるのは英国のオークスフォード大学と大体皆さんそうなんですが、これもオクスフォードの 1 つの世界共通のブランドということも影響をしているということになります。さあ、そこで はい。はい。ハーバードでございます。 はい。 OBを有名人を探したら多すぎて 選ぶのに3時間以上かかりました。 そんなに、 え、まさにハーバード大学はもうあえて正式国家名をかわせただきました。アメリカ合衆国の歴史エリートを象徴しております。厳選して 6人です。はい、どうぞ。 え、まず大統領が普通にいます。 え、バマさん、それからもう日本の政治家方でも尊敬してるが多い、え、ジョン Fケネディさん。え、高合様もそうです。 え、それからですね、 ノーベル賞162人もました。 え、知らない人を選びました。私が はい。カープラスさん。 ええ、偉いんです。以上。はい。 え、ビルゲさん。はい。もう有名です。もう我々はもう世界がお世話になってるね。このコンピューターを便利にした人。 はい。はい。ナチャリーポマンさんです。 え、アカデミーです。 ハーバードです。すごいね。 すごい方がたくさんいるのよりました。 す、さらに宮屋で私の横にいるパックもそうです。 はい。あ、7人紹介しました。 で、米国はですね、ま、効率大学もたくさんあるんですが圧倒的に梅大学率が多いんですね。 ということになりますと高い 学費がそうですね もうね普通に行って1000 万クラスがゴロゴロというところなので学生さんみんなあのローンだとかあるいは小学金とかいう方が多いんですがこれがトランプさんの指示層から見るとですね うん まアメリカ人から見てもアメリカの中でも代々のエリートじゃないかと でさらにトランプさんが避難するように海外から来てる人もみんなエリートじゃない。いや、そりそうなんです。 エリートを受け入れてそれぞれの国のエリートにまた戻っていくからアメリカの力を強くするという発想もあるんですが実はトランプ者よくマガと言われます。あの赤い帽子がお好きな方々です。 皆さんやっぱりそれぞれの地方で地元で暮らして地に同税をしてという方からするとお払った税金で外国人の勉強させてんだと いうような声をトランプさんは大弁してるおつもりなので、やはりそのトランプ審者のこ、ま、ガス向きという意味合いでも今回の、ま、こういった大学を、ま、言葉きついですが締め上げるということもですね、あの、トランプ指示者からはそんなに反対がない。ちょっと事後小さくしましたけど。 アメリカ人はこれが響くんですよね。トランサージにはアメリカ人が入学するためのアメリカの大学じゃないのかと。これはやっぱりその赤い帽子を被ってる皆さんにもうストレートに響くわけですね。 で、怖いのはさあ、こっからです。 あの完税はそれぞれの国との交渉ですが 学生さんってのは米国では大変な力を時に持ちます。 うん。 戦争を左右します。戦争するかしない かってのはもちろん大統領含めて権力の 最高のまあその力の行師なわけですが、え 、これ黒木さんなんか生まれる前です。え 、長く続いたベトナム戦争は学生さんの 反対でもから始まって、だって学生さんは 自分が戦場に行くんですからということで 、え、実情、ま、政権が始めた戦争を 終わらせたと。そして今の戦争はガザの 進行です。ですから、え、トランプ大統領 としてはですね、やはりイスラエル指示を 明確にされてますので、え、そのアラブ系 から、あ、留学しているこういう学生さん たちが、これ、あの、ニューヨークの コロンビ大学ですけども、こういった 反イスイスラエルのデモをするというのが 、ま、許しがいというところもあるんです が、この力が大きくなればなるほどですね 、やはりこういうことになってきます。 反線の反が反整政権になってくると。そう するとね、やっぱり学生さんたちの先ほど 申し上げた世界からの留学もいらっしゃい ます。うん。 世界にその反が広がるということがありますが、片や一方でやはりあの世界から留学生を受け入れてきたということがこう米国の強さというものを広げてきたんですね。その人間が大統領の数にいます。はい。 うん。この人です。そう。 大体この人は南アフリカ出身でカナダの大学に行ってました。で、米国に留学したんです。 留学生なんです。 で、米国に行ってから会社を作り、 どんどん会社が大きくなり、今や大統領のすぐ横にいるわけです。 ただですね、やっぱりあのこのイロマスクにも徴されるように世界中の若い人たちに夢を与えるってのもこの国の特徴でしたよね。で、我が国です。 で、我が国もですね、未来への繋がりができるかもしれないという期待を抱いてアメリカに行かれてリーダーになってる筆が実は今 トランプさんと1 番合ってもらえてる人です。 はい。うん。 え、この方もあのカリフォルニアの大学に行ってそこでいいろんなあの先端産業の後のリーダーたち、 え、と、ま、交流をして、え、今やもう世界有数の投資家になっておられるわけですね。 で、世界はじゃあ今回のこの件をどう見てるかってです。で、やはりあの世界有数の頭脳も集まってるわけですから。ノーベル賞 162 人ですから。そうするとそのアメリカから出ていけともし言われてしまったら私のところで引き受けますというの争奪性になっておりまして筆頭が香港と書いてますが当然後ろに中国がいます。で、香港はもう今中国ですから 無条件で受け入れます。 うん。うん。 もう無条件という意味はね、もう学生さんが家がないんです。ああ、もう家はうん ねえ。研究者あ、 もう全部用いたします。 で、EU はですね、もう現金融の額を明らかにしました。 800 億円のもう資金を用意してますから。 どうぞ皆さん言てくださいます。 我が国です。相変わらず遅い。 うん。 全大学に受け入れ検討を政府は依頼をしてります。 検討してる間に持ってかれるよということなんですが、やはりね、我がよく言われます。こういう時に優秀なあの技術者あるいは研究者を逃してしまうのは 1も2 も未だにそうです。あの医療関係の人なんかが日本でえ、免許取ってもらう時に日本語で試験あるんですよね。で、これあの世界中からやっぱアメリカに行かれるような英語があるってこともありますが日本語 1 からやってから来いなんて言ってたらそれはもう全然違うとこ行かれます。 さらにですね、やっぱり彼らはあの学生さんたちは世界的に学生さんたちはこれを見るんです。暮らしやすいですか?すいません。わざと安さと書いてます。今米高いです。はい。それから大学の設備ね。え、これももうあのアメリカの大学は素晴らしい設備です。寄付金も多いで 1 話ね、これ卒業後どうなるんですか?ということなんです。で、そうするとね、あの私インドで、え、ある工業大学に行った時に隣の部屋で面接やってました。日本の就活と違います。 学生行かないです。え、Google が来てます。Apple が来てます。で、日本企業もみんな来てます。あの、面接を逆に受けてくださいって来るんですね。え、皆さんオファーは初人休数千万クラスです。 うん。 だから日本の学生さんみたいに入ってから頑張りますじゃないんですよ。もういる間に何の論文を書きましたかと。あなたどんな発明を目指してますかということでこれぐらいのお金をもらう人たちがこれから世界が取り合いになるかもしれない。それですさにうん。はい。 やっぱり彼らが求めるのはビジネスフード。 ですね。で、アイデアが出る。それをすぐにビジネスにしようじゃないかと。お金持ちが応援をしてくれますし、だからシリコンバレってのがやっぱりあるわけですよね。はい。 だから、ま、こういったところをあの日本が提供できないとどうなるかという。ただやっぱりその政治家側は難しいのはですね、あのアメリカの 1 つの弱点でもあります。いいところでもあります。あの自由民主義ですよね。 うん。 ですから選挙もありますということになると未来のこの長さが学生さんてのは遠い未来を支えてくれますが、近未来がやっぱり政治家にはやっぱあるわけですね。で、そうするとね、着地点どうするんだろうって話なんです。で、ここはね、私あえて申し上げると完全と似てるようなことをやると思います。あの、トランプ大統領って完全もそうですが、必ずまず自分でハードル作ります。ゴーンとハードル上げます。ゼロに戻すとメンツを失うので、完全もこう言いましたね。 中国もだいぶ負けてもらいましたね 。私の配慮で下げてあげる。私優しいから いう風に言って、え、やらないとですね。 あの、指示率もちょっと今厳しくなってき てます。それからGDPもマイナスになっ てきました。で、え、やっぱり公約した ことはあのね、留学生の問題もそうですが 、関税もそうだし、アメリカの黄金時代を 作るというところだから、やっぱ落としど いるわけですよ。そうすると0 にはしないけれども、今も日本完税交渉やってますが、かなりちょっと下げる。だから留学生も 3 割出ていけって言ったけども、じゃあ 15% は残っていいとかいうような具体的な数字が実は 1つのうん。期間がありました。 アメリカのメディアがよく言いますが、あと 75 周に迫ってます。え、2026年の11 月の3 日アメリカの中間選挙ですね。はい。 で、この中選挙のとはですね、え、やっぱり、え、トランプ大統領の権力が今後維持するかどうかということを左右するわけなんです。ですからやっぱりそこに向けて、え、は、妥協してくるだろうと言われてます。 はい。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録是非お願いします。 月曜から金曜の夕方は関西報得10点。
先月、アメリカのトランプ大統領が語気を強めて攻撃したのは162人ものノーベル賞受賞者を輩出した名門・ハーバード大学。火種となったのはイスラエルによるガザ侵攻をきっかけに起きた全米の大学での抗議デモです。ハーバード大学に対し、外国人留学生を受け入れる資格を取り消すと通知。さらに、自身のSNSで、連邦政府から支給されている助成金30億ドル=約4300億円を打ち切る考えを明らかにしました。アメリカ屈指の名門大学に攻撃の手を緩めないトランプ大統領。露骨な圧力の背景には何があるのでしょうか。徹底解説します。
(かんさい情報ネットten. 月曜・火曜は「タカオカ目線」2025年5月27日放送)
★「タカオカ目線」は毎週月曜・火曜日20時半からプレミア公開!★
(都合により時間が前後したり、配信を取りやめる場合がございます。予めご了承ください)
▼タカオカ目線の再生リストはこちら
▼読売テレビニュース
https://www.ytv.co.jp/press/
▼かんさい情報ネットten.
X(旧Twitter)https://twitter.com/ytvnewsten
webサイト https://www.ytv.co.jp/ten/
Instagram https://www.instagram.com/ytv.ten/
Facebook https://www.facebook.com/ytvten/
▼情報ライブ ミヤネ屋
https://www.ytv.co.jp/miyaneya/
▼ニュースジグザグ
X(旧Twitter)https://x.com/ytvzigzag
webサイト https://www.ytv.co.jp/zigzag/
▼す・またん!
HP:https://www.ytv.co.jp/cematin/
X(Twitter):@sumatanent
Tweets by sumatanent
Instagram:@sumatanentame
https://www.instagram.com/sumatanentame/?hl=ja
TikTok:@sumatantiktok
@sumatantiktok
▼読売テレビ報道局のSNS
TikTok https://www.tiktok.com/@ytvnews
X(旧Twitter) https://twitter.com/news_ytv
▼情報提供はこちら「投稿ボックス」
https://www.ytv.co.jp/toukou_box/
#読売テレビ #ten #タカオカ目線 #読売テレビニュース #高岡達之 #かんさい情報ネットten
#ハーバード #大学 #圧力 #トランプ #反戦 #学生運動 #アメリカ