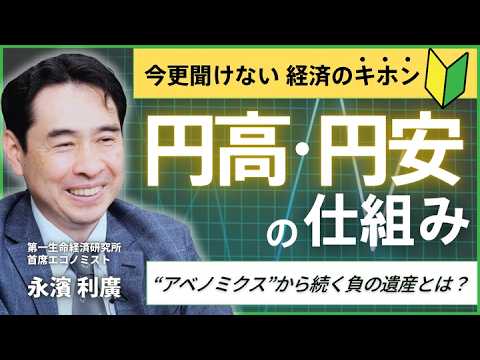【経済超入門】「円安=悪、円高=善」は罠?/新NISA戦略と意外な投資リスク(第一生命経済研究所 首席エコノミスト 永濱利廣)【ニュースの争点】
私たちの生活にとって円安と円どっちがいいのっていうところで時刻の経済状況が加熱してるのか冷え込んでるのかでも変わってくるのかなと思うんですね。円安で 1 番投行する経済主体って国内って家計企業政府ってるんですけど恩恵を受けるのは政府と大企業なんですね。 とかくその金縮財政をいう方々って一刻の 経済って家計と企業と政府があるのに政府 のところだけにですね、焦点は当てがちな 感じがします。なんでこんな日本経済停滞 してきたかというと、なんで今日本の供給 力がこんな減っちゃったかっていうと、 安倍のミ薬水勢までずっと行き過ぎた円高 放置してしまったからこそ国内からですね 、あの生産拠点が空道化で出ていって しまってで供力減って色々な物足になっ ちゃって 。 本日のニュースの送点は第一生命経済研究所の長浜俊博先生をお招きし、ま、現在のわせの問題、またそもそも円高円安って、ま、何なのかという本当基本的なところから、あ、日本経済の問題についてお話を伺います。え、本日はよろしくお願いします。 よろしくお願いします。 え、ま、まず本当基本的な質問なんですけれども、ま、円高円安って、ま、ニュースで見て、ま、ここ 23 年は円安で、今現在こうトランプ政権になってからはちょっと、ま、 円ダカにっていう言いながらも はい。 ま、まだまだ昔の基準からすると円安だなと思いながらニュースを見ているわけですけれども、そもそも円高円安ってこう決まった金額っていうのがあるのかとか、じゃどういう決まその仕組みで決まっているのかっていうところを教えていただけますか? はい。あ、えっと、ま、これ円高円安って何を基準にするかによって見方も変わってくるんですけども はい。 ま、基本的に、ま、替って、あの、どういうものかというとですね、ま、 2国間の通貨の交換比率なんですけども、 え、その中でもあの記軸通貨がドルですから はい。 ま、基本的にドルに対してそれぞれの国の通貨が、あ、ドルに対してどれだけ上がってるか下がってるか、 この比率を見たのが、あ、ま、かわせで、 え、で、これが基本的に過去よりもドルに対して円が高くなれば高、 あ、過去に比べて、え、ドリも円が安くなれば円安。 うん。ふん。ふん。ふん。 というのが、ま、基本的なあの方向性になるんですけども、ただ中にはこうね、水準で、え、見る意見もあって、で、これも水準もどこが基準になるかによってかなり変わってくるんですけども、多分 1 つなんですかね、我々の実感に1 番近いところで言うと、例えば企業企業経営者の方々なんかに望ましいかせレートっていくらぐらいですかってアンケート取ると大体 130円ぐらいなんですね。へえ。そう。 うん。となると仮にじゃあ130 円ぐらいとするとですね、え、今まだあの少し円高に触れてきたとはいえ、まだ 140 円台ってことはあ、ま、方向は円高に触れてきてるけども水準としてはやま安かなと。 ま、そういう方もできるっていうのがあります。うん。 はい。あともう1 つ経済理論的な側面でくと公倍力陛下っていうのがあって はい。 これ何かって言うとあ、ま、端的に言うとアメリカで買っても日本で買っても同じものが同じ値段で買える。 うん。ふん。ふ。 ま、だからビッグマックスてあるありますけど、あれの うん、 初物価全体で見たようなで、それで見るとですね、実は IMFとかOCD が計算していて、それで計算するとですね、実は公倍力陛下ってドル円で見ると 100円切ってるんですね。へえ。そう。 それから見ると今めちゃめちゃ円安という見方もできますけども はい。 ま、ただそれはあくまで理論的な話なので はい。 え、まあ、多分方向性から言うと過去よりも上に行ってるか下に行ってるか、あと水準で考えると、まあ、多分今だと平均で 130 ぐらいを基準に上かしたかっていうのでエンダーがいやすっていうのが なるほど。一般的な見方かなと思います。 それでやっぱりこう日本がずっと長らくで触れで物価が上がってないから はい。 公倍力陛下がそんな下がってるっていう目もあるんですか? え?あ、そういうことになります。 ああ、なるほどなるほど。 ありがとうございます。 で、そうなるとこう次にじゃ、私たちの生活にとって円安と円高どっちがいいのっていうところで はい。はい。はい。 ま、やっぱりこうからの物価高を見ると円高の方がいいのかなって思う人もいる一方でやっぱりこの 30 年の日本経済を見るとやっぱ円高のデフレだったわけでそうした中ではい。 じゃあて言ってこう製造拠点が はい。 海外に出て日本が空洞化してった中で、ま、やはり雇用が不安定化していったっていう局面もあると思うので、 どっちがいいのかなって難しい。 うん。 ですけれども、先生はどのように考えてらっしゃいますか? え、ま、これもろんな切り口があると思うんですけども、 え、まず1つ目の切り口としては 自刻の経済状況が、 あの、ま、加熱しているのか冷え込んでるのか うん。ふん。 でも変わってくるのかなと思うんですね。え、どういうことかというと、特に経済加熱してるような状況、こういう時っていうのはむしろあのインフレが高まりやすくなっちゃうので、え、ま、時刻通貨がですね、高くなって移入品が安くなると でかつ要は円高になるってことはそれだけ経済を冷やす効果もありますから、ま、そういう時というのはあの円高の方がましいと うん。うん。 一方でまだ国内の経済があのんでる、ま、ざっくりと需要不足的な状況に、 え、ある場合はですね、え、ま、あまり行きすぎてもね、あの円高で円安で割り置く人もいるので 行きすぎちゃまずいと思うんですけども、ただやっぱり国内経済がまだあの不的な、あの厳しい状況の時にはやっぱり円安気味な水準を維持して、え、やっぱり GDPOを引き上げて、 え、不足を解消すると。 うん。うん。 いう方がいいのかなという見方がまず1 つありますね。はい。あとはあのやっぱり当然円高の方がいい人円安の方がいい人ってこう人というか立場にと分かれると思うんですね。 うん。うん。 で、円安の方がいい人たちってどういう人たちかって言うと はい。 個人で考えると、え、おそらく、ま、大企業とか輸出関連級に務めてる人 うん。ですね。はい。 で、こういう人はやっぱりあの円安になるとこれもね、経済主体別で見ると結構分かりやすいんですけど円安で 1 番投稿する経済体って国内って家計企業政府ってあるんですけど、 え、恩恵受けるのは政府と大企業なんですね。 大企業はグローバル展開してるんで儲けが増えます。 っていうことプラスなんですけど。 で、え、政府についてはやっぱり円安になると物価が上がりやすくなるし、え、大企業が儲かってやっぱり税金払ってる企業のって大企業が多いので 税収も増えると いうところがあるんですけども、一方で短期的にやっぱりマイナスの要素っていうのが強いのが、ま、家計かなと。うん。 うん。それをやっぱりあの、買うものが高くなってしまいますからね。 そうですね。うん。 ただ、まあ、大企業とかその円安の恩受けを受けられる企業に染めてる人であればですね、タイムラウが伴って給料が増えるっていう則側面もあるんですが、円安になって全く恩恵ほぼ受けられない人っていうのは、 え、働かずも働いてもいいなく、さらに投資もしていない、もう年金暮らしをしてるような、あの、深夜の方々、 こういった方々からするとですね、え、当然あの年金っていうのはマクロ経済なんで うん。 あの、物価は下がった方がいいわけですよね。 うん。ふん。うん。 となると円高の方がいいですと。うん。 で、別に円高になって景気悪くなって給料が減る方が関係ないですね。 はい。 要は円高で、え、年金が減りにくくなって買う物のが安くなる音恵しか 受けないので。うん。そうですね。 そういう方々で取ってみれば高いと なるほど。いうことになると思います。 なるほど。はい。 ま、一方でこう昨円安だった時に悪い円安論って、ま、散々聞いたわけですけれども はい。はい。 で、その後、ま、日本銀行が、ま、利上げをしててなった時にや、どこかこう円安って悪いもの はい。 で、円高の方がいいんだ。 ま、金の正常かっていう言葉がそうだと思うんですけど、何かこういう 理想的な状態があるようなイメージを、ま、いわゆるこう日本銀行のメッセージとかいろんな、ま、エコノミストの方の意見から感じるんですけれども、 やっぱそこはこう長浜先生とは違う意見っていうのが結構あるわけですか?はい。 なんかいわゆるそのこ正常な状態だとか そうですね。 円がいいとかなんかそういう意見って多いんですかね? はい。多いですね。 あの、特に国内の主流派、あの、あ、ま、学者の先生とか エコノミストに多い考え方ですね。 ま、一言で主流派って言ってもちょっとね、海外と日本でも主修流派てはちょっと違っていてですね。 はい。 で、え、そこでじゃどういう、どうしてそういうこう私からすると違うと思ってるんですけど、どうしてそういう思考になるかというと、現状の自分の例えばあの経済を体に例えると現状の自分の体調があどういうのかを度して理想的な姿ばっかり追い求めてしまってるっていうことです。 なるほど。なるほど。だ、 例えば理想的な姿がですね、え、近流の体型だとすると ま、そうなるにはですね、やっぱり筋トレとか激しい運動した方がいいわけですよね。 うん。 で、経済が正常な、体が正常な時であればですね、え、激しいトレーニングをすることによって理想的な体になるわけですけども、ただそれをですね、え、例えば病気の時にですね、筋トレなんかやっちゃうとですね、え、病気がさらに悪化してしまうわけですね。 そうですね。余計体調悪くなりますね。 はい。 で、そこで要はそのじゃ、今の日本経済の状況が人間の体に例えたら健康な状態なのか、不健康な状態なのか、 ま、多分ここの判断で見方がかかってくると思うんですけども、おそらくう、ま、円高で、え、例えば、ま、利上げもして財線も閉めていった方がいいと いう風に主張される方はおそらく今の日本経済のことを健康状態という取られてますね。 うん。うん。うん。 ただ私は、ま、私だけじゃないですけども、あの、そうじゃないという人たちっていうのは はい。 え、やっぱり今の日本経ってまだ健康な状況じゃないと うん。ふん。ふん。ふん。ふん。 ま、よく言ってやみ上がりはい。 となるとやはりちょっとそういった金融財政の引き締め正常策っていうのは、 ま、接続なんじゃないかなと。 ま、そういったところで判断が分かれてくるんじゃないかなと思います。うん。 なるほど。 いや、そう思うとそいつたどうやって日本経済の現状っていうものを分析してるんですか?だって要はその同じデータを見て、 ま、ちょっと答えにくいかもしれないです。同じデータを見て 調べるものが違うわけじゃなくて、同じデータを見て解釈するわけなので、 日本経済の現状分析に違いが出るっていうのがなかなかこう一般人からするとあ、 はい。 お、想像ができしづらいんですけれども はい。 だからね、これあくまで私の憶測ですけども、もしかしたらこういう考え方があるのかなっていうのが 1つあってはい。 え、例えば、あの、やはり、え、ま、政府と中央銀行って、まね、政策当局があるわけですけども、やっぱりね、え、政府がね、その財政策をやる時っていうのは最大の目的っていうのはやっぱり財政策って 国の財政運営っていかに日本経済全体を発展成長させていくかと うん。ふんふんふ。 え、ま、いうところがですね、え、最大のポイントだと思うんですね。 はい。 ただこれもその主の学者の方なんかもよく言うんですけども、とかその縮財ういう方々ってもうあの一国の経済で家計と企業と政府があるのに政府のところだけにですね、焦点を当てがちな 感じがします。はあは。それ例えばあの、 要は政策当局者になっちゃうとやっぱりね 、え、国の財政とかそこはやっぱりね、え 、当然直接を轄してるわけですから、そこ に目が行くのは、あの、ま、仕方がない ことかもしれませんけども、例えば 分かりやすい例でいくとね、私ももう エコノミストやって世紀ぐらいなんです けども、私があのエコノミストに成り立て の頃、あの、上からというか、いろんな人 からこう学んだことの政府の借金が増える と国際の授業が必迫するから うん。ふんふんふん。あ、金利が上がると うん。教えられてきたわけ。 はい。今でもよく聞きますけどね。 うん。でもあのその後起きてきたこと何かって言うと、政府の債目が増えるば増えるほど それと反例して金利が下がってきたわけですね。 うん。うん。うん。 それでなんでこういうことが起きてるかって言うと、要は結局その金利って何決まるかって言うと、政府部門だけのお金の授業で決まるわけじゃないわけですね。 家計も企業も全部ひっくるめて考えるわけで、え、となるとあの政府債務残一方で日本では不興だから家計もお金使わないし、ま、企業も貯蓄しということで結局国内全体で経済悪くてお金が真内でお金が余ってたから気にかかなかったわけですね。 そういう形でその本来マクロ経済全体で見なきゃいけないのに部分的なところに商点が行ってしまうと おいうのが1つあるのかなと。 それで言うと、例えば、あの、これも金融政策も一緒だと思うんですけども、日銀の金融政策もですね、あの、最大の目的っていうのは物価の安定と金融システムの安定だと思うんですけども、え、それよりもですね、やっぱりこう中央銀行の当局にいるとですね、そういったマクロ経物価とか金融システムよりも やはりとかくその中央銀行のバランスシートとかそっちの方にこう 意識が行きがち なあの嫌 が私あるんじゃないかなと思っていて あるし企業経営者的な視点になってしまうと。そうそうそうそうそうそうそう だってよく言うじゃないですか。あの ま、日金がね保有してる国際自価会計すると あの含み損が出てますとかね。言う人いますね。要はこう日銀が債務長会になるみたいな。 はい。 でも一方で、あの、それ以上にETF の、え、自、自価総額でね、え、価値が上がってるんですけども、でもそれって、え、これはね、あの、ま、上田総裁、ま、以前の黒田総裁も国会で答弁してますけども、別に日銀の財務状況って、え、その国の金融政策のですね、機能に悪を及ぼすことはないって言ってますから。うん。 ただやっぱり中にはやっぱりそういう風な考える方々もいるかなと。 うん。 で、さにうとこれは特にエコノミストはそうなんですけども、やっぱりあのエコノミストってえ、ま、民間団に属してる人が多くて うん。 大体民間って、ま、金融期間にあることが多いですね。 はい。ふんふん。 で、そうなるとですね、やっぱり金融期間って日本経済全体で考えると経済ないのに金利が上がることは悪いことなんですけども はい。 経済がそんな良くなくても金利が上がるとですね、金融機関にはプラスなんですね。あ あ、なるほどなるほど。 ま、それ収益増えますもんね。 はい。となるとやはり、ま、金融期間に近い い、ま、組織の、ま、イコノミストはそういうバイアスがる人もしかしたらいるかもしれない。その可能性もあるということですね。 ま、そういったところが影響してるんじゃないかなと思。 なるほど。なるほどなるほど。 え、それで言うと、その例えば今は、ま、新兄さんも始まってこう政府が投資を推進してますけれども はい。 となるとよく言うのはS&P とか、ま、アメリカ米国株とかそのう外国の投資商品に投資するっていうのが、ま、いろんなこう YouTube とかで見ててもそういう声ありますけれども、ま、一方で買わせがこれだけ動くと投資の分の利益を買わせの再でペ、ま、総裁されてしまうことだってあるわけで、 いざ投資投資って言われてもじゃあこうしたこう替わせたいなところてあんまり一般の人ってわからないと思うんです。 ですけれども、ま、どういう風に替って考えたらいいんですか? 川せディスク。え、そうですね。 えっと、ま、ある程度理解したら分かると思うんですけども はい。 当然ね、あの、円になれば、あの、要は今までよりもあの、少ない円でドルが買えるわけですから、 そう返せばドル建てのものは円に対して下がるわけですね。 でもこれで実は結構あの誤解されている方もいらっしゃって じゃあ例えばあの円そういう買わせリスクがあるから SP500 とかオルカンよりも日経平均の方がいいかって言うと実は日経平均もご案内取り円打高になったら日経益金も下がるんですよ。 うん。うん。となると実はあの円打ての SP500 とかオルカンと日経平均と比較しても実はパフォーマンスそんなに変わんないんですよ。 なるほど。なるほど。 だそういった意味からすると実はあんまり買わせて株式投資に関しては うん。ふんふんふん。 あの、そこまで意識しなくてもいいのかなと。あの、特にあの、長期みたいのインデックス型投資で考えたらですね。はい。 いいと思います。うん。なるほど。て、どちらかというと、やっぱりこう買わせて影響が受けるのは、ま、日本の大企業や、ま、そういった一般人からすると、ま、生成食品のような輸入品の物価とかそっちの方が結構身近だってことですね。 はい。あ、そうですね。はい。すぐ聞いてくるので。うん。うん。 やっぱ輸関連産業は利益が増えて起きる増えるのってやっぱ 1年ぐらい遅れますから。はい。はい。 はい。はい。 目先はそのあの悪のがあ、顕在化しやすくて、 え、恩恵が受けにくい。うん。 ただ裏をせばじゃこれまでの日本経って特に安売り返るとなんでこんな日本経してきたかというとなんで今日本の供給力がこんな減っちゃったかっていうと安倍ノミクスゼまでずっと行き過ぎた円高放置してしまったからこそ 国内からですね産拠点が空動化で出ていってしまって で狂気力減って色々なもの不足になっちゃってるわけですから、 ま、そういうこと考えるとやっぱり円高も行きすぎるとよくないと うん。 ま、いうことをやっぱり言えるんじゃない。 ま、そうなると本当にこう柔軟に状況を見て、ま、せ政策、ま、金融政策ですね。金融政策と財政策を打てる柔軟な政府やま、中央銀行が必要であるというのがすごくよくわかりました。先生の話を聞いてると。 あ、ですから、あの、やっぱ連携が必要なわけですよ。 うん。うん。だ、 例えば今みたいな状況であればですね、え、ま、結構円安が生きすぎてる感じじゃないですか? そうですね。うん。 なんだけども円安が行きすぎてる一方でその恩恵もあって政府の税収は過去最高更新し続けてきてるわけですね。 うん。はい。 え、となると本来であれば、あの、ま、そこまでね、え、そのせを無理やり高にするような利上げをするよりも ある程度演は、あ、放置をしときながらですね、え、ま、上振りした自をですね、円高で苦しんでいる方々や主体に対して、え、手当てすると いう政策の方が、あの、経済全体のですね、あの長いめには成長率にとってはプラスなのかなと。 うん。 やっぱ円安の方がですね、え、国空内の立プラスになるわけですからね。円高になっちゃうとやっぱりね、 立競争力マイナスになっちゃいます。 そうですね。 で、それもやっぱり政府と中央銀行の連携が必要なんですけども、ただ今の日本の場合だとある程度その政府の方が財政記率が強いのであまり財政出したくないので、ま、その分、ま、日銀が、あ、あの、ちょっと悪影響あるんだけども、 ま、利上げを、ま、進めて、 え、円高に円安に行き過ぎなにしてると、 ま、そういう対応に見えるかなと思います。 なるほど。ありがとうございます。 ま、最後の質問なんですけれども、ま、もっかこうトランプ政権の完税政策によって非常に世界混乱しておりますが、ま、日本もそうですけれども、 こう現在の変動相場す、え、変動替せ相場性の状態だとあんま完全政策 に意味がないっていう人も一部いて、より安になれば相細されるんだみたいなことを言う人もいるんですけれども はい。 ま、このでも実際完税政策によって買わせが動いたりもするわけで、 この辺りこうそうなんて言うんですかね、そんな理論通り行くとも思えないんですけれども先生こういった意見どのように 感じられますか? はい。あのはい。あの、その可能性もあると思います。 ただ一昔前に比べるとそので調整されてしまう力は弱まってる可能性があります。 どういうことかというと多分そなんでそういう考え方になるかというと例えば完税を貸すことによってですね はい 要はだからトランプその貿易赤字を減らそうとしてるわけですね できることな貿易黒字にしたいと うん で仮に貿易黒字にするとなるとですねえこれ一昔前だとやっぱり替せの変動って統期的な要因もよりも実の要因が大きかったんですね。 例えば今では貿易収支とかわせなんてほとんど関係ないですけど昔は アメリカの貿易収支とかわせって結構連動してたんですよ。 へえ。 となると完税をかけることによって貿易赤字が縮小し仮に黒字とかなると さらにドル高が住みやすくなるんですね。 うん。 そうすると当然輸出する側からすると安くなるからおっしゃる通り追加完税かけてもその分時刻通貨が 輸出する側の通貨が安くなることによって 完税の効果で薄れるとうん。 そういう考え方だと思うんですけど今はまさに私申し上げた通り あの買わせて実よりも 金融政策とかその登期的な要因によって大きく左右されてしまうのでうん。 その相細されてしまう効果っていうのは人昔に比べると小さくなってると ああは言えると思います。 ま、それだけこう金融市場がもう拡大してはい。 そうです。いるとそうです。 なるほど。なるほど。 だ今まで一昔前までは昔はだからその替っていうのはどちらかというと貿易とかそういった本当に実物経済の取引取引によって買わせの売理解が うん。 中心だったのが今では圧倒的に何も買うわけでもなくお金儲けのために 川わせ市場で真似が取引されてる。 こちら圧倒的に大きいので。そうするとだからこそあの例えばあ、替と、え、金利差なんかうん。 比較するとですね、結構連動するじゃないですか。 うん。 で、これも一昔前はですね、え、アメリカの貿易収支と買わせて連動したんですよ、結構。 今全然連動してないですね。 てことからするとはい。やっぱりあの、取引が変わってるので、昔ほどはそういう状況にならないと思います。うん。なるほど。ありがとうございます。いや、非常に勉強になりました。 本日のニュースの総点は長浜俊浩先生を 招きし、え、ま、為せについて、え、ま、 基本的なことから、ま、現在の問題に つがると点まで、え、幅広くお聞きしまし た。え、またこのような情報を広げるため にもチャンネル登録と高評価をお願いし ます。え、先生、本日はありがとうござい ました。ありがとうございました。
ご視聴いただき、ありがとうございます。
ぜひチャンネル登録、いいねボタンとコメントをお願いします!
「ニュースの争点」では
・日本の将来に役立つ知見
・ニュースを見ているだけでは見えてこない社会の構造
を専門家の解説とともにお届けします。
他にも、テレビや新聞では聞けない専門家による
ニュース解説や特別座談会・対談コンテンツを配信中です!
↓↓永濱利廣先生出演回↓↓
【アメリカvs.中国】 関税戦争勃発!トランプ大統領が目論む?”裏シナリオ”とは(第一生命経済研究所 首席エコノミスト 永濱利廣)【ニュースの争点】
↓↓オススメのコンテンツはコチラ↓↓
なぜ日本企業は世界から出遅れたのか?/日本人の足を引っ張るエリートの罪(中野剛志・施光恒・古川雄嗣・岩尾俊兵)【特別座談会Part1】
【丸わかり】トランプ政権ブレーンの脳内/PayPalマフィアが目指す世界とは?(思想史家 会田弘継)【ニュースの争点】
なぜ私たちは学問をするのか?/学者同士の争いが無意味なワケ/議論と論破の違いとは?(評論家 中野剛志×儒学者 大場一央)特別対談前編